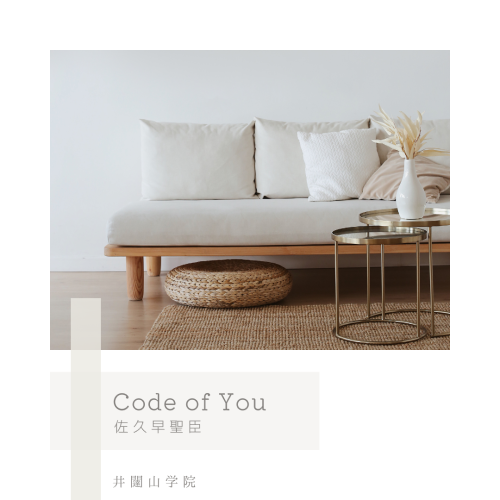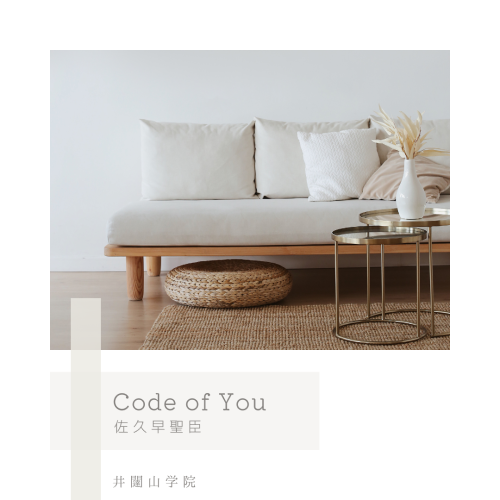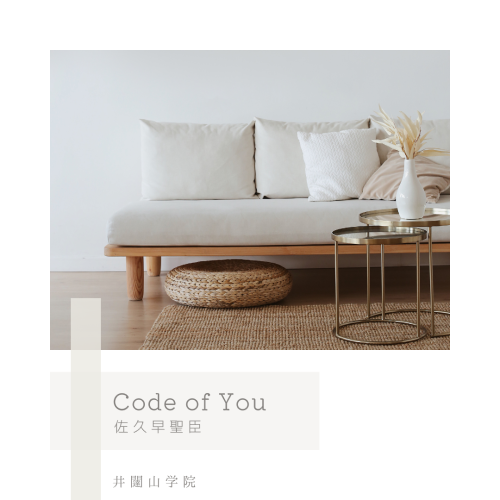
幸せは、服を着た兄の先に。
それから暫く、俺は
苗字家のリビングの扉に近づくことを避けていた。いや、正直に言えば、二度とその取っ手に触れたくなかった。あの忌まわしい記憶――全裸でソファに鎮座する
苗字兄貴の姿が、網膜の裏側にこびり付いて離れない。初めて訪れた日の衝撃は、今でも背筋を冷たく這う悪寒となって蘇る。あの光景を再び目にするくらいなら、いっそこの足で地球の裏側まで逃げ出したい。
幸い、このマンションには救いがあった。玄関を抜けた廊下が
名前の部屋まで一本道で繋がっていて、リビングを回避できる動線が確保されている。訪れる度、
名前が俺の手を引いて、そのまま彼女の部屋へ導くのが暗黙の了解になっていた。彼女の指が俺の掌に触れる瞬間、かすかな温もりが心を落ち着かせ、あの扉の存在を一時的に忘れさせてくれる。
「臣くん、兄さんの姿をもう一度見たくはない?」
時折、
名前が悪戯っぽく囁く。その声は風に揺れる木の葉のようで、軽やかさと意地悪さが絶妙に混じり合っている。俺は毎回、全力で首を振る。「冗談でもやめてくれ」と喉元までせり上がる言葉を飲み込み、ただ無言で眉を寄せるだけだ。彼女の瞳が笑う度、心のどこかで小さく波が立つ。愛らしいと思う反面、あの"禁忌"の記憶がちらつき、複雑な気分にさせられる。
だが、そんな平穏な日々にも終わりは訪れる。突然、音もなく忍び寄るように。
その日は、
名前の部屋でいつものように過ごしていた。ベッドサイドに腰掛け、窓から差し込む午後の陽光がカーテンの隙間を縫って床に細長い影を落としているのをぼんやり眺めていた。室内には彼女の気配が染み付いていて、ミントと桜が混ざったような淡い香りが漂う。俺にとって、それは安心の匂いだ。
なのに、彼女が部屋を出てから妙に時間が経っていることに気づいた。紅茶を淹れに行っただけなら、五分もあれば戻ってくる筈だ。時計の針が静かに進む音が、奇妙に耳に刺さる。
「……あれ?」
嫌な予感が胸の底を掠めた。背中を這う冷たい感覚は、初めてリビングの扉を開けた瞬間に似ていた。指先が微かに震え、俺は無意識に膝に置いた手を握り潰す。
そして、次の瞬間。
ガチャリ。
扉の開く音が、静寂を切り裂いた。
「臣くん、こっちに来てくれない?」
廊下の向こうから、
名前の声が響く。澄んだ音色はガラス細工のようで、穏やかさの中に微かな期待が滲んでいる。だが、その言葉の行き先に、俺の心は凍り付いた。
「……どこに?」
声が掠れた。喉が締め付けられる感覚に、言葉がうまく形にならない。
「リビング」
「嫌だ」
即答だった。反射的に口をついて出た拒絶は、頭で考えるよりも先に身体が動いた証拠だ。心臓が早鐘を打ち、掌にじっとりと汗が滲む。あのリビングには、俺の精神を砕く何かが潜んでいる。それが服を着ていようと裸であろうと、もう関係ない。ただ、あの空間に足を踏み入れること自体が、本能的な恐怖を呼び起こす。
だが、扉の向こうで
名前が小さく笑った。クスクスという音は、まるで春の小川が石を撫でるような軽やかさだ。
「大丈夫だよ、兄さんは服を着ているから」
信用できない。
苗字兄貴という男は、常識の枠を超えた存在だ。あの日の全裸は、俺の信頼を根こそぎ奪い去った。あの優雅な仕草でコーヒーを啜りながら「俺の家だから」と言い放った顔が、今でも脳裏にちらつく。あれが服を着ている保証など、どこにもない。
「……本当に?」
念を押す声は、自分でも情けないほど弱々しかった。だが、慎重にならざるを得ない。あの禁忌に再び挑むには、確信が必要だった。
「本当」
名前の返答は、珍しく力強かった。彼女の声に宿る確信が、俺の躊躇を少しだけ溶かす。彼女の瞳がこちらを見ている姿を想像すると、何故かその言葉を信じたくなる衝動が湧いた。
俺は深く息を吸い、吐き出す。膝に置いた手が汗で湿っているのをウェットティッシュで拭い、立ち上がった。足元の床が軋む音が、まるで覚悟を試すように耳に響く。あのリビングの扉を再び開ける――それは、俺にとって小さな戦いの始まりだった。
廊下を進む度、心臓の鼓動が耳に届く。
名前の部屋からリビングまでの距離は短い筈なのに、果てしなく遠く感じられた。壁に掛かった小さな鏡に映る俺の顔は、緊張で強張っている。彼女の手を握ることもなく、一人でその扉に近づくのは初めてだ。
そして、遂に。
冷たい取っ手に指を掛け、禁断の扉を開けるかのように、ゆっくりと押した。扉が開く瞬間、微かな風が頬を掠め、俺の髪を揺らす。目を細めながら室内を見渡すと――
そこには、しっかりと服を着た
苗字兄貴が居た。
「……
兄貴さんが服を着ている」
声に出して確認したのは、自分を納得させる為だった。黒いシャツとズボンに身を包んだ彼は、別人のように普通に見える。ソファに腰掛け、膝に置いた本を手に持つ姿は、確かにあの日の全裸の王とは対極的だ。
「君は、俺をどんな存在だと思っているんだ?」
兄貴さんの声には、微かな苦笑が混じっていた。あの日の余裕たっぷりな口調とは違い、少しだけ人間らしい響きがある。彼の視線が俺を捉え、その瞳の奥に何か真剣な光が宿っているように見えた。
「少なくとも、基本的に裸の生物だとは思っていました」
本音が零れた。俺なりのユーモアを込めたつもりだったが、どこか本気じみている自分に気づく。
兄貴さんは小さく笑い、首を振った。
「確かに、あの日は悪かったね。だが、今日は違う。君に話がある」
その言葉に、俺の背筋がピンと伸びた。軽い調子から一転した真面目な声音に、空気が張り詰める。
「……なんです?」
喉が僅かに締まり、声が硬くなる。
兄貴さんの瞳が俺をじっと見つめ、その視線に何か重いものが宿っているのが分かった。俺の内側を透かし見るような鋭さだ。
「妹のことを頼むよ」
シンプルな一言だった。だが、その言葉は俺の胸に鋭く突き刺さり、心臓が一瞬止まったかと思う程だった。耳の中で反響するその響きは、静かで、深く、そして温かい。
「……当たり前です」
短く答えた。声が震えないよう、意識して抑えたつもりだ。だが、心の中では波が荒れ狂っていた。
兄貴さんの言葉が、俺と
名前の関係に一本の太い糸を結び付けたような感覚があった。
「ふふ、兄さん、ちゃんと認めてくれたんだね」
隣で
名前が嬉しそうに笑う。彼女の声は、風に揺れる花びらのように柔らかく、俺の耳にそっと届く。視線を向けると、彼女の瞳が月明かりのように輝いている。そこには純粋な喜びと、俺への信頼が混じっていた。
その瞬間、ふと、心の底から言葉が浮かんだ。
*幸せを見つけた*
昔の俺は、一人で居ることが当たり前だった。誰かと心を通わせることなんて考えもしなかったし、周囲も俺に踏み込むことを避けているようだった。孤独が俺の影だった。でも今、目の前に
名前が居る。彼女の存在が、俺の過去を塗り替えていく。
無意識に手を伸ばし、彼女の指先に触れた。細い指が俺の掌に絡み付き、その温もりがじんわりと伝わる。彼女の肌は柔らかく、春の新芽のような感触だ。
「臣くん、どうかした?」
名前の声に、俺は我に返る。彼女の瞳がこちらを覗き込み、不思議そうに首を傾げている。その仕草が余りにも愛らしくて、胸の奥が締め付けられた。
「いや」
短く答えてから、リビングの扉に視線を移した。あの扉が、且ては恐怖の象徴だった。でも今、
兄貴さんが服を着て座り、
名前が隣で微笑むこの空間は、まるで別の場所のようだ。俺の中で、何かが変わった。
「俺はもう、この扉を開けることを怖がらない」
呟きが自然と口をついて出た。例えその先に何が待っていようと――全裸の
兄貴さんが再び現れるとしても――
名前が居るなら、俺は立ち向かえる。そう思えた。
兄貴さんが小さく笑い、
名前が俺の手をぎゅっと握り返す。その瞬間、リビングの窓から差し込む光が、俺達の影を床に長く伸ばした。外では風が木々を揺らし、かすかな葉擦れの音が聞こえる。扉の向こうに広がる世界が、少しだけ愛おしく感じられた。