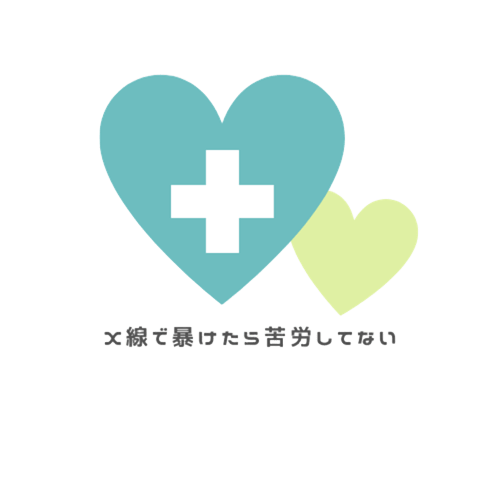
X線で暴けたら苦労してない
苗字名前と云う人間は、俺にとって、最高難易度のブロックであり、解読不能な暗号であり、攻略し甲斐のある最終ボスだ。
体育の授業で露わにした、静かな独占欲。あの一件以来、俺は未だに幸福と混乱の坩堝へ叩き込まれたままだ。嬉しい。途方もなく嬉しい。だがしかし、分からない。あれ以降も、苗字さんの態度は以前と何ら変わりない。時折交わす言葉も、同じく淡々としている。例の言動は、一体、何を意味していたのか。好意の表れと解釈していいのか? それとも、只の気紛れ?
思考の迷宮に迷い込んだ俺は、ネット際でトスを待つスパイカーのように、次の最適な一手を決め兼ねていた。強気に攻めるべきか、一度、様子を見るべきか。選択を誤れば、即シャットアウトだ。俺の初恋は、余りにも繊細なゲームバランスの上で成り立っている。
そんな、俺の悶々とした日々は、バレーのプレーにも、如実に影響を及ぼし始めた。
「工ァ! 今のボール、目で追ってなかったべや!」
「うすっ! 済みません!」
鷲匠監督の雷が体育館に轟く。駄目だ。集中できない。ブロックの向こう側、スパイクを打つべきスペースに、苗字さんの無表情が幻みたいにチラついて、反応が一瞬遅れる。レシーブ練習では、球の軌道と、彼女の視線が脳内で交錯し、無様にボールを逸らしてしまう。
「おい、五色。最近、挙動がおかしいけど、頭でも打ったの、お前」
部活後、呆れたように声を掛けてきたのは、白布さんだった。氷の如き眼差しが、火照った脳天に心地良い。
「いえ、別に……絶好調です!」
「どの口が言ってる。さっきのレシーブ、小学生にすら負けてるけど」
「ぐっ……」
正論過ぎて、ぐうの音も出ない。俺は唇を噛み締め、床に落ちる汗を見つめた。
このままでは駄目だ。エースへの道が遠退く。何より、苗字さんの前で、情けない姿は晒せない。
その日の夜。俺は寮の自室にて、ベッドで大の字になり、天井を睨み付けていた。
どうすればいい。どうすれば、苗字さんの心を正確に読み解くことができるんだ。彼女の静かな瞳の奥で、一体、どんな感情が渦巻いているのか。
いっそのこと、病院にあるX線撮影装置や心電図、ドップラー血流計で、苗字さんの胸の内を透視できたら……。そうすれば、心臓の鼓動の速さや、血流の変化で、彼女の本当の気持ちが分かるかもしれない。俺は、そんな非科学的で、余りにも馬鹿げた妄想を、大真面目に繰り広げていた。
「……うおおお、駄目だ! 全然分からん!」
俺は勢いよく起き上がると、意味もなく室内をうろうろし始めた。まるで、檻の中の熊だ。このままでは、思考回路がショートして、頭から煙を噴いてしまう。
そうだ、こう云う時は、誰かに相談するに限る。
白布さんは論外だ。「下らねぇ」と一言で斬り捨てられるのが、目に見えている。牛島さんは……恋愛相談なんて、抑々概念として、理解してもらえるかすら怪しい。獅音さんは優しく聞いてくれるだろうが、きっと「青春だな」と微笑むだけで、具体的な解決策は示してくれない気がする。山形さんや瀬見さんも親身にはなってくれそうだが、的確なアドバイスをくれるかは未知数だ。川西さんは……白布さんと一緒になって、冷めた目で見てくるか、揶揄われるに違いない。
そうなると、残るは一人しかいない。あの予測不能で、人心を弄ぶのを得意とする、ゲスの怪物。
俺は意を決して、隣の隣、天童さんの寮室の扉をノックした。
「はーい? どちら様かなー?」
中から聞こえたのは、いつものようにお道化た声だった。俺が名乗ると、勢いよくドアが開かれ、逆立った赤毛がひょこりと顔を出す。
「おやー? 工じゃないの。どうしたの、そんな深刻な顔しちゃって。さてはまた、ボムちゃんのことでお悩みかな?」
「ボ、ボムちゃん……?」
聞き慣れない呼称に、俺は首を傾げる。天童さんはニヤリと笑い、「俺が付けた、苗字さんのコードネームだよ」と悪びれもなく言いのけた。
「そ、そんなことより、天童さん! 俺、もう駄目かもしれません! 苗字さんの考えていることが、1ミリも分からないんです!」
俺は部屋に招き入れられるや否や、堰を切ったよう、悩みをぶち撒けた。体育での一件以降も、苗字さんの態度が全く変わらないことへの戸惑い。彼女の真意を測り兼ねて、プレーに集中できない現状。最終手段として、脳内を支配し始めた、非現実的なX線透視計画まで。
俺の必死の訴えを、天童さんはチョコの棒アイスを食べながら、面白そうに聴いていた。そして、話し終えるのを待って、こう言った。
「工クンさあ、バレーの試合中に、相手チームの全員が考えてること、全部読める?」
「へ? いえ、そんなことは……。読めるのは、相手のアタッカーの動きとか、セッターの癖とか……」
「だろ? ぜーんぶお見通しなんて、無理だし。抑々、面白くないじゃん」
天童さんはアイスの棒をぺろりと舐めると、それをゴミ箱に放り投げた。次いで、ぎょろりとした大きな両目で、俺を真っ直ぐに見据える。
「ゲス・モンスターの俺でも、あのボムちゃんの心は、完全には読めない。だから、面白い。次は何をしてくれるんだろうって、ワクワクする。全部読めちゃったら、只の作業だろ? 恋もバレーも、予測不能だから、最高に楽しいんじゃないの?」
その言葉は、強烈なスパイクのように、俺の脳天に突き刺さった。
確かに、そうだ。俺は、苗字さんの全てを理解しようとして、勝手に苦しんでいた。だが、分からないからこそ、知りたくなる。予測できないからこそ、心が揺さぶられる。試合中のスリリングな攻防と、何ら変わりないじゃないか。
「……成程!」
頭の中に巣食っていた靄が、一気に晴れていく感覚。目の前に、一本の光明が差し込んだ気がした。
そう、俺は難しく考え過ぎていた。苗字さんの心を無理に抉じ開けようとするんじゃなく、彼女が発する微かなサインを、一つずつ丁寧に拾い上げていけばいいんだ。ブロックの、僅かな隙間を見つけるように。
「ありがとうございます、天童さん! 俺、目が覚めました!」
「おー? そりゃ良かった。まあ、精々頑張りなよ」
天童さんはひらひらと手を振り、ジャンプの世界へと没入していく。俺は深く頭を下げると、晴れやかな気持ちで部屋を後にした。
そうだ。俺は、五色工。白鳥沢のエースになる男。
どんな難解な相手だろうと、観察し、分析して、最高のパフォーマンスで打ち破るまでだ。
X線なんて、必要ない。俺には、この目と心がある。
翌日から、俺は生まれ変わった。
授業中、苗字さんの横顔と黒板を、ほぼ同じ割合で見つめるようになった。教科書のページを捲る、指先の動き。問題を解く時、僅かに顰められる眉。窓の外を眺める瞬間の、眸の色の微かな変化。全てを網膜に焼き付け、脳内のデータファイルに記録する。
それは地道で、途方もない作業だった。だが、不思議と苦ではなかった。寧ろ、今まで見えていなかった、苗字さんの新たな一面を発掘する度に、宝物を探り当てたような高揚感が、胸を満たす。
苗字さんはシャーペンの芯を出す際、必ず二回、カチカチと鳴らす癖があるらしい。
数学の授業より、古文の方が、少しだけ背筋が伸びている。
昼休み、観葉植物に水をやる時、葉っぱの裏側まで、丁寧に霧吹きを掛けている。
そんな、誰にも気づかれないような、細やかな発見。
一つひとつが、俺にとってはサービスエースを決めるのと同じくらい、価値があった。
読めないからこそ、面白い。
天童さんの言葉が、俺の中で、確かな意味を持ち始めていた。
苗字名前と云う名の最高にエキサイティングな試合は、まだ始まったばかりだ。俺はこのマッチ、全てのセットを全力で楽しんでやろうと、心に誓った。
心臓が試合開始のホイッスルみたいに力強く、期待に満ちて高鳴っていた。