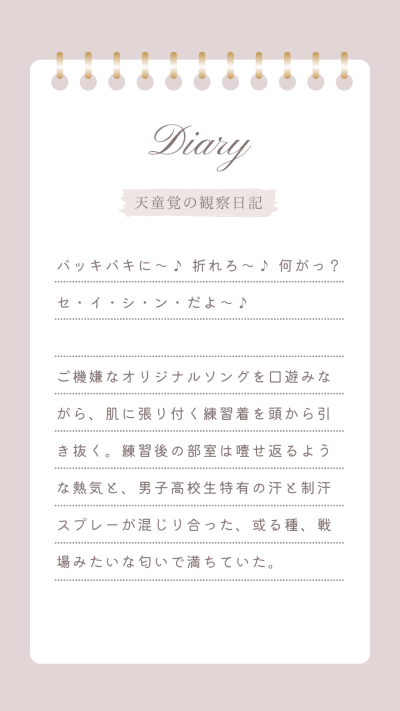
天童覚の観察日記
バッキバキに~♪ 折れろ~♪ 何がっ? セ・イ・シ・ン・だよ~♪
ご機嫌なオリジナルソングを口遊みながら、肌に張り付く練習着を頭から引き抜く。練習後の部室は噎せ返るような熱気と、男子高校生特有の汗と制汗スプレーが混じり合う、或る種、戦場みたいな匂いで満ちていた。俺、天童覚にとっては、楽園の芳香みたいなもんだけどね。
いつものように、ロッカーから愛読書である週刊少年ジャンプを引っ張り出そうとした俺の視界の端に、奇妙な物体が映り込んだ。
「……んん?」
思わず、二度見する。そこに居たのは、一年坊主の五色工。奴はロッカーの扉を鏡代わりに、前髪を鬼気迫る表情で弄くり回していた。指先で数ミリ単位の調整を繰り返し、時折、誰にも見せたことのないような、ふにゃりと蕩け切った笑みを浮かべては、ハッと我に返り、顔を引き締める。その一連の動作は、最早、儀式の域に達していた。
「おやー? 工クン、どうしたの。大事な前髪に、何か面白いことでも書いてあんの?」
「て、天童さん! い、いえ! 何でもありません! 前髪のコンディションは、常に完璧であるべきかと!」
びくんと肩を揺らし、慌てて振り返る工。顔が発熱しているみたいに赤い。今日の練習中も、工はどこかおかしかった。スパイクが決まる度に「うおおお!」と雄叫びを上げるのは普段通りだが、声に妙な甘さが混じっていたし、ボールが床に突き刺さる瞬間、一瞬だけ虚空を見つめ、恍惚の表情を滲ませていた様を、俺は見逃さなかった。
これは間違いなく、何かあった。俺のゲスな勘が、ピコンピコンとけたたましく警報を鳴らしている。
「へーえ? 何でもない、ねえ。そんな茹蛸みたいな顔色で言われても、説得力ゼロだよ。さては、例の彼女関連で、何か進展があったとか?」
「か、彼女では、ありま……せん……が……」
蚊の鳴くような語尾になり、工は視線を彷徨わせる。その分かり易い反応、実にイジり甲斐があって宜しい。俺はニヤニヤしながら肩を組み、軽く体重を預けつつ、顔を覗き込んだ。
「はいはい、彼女『候補』ね。で? 何があったワケ? この面白いことが大好きな天童先輩に、洗い浚い報告しなさい」
「う、うぅ……」
観念したのだろう。工は小声で、ぽつり、ぽつりと、体育の授業での出来事を白状し始めた。女子に背中を叩かれたこと。その刹那、苗字さん――工が想いを寄せる、例のミステリアスな少女――と目が合ったこと。そして、彼女から静かに告げられた、破壊力抜群の一言。
「……『わたし以外の女の子に、安易に触れさせないでほしい』……と……」
台詞を復唱する工の声は、羞恥と歓喜で震えていた。
俺は一瞬、思考を停止させた。脳内で言葉の意味と、工から断片的に聞いていた、彼女の人物像を照合する。そして、次の瞬間。
「ぶっははははは! 何それ! 最高じゃんか! アッハハハ!」
腹筋が捩れるかと思う程、盛大に噴き出した。部室に居た他の部員達が、何事かと訝しげに見てくるが、今はお構いなしだ。
「わ、笑い過ぎです、天童さん!」
「いやいやいや! 笑うなって方が無理でしょ、これは! 工の話から推測するに、絶対言いそうにないクールビューティーが、そんな、少女漫画の王道みたいなセリフを!? マジで!? 録音してないの!?」
「してるわけないじゃないですか!」
工が女神と崇める女子。俺は未だ、その顔を直接拝んだことはない。けど、工の熱に浮かされたような説明――「静かで、綺麗で」「何を考えてるか、全然分からなくて」「でも、時々、凄く可愛いんです」――から脳内で組み立てたイメージは、感情と云う名のソフトウェアがインストールされてない、精巧なアンドロイドみたいな少女だった。そんな彼女が仄暗い独占欲を瞳に宿し、氷の声で囁く姿を想像する。……ゾクゾクする。面白過ぎる。これは、俺がここ最近で遭遇したエンターテイメントの中で、間違いなく最高傑作だ。
「へー、へー、へー! その子、そんなタマだったんだ。いやー、人は見掛けによらないとは言うけど、ここまでとはね。で、工は当然、平伏したワケだ?」
「平伏してません! 只、『は、はいぃぃぃっ!』と、返事を……」
「ほぼ平伏してるようなもんじゃん!」
一頻り笑い転げた後、俺はふと、或る事に気づいた。工は彼女のヤキモチを喜んでいる。それはもう、全身の細胞で、魂の奥底から。でも、同時に心の底から困惑している。この気持ちの振れ幅が、工の表情に可笑しなグラデーションを描き出していた。
「でも、俺、全然分からなかったんです。苗字さんが、そんな風に思ってくれてるなんて。あの時、いつもの無表情だったから……俺、何かやらかしたのかって、心臓が凍るかと思いました」
工の言葉に、俺のゲスな好奇心は更に加速する。
成程。工は彼女の心の動きが読めなくて、パニック寸前なのか。話を聞く限り、苗字さんと云う女子は、顔色から感情を推し量るのが、極めて困難なタイプらしい。完璧なポーカーフェイスで相手を翻弄する、トリッキーなセッターみたいじゃない?
「これは、直接、この目で観察するしかないネ」
「へ?」
「決ーめた! 明日の休み時間、俺、一年四組に遊びに行く!」
「えええ!? な、何でですか!?」
「決まってんじゃん。面白いからだよ」
俺はそう言い放つと、工の絶望的な悲鳴をBGMに、上機嫌でロッカーを閉めた。
翌日、俺は有言実行した。二限目と三限目の間の、十分間の休み時間。俺は「やっほー! 工クン、購買で限定のチョコパン売ってたけど、要るー?」なんて、自分でも白々しいと思う口実を掲げ、一年四組のドアをガラリと開けた。
教室中の視線が、一斉に突き刺さる。まあ、三年、しかも、俺みたいな目立つ風貌の先輩が来れば、そうなるわな。俺はそんな眼差しを愉しむように、ひらひらと手を振りながら、目的の人物――五色工と、隣席の女子――をロックオンした。
工は、俺の姿を認めるなり、顔を真っ青にして、石像みたいに硬直している。分かり易い奴め。その隣、窓際の席に、彼女は居た。
苗字さん。
彼女の相貌を捉えた瞬間、俺は内心で、軽く息を呑んだ。教室の喧騒など、まるで存在しないかのように、彼女の周りだけが静寂に包まれている。陽光を浴びて透ける、色素の薄い肌。人間と云うより、球体関節人形を思わせる、完璧に整った造形。そして、感情の色が一切乗らない、深く、静かな双眸。
成程、これは、確かに手強い。工が「女神」と呼ぶのも、「何を考えてるか分からない」と嘆くのも、両方納得だ。
「よっ、工。パン、ラスイチだったけど、お前にやるヨ」
「あ、あざっす……」
工の机にパンを置き、俺はそのまま居座ることにした。さあ、見せてもらおうか。二人の間に、どんな化学変化が起きているのかを。
観察開始。
一見、何も変わらない。工は、俺の存在に恐縮しきりで、苗字さんは我関せずと云った様子で、教科書に視線を落としている。だけど、俺のゲス・ブロックで鍛えられた観察眼は、常人には見えない微細なサインを捉えていた。
――ピクリ。
俺が「今日の練習、気合入れろよ~」と、工の肩に腕を回した瞬間、苗字さんのページを捲ろうとしていた指先が、ほんの一瞬、止まった。コンマ数秒にも満たない、些細な停止。普通のレシーバーなら、間違いなく見逃すフェイントだ。
――スーッ。
工と同じクラスの新入部員が「天童先輩、今週のジャンプ、面白かったですね!」と、俺に話し掛けた際、苗字さんの視線が教科書から僅かに持ち上がり、俺らの方へと移動した。そして、何事もなかったみたいに活字へと戻る。一連の流れは、水面へ落ちる木葉のように自然で、滑らかだった。でも、俺のセンサーは微弱な軌道変化を、確かに検知している。
――トクン。
極め付けは、工がパンの礼を言った時だ。「あ、ありがとうございました、天童さん! これ、すげー美味かったです!」と満面の笑みを浮かべた、その直後。
苗字さんの口角が、ミクロン単位で上がったのを、俺だけが見抜いた。微笑みとも呼べない、本人ですら無意識かもしれないってレベルの変化だけど。工の喜びに対する、確実に肯定的な反応だった。
面白い。
ああ、なんて面白いんだ。
この子は無表情じゃない。感情の表出が、極端に小さいだけだ。ブロックに当てるだけの、軟打のスパイクみたいに。普通の奴なら見逃してしまう、細やかな移ろい。それを読み切った時の快感は、若利くんの強打をシャットアウトするのに匹敵する。……止めたことないけど。
予鈴が鳴り、俺は「じゃあね、工!」と手を振って、教室を後にした。廊下を歩きながらも、俺の口許には抑え切れない笑みが浮かんでいた。
あの子は爆弾だ。静謐な見た目の下に、途方もない感情を溜め込んだ、時限爆弾。その起爆スイッチを握っているのが、単純で熱血な後輩だなんて、何の冗談だ。
工は、苗字さんの心が読めないと思っている。けど、違う。彼女はちゃんと、工にだけ伝わるよう、微弱なサインを送り続けているんだ。気づけるかどうかは、工の観察力次第。
これは最高のショーになる。
俺は、この興味深く、底知れない観察対象に、敬意と親しみを込めて、新しい呼び名を授けることにした。
「爆弾ちゃん、ねえ……」
呟いた名前は、思った以上に、しっくりと口に馴染んだ。
ゲス・モンスターの俺でも、ボムちゃんの心は、完全には読めない。
だから、面白い。
俺は、今後も続くであろう予測不能なラブコメディの観客として、二人の行く末を特等席で見守ろうと決めたのだった。