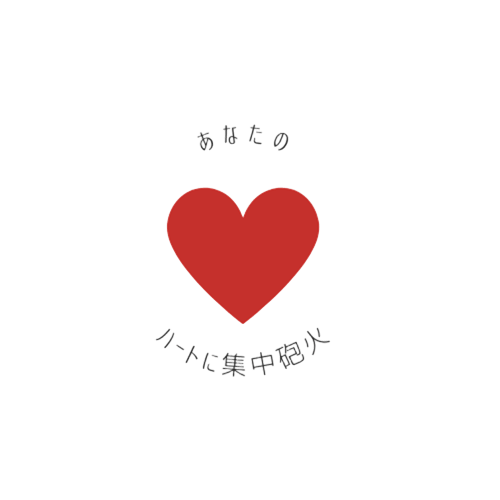
あなたのハートに集中砲火
青く、静かな焔へと姿を変えた筈の闘争心は、翌朝にはすっかり鎮火し、焦げ臭い黒煙を燻らせていた。寮室、硬いベッドの上で目覚めた俺は、天井の染みを眺めながら、己の戦略の根本的な誤りに気づかされたのだ。
俺の武器は、キレキレのストレート。駆け引きなしで、相手の心を真っ直ぐに射抜く、俺の在り方そのものだと思っていた。だから、恋愛でも小手先のテクニックじゃなく、真正面から情熱でぶつかるのが最善だと信じて疑わなかった。だが、それは只の思い上がりだった。牛島さんを超える為に、俺はストレート一辺倒ではなく、ブロックアウトを狙う技術や、緩急を付けた攻撃も磨いてきた筈じゃないか。コート上では冷静に敵を見て、最善手を探ると心掛けているのに、どうして、苗字さんの前では猪突猛進なだけだったんだ。
そうだ。恋愛も、バレーボールと同じ。
猛進だけでは、頂点に立てない。時には、頭脳を使わなければいけないんだ。
「――作戦変更。本日より、頭脳戦に移行する!」
ベッドから跳ね起き、高らかに宣言する。幸い、隣室の白布さんは既に洗面所へ向かった後らしく、氷点下の叱責を壁越しに飛ばされることはなかった。
俺の新たな作戦、名付けて『苗字名前のハートに集中砲火』。その第一歩は敵情視察からだ。彼女の趣味は読書。なら、俺も同じフィールドに立つ。一度は断念したが、共通の話題で、心の距離を縮めるんだ。
放課後、俺はバレー部員が行くことなど、滅多にないであろう場所へ足を踏み入れていた。駅前の大きな書店。新しい紙とインクの匂いが混じり合う独特の空気が、筋肉とは無縁の世界へようこそ、と告げているようだった。文学書のコーナーで、俺は途方に暮れる。ずらりと並ぶ背表紙の、難解な漢字の羅列。どれが、苗字さんのハートを射抜く一冊なのか、見当もつかない。
「……ええと、『柔らかな絶望』……? 柔らかい絶望って、何だよ……」
独り言を呟きながら、本を手に取る。パラパラとページを捲るが、まるで暗号文だ。バレーの戦術書なら、一晩で丸暗記できる自信があるのに。この比喩や心理描写の応酬は、ブロック不能のフェイント攻撃みたいに、俺の脳を翻弄する。
それでも、俺は諦めなかった。エースたるもの、弱音は吐かない。一番分厚く、最も権威のありそうな一冊を購入し、寮への帰路を急いだ。
結果から言えば、惨敗だった。
自室の机に向かい、買ったばかりの文学小説を開くこと、約十分。俺の意識は、主人公の繊細な心の機微を描く文章の上を滑り、三頁目で完全にブラックアウトした。次に目覚めた時、頬にはくっきりと角の跡が刻まれ、窓の外はすっかり闇に包まれていた。駄目だ。活字のレシーブは、俺の専門外らしい。
翌日、俺は新たな情報を得るべく、教室で女神の動向を注意深く観察していた。読書以外に、何か手掛かりはないものか。すると、昼休みのことだった。苗字さんは窓際に置かれたクラス共有の観葉植物の鉢を、そっと自分の机へ運んだのだ。そして、持参したらしい小さな霧吹きで、葉っぱに優しく水を掛けている。
陽光が彼女の柔らかな髪を透かし、横顔を淡く照らし出す。葉の一枚一枚を慈しむように見つめる、静かな眼差し。それは、本を読んでいる時の真剣な表情とはまた違う、穏やかで女の子らしい色を帯びていた。
俺の心臓が、未知のビートを刻む。そうだ、苗字さんは自己紹介の際、趣味は読書です、としか言わなかった。だが、あれは数ある嗜好の一つに過ぎなかったのかもしれない。
園芸。
俺の脳内に、新たなキーワードが光明のように差し込んだ。これだ。これなら、俺にもできるかもしれない。
部活後、俺は書店とは逆方向に在る、小ぢんまりとした園芸店へ駆け込んでいた。花の甘い香りと、土の匂いが満ちる店内。色とりどりの植物に囲まれ、俺は"勝利"を齎してくれそうな一鉢を真剣に吟味する。
「あの、初心者でも育て易いのって、どれですか」
「それなら、サボテンなんてどうですか?」
人の良さそうな店主に勧められ、俺は小振りな丸いサボテンを選んだ。鉄壁のブロックを思わせる、無数の鋭い棘。不屈の佇まいが、エースを目指す俺の魂と共鳴しているような気がした。名前はもう決めている。『エース』だ。この相棒と共に、苗字さんの心を攻略する。
寮に帰り着き、意気揚々と『エース』を窓辺に置こうとした、その時だった。
ちくり、と指先に奔る、鋭い痛み。
「いっ……!?」
見れば、人差し指の先に、小さな棘が深々と突き刺さっている。バレーボールを扱う、俺の命とも云える指頭に。
「なっ……この、裏切り者ぉっ!」
俺は思わず、サボテンに向かって叫んだ。買ってきたばかりの相棒から受けた、予期せぬ攻撃。まさかの同士討ち。余りの衝撃に、俺はその場で膝から崩れ落ちた。
翌朝。俺は人差し指に大袈裟な絆創膏を巻き、沈んだ気持ちで席に着いた。俺の輝かしい園芸ライフは、僅か一日で幕を閉じたのだ。とは言え、サボテンを捨てるなんてことはできなかった。裏切られてしまったものの、一度は『エース』と名付けた仲間だ。それに、こいつにも生きる権利がある。俺はブツブツと呟きながら、部屋の隅、日当たりは良好だが、直射日光の当たらない場所にそいつを置き、複雑な心境で寮を出たのだった。
物思いに耽っていると、隣から澄んだ声が掛けられた。
「五色くん。その指、どうしたの」
苗字さんが、俺の指先を真っ直ぐに見つめていた。深い夜の海みたいな瞳に、僅かながら心配の色が浮かんでいるように映ったのは、きっと気の所為じゃない。
「あ、いや、これは……」
俺は昨夜の一部始終を、正直に打ち明けた。園芸に挑戦しようと思ったこと。『エース』と名付けたサボテンに、早々に裏切られてしまったこと。エースの名を冠する者(予定)として、情けない限りだと。
俺が俯き、大真面目に己の不甲斐なさを嘆いていると、不意に空気が振動した。
顔を上げる。
目の前の苗字さんが、口許にそっと手を当て、薄い肩を震わせていた。
時が止まった。教室の喧騒が、嘘のように遠退き、世界から音が消える。
苗字さんの静謐な表情が、硬い蕾がゆっくりと綻ぶよう、微かに形を変えていく。そして。
「……くすっ」
鈴が鳴るような、小さな笑い声が漏れた。
俺は雷に打たれたかの如く固まった。今まで一度も見たことのなかった、苗字さんの笑顔。それは、どんな強烈なスパイクよりも、どんな勝利の瞬間よりも、俺の魂の核を直接揺さぶる、途方もない破壊力を持っていた。
指の痛みも、文学小説での挫折も、嫉妬に狂った夜も、全てがこの一瞬の為にあったのだと思えた。
俺の不器用で的外れな集中砲火は、どうやら鉄壁の要塞の、ほんの一角を確かに撃ち抜いたらしい。
絆創膏の下で、血液が歓喜の雄叫びを上げていた。
上等だ。エースへの道も、苗字さんへの道も、ここからが本番だ。
俺は初めて向けられた女神の微笑みに、完全に心を奪われていた。