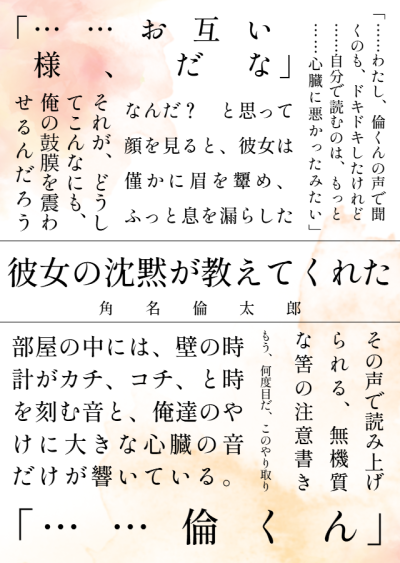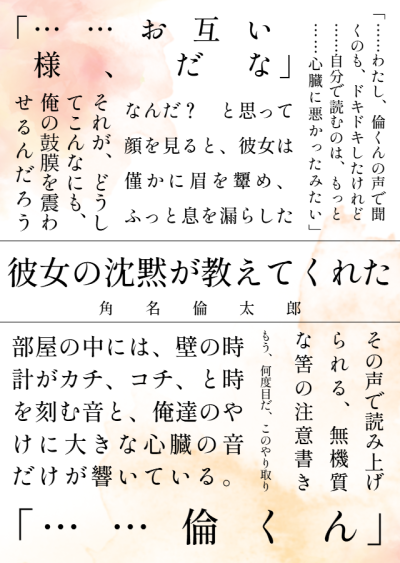彼女の沈黙が教えてくれた | Title:視線の先にはいつも君がいた
俺のスマホが悪魔の囁きみたいに、
兄貴さんのメッセージを映し出している。【俺の妹に手を出す気か】……って、いや、タイミング良過ぎでしょ、兄さん。エスパーか何か? それとも、この部屋のどこかに小型カメラでも仕掛けてる? んなワケないか。いやでも、あの人なら……。
俺が内心でくだらないツッコミを繰り広げていると、隣で
名前ちゃんがくすくすと笑った。その夜色の瞳が悪戯っぽく細められて、キラキラと輝いている。あーもう、この顔に、俺はとことん弱いんだ。
「ふふ、兄さん、面白いことを言うね」
「いや、笑い事じゃないからね? 俺、本気で寿命縮んだんだけど」
心臓、まだバクバク言ってる。マジで。
名前ちゃんは、俺の抗議なんてどこ吹く風って感じで、ふわりと立ち上がった。そして、ローテーブルの上に無造作に置かれている、例の箱――俺がドラッグストアで、清水の舞台から飛び降りる覚悟で選んだあのブツを、事もなげに手に取った。
「じゃあ、次はわたしが読むね」
え。
マジで?
さっきの「次はわたしが音読する?」って、冗談じゃなかったの?
俺の思考が完全にフリーズするのを待たずに、
名前ちゃんは隣の座面にちょこんと腰を下ろした。近い。さっきよりも、もっと近い。シャンプーの甘い香りが、濃密に鼻腔を擽る。
「倫くん、ちゃんと聞いていてね」
そう言って、彼女は箱の裏側に書かれた説明に視線を落とした。長い睫毛が伏せられて、その下に影を作る。その仕草の一つひとつが、やけに艶めかしく見えるのは、俺の気のせいだろうか。
「ええと……『この製品は、取扱説明書を必ず読んでからご使用ください』」
淡々とした、それでいて鈴を転がすような、彼女特有の澄んだ声。
その声で読み上げられる、無機質な筈の注意書き。
それがどうしてこんなにも、俺の鼓膜を震わせるんだろう。
視線の先には、いつも
名前ちゃんが居た。
学校の教室で初めて会った時から、こうして隣に座って、俺の心臓を好き勝手に掻き乱すこの瞬間まで、ずっと。俺の目は、無意識の内に彼女の姿を追ってしまう。
今はその白い頬が、ほんのりと上気しているように見える。外灯の頼りない光の下で見た時とはまた違う、部屋の暖かい照明に照らされた彼女の肌は、上質なシルクみたいに滑らかだ。
「『コンドームの使用は、一個につき一回限りです。その都度、新しいコンドームをご使用ください』……ふぅん、一回限りなんだね」
独り言のように呟いて、
名前ちゃんはちらりと、俺の顔を見上げた。その瞳には好奇心と、それから……なんだろう、何かを試すような光が宿っている。
やめて。その目で見ないで。
俺の心臓がまた一つ、大きく跳ねた。
「……そりゃ、そうでしょうよ……」
掠れた声で答えるのが精一杯だった。平静を装おうとすればする程、声が上擦る。
名前ちゃんは、俺の反応が可笑しかったのか、小さく噴き出した。
「ふふ。倫くん、顔、また赤くなってる」
「……っ、
名前ちゃんの所為だからな、それ」
もう、何度目だ、このやり取り。
なのに、毎回新鮮に打ちのめされる俺って、一体……。
彼女は悪戯っぽく笑みを深めると、再び説明書きに視線を戻した。
「『この包装に入れたまま、冷暗所に保管してください。また、防虫剤等の揮発性物質と一緒に保管しないでください』……ちゃんと、保管しないとね」
うん、そうだね。保管、大事だね。
って、そうじゃなくて。
なんでそんな、大事な宝物の扱い方を確認するみたいに、真剣な顔で言うんだよ。
俺はもう、羞恥心と得体の知れない期待感とで、頭の中がぐちゃぐちゃだった。さっきまで食べていた美味しい和食の味なんて、とっくにどこかへ消し飛んでいる。ただ、
名前ちゃんの声だけが、やけにクリアに耳に届く。
彼女の唇が、また動く。
「『使用直前に、コンドームを個別包装の端から、傷付けないように慎重に開封し……』」
一瞬、言葉が途切れた。
なんだ? と思って彼女の顔を見ると、
名前ちゃんは僅かに眉を顰め、ふっと息を漏らした。
「……倫くん」
「……な、なに?」
「『先端の精液だまりの空気を抜いてから、勃起したペニスに……』」
そこまで読んだところで、
名前ちゃんはぴたりと口を噤んだ。
そして、ゆっくりと顔を上げて、俺の目を真っ直ぐに見つめた。
彼女の白い頬が、さっきよりも明らかに赤みを増している。耳まで、ほんのりと桜色に染まっているのが見えた。
沈黙。
部屋の中には、壁の時計がカチ、コチ、と時を刻む音と、俺達のやけに大きな心臓の音だけが響いている。
「……っ、」
先に限界を迎えたのは、俺の方だった。
もう無理だ。これ以上、この甘美な拷問に耐えられる自信がない。
「っ、
名前ちゃん、もう、いい……いいから」
思わず、彼女の手から箱を奪い取ろうとして、俺の手が
名前ちゃんの冷たい指先に触れた。びくり、と彼女の肩が小さく震える。
名前ちゃんは、俺の手を避けようとはしなかった。ただ、じっと俺の目を見つめ返してくる。その瞳は潤んでいるようにも見えたし、何かを訴え掛けているようにも見えた。
「……どうして?」
小さな、掠れた声。
「わたし、ちゃんと最後まで読みたい」
「いや、でも、その……」
言葉に詰まる俺を見て、
名前ちゃんはふふ、と力なく笑った。
「……倫くんが、そんな顔をするから」
「俺の所為なの!?」
「うん。……だって、倫くんがあんまり可愛い反応をするから、わたしも……ちょっと恥ずかしくなってしまった」
え。
今、なんて?
名前ちゃんが、恥ずかしいって……?
信じられない言葉に、俺は思わず彼女の顔を凝視した。確かに、いつもは感情の読み難い彼女の瞳が、今は分かり易く揺れている。白い肌も、ほんのりと熱を帯びているように見える。
なんだよ、それ。
反則だろ、そんなの。
俺は手に持っていた箱をローテーブルの上にそっと置いた。もうこれ以上、この箱の文字を目に入れるのは危険だ。俺にとっても、多分、
名前ちゃんにとっても。
「……もう、読まなくていいよ」
俺が言うと、
名前ちゃんはこくりと小さく頷いた。
「……うん」
そして、次の瞬間。
ふわり、と。
名前ちゃんが、俺の肩に頭を預けた。
シャンプーの甘い香りが、今度はもっと直接的に感覚を刺激する。肩に感じる、彼女の髪の柔らかさと、小さな頭の重み。
「……倫くん」
耳元で囁かれる、甘い声。
「……わたし、倫くんの声で聞くのも、ドキドキしたけれど……自分で読むのは、もっと……心臓に悪かったみたい」
そう言って、
名前ちゃんは俺のTシャツの裾を小さく、でも、しっかりと掴んだ。
その仕草が堪らなく愛おしくて、俺は思わず腕を伸ばして、彼女の華奢な肩を抱き寄せていた。
「……お互い様、だな」
俺がそう言うと、
名前ちゃんは肩口でくすくすと笑った。
視線の先には、いつも
名前ちゃんが居た。
そして、これからもきっと、ずっと。
この予測不可能な愛しい人に、俺は振り回され続けるんだろう。
でもまあ、それも悪くない。
いや、寧ろ最高だ。
俺はそっと、
名前ちゃんの髪に鼻を埋めた。
甘い香りに包まれて、さっきまでの緊張が嘘みたいに解けていく。
――ああ、本当に敵わないな、この子には。
心の中で、何度目か分からない降参宣言をしながら、俺は彼女の温もりを確かめるように、ぎゅっと抱き締める力を強めた。ポケットの中のスマホが、もう一度震えた気がしたけれど、今はもうどうでもよかった。