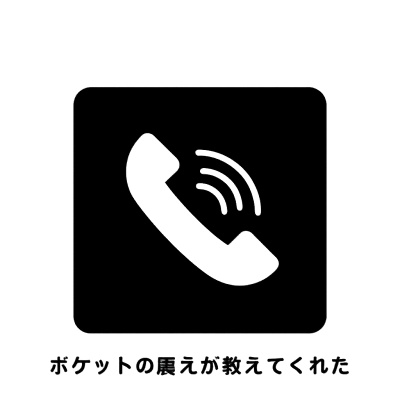ポケットの震えが教えてくれた
∟恋の温度は平熱じゃない。
土曜日の放課後。
汗の匂いが染み付いた練習着を脱ぎ捨て、気怠い熱気が残る部室でざっと身体を拭く。自販機で買った冷たいスポーツドリンクの味気なさが、妙に咽喉に沁みた。湿ったタオルをエナメルバッグに突っ込み、スマホをジャージのポケットに滑り込ませると、俺は重い足取りで出入口へと向かった。
ギィ、と軋む音を立て、重量感がある鉄製のドアを押し開ける。むわりとした生温かい外気が肌に纏わり付く。体育館の熱気とはまた違う、湿気を帯びた夕暮れの空気だ。解放感とも倦怠感ともつかない曖昧な感覚に包まれた瞬間、内懐の中でスマホが小刻みに、自己主張するように震え出した。
ディスプレイに灯った名前を見て、心臓が跳ねた。いや、跳ねたどころじゃない。鷲掴みにされたみたいに、ぎゅっと縮こまる。
【
名前ちゃん】
「……っ、うわ、マジか」
喉の奥から、擦れた声音が漏れ出た。周囲に誰も居ないことを確認し(いや、居ても居なくても関係ないか、今は)、慌てて通話ボタンをタップする。耳に押し当てたスマホの無機質な冷たさが、やけにリアルだ。
「……もしもし」
努めて平静を装う。声、震えてないか? 大丈夫か、俺。
『倫くん』
たった一言。
名前ちゃんの、少し甘くて、耳朶を擽るような声質。
それだけで、俺の表情筋は完全に制御不能に陥った。口角が意志に反して、じわじわと持ち上がっていくのが分かる。
いや、ヤバい。これは本当にヤバい。
ドアを押さえたままの指先まで、じんと熱を持っている。まだ誰にも見られてない。セーフ。セーフだけど、今の俺の顔、多分、相当締まりがない。鏡があったら叩き割りたくなるレベルで、だらしなく顔面崩壊してる。自信ある。
「うん。どした? なんかあった?」
平静、平静。クールな俺を演じろ。
『あのね、
兄貴兄さん、今日は絵本の打ち合わせで遅くなるんだって。だから、もし良かったら、夜ご飯、一緒にどうかなって』
そこで、一瞬の間。電話の向こうで、小さく息を吸う気配がした。
『……わたし、倫くんに逢いたい』
…………。
…………。
…………。
うわ。
無理。
これは反則だろ。
さっき、タオルで身体を拭いた意味、秒で消滅する勢いで、じわじわと汗が噴き出すのを感じる。無意識の内に、履き慣れたスニーカーの爪先で、地面を無意味に蹴っていた。靴裏のアスファルトの感触だけが辛うじて、俺をこの場に繋ぎ止めている。
「うん。行く。直ぐ行く」
一秒も、いや、コンマ一秒も迷いはなかった。
即答。考えるより先に、返事が口を衝いてた。
嬉し過ぎて、足許が覚束ない。地球から数センチ浮いてるんじゃないかってくらい、ふわふわした感覚。間違いなく、今の俺、誰が見ても一目で"彼女からデレられて、頭の中がお花畑になってる彼氏"って顔してる。マジで、スマホの画面がグレアじゃないお陰で、自分の姿が反射しないことに、心の底から安堵した。
待ち合わせ場所に指定されたのは、いつものマンションから少し歩いた所にある、小さな公園だった。大通りに面しているわけでもなく、遊具も錆び付いてて、夜には殆ど人通りがなくなるような立地。こう云う人目を避けた、秘密基地みたいな空間を選ぶ辺りが、如何にも
名前ちゃんらしいなと思う。
西の空には、まだ夕暮れの燃えるような赤色が淡く残っていて、徐々に宵の深い藍色へ溶け込もうとしていた。外灯がぽつりぽつりと点り始め、昼間の喧騒が嘘みたいに静まり返った広場で、ぼんやりとグラデーションを眺めていた、その時だった。
ふわり、と。
夜の帳から滲み出るかのように、白いワンピースを着た
名前ちゃんが現れた。
風が、彼女の艶やかな髪を優しく梳かす。電灯の頼りない光を受けた白い肌は、上質な陶器みたいに滑らかで、儚げで。夜闇に吸い込まれてしまいそうな程の危うい美しさだった。
「倫くん」
名前を呼ばれ、はっと我に返る。
駆け寄ってくる
名前ちゃんの足音は、殆ど聞こえないくらい小さかった。それでも軽いステップの一つひとつが、俺の心臓をダイレクトに揺さぶる。
「よ」
何とか、いつも通りのぶっきら棒なトーンを意識して返したつもりだった。だけど、もうダメだ。顔の筋肉が仕事をしてくれない。緩みっ放しだ。
ぴたり、と目の前で足を止めた
名前ちゃんは、躊躇うことなく手を伸ばし、俺のTシャツの裾を遠慮気味に掴んだ。指先から伝わる、彼女の微かな温かさ。
「……倫くん、熱いね」
「ん。うん。……多分、これ、
名前ちゃんの所為」
自覚はある。電話で声を聞いた瞬間からずっと、俺の体温は真面じゃない。平熱って何だっけ、レベルだ。
俺の言葉に、
名前ちゃんは悪戯っぽく双眸を細め、裾をもう一度、きゅっと小さく引っ張った。そして、ふわりと花が綻ぶように笑った。
もう、マジで。
勘弁してほしい。
可愛い、とか云う次元を超えてる。
「ご飯の前にね、ちょっとだけ、寄ってほしい所があるんだ」
「んー? どこに」
名前ちゃんは少しだけ視線を彷徨わせてから、意を決したように、俺の目を真っ直ぐに見つめた。
「……ドラッグストア」
「……え?」
予想外の単語に間抜けな疑問符が出た。
名前ちゃんは声を潜めながらもはっきりと、俺の耳に届く発音で続けた。
「……倫くんと、使う日の為に……必要なもの、買っておきたいなって」
小声。
なのに、鼓膜を直接殴られたみたいな衝撃。
世界が一瞬、無音になった気がした。
「マジかよ……」
蛍光灯がやけに眩しい、無駄にだだっ広いドラッグストアの通路。俺は或る特定の棚の前で、完全に石化していた。
目の前の陳列棚には、色とりどりのパッケージが、これでもかと主張するように並べられている。
そう、コンドーム。
避妊具、だ。
ピンクとか、ゴールドとか、ブラックとか。やたらと艶っぽいデザインとか、なんかもう効果やら素材やらが細かく書かれたヤツとか。情報量が多過ぎる。
「……」
「……」
隣には、何食わぬ顔、とまではいかないまでも、比較的、澄ました表情を装っている
名前ちゃん。でも、白い耳の先っぽだけが、ほんのりと桜色に染まっているのを、俺は見逃さなかった。
――ダメだ、これは。完全にキャパオーバーだ。
「……マジで、選べねえ……こんなの……」
掠れた声で呟くと、肩を並べる
名前ちゃんが事もなげに言った。
「……倫くんに選んでほしいな」
「俺に選ばせるんだ……この状況で……?」
発音、完全に裏返った。情けない。
一人でこっそり買うならまだしも(いや、それも相当ハードル高いけど)、傍に張本人が居るのだ。この可憐な生き物が。"使う日"の事をちゃんと考えてくれてる本人が、俺の直ぐ横に立って、俺が選ぶのを待っている。
バクバクと暴れ回る心臓を落ち着かせようと、無駄な努力を試みる。指先が冷たくなっているのを感じる。
「……えっと、じゃあ……これとか、
名前ちゃんが好きそうな、なんか、可愛い感じのヤツにする……?」
口走ってから、自分でも何を言っているのか分からなくなった。
「可愛いの、あるの?」
名前ちゃんが小首を傾げ、純粋な瞳で問い掛ける。やめてくれ、その目は。
「え、いや、あの、なんか、パッケージがピンクだし……? イチゴ味とか、そう云うことじゃないよな……? うわもう何言ってんだ俺、マジで……」
顔から火が出る、ってこう云う事を言うんだな。今、俺の顔面、多分、沸騰してる。
そんな俺を見て、
名前ちゃんは遂に堪え切れなくなった様子で、くすくすっと鈴を転がすような声で笑った。
「ふふ、倫くん、可愛い」
「っ、
名前ちゃん……? よくも……言ったな……」
本気でその場に蹲り、火元を覆いたくなる衝動を、なけなしの理性で必死に抑え込む。
ヤバい。
マジで、俺、今夜辺り、心臓発作か何かで死ぬかもしれない。尊死ってヤツ? いや、まだ死ねない。
「……よし、じゃあ、これにしよ」
深呼吸を一回。なるべく冷静な表情、ポーカーフェイスを作って(できてるかは不明)、俺は棚から一つの箱を手に取った。一番シンプルで、一番普通っぽいヤツ。ゴテゴテした装飾も、変な謳い文句も書いてないヤツ。
これなら、多分、大丈夫。……多分。
目的のブツをカゴに入れ、レジに向かう途中、
名前ちゃんがふと足を止めて、日用品の陳列棚を見上げた。
「あ、そうだ。倫くん、夜ご飯、何がいいかな? 冷蔵庫にあるもので作ろうと思うのだけれど」
唐突な話題転換に、一瞬、思考が停止する。先程までの緊張感とのギャップが激し過ぎる。
「え? ああ、夜ご飯……。うーん……」
正直、今の俺の脳内は、さっき選んだ箱のことで八割方埋め尽くされている。食事の内容なんて、一ミリも考えてなかった。
「……
名前ちゃんが作ってくれるものなら、何でも美味いから大丈夫だよ」
完全に思考停止した結果、出てきたのはそんな模範解答みたいな科白だった。いや、本心だけど。
名前ちゃんは、俺の言葉を聞き、嬉しそうに目を細めた。
「ふふ、ありがとう。じゃあ、今夜は和食にしようかな。お魚なら、あったと思うし」
「うん、和食も好き。楽しみにしてる」
その笑顔に、今し方までの緊張が、少しだけ解けるのを感じた。
無事に(?)レジを通過し、控え目なデザインのビニール袋を片手に、俺達はドラッグストアを後にした。目的のマンションへと続く夜道を二人で歩く。
ひんやりとした夜風が、火照った頬を撫でていくのが心地良い。
ふわり、と風が吹く度に、隣に並ぶ
名前ちゃんの髪がさらさらと流れ、シャンプーの甘くて清潔な香りが微かに鼻先を掠めた。
「倫くん、顔、まだ赤いよ」
「……赤くもなるだろ、そりゃ……あんなことがあったら」
「ふふ」
擽ったくも、全てを包み込んでくれる優しい微笑み。
傍に居るだけで、心臓が煩くてどうにかなりそうだ。
でも同時に、今の俺は間違いなく、この世界で一番幸せな気分だった。
ポケットの中のスマホが、また謙虚に震えた。
チラリと画面に視線を落とす。そこには、さっきの出来事の続きみたいに、
名前ちゃんからのメッセージが表示されていた。
【
名前ちゃん:倫くん、大好き】
ぶはっ、と変な息が漏れた。
ダメだ。もう完全に表情筋が言うことを聞かない。勝手に、にやけてしまう。
これ、多分、俺の一生治らない病気だ。
でもまあ、別にいいか。
だって、きっと、今日の夜も、明日も、明後日も。
これから先、いつまでも、俺はこの子の一挙手一投足に、一言一句に振り回されて、ニヤニヤさせられて生きていくんだろう。
嬉しくて、愛しくて、どうしようもない、って顔で。
ずっと、こうして隣を歩いていくんだ。
――
名前ちゃんと二人で。掛け替えのない時間を重ねながら。