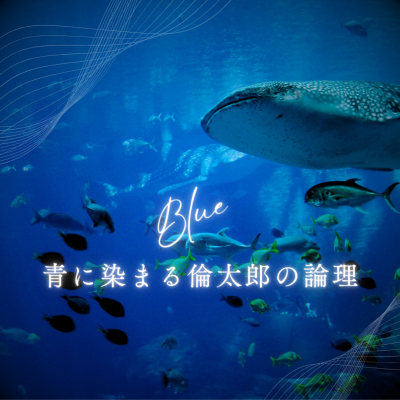青に染まる倫太郎の論理
∟青い世界で、名前の感性に侵食されていく。
俺、角名倫太郎は、基本的に平穏を愛している。感情の波は凪いでいる方がいいし、心拍数は一定に保たれている方が楽だ。だから、彼女、
苗字名前からの「水の中を歩いてみたい」と云う、凡そ現実的ではない願望を聞いた時も、俺は冷静に代替案を提示した。
「……じゃあ、水族館行こっか」
「うん。それがいい」
あっさりと頷く彼女に、些か拍子抜けしながらも、俺達は日曜日に海沿いの大きな水族館へ行く約束をした。
そして、当日。待ち合わせ場所に現れた
名前は普段と比べ、少しだけ雰囲気が違った。ふわりとした白いワンピースに、髪には小さな真珠の髪飾り。普段のミステリアスな印象に、どこか柔らかな光が差したようなその姿に、俺の心臓は簡単に予定外の速さで脈打ち始める。
(うわ。マジでヤバい……)
内心の動揺を悟られまいと、俺はいつも通りの気怠げな表情を貼り付けた。
「……おはよ、
名前ちゃん」
「お早う、倫くん。待った?」
「んーん、今来たとこ」
嘘だ。三十分前から、近くのコンビニで時間を潰していた。彼女を待たせるなんて選択肢は、俺の中には存在しない。
館内に足を踏み入れると、ひんやりとした空気が肌を撫でた。外の喧騒が嘘のように遠ざかり、辺りを満たすのは水の匂いと、静かな騒めきだけ。頭上から降り注ぐ青い光が、俺達の影を長く伸ばしている。
「わぁ……」
隣で、
名前が小さく感嘆の声を漏らした。その瞳は、目の前の巨大なパノラマ水槽に釘付けになっている。夜の海を切り取ったかのような深い蒼の中を、大小様々な魚達が悠然と泳ぎ回っていた。いつもは静謐な水面染みた彼女の双眸が、今は好奇心の色を映し、きらきらと揺らめいている。
(……撮っとこ)
俺は自然な動作でスマホを取り出し、水中に見入る彼女の横顔にレンズを向けた。瑠璃色の光に縁取られた輪郭、微かに開かれた薄桃色の唇、長い睫毛が落とす仄かな影。その全てが、この世のものとは思えない程に美しくて、俺はシャッターを切る指先に、知らず力が籠もるのを感じた。
「倫くん、見て。あのエイ、笑っているみたい」
名前が指差す方を眺めると、確かに白い腹を見せて遊泳するエイの口許が、にっこりと弧を描いているように見えた。
「……ホントだ。アランくんみたい」
「アランくん?」
「ん。ウチの先輩。いつも豪快に笑うから」
「ふふ、そうなんだね。面白い」
名前は楽しそうに笑って、俺の服の裾をきゅ、と掴んだ。その無意識の仕草に、心臓がまた一つ、大きく跳ねる。やめろ、そう云う不意打ちは。俺の省エネモードがオーバーヒートする。
俺達は迷路のような順路をゆっくりと進んだ。イワシの群れが銀色の竜巻を描く水槽の前では、二人して言葉もなく立ち尽くした。光を浴びた鱗が一斉に煌めく光景は、まるで銀河の誕生を見ているようで、圧巻だった。
「凄いね……。一匹一匹は小さいのに、集まると、こんなに大きな流れになるんだ」
「……うん。侑と治みたい」
「侑と治?」
「双子のチームメイト。いつも二人で騒がしい流れ作ってるから」
「……倫くんの例えは、全部、バレー部の人なんだね」
名前がくすくすと笑う。俺は少し気まずくなって、「……まあ、毎日見てるから」とぶっきら棒に返した。
次に辿り着いたのは、無数のクラゲが漂う、幻想的な空間だった。円柱の水槽の中で、色とりどりの照明に浮かび上がるクラゲ達が、音楽に合わせて踊るように、傘を開いたり閉じたりしている。
「綺麗……」
名前は硝子の表面に額をくっ付けるようにして、その光景に見入っていた。
「この子達、脳も心臓もないのに、こうして生きて泳いでいるなんて、不思議だね。哲学を感じる」
(出たよ、
名前ちゃんワールド)
俺は内心で呟きながら、そんな彼女の隣に並んだ。水槽のガラスに、俺達の姿がぼんやりと映っている。ゆらゆらと漂うクラゲと、それを見つめる二人。いつしか自分達まで、この青い世界に溶け込んでしまったかのような、不思議な感覚に陥った。
「ねぇ、倫くん」
不意に、
名前が俺の方を振り向いた。間近に在る彼女の瞳に、真っ直ぐに射抜かれる。
「あのね、あそこに居る魚」
名前が指差したのは、水槽の隅でじっとしている、一匹の小さな熱帯魚だった。鮮やかで、どこか深みのある緑色の鱗を持っている。
「倫くんの眸の色に、よく似ているね。光が当たると、きらきらして見えるところも」
その言葉は、何の屈託もなく放たれた、只の感想だったのだろう。だけど、俺の心臓には、北さんの正論パンチ以上の威力で突き刺さった。
「……っ、」
息が詰まる。顔面に、じわりと熱が集まるのが分かった。
「……そりゃ、どうも」
平静を装って返すのが精一杯だった。頼むから、こっちを見ないでくれ。今の俺、多分、めちゃくちゃ締まりのない顔になってる。
名前は、俺の動揺に気づいているのかいないのか、ふわりと微笑むと、再び水槽に視線を戻した。その横顔を盗み見ながら、俺は必死に高鳴る鼓動を鎮めようと試みる。
(アチャ……。もう無理、降参)
彼女の前では、俺の平静なんて、水に浮かべた木の葉のように脆い。
順路も終わりに近づき、俺達は一番奥にある深海のエリアに辿り着いた。そこは、今まで以上に照明が落とされ、静寂に包まれていた。訪れる人も疎らで、聞こえるのは空調の低い唸りと、自分達の足音だけ。
海水の中では、タカアシガニが長い脚をゆっくりと動かし、発光する生物達が青白い光を点滅させている。現実離れした光景は、まるで宇宙空間に迷い込んだかのようだった。
「……ここが、地球の底なんだね」
名前が囁くように言った。その声が、静寂に溶けていく。
彼女は一つの水槽の前で足を止め、ガラスに映る二人の姿をじっと見つめていた。
「こうしていると、わたし達も水の中に居るみたい。光も音も届かない、静かな場所に」
その言葉と、マリンアクアの青い光に照らされた、儚げな横顔に、俺の中で何かの糸がぷつりと切れる音がした。さっきからずっと、ギリギリの所で保っていた理性のダムが決壊する。
「……
名前ちゃん」
俺は掠れた声で彼女の名前を呼び、その細い腕を引いた。
「え……、倫く……?」
戸惑う彼女を、近くにあった太い柱の影へと引き寄せる。壁に背中を預ける形になった
名前が、俺を不安気に見上げていた。潤んだ瞳が、暗がりの中で揺れている。
もう、我慢できなかった。
「……ちょっと、静かにして」
囁きながら、俺は彼女の顔に自分のそれを近づけた。抵抗する間も与えず、薄桃色の、少しだけ冷たい唇に、自分の口唇を重ねる。
触れるだけの、優しいキス。それでも、心臓は全力疾走した後のように煩く鳴り響いていた。驚きに見開かれた
名前の瞳が、やがてゆるりと閉じられる。俺のTシャツの裾を掴む彼女の指先に、きゅっと力が籠もるのが分かった。
どれくらいの時間、そうしていただろう。ほんの数秒だったかもしれないし、もっとずっと長かったのかもしれない。ゆっくりと唇を離せば、気まずさと甘さが入り混じった、濃密な空気が二人を包んだ。
目の前の
名前は白い肌を朱に染め、俯いてしまっている。その反応が堪らなく愛おしいのと同時に、自分の顔も、きっと彼女以上に真っ赤になっているだろうと気づき、羞恥心でどうにかなりそうだった。
「…………今の、なし」
照れ隠しの、我ながら情けない言葉が口から滑り出る。すると、伏し目がちだった
名前が、そろりと視線を上げた。
「……どうして?」
僅かに首を傾げ、潤んだ眼差しで、俺を見つめる。
その破壊力抜群の仕草に、俺は完全にノックアウトされた。
(ひぃ~……)
脳内で悲鳴が上がる。これはダメだ。絶対に抗えない。なんだ、この生き物は。可愛い。可愛過ぎる。無理。
俺は観念して、大きく一つ、溜め息をついた。照れを誤魔化すように、
名前の小さな手指を優しく握り込む。
「……なしじゃ、ない」
「……うん」
「……帰りに、写真撮ろ。記念」
「……うん」
こくりと頷く
名前の耳が赤くなっているのを見て、俺は漸く、少しだけ笑うことができた。
このどうしようもない引力に、俺はきっと、一生敵わない。
水槽越しの魚達に見守られながら、俺は彼女の手を引いて、もう一度、光の中へと歩き出した。空の写真立てに収まる、たった一枚の想い出を作る為に。