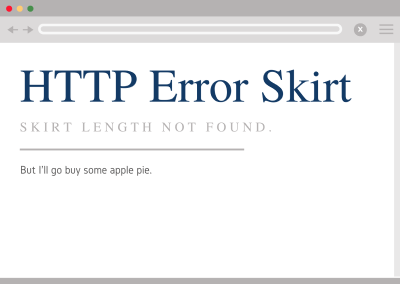視覚認識エラー:彼女のスカート | Title:短いスカート
あの、ワケの分からない夢の残滓が、数日経っても脳の片隅にこびり付いていた。
湿った空気と、苔生した石畳の冷たい感触。音駒の体育館が、何故か薄暗い洞窟に変貌していて、床には体操服を着たウーパールーパー達が、一糸乱れぬ動きでストレッチを繰り返している。ピンク色の柔らかな体が、妙な律動感を以って伸び縮みする光景は、何度思い出してもシュールとしか言いようがない。
そして、洞窟の奥には巨大なシュウマイが鳥居代わりに聳え立つ神社。祭壇には、更に巨大な、湯気を立てているかのようなシュウマイが鎮座し、その脇には『猫又監督に捧ぐ』と刻まれた石碑。極め付けは、そこに奉納品のように置かれていた、1/8スケールの、どこからどう見ても不機嫌そうな顔をした"おれ"のフィギュア。
――まあ、夢なんだけど。
我ながら、意味不明な夢を見たものだと思う。最近、新しい謎解きゲームにハマっている所為かもしれない。
そんな奇妙な夢の記憶が、まだ薄らと残る数日後の朝、スマホの通知音で目が覚めた。トークアプリのポップアップには、
名前からのメッセージ。『今日の放課後、練習を見学しに行ってもいい?』と、それだけ。
布団の中でぬくぬくと温もりを堪能しながら、ぼんやりとした頭で既読を付け、『うん』とだけ返信して、再び意識を手放した。――そして、案の定、寝過ごした。保険のけたたましいアラーム音で飛び起き、慌てて身支度を整えた。朝練にはギリギリ間に合ったものの、芸術的とすら言える寝癖は直す時間もなく、視界の端には夢の残り香がチラついていて、頭の中はずっとふわふわしたままだった。
放課後。
蒸し暑い体育館の中、基礎練習の合間に給水ボトルに口を付けた、その時だった。
「……来た」
誰かが呟いたのか、それとも、おれの心の声だったのか。体育館の重い扉が、ギィ、と独特の音を立てて開いた瞬間、ガタン、と軽い衝撃音がフロアに響き、そこに立つ
名前の姿がスローモーションのように、はっきりと目に飛び込んできた。
彼女の艶やかな髪は、いつもより丁寧にブローされているのだろうか、窓から差し込む西日が反射して、天使の輪のように柔らかい光を放っている。陶器のように白い肌、その上に浮かぶ薄桃色の唇が微かに動き、「研磨」と、おれの名前を呼ぶ。その声は、体育館に響き渡るバレーボールの鋭いスパイク音や、シューズが床を擦る摩擦音よりも先に、鼓膜を通り越して、直接、心臓に届いたような気がした。
――あ、スカート、短い。
意識していたワケじゃない。本当に。でも、おれの視線は引力に引かれるように、彼女のスカートの裾へと吸い寄せられていた。
態とじゃない。絶対に。でも、無意識の内に、いつもとの数センチの違いを感じ取ってしまったおれの脳は、きっと、クロがよく言う「思春期の本能」とかいう、よく分からないけれど、抗えない何かの所為で、強制的にスリープモードから叩き起こされていた。ゲームで言えば、隠しイベントの発生条件を満たしてしまったような、そんな感じ。
(……なんで、そんなに短いんだろう)
名前の制服のスカートは元々、他の女子生徒達よりも、少しだけ丈が短い。それは知っていた。けれど、今は更にそこから数センチ分、世界が、いや、おれの視界が劇的に変わっていた。
細くて、でも、しなやかなラインが縁取る、華奢な脚。彼女が体育館の入り口から数歩、こちらへ近づく度に、短いスカートの裾が意志を持っているかのように、ほんの少しだけ左右に揺れる。もし、不意に強い風でも吹こうものなら、その不安定な領域の向こう側が、いとも簡単に見えてしまうのではないか。そんな、いけない想像が頭を過り、目が離せなくなった。心臓が、さっきまでの練習よりも、ずっと速いリズムを刻み始めている。
「あのね、今日はちょっと、実験してみたくて」
言って、
名前は悪戯っぽく、にこりと微笑む。それは、難しいゲームの攻略法を見つけた時のような、或いは新しいアイテムを手に入れた時のような、そんな種類の笑顔。夜の海の色を湛えた彼女の瞳の奥が、きらりと意味あり気に光るのを、おれは見逃さなかった。
「……実験?」
おれは、なんとか平静を装って聞き返した。声が、少し上擦っていなかっただろうか。
「うん。わたしがいつもよりスカートを短くしてきたら、研磨はどれくらい目を逸らさずにいられるのかなって、思って」
(………………)
おれは一瞬、息が止まった。思考も。
やっぱり、意図的だったのか。今日に限って、彼女の脚がやけに目に焼き付くような気がしたのは、おれの視神経がおかしくなった所為でも、あの変な夢の続きを見ているワケでもなかった。これは、
名前による、明確な"攻撃"だ。
「……分かんないけど、それ、何の意味があるの? そんなことして」
おれの言葉は、自分でも驚く程に弱々しく、そして、少しだけ非難の色を含んでいたかもしれない。
「あるよ、勿論。恋人の反応を観察するのって、楽しいでしょう? 研磨がゲームで、新しいキャラクターの動きを研究するみたいに」
無邪気な声色で、でも、その言葉の端々には、明らかに挑発的な響きが隠されている。
名前は体育館の壁際に立ったまま、僅かに首を傾げ、おれを見上げるようにして言う。ボールの音も、チームメイトの声も遠退き、体育館の空気が一瞬でピンと張り詰めたような錯覚に陥った。
「でも……あんまり、他の人に見られたくないって、思ってるんでしょ? そういうの」
おれの声は確実に掠れていた。喉が渇く。
「うん、そうかもしれない。それは本当。でもね、研磨になら、見られたいとも思っているよ」
そう言って、
名前は猫が獲物に忍び寄るような、しなやかな動きで、ぐっと一歩、おれに近づいた。
たったそれだけの、ほんの僅かな動作で、短いスカートの裾がひらりと軽やかに舞った。その瞬間、再び体育館の空気が変わった気がした。質量を持った熱のようなものが顔に集まる。多分、今、おれの顔は茹でダコみたいに真っ赤になっているに違いない。
「研磨って、わたしのこと……どれくらい、好き?」
不意打ちのような質問。でも、その声はどこまでも真剣で、おれの答えを待っている。
「……物凄く。カンストするくらい」
迷いはなかった。即答だった。それは、どんな単純なパズルを解くよりも、ずっと簡単な答え。
名前がふわりと微笑んだ。満足そうに、そして、おれの答えを確かめるように小さく頷く。そして、おれの着ている練習着の裾を、細い指先できゅっと掴んだ。そのまま、くるりと回り込む。その動きに合わせて、彼女のスカートの裾が、ふわり、ふわりと揺れて、おれの膝に、柔らかな感触が触れた気がした。
「良かった。わたしも、研磨のこと、物凄く好き。だから……つい、揶揄ってみたくなってしまうんだ。ごめんね」
「……今日の
名前、攻撃的だね。いつものパッシブスキルはどうしたの」
おれは、なんとか軽口を叩こうとしたけれど、声はまだ震えていた。
「研磨が、可愛いからだよ」
その言葉は、トドメの一撃だった。耳まで、いや、首筋まで熱くなるのが分かった。
おれはもう、
名前の顔を正面から見ることができなくて、思わず目を逸らして、体育館の床に視線を落とした。そこには、あの夢で見たウーパールーパーの幻影が、まだ薄っすらと残っているような気がした。いや、もう夢はとっくに終わっている。ここは地下迷宮じゃないし、巨大なシュウマイ神社もない。今、ここに居るのは、バレー部の皆と、いつもよりちょっとだけ短いスカートを穿いて、おれを翻弄して楽しんでいる
名前と、そのことに、思春期のどうしようもない感情をグラつかせている――おれだけだ。
「……ねぇ、研磨。今日は、アップルパイを買って帰らない? 新しいお店を見つけたんだ」
「……うん、いいけど」
おれがそう答えると、
名前がふっと顔を近づけて、おれの横顔を覗き込んできた。悪戯が成功した子供のような、満足気な笑みを浮かべて。深い色の瞳と、視線が絡み合う。思わず反射的に一歩、後退ってしまった。
でも、その瞬間だった。
「……あ」
体育館の扉が、さっきから開いたままだった。そして、タイミングを計ったかのように、サーッと、やや強い風が吹き込んだ。
名前の短いスカートが、ふわりと、蝶が羽ばたくように宙に浮いた。そして、おれの視界の端で、ほんの一瞬、ぎりぎりのラインが、白い何かが、掠めた。
――見た、かも。いや、見てしまった、絶対に。
「……研磨、今の、見た?」
名前の声は、仄かに期待するような響きを帯びていた。
「…………見てない。何も」
おれは頑なに否定した。心臓は警報みたいに鳴り響いているけれど。
「見たよね」
名前は確信したように言った。
「見てないってば……」
「嘘だよ」
名前が少しだけ口を尖らせて、おれをじっと見つめてくる。おれは俯いたまま、返す言葉を失って、体育館の隅の方へ、敵から逃げるように、そろそろと移動しようとした。これ以上、彼女の術中にハマって堪るもんか。
「やっぱり、可愛い」
背後から聞こえてきた
名前の声は、さっきよりもずっと小さく、そして、何よりも優しかった。
そんな風に言われたら、おれはもう絶対に勝てない。降参するしかない。
――本当に、ズルいよ、
名前は。
短いスカートなんか、反則だ。チートアイテムと同じくらい、ズルい。
でも、まあ……
名前が、あんな風に楽しそうに笑っているなら、それもまた、悪くないのかもしれない。
おれは、まだ熱い顔を隠すように俯きながら、心の中で小さく溜め息をついた。今日の帰り道はきっと、アップルパイがいつもより甘く感じるんだろうな、なんてことを、ぼんやりと考えていた。