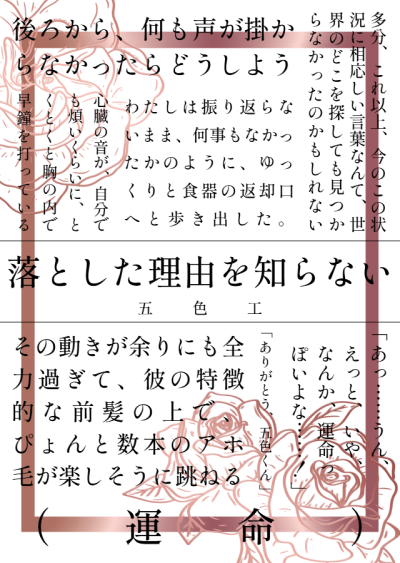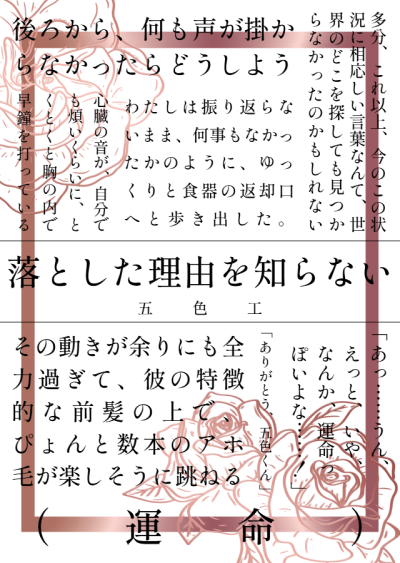落とした理由を知らない | Title:運命だよね?
週の真ん中、水曜日。
朝から降り続いていた細やかな雨は、昼過ぎには気紛れな子供が飽きたかのようにぴたりと止んで、校庭では幾つもの水溜まりが鏡のように空を映していた。雲間から覗く太陽の光が、その水鏡をきらきらと照らし、洗い立ての世界みたいに何もかもが清々しく輝いて見える。
五色くんが、わたしのことを見ている――
その熱を帯びた視線に、わたしはもう随分と前から気づいていた。教室で、廊下で、そして、この賑やかな食堂でも。向日葵が太陽を追うように、彼の真っ直ぐな眼差しは、いつもわたしを捉えている。
それでも、わたしはまだ一度も、彼の名前を口にしたことがなかった。この心地良いけれど、どこか不安定な距離感が、些細なことで薄氷のように壊れてしまうのが怖かったのだ。
けれど、昨日。
あの、牛乳の一件。盛大に咽て、顔を真っ赤にしながらも、必死に笑顔を作ろうとしていた彼の姿を思い出すと、胸の奥が擽ったいような、それでいて、ほんの少し切ないような、不思議な感覚に包まれる。あの不器用な一生懸命さが、わたしの心の扉を僅かに抉じ開けたのかもしれない。
だから、わたしは一寸だけ、勇気を出すことにしたのだ。ほんの、小さな一歩を。
昼休み。わたしは今日も一人、いつもの窓際の席に腰を下ろし、買ったばかりの惣菜パンとコーンポタージュ、保温ボトルに入れてきた温かい紅茶で軽い昼食を取っていた。食堂の喧噪は相変わらずだけれど、雨上がりの所為か、窓から差し込む光は常よりも柔らかく、穏やかな空気が流れているように感じられた。
食後、わたしはコップに残った紅茶を飲み干すと、徐に立ち上がった。そして、スカートのポケットから取り出した薔薇の刺繍のハンカチを、何でもないことのように、持った指ごと机の端にそっと引っ掛けるようにして――"うっかり"落とした。
パサリ、と乾いた、けれど、確かな音を立てて、白いハンカチが床に舞い落ちる。
わたしは振り返らないまま、何事もなかったかのように、ゆっくりと食器の返却口へと歩き出した。
心臓の音が、自分でも煩いくらいに、とくとくと胸の内で早鐘を打っている。オーケストラのティンパニがクライマックスを告げるみたいに。
後ろから、何も声が掛からなかったらどうしよう。
誰も拾ってくれなかったら。
それどころか、気づかれさえしなかったら。
まさかとは思うけれど、このまま清掃の人に持っていかれてしまったら――ううん、流石に、それは考え過ぎだと思いたい。母が選んでくれた、大切なハンカチなのだから。
一歩。また一歩。三歩。
……来ない。
背中に感じる筈の視線も、呼び止める声も、まだない。
そもそも、彼はこの食堂に居るのだろうか? きちんと確認していなかった。なんて間の抜けたことをしてしまったのだろう。でも、普段の彼なら、この時間は大体――
「……これ、落としたよ」
その声に、わたしはぴたりと足を止めた。
聞き慣れていない筈なのに、どうしてだろう、鼓膜が、いや、もっと奥深くの魂のようなものが、その声を確かに記憶していた。何度も、何度も、心の中で想像していた、少し低くて、どこか不器用な響きを持つ少年の声。
ゆっくりと振り返ると、そこには彼――五色くんが立っていた。その手には、わたしの白いハンカチが。ぎこちないけれど、壊れ物を扱うかのように両手で持ち、大切な薔薇の刺繍の部分には指が触れないように、細心の注意を払っているその手つきに、胸の奥がぎゅうっと締め付けられるような感覚を覚えた。
「ありがとう、五色くん」
わたしは言った。
昨日、眠りに就く前に、心の中で幾度も予行練習した通りに。
声のトーンも、目線の高さも、できるだけ自然に、優雅に見えるように。
けれど、その言葉を発した瞬間、彼の耳朶までもが見る見るうちに真っ赤に染まっていくのを見て、ああ、自然体でいるなんて、到底無理な相談だったのだと悟らざるを得なかった。だって、彼のこの反応は、余りにも――
「あっ……うん、えっと、いや、なんか、運命っぽいよな……!」
彼はわたしの手元にハンカチを慌てて差し出しながら、そんな言葉を、試合中の咄嗟の判断で叫ぶみたいに、勢いよく吐き出した。
(運命)
どうして、そこで、そんな大袈裟な言葉を選ぶのだろう。思わず、ほんの少しだけ吹き出してしまいそうになる。けれど――
不思議と、その言葉はすとんと胸に落ちてきた。
多分、これ以上、今のこの状況に相応しい言葉なんて、世界のどこを探しても見つからなかったのかもしれない。
「……うん、運命……かもしれないね」
わたしは微笑んで、五色くんからハンカチを受け取った。指先がほんの僅かに触れ合う。
目が合ったまま、彼は固まっている。突然、フリーズしてしまったパソコンの画面みたいに、全く微動だにしない。その大きな瞳が驚きと、それから、僅かな戸惑いと、隠し切れない喜びの色を映して、わたしをじっと見つめている。
その様子が何だかとても可笑しくて、でも、ちゃんと心の底から愛おしいと感じた。
わたし達はまだ、きっと何も知らない。
こうして名前を呼び合うことの本当の意味も、視線を交わすことの重さも、ましてや、触れることのその先に広がる世界のことも。
それでも、こんな風に、まるで遠い星々が引かれ合うように、世界の端と端が、ふとした拍子に重なり合う瞬間があるのなら――
「今度、良かったら……一緒に、帰らない?」
わたしがそう口にすると、五色くんは大きく目を見開いたまま、次の瞬間、バネ仕掛けの人形みたいに勢いよく頷いた。その動きが余りにも全力過ぎて、彼の特徴的な前髪の上で、ぴょんと数本のアホ毛が楽しそうに跳ねる。
「うん! あ、あの……はいっ!」
喜びと緊張の入り混じった声が、少しだけ裏返る。
そして、言葉に詰まったのか、こほん、と小さな咳払いを一つした。
……多分、また牛乳を飲んだ直後だったのだろう。
先日、あれだけ盛大に咽せていたというのに、本当に懲りない人。
でも、そんなところも、五色くんらしいのかもしれない。
――運命っぽい。
なんて、笑って言ってしまえるような、ささやかな奇跡が、今日という、ただの水曜日を、少しだけ特別な色に染めてくれたような気がした。
わたしのハンカチの薔薇が、本当にふわりと香り立つみたいに、甘やかな予感が胸いっぱいに広がっていく。
次に会う時、わたしはどんな顔をして、どんな言葉を交わすのだろう。
そのことを考えると、またちょっぴり、心臓が騒がしくなるのだった。