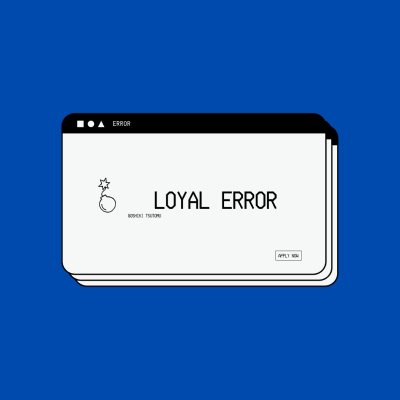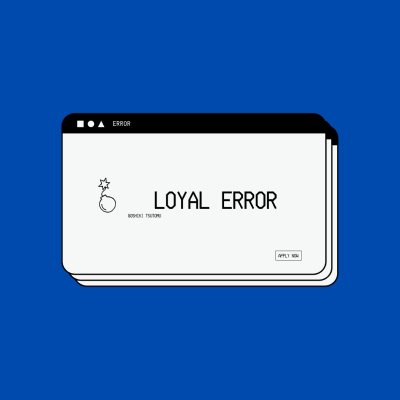ロイヤル・エラー
∟青い宝物を温存した結果、俺が晒したのは自尊心の全裸。
眠りに落ちる寸前、意識が水底へと沈んでいくような微睡みの中で、俺は時々、あり得るかもしれない未来を夢想する。それは大抵、牛島さんからエースの座を奪い取る輝かしい勝利の光景か、或いは、
名前とのまだ見ぬ未来を描いた、甘やかな幻想だ。
だけど、今夜、俺の意識が迷い込んだのは、そんな輝かしい場所ではなかった。
それは地獄の釜の蓋が開く、ほんの数週間前の、あの朝だった。
白鳥沢の寮、その一室。俺は絶望の淵に立っていた。
洗濯の失敗。空っぽのチェスト。そして、クローゼットの棚の上で、聖遺物のように静かな光を放つ、
名前からの贈り物。あの鮮烈なロイヤルブルー。
夢の中の俺は、現実の俺よりも頑固で、その上、愚かだったらしい。
「これは……! これは、
名前との誓いの証。俺が日本一のスパイカーになる、その特別な瞬間の為の……! こんな、ただの洗濯をしくじっただけの日に、穿いていい筈がない!」
誰に聞かせるでもない決意を叫び、俺は小箱の蓋を固く閉じた。そして、覚悟を決めた。そうだ、選択肢は、まだ一つだけ残されている。
――ノーパンで、一日を過ごす。
誰にもバレなければ、問題はない。ズボンさえ穿いていれば、その内側で何が起きていようと、誰にも分かりはしないのだ。俺は自分にそう強く言い聞かせ、いつも通りを装って、部屋を出た。
その決断が、全ての過ちの始まりだった。
朝のランニング。風が、やけに生々しく肌を撫でていく。布一枚、隔てていないだけで、世界はこんなにも無防備に感じられるものなのか。落ち着かない。スースーして、どうにも足の運びがぎこちない。
授業中。硬い木の椅子に腰を下ろす度、その感触がダイレクトに伝わり、背筋に冷たいものが走る。少しでも姿勢を崩せば、ズボンのチャックの隙間から、何かが「こんにちは」してしまうのではないか。そんな馬鹿げた妄想に囚われ、俺は黒板の文字の半分も頭に入れることができなかった。
そして、運命の放課後。蒸し暑い体育館の熱気が、常よりも肌に纏わり付くように感じられた。
「五色、レシーブ練、入るぞ」
「は、はい!」
白布さんの声に、俺はいつもより、半音ズレたような返事をした。フロアに滑り込むのが、怖い。床の冷たさと硬さ、摩擦熱を想像しただけで、全身の毛が逆立つ。案の定、俺の動きは精彩を欠いていた。
「おい、五色! 腰が高いぞ!」
「足が動いてねぇ!」
先輩達の叱責が、ぐさぐさと胸に突き刺さる。違う、そうじゃないんだ。俺は、俺の、この、どうしようもなく心許ない下半身の所為で……!
言い訳もできず、ただ歯を食い縛る。そして、地獄の時間は、スパイク練習でクライマックスを迎えた。
「五色、ラスト!」
白布さんの声。トスが上がる。いつもなら、全身の細胞が歓喜する瞬間だ。だけど、今の俺には、その跳躍さえも恐怖だった。踏み切り、宙を舞う。全身のバネを使い切る、その刹那。
ビリッ、と。
リアルと同じ、布が裂ける音が、やけに明瞭に体育館に響いた。
一瞬の静寂。
でも、その後に続いたのは、あの時のような笑い声ではなかった。シン、と水を打ったような沈黙の中、誰かが息を呑む音と、呆れたような、或いは憐れむような視線が、槍となって、俺の背中に突き刺さる。
「……おい、五色」
白布さんの声は、現実の時よりも数段低く、温度がなかった。
「はい! 今のスパイク、どうでしたか!」
夢の中の俺は、まだ悲劇に気づかず、虚勢を張る。その言葉が、更に場の空気を氷点下へと引き摺り下ろした。
「いや、そうじゃなくて。お前、ケツ」
「ケツ、ですか?」
きょとん、と首を傾げ、俺は自分の背後に手をやった。そして、触れてしまった。布がない、と云う騒ぎどころではない。裂けたハーフパンツの隙間から、俺の肌が、直接、体育館の空気に晒されている、その事実に。
血の気が、サーッと引いていく。
現実の時、あの派手なパンツは、先輩達にとって格好の"笑いの的"になった。だけど、今は違う。そこには笑いの要素など、一片も存在しない。在るのはただ、理解不能な行動を取った後輩への困惑と、生物として、余りに無防備な姿を晒した人間への、どうしようもない憐憫の情だけだ。
「……マジかよ」
「いや、なんで……?」
川西さんの呟きも、天童さんの困惑の声も、全てがスローモーションで聞こえる。誰も笑わない。誰も野次を飛ばさない。その沈黙が、何よりも雄弁に、俺の愚かさを断罪していた。
白鳥沢の次期エース。その看板を背負う男が、体育館のど真ん中で、尻を丸出しにしている。こんな、喜劇にも悲劇にも成り切れない、只々惨めで、みっともない光景があるだろうか。
現実では、この絶望の淵から、女神が俺を救い上げてくれた。
だけど、夢は非情だ。
ギャラリーに目をやっても、そこに
名前の姿はない。彼女は、この地獄には居ない。その事実に、ほんの少しだけ安堵している自分が、俺を更に惨めにさせた。
「……五色、取り敢えず、これ着てろ」
見兼ねた山形さんが、自分のジャージを無言で投げて寄越した。床に落ちたそれを拾い上げる指が、屈辱に震える。腰に巻き付ける間も、突き刺さる視線は和らがない。それは好奇ではなく、純粋な「なんで、こいつはこんなことになってるんだ?」と云う、問い掛けの視線だった。
誰にも、言い訳ができない。
洗濯を失敗したから、ノーパンで来ました、などと。そんな間抜けな理由、俺のプライドが許さない。
俺は誰にも救われないまま、ただ一人、体育館と云う名の処刑台の上で、立ち尽くしていた。
「――――っ、うわあああああっ!」
絶叫と共に、俺は勢いよく身を起こした。
心臓が警鐘のように、激しく脈打っている。全身は冷や汗でぐっしょりと濡れ、寝間着が肌に張り付いて不快だった。ぜえ、ぜえ、と荒い呼吸を繰り返しながら、俺は恐る恐る、自分の下半身に手をやった。
そこには、使い慣れたコットンの、確かな感触があった。
「……はぁ、夢、か……」
安堵の息を吐き出した、その時。
隣で眠っていた筈の気配が、小さく身じろいだ。
「……工くん?」
掠れているけれど、聞き間違えるわけがない、愛しい声。
名前が、ゆっくりと身体を起こした。月明かりが窓から差し込み、彼女の輪郭を淡く縁取っている。その静かな双眸が、心配そうに俺を捉えていた。
「どうしたの。酷く、魘されていたよ」
「……
先頭文字、
名前……」
彼女の存在を認識した瞬間、悪夢の残滓が霧散していく。体育館の冷たい床の感触も、先輩達の憐れむような視線も、全てが遠ざかり、代わりに、
名前の体温と、彼女の部屋の甘い匂いが、俺の五感を満たしていく。
「悪い、夢を見ただけだ。なんでもない」
夢の内容は、口にできる筈もなかった。あんな惨めな姿を、彼女に知られたくはない。俺がそう返して笑おうとすると、
名前は何も言わずに、そっと手を伸ばした。その白い指先が、俺の額に滲んだ汗を優しく拭う。
「……そう」
名前は深く追及せず、ただ静かに頷いた。そして、今度は両腕を差し出すと、俺の背中に回し、ぎゅっと抱き締めてくれた。華奢な身体のどこに、こんな力があるのだろう。彼女の温もりが、冷え切っていた俺の心臓を、ゆっくりと溶かしていく。
「大丈夫。わたしが居るよ」
耳元で囁かれた言葉が、まるで魔法のように、俺の心を鎮めていく。
そうだ。俺はあの時、愚かではあったけど、間違った選択はしなかった。
名前がくれた、あの青い宝物を身に着けることを選んだ。その結果、俺は笑い者にはなったが、憐れみの対象にはならなかった。そして何より、
名前が女神のように現れて、俺を救ってくれた。
名前の独占欲が、彼女の"好き"が、結果的に、俺のどうしようもないプライドを守ってくれたのだ。
「……
名前」
「なあに、工くん」
「……
名前が居てくれて、良かった」
絞り出した声は、まだ少し震えていた。
だけど、それは紛れもない、俺の本心だった。
抱き締める腕に、僅かに力が籠もる。
名前は、俺の胸に頬を埋めたまま、くぐもった声で答えた。
「うん。わたしも、工くんが居てくれて、嬉しいよ」
俺は、このどうしようもなく愛しくて、敵わない恋人を、強く抱き締め返した。
胡散臭い恋愛指南書なんて、やっぱり必要ない。
俺の最大のピンチを救ってくれるのは、女神なんかじゃない。ただ隣でこうして、俺を温めてくれる、
苗字名前、その人なのだから。
悪夢の後の世界は、驚く程に優しく、甘い香りに満ちていた。俺は、
名前の温もりの中で、ゆっくりと目を閉じた。もう、怖い夢を見ることはないだろう。