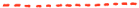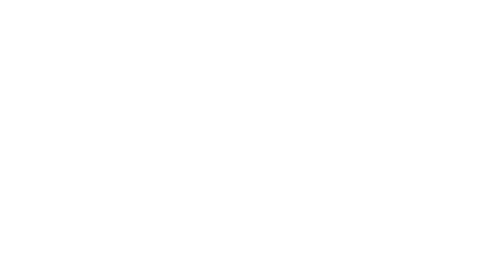ただの遊びじゃ終わらない、心の救済と再生。
ぎぃ、と心地良いリズムを刻むブランコ。俺が背中を押す度、名前ちゃんの髪がふわりと空気を孕んで、初夏の風に溶けていく。その光景がスローモーションみたいに目に焼き付いて、俺はただ、馬鹿みたいに口角が上がるのを止められなかった。
振り返った彼女の「ありがとう」は、逆光の所為で表情こそ見えなかったけれど、どんな言葉よりも、どんな笑顔よりも、俺の心のど真ん中に真っ直ぐ届いた。
「今日の俺、文句なしの120点ッ!!!」
俺が胸を張って叫ぶと、名前ちゃんは「採点が甘いよ」なんて言いながら、くすくすと笑ってブランコから降りた。その足取りは軽やかで、もうどこにも"人形"の面影なんてない。俺がこの手で、彼女の寂しい記憶を全て吹き飛ばしてやったんだ。そんな万能感にも似た高揚が、全身を駆け巡っていた。
二人で並んで、白いガゼボへと戻る。庭園の薔薇の甘い香りと、刈り揃えられた芝生の青い匂いが混じり合って、胸いっぱいに吸い込むと、頭がくらりとする程に幸せだった。
ガゼボのテーブルには、いつの間にか使用人の人が用意してくれたのだろう、銀のポットや繊細な絵付けのティーカップが並んでいた。俺達の王子様ごっこの続きを祝ってくれているみたいだ。
「……約束だから」
名前ちゃんはそう呟くと、白い指先で慣れたように準備を始めた。
ポットにお湯を注ぎ、カップを温める。茶葉の入った缶を幾つか吟味し、その中の一つを手に取る。その一連の動作は、水の流れのように滑らかで、無駄が一切ない。俺はただ、その完璧な横顔に見惚れていた。
――覚くんの好きな紅茶を淹れて、ハグして、沢山キスして……。
今朝の、まだ夢の続きみたいな時間の中で交わされた約束が鮮明に蘇る。心臓が期待にきゅう、と甘く締め付けられた。
やがて、琥珀色の液体がカップに注がれ、柑橘系の爽やかな香りがふわりと立ち上った。アールグレイだ。俺が以前、彼女の部屋で何気なく「この香り、好きだな」と零した、ただそれだけの言葉。それを、名前ちゃんは憶えていてくれた。
「どうぞ。お口に合うといいけれど」
「合うに決まってるじゃん! 名前ちゃんが淹れてくれたんだから、1000点満点だよ!」
一緒に用意されていたチョコレートムースのケーキをフォークで突きながら、俺は満面の笑みで答えた。紅茶を一口含むと、芳醇な香りと柔らかな渋みが口の中に広がる。完璧な温度。完璧な味。
「……美味しい?」
「うん。世界一」
俺が真剣な顔で言うと、名前ちゃんは少しだけ目を伏せて、嬉しそうに微笑んだ。その表情一つで、俺の心は簡単に満たされてしまう。本当に現金なものだ。
ケーキを食べ終え、紅茶を飲み干し、心地良い沈黙がガゼボを包む。風が木々の葉を揺らす音と、遠くで鳥が鳴く声だけが聞こえる。
すると、名前ちゃんがカップをソーサーに置く、カチャリという小さな音を合図にしたかのように、真っ直ぐに、俺を見つめて言った。
「次は、ハグ」
俺は一瞬息を呑み、それから悪戯っぽく笑って両腕を大きく広げた。
「姫、どうぞこちらへ」
名前ちゃんは躊躇うことなく立ち上がり、俺の胸に、とん、と身を預けた。俺は彼女の華奢な身体を、壊れ物を扱うように、それでいて、二度と離さないと言うように強く抱き締めた。
肩口に埋めた顔から、名前ちゃんのシャンプーの匂いがする。背中に回された腕の、確かな力。トクントクンと伝わる心臓の鼓動。ガラスの壁なんて、どこにもない。温かくて、柔らかくて、確かにここに在る。
「……次は、キス」
腕の中で、顔を上げた名前ちゃんが囁いた。潤んだ夜の海の瞳が、俺だけを映している。
もう、我慢なんてできなかった。
俺は彼女の顎にそっと指を添え、顔を傾ける。触れるだけのキスじゃない。お互いの存在を確かめ、溶け合わせるような、深くて長いキス。薔薇の甘い香りと、紅茶の残り香と、名前ちゃんの味が混ざり合って、思考が蕩けていく。これが、俺の欲しかった全てだ。
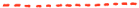 唇が離れても、覚くんの腕の力は弛まなかった。わたしは彼の胸に額を押し付けたまま、大きく揺さぶられた心が鎮まるのを待っていた。彼の心臓が、わたしと同じくらい速く、強く脈打っているのが分かる。それがどうしようもなく愛おしくて、胸の奥がきゅんと痛んだ。
――愛する手段を、全部、奪われた人形。
且てのわたし。この美しい庭を、ただ憎むことしかできなかったわたし。
でも、今は違う。
「ねぇ、覚くん」
「んー……?」
まだキスの余韻に蕩けたような、甘い声が頭上から降ってくる。
「死んだのは、何だったと思う?」
唐突なわたしの問いに、覚くんの身体がぴくりと強張るのが分かった。腕の力が僅かに弛み、訝しげな気配が伝わってくる。
「え……? なに、急に。どういう意味……?」
「この庭で、わたしの一部が死んだんだよ」
わたしは顔を上げずに、彼の胸元に響かせるように言葉を続けた。
驚きと混乱が、彼の全身から放たれている。きっと、怖いことを言っていると思われているだろう。でも、言わなければならなかった。彼に伝えたかった。
「ガラス越しに世界を眺めることしかできなかった、人形のわたし。覚くんがブランコを押してくれた時、わたしの手を引いて薔薇に触れさせてくれた時……あの、何もできなかったわたしは、確かに死んだんだ」
息を詰める気配。覚くんが、わたしの言葉を一つひとつ、必死に理解しようとしてくれているのが分かった。
「そっか……」
やがて、絞り出すような声が聞こえた。それは安堵の色を帯びていて、わたしは少しだけ笑ってしまった。
「じゃあさ、お墓でも建ててやるか。『此処に、可哀想な姫君、眠る』って。ゲス・モンスター謹製、スペシャル墓石!」
いつもの冗談めかした明るい声。でも、わたしを抱き締める腕には、先程よりもずっと優しい力が込められていた。この不器用な優しさが、わたしを救ってくれたんだ。
「それは要らないよ」
わたしは顔を上げて、彼の赤みを帯びた瞳を真っ直ぐに見つめた。
「だって、死んだ代わりに、新しいわたしが生まれたから」
「……新しい、名前ちゃん?」
「うん」
わたしはこくりと頷いて、精一杯の勇気を込めて、微笑んでみせた。
「覚くんを愛する手段を、沢山持っているわたしが、ね」
覚くんの瞳が驚きに見開かれる。大きく開いた目が、これ以上ないくらいに丸くなって、やがて、その瞳にじわりと熱が滲んだ。ああ、泣かせたいわけじゃなかったのに。
「……それ、反則じゃん……」
「そうかな?」
わたしは彼の頬にそっと手を伸ばし、親指でその熱い目尻を拭う。そして、朝の約束の、最後の一欠けらを、覚くんの耳元で囁いた。
「……夜にも、続きを、でしょう?」
瞬間、覚くんの身体が石みたいに固まった。見る見るうちに、首筋から耳までが真っ赤に染まっていくのが見えて、思わず笑みが零れる。
「覚くんが、恥ずかしくないなら、だけど」
「……ッ、恥ずかしいワケないじゃん! 超絶最上級で楽しみにしてますッ!!!」
数秒のフリーズの後、大声で復活した覚くんは、わたしのことをもう一度、今度は空気がなくなるくらい強く抱き締めた。
彼の腕の中で、わたしはもう一度、くすくすと笑った。
死んだのは、孤独だった過去のわたし。
そして、今日、この薔薇の庭で生まれたのは、愛する人の腕の中で未来を夢見ることができる、新しいわたし。
夕陽に染まる庭園に、二人の笑い声がいつまでも響いていた。この確かな温もりと、交わした甘い約束だけが、これからのわたし達の、唯一の真実になる。そんな幸福な予感に、わたしの心は満たされていた。
唇が離れても、覚くんの腕の力は弛まなかった。わたしは彼の胸に額を押し付けたまま、大きく揺さぶられた心が鎮まるのを待っていた。彼の心臓が、わたしと同じくらい速く、強く脈打っているのが分かる。それがどうしようもなく愛おしくて、胸の奥がきゅんと痛んだ。
――愛する手段を、全部、奪われた人形。
且てのわたし。この美しい庭を、ただ憎むことしかできなかったわたし。
でも、今は違う。
「ねぇ、覚くん」
「んー……?」
まだキスの余韻に蕩けたような、甘い声が頭上から降ってくる。
「死んだのは、何だったと思う?」
唐突なわたしの問いに、覚くんの身体がぴくりと強張るのが分かった。腕の力が僅かに弛み、訝しげな気配が伝わってくる。
「え……? なに、急に。どういう意味……?」
「この庭で、わたしの一部が死んだんだよ」
わたしは顔を上げずに、彼の胸元に響かせるように言葉を続けた。
驚きと混乱が、彼の全身から放たれている。きっと、怖いことを言っていると思われているだろう。でも、言わなければならなかった。彼に伝えたかった。
「ガラス越しに世界を眺めることしかできなかった、人形のわたし。覚くんがブランコを押してくれた時、わたしの手を引いて薔薇に触れさせてくれた時……あの、何もできなかったわたしは、確かに死んだんだ」
息を詰める気配。覚くんが、わたしの言葉を一つひとつ、必死に理解しようとしてくれているのが分かった。
「そっか……」
やがて、絞り出すような声が聞こえた。それは安堵の色を帯びていて、わたしは少しだけ笑ってしまった。
「じゃあさ、お墓でも建ててやるか。『此処に、可哀想な姫君、眠る』って。ゲス・モンスター謹製、スペシャル墓石!」
いつもの冗談めかした明るい声。でも、わたしを抱き締める腕には、先程よりもずっと優しい力が込められていた。この不器用な優しさが、わたしを救ってくれたんだ。
「それは要らないよ」
わたしは顔を上げて、彼の赤みを帯びた瞳を真っ直ぐに見つめた。
「だって、死んだ代わりに、新しいわたしが生まれたから」
「……新しい、名前ちゃん?」
「うん」
わたしはこくりと頷いて、精一杯の勇気を込めて、微笑んでみせた。
「覚くんを愛する手段を、沢山持っているわたしが、ね」
覚くんの瞳が驚きに見開かれる。大きく開いた目が、これ以上ないくらいに丸くなって、やがて、その瞳にじわりと熱が滲んだ。ああ、泣かせたいわけじゃなかったのに。
「……それ、反則じゃん……」
「そうかな?」
わたしは彼の頬にそっと手を伸ばし、親指でその熱い目尻を拭う。そして、朝の約束の、最後の一欠けらを、覚くんの耳元で囁いた。
「……夜にも、続きを、でしょう?」
瞬間、覚くんの身体が石みたいに固まった。見る見るうちに、首筋から耳までが真っ赤に染まっていくのが見えて、思わず笑みが零れる。
「覚くんが、恥ずかしくないなら、だけど」
「……ッ、恥ずかしいワケないじゃん! 超絶最上級で楽しみにしてますッ!!!」
数秒のフリーズの後、大声で復活した覚くんは、わたしのことをもう一度、今度は空気がなくなるくらい強く抱き締めた。
彼の腕の中で、わたしはもう一度、くすくすと笑った。
死んだのは、孤独だった過去のわたし。
そして、今日、この薔薇の庭で生まれたのは、愛する人の腕の中で未来を夢見ることができる、新しいわたし。
夕陽に染まる庭園に、二人の笑い声がいつまでも響いていた。この確かな温もりと、交わした甘い約束だけが、これからのわたし達の、唯一の真実になる。そんな幸福な予感に、わたしの心は満たされていた。