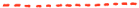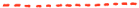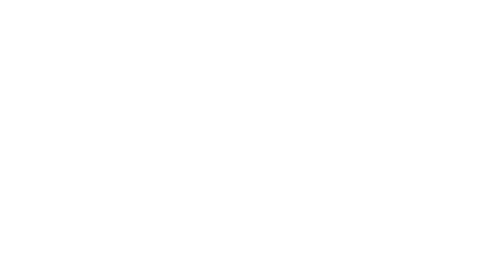彼女の心を掴む為に仕掛けた罠に、自分が堕ちていた――
これは、天童覚が"恋に捕まる"物語。
夕空の下、ブランコが描く放物線の頂点で、名前ちゃんの笑い声が弾けた。風に舞う髪がきらきらと光を散らし、その一瞬が永遠みたいに、俺の網膜に焼き付く。
「今日の俺、文句なしの120点ッ!!!」
俺が胸を張って叫ぶと、ブランコを緩やかに揺らしながら降り立った名前ちゃんが悪戯っぽく唇の端を上げた。
「……そうだね。今日は及第点をあげてもいい」
「えぇーっ、120点満点中!? 辛辣ゥ!」
「ふふ、冗談だよ。満点。ありがとう、覚くん」
その「ありがとう」は、今までのどんな言葉よりも深く、温かく、俺の心のど真ん中にすとんと落ちた。ガラスの向こう側にあった彫刻が、今、俺の隣で確かに微笑んでいる。ああ、本当に堪らなく好きだ。
名残惜しい気持ちで庭園を後にして、俺達は屋敷の中へと戻った。ひんやりとした大理石の廊下を抜け、通された応接室では、既に兄貴くんが優雅に紅茶を飲んで待っていた。
「おや、お帰り。随分と楽しそうな声が聞こえていたよ。ゲス・ホースは中々、元気の良い馬のようだね」
「兄貴くん、聞いてたの!? 恥ずかしいッ!」
「はは、君は本当に面白い。名前のあんな顔を引き出せるのは、世界中を探しても君だけだろうな」
兄貴くんはそう言って、俺と名前ちゃんに新しいティーカップを差し出してくれた。注がれた紅茶は薔薇の庭園を思わせる華やかな香りがする。
俺が恐縮しながら席に着くと、名前ちゃんはごく自然に、兄貴くんの隣に座った。その光景に、また少しだけ胸がちり、と疼く。俺の知らない、兄妹だけの時間。その積み重ねが、二人の間の揺るぎない空気を作っている。
「名前は昔から、大きな音や派手なものが、少し苦手でね。けれど、些細な音には、とても敏感だった」
兄貴くんの言葉に、俺はカップを持ち上げたまま、ぴたりと動きを止めた。
その一言が、錆び付いた記憶の扉を開ける鍵になる。
――そうだ。あの日も、そうだった。
脳裏に蘇るのは、まだ互いの輪郭を手探りでなぞっていた、あの初夏の日の光景だ。
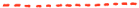 あれは確か、俺が初めて名前ちゃんを自分の部屋に招いた日だった。
白鳥沢の寮の一室。殺風景で、面白味も何もない、ただ寝る為だけの空間。そこに、この世の美しいものを全て集めて形にしたような彼女が居る、という事実だけで、俺の心臓はとっくにキャパオーバーを起こしていた。
「ど、どうぞ! 汚いけど! いや、昨日、めちゃくちゃ掃除したから綺麗だけど!」
「……うん。お邪魔します」
しどろもどろな俺の言葉に、名前ちゃんは静かに頷いて、ちょこんとベッドの端に腰掛けた。その仕草一つで、無機質なパイプベッドがどこかの国の王女様の寝台みたいに見えてくるから不思議だ。
どうしよう。何を話せばいい?
女の子を部屋に呼ぶなんて初めての経験で、俺は完全にフリーズしていた。バレーの試合なら、相手の次の動きも、その次の次くらいまでゲスできるのに。目の前の彼女の心の中は、深い霧に包まれた森のようで、一歩先すら見えやしない。
(そうだ、音楽! 女の子はオシャレな音楽とか好きでしょ!)
俺は慌ててCDプレイヤーの電源を入れた。流れてきたのは、セミセミ――英太くんに借りた、流行りの洋楽だ。「これ、女子にウケるぞ」って言ってたヤツ。
でも、名前ちゃんは特に表情を変えることなく、ただ窓の外を眺めている。
(……違ったか。じゃあ、お菓子! チョコのアイスとか!)
「あ、あのさ、アイスあるけど、食べる?」
「ううん。大丈夫」
にべもない返事。俺の心のHPがごりごりと削られていく音がする。
沈黙が気まずい。何か、何か話さないと。名前ちゃんの興味を引くような、面白い話を。
「この前さ、若利くんが――」
俺が必死で捻り出したバレー部の面白エピソードも、彼女は「そう」と相槌を打つだけで、その瞳はどこか遠くを見ているようだった。
ああ、ダメだ。終わった。
俺、嫌われたんだ。「妖怪っぽい」って、やっぱり思われてるんだ。彼女の綺麗な世界に、俺みたいなガサツな奴は似合わないんだ。
心がずぶずぶと沼に沈んでいくような感覚。彼女の心を掴もうと伸ばした手は、尽く空を切る。まるで、こちらの存在に気づいてすらいないかのように。
手探りで進んだ先は行き止まりだった。
俺が諦め掛けて黙り込んだ、その時だった。
開け放っていた窓から、ふわりと初夏の風が吹き込んだ。
何の変哲もない、寮に備え付けの、草臥れた無地のカーテン。それが、さわさわと音を立てて揺れた。
「……この音、好き」
ぽつり、と。
今まで聴いたどんな言葉よりも小さな、けれど、誰よりも鮮明な声で、名前ちゃんが呟いた。
「え?」
俺が間抜けな声で聞き返すと、名前ちゃんは初めて、俺の目を真っ直ぐに見て、もう一度言った。
「乾いた布が、擦れる音。落ち着く」
心臓を鷲掴みにされた。
俺が良かれと思って用意した流行りの音楽でも、甘いお菓子でも、面白い話でもない。
ただ、そこにあっただけの何気ない、有り触れた音。
名前ちゃんの心に触れたのは、そんな些細な欠片だったのだ。
その瞬間、俺は悟った。
彼女の心を捕まえようと、俺があちこちに仕掛けたつもりの甘い餌は、全部見向きもされなかった。だけど、手探りで迷い込んだ道の果て、思いもよらない場所に、彼女の心に繋がる小さな扉が隠されていた。
いや、違う。
これは、俺が彼女を捕まえる為の罠なんかじゃない。
俺の方が、彼女が仕掛けた見えないネズミ捕りに、まんまと嵌ってしまったんだ。彼女の繊細な感性という、抗いようのない、美しい罠に。
がちり、と。心の奥で捕獲された音がした。
もう逃げられない。
この子のことを、もっと知りたい。この子が「好き」だと思うものを一つ残らず、俺が集めてあげたい。
あれは確か、俺が初めて名前ちゃんを自分の部屋に招いた日だった。
白鳥沢の寮の一室。殺風景で、面白味も何もない、ただ寝る為だけの空間。そこに、この世の美しいものを全て集めて形にしたような彼女が居る、という事実だけで、俺の心臓はとっくにキャパオーバーを起こしていた。
「ど、どうぞ! 汚いけど! いや、昨日、めちゃくちゃ掃除したから綺麗だけど!」
「……うん。お邪魔します」
しどろもどろな俺の言葉に、名前ちゃんは静かに頷いて、ちょこんとベッドの端に腰掛けた。その仕草一つで、無機質なパイプベッドがどこかの国の王女様の寝台みたいに見えてくるから不思議だ。
どうしよう。何を話せばいい?
女の子を部屋に呼ぶなんて初めての経験で、俺は完全にフリーズしていた。バレーの試合なら、相手の次の動きも、その次の次くらいまでゲスできるのに。目の前の彼女の心の中は、深い霧に包まれた森のようで、一歩先すら見えやしない。
(そうだ、音楽! 女の子はオシャレな音楽とか好きでしょ!)
俺は慌ててCDプレイヤーの電源を入れた。流れてきたのは、セミセミ――英太くんに借りた、流行りの洋楽だ。「これ、女子にウケるぞ」って言ってたヤツ。
でも、名前ちゃんは特に表情を変えることなく、ただ窓の外を眺めている。
(……違ったか。じゃあ、お菓子! チョコのアイスとか!)
「あ、あのさ、アイスあるけど、食べる?」
「ううん。大丈夫」
にべもない返事。俺の心のHPがごりごりと削られていく音がする。
沈黙が気まずい。何か、何か話さないと。名前ちゃんの興味を引くような、面白い話を。
「この前さ、若利くんが――」
俺が必死で捻り出したバレー部の面白エピソードも、彼女は「そう」と相槌を打つだけで、その瞳はどこか遠くを見ているようだった。
ああ、ダメだ。終わった。
俺、嫌われたんだ。「妖怪っぽい」って、やっぱり思われてるんだ。彼女の綺麗な世界に、俺みたいなガサツな奴は似合わないんだ。
心がずぶずぶと沼に沈んでいくような感覚。彼女の心を掴もうと伸ばした手は、尽く空を切る。まるで、こちらの存在に気づいてすらいないかのように。
手探りで進んだ先は行き止まりだった。
俺が諦め掛けて黙り込んだ、その時だった。
開け放っていた窓から、ふわりと初夏の風が吹き込んだ。
何の変哲もない、寮に備え付けの、草臥れた無地のカーテン。それが、さわさわと音を立てて揺れた。
「……この音、好き」
ぽつり、と。
今まで聴いたどんな言葉よりも小さな、けれど、誰よりも鮮明な声で、名前ちゃんが呟いた。
「え?」
俺が間抜けな声で聞き返すと、名前ちゃんは初めて、俺の目を真っ直ぐに見て、もう一度言った。
「乾いた布が、擦れる音。落ち着く」
心臓を鷲掴みにされた。
俺が良かれと思って用意した流行りの音楽でも、甘いお菓子でも、面白い話でもない。
ただ、そこにあっただけの何気ない、有り触れた音。
名前ちゃんの心に触れたのは、そんな些細な欠片だったのだ。
その瞬間、俺は悟った。
彼女の心を捕まえようと、俺があちこちに仕掛けたつもりの甘い餌は、全部見向きもされなかった。だけど、手探りで迷い込んだ道の果て、思いもよらない場所に、彼女の心に繋がる小さな扉が隠されていた。
いや、違う。
これは、俺が彼女を捕まえる為の罠なんかじゃない。
俺の方が、彼女が仕掛けた見えないネズミ捕りに、まんまと嵌ってしまったんだ。彼女の繊細な感性という、抗いようのない、美しい罠に。
がちり、と。心の奥で捕獲された音がした。
もう逃げられない。
この子のことを、もっと知りたい。この子が「好き」だと思うものを一つ残らず、俺が集めてあげたい。
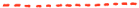 「――覚くん?」
名前ちゃんの声に、はっと我に返る。
目の前には、心配そうにこちらを覗き込む、夜の海の瞳。俺はいつの間にか、紅茶のカップを持ったまま、完全に思考の海にダイブしていたらしい。
「あ、ごめん! ちょっと、昔のこと思い出してた!」
「昔のこと?」
「うん。俺の部屋のカーテンの話」
俺がそう言うと、名前ちゃんは少しだけ意外そうな顔をして、それから、ふわりと花が綻ぶように微笑んだ。
「……憶えていてくれたんだね」
「当たり前でしょ! あの日、俺は名前ちゃんに、完膚なきまでに心を奪われたんだから!」
俺が大袈裟に胸を押さえてみせると、兄貴くんが「ほう、それは聞き捨てならないな」と面白そうに目を細めた。
俺はあの日のことを、武勇伝のように語って聞かせた。自分がどれだけ空回りして、どれだけ焦って、そして、たった一言でどれだけ救われたか。
「……だから、俺の部屋のカーテンは、あの日からずっと、夕陽を吸い込んだみたいなオレンジ色なんだ。名前ちゃんが好きそうかなって」
言い終えて、なんだか急に恥ずかしくなって、ガブガブと紅茶を呷る。
名前ちゃんは何も言わず、ただテーブルの下でそっと、俺の手を握った。その指先がほんの少しだけ震えていることに、俺だけが気づいていた。
手探りで見付けたのは、ネズミ捕り。
でも、その罠に捕らえられた俺は、今、最高に幸せだ。
「届かない」なんて、もう思わない。君が零す小さな「好き」をこれからも一つずつ、宝物みたいに拾い集めていく。そうやって、俺達だけの地図を作っていくんだ。
握り返した手の温もりが、疑いようのない、俺達の答えだった。
「――覚くん?」
名前ちゃんの声に、はっと我に返る。
目の前には、心配そうにこちらを覗き込む、夜の海の瞳。俺はいつの間にか、紅茶のカップを持ったまま、完全に思考の海にダイブしていたらしい。
「あ、ごめん! ちょっと、昔のこと思い出してた!」
「昔のこと?」
「うん。俺の部屋のカーテンの話」
俺がそう言うと、名前ちゃんは少しだけ意外そうな顔をして、それから、ふわりと花が綻ぶように微笑んだ。
「……憶えていてくれたんだね」
「当たり前でしょ! あの日、俺は名前ちゃんに、完膚なきまでに心を奪われたんだから!」
俺が大袈裟に胸を押さえてみせると、兄貴くんが「ほう、それは聞き捨てならないな」と面白そうに目を細めた。
俺はあの日のことを、武勇伝のように語って聞かせた。自分がどれだけ空回りして、どれだけ焦って、そして、たった一言でどれだけ救われたか。
「……だから、俺の部屋のカーテンは、あの日からずっと、夕陽を吸い込んだみたいなオレンジ色なんだ。名前ちゃんが好きそうかなって」
言い終えて、なんだか急に恥ずかしくなって、ガブガブと紅茶を呷る。
名前ちゃんは何も言わず、ただテーブルの下でそっと、俺の手を握った。その指先がほんの少しだけ震えていることに、俺だけが気づいていた。
手探りで見付けたのは、ネズミ捕り。
でも、その罠に捕らえられた俺は、今、最高に幸せだ。
「届かない」なんて、もう思わない。君が零す小さな「好き」をこれからも一つずつ、宝物みたいに拾い集めていく。そうやって、俺達だけの地図を作っていくんだ。
握り返した手の温もりが、疑いようのない、俺達の答えだった。