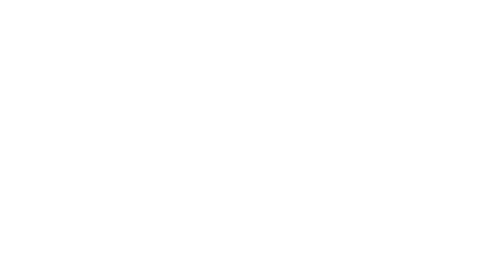不器用な王子様ごっこが導いたのは、
彼女が隠してきた"ガラス越しの孤独"への扉だった――。
昨夜、腕の中で確かめ合った温もりと、朝の光の中で交わした不器用な誓い。それらを燃料みたいに心のタンクに満タンにして、俺は今、人生で一番そわそわしていた。
だって、これから行くのは、あの名前ちゃんの実家――苗字家の庭園なのだ。
マンションまで迎えに来てくれた、黒塗りのピカピカな車の後部座席。柔らか過ぎるシートに深く身を沈めながら、俺は隣に座る名前ちゃんの横顔を盗み見た。車窓を流れる景色を映す彼女の瞳は、いつも通り静かで、何を考えているのか読み取れない。
「……ねぇ、名前ちゃん」
「なに?」
「もしかして、"ゲスの白馬に乗った王子様ごっこ"、嫌だった?」
俺がしょんぼりした声色で訊くと、名前ちゃんはぱちりと一度瞬きをして、こちらに顔を向けた。
「嫌じゃないよ。覚くんが楽しそうだから、わたしも楽しみ」
「ホントに!? やった! じゃあ、姫役、ちゃんとやってくれる?」
「……それは、覚くんの演技次第かな」
くっ……! またしても、その試すような物言い! ズルい、ズル過ぎる! でも、それが堪らなく好きだ。燃えてきた。最高の王子様、演じ切ってやろうじゃないの。
やがて車が滑るように停止したのは、映画でしか見たことのないような、立派な門構えの屋敷の前だった。運転手さんが恭しくドアを開けてくれて、俺は何だか自分が本当の王子様にでもなったかのような錯覚に陥る。
「やぁ、覚くん。よく来てくれたね」
玄関で俺達を迎えてくれたのは、名前ちゃんのお兄さん――兄貴くんだった。今日も全身真っ黒な服だけど、胸元には『才能の無駄遣い』って書かれたTシャツが自己主張している。相変わらずセンスが独創的だ。
「お邪魔します、兄貴くん! 今日は姫を迎えに上がりました!」
「はは、一緒に来たのに、面白いね。名前、良かったじゃないか。退屈しないで済みそうだ」
兄貴くんは楽しそうに目を細め、名前ちゃんの頭を優しく撫でた。その光景は一枚の絵画みたいに綺麗で、俺は少しだけ胸がちくりと痛む。この兄妹の間に流れる、俺の知らない長い時間を思ったからだ。
兄貴くんに見送られ、俺達は屋敷の裏手にある庭園へと足を踏み入れた。
その瞬間、俺は息を呑んだ。
「……うわぁ」
思わず、間抜けな声が漏れる。
そこは、正に童話の世界そのものだった。
丁寧に手入れされた芝生の絨毯。色とりどりの薔薇が咲き誇るアーチ。風に揺れるラベンダーの紫と、その甘い香り。木漏れ日がきらきらと地面に光の模様を描き、空気までもが澄み切って、特別な色をしているように感じられた。
「どう? わたしの自慢の場所」
「自慢って……レベルが違うでしょ、コレ! テーマパークじゃん!」
俺が興奮気味に叫ぶと、名前ちゃんは嬉しそうに唇の端を綻ばせた。その表情に、俺の心臓はまたしても鷲掴みにされる。よし、やるぞ。
「――姫! 長らくお待たせ致しました!」
俺はわざとらしく片膝を突き、恭しく手を差し伸べる。勿論、ここに白馬は居ない。だが、俺の脳内には、純白の鬣を靡かせた立派な馬が見えている。
「さぁ、我がゲス・ホースへ! この覚王子がエスコート致しましょう!」
「……ゲス・ホース?」
「そう! 俺の推測(ゲス)に応えてくれる、最高の馬なのだ!」
俺は立ち上がると、見えない馬に跨るジェスチャーをして、手綱を握る真似をした。そして、即興の歌を高らかに歌い上げる。
「♪ゲスゲスゲ~ス、ゲス・モンスター♪ ブロックも恋も、推測だ~♪ 姫のハートを読み切って~♪ 今日もお迎え、120点ッ~♪」
我ながら、酷い歌詞とメロディだ。若利くんに聞かれたら、真顔で「どういう意味だ?」と訊かれるに違いない。
名前ちゃんは案の定、呆れたように小さく溜め息をついた。でも、その口元は隠し切れない笑いを堪えるように、ぷるぷると震えている。
「……覚くん、その馬、ちゃんと前に進んでいるの?」
「ギクッ……! さ、流石は姫! 俺のゲス・ホースは今、嬉しさの余り足踏みをしているのです!」
俺は慌てて、変なステップを踏みながら庭園を練り歩き始めた。スキップしてみたり、片足でぴょんぴょん跳ねてみたり。名前ちゃんを笑わせたい、ただそれだけの一心で、俺は完全に道化と化していた。
「あはっ……ふふ、ふ……っ」
遂に堪え切れなくなった名前ちゃんから、鈴が鳴るような笑い声が零れた。
その瞬間、世界から音が消えた。
俺の目には、心の底から楽しそうに笑う、彼女の姿だけが映っていた。あのガラスの壁なんてどこにもない、無防備で、柔らかで、愛おしい笑顔。
ああ、これだ。俺は、この顔が見たかったんだ。
王子様ごっこに満足し、二人で庭園の奥にある白いガゼボで一休みすることにした。心地良い風が火照った頬を撫でていく。
「楽しかった?」
「うん。覚くんは、本当に面白いね」
名前ちゃんはそう言って、幸せそうに目を細めた。その穏やかな表情に、俺の心も温かいもので満たされる。
けれど、ふと、彼女の視線が庭園の隅にある、古びたブランコに向けられていることに気づいた。その瞳に一瞬だけ、翳りが差したように見えた。
「……わたしね、昔はこの庭が、少しだけ嫌いだった」
ぽつりと呟かれた言葉に、俺は耳を疑った。
「え、なんで? こんなに綺麗なのに」
「綺麗だから、だよ」
名前ちゃんは静かに語り始めた。
幼い頃、病弱で、殆どの時間をベッドの上で過ごしていたこと。窓から見えるこの美しい庭園を、ただ眺めることしかできなかったこと。
「皆がここで笑ったり、走ったり、花に触れたりしているのを、わたしはガラス越しに見ているだけ。ブランコに乗りたくても、乗れなかった。薔薇の香りを嗅ぎたくても、近くに行けなかった。……まるで、愛する手段を、全部、奪われた人形みたいだった」
――人形。
その言葉が雷のように、俺の胸を撃ち抜いた。
俺が感じていた、ガラスの向こうの彫刻。その正体は、彼女自身が自分に課していた、どうしようもない隔たりだったんだ。触れたいのに触れられない。行きたいのに行けない。そのもどかしさが、彼女の世界を覆っていたんだ。
「届かない」という言葉の根っこに、漸く触れた気がした。
俺は何も言わず、そっと立ち上がって、名前ちゃんの手を取った。彼女は驚いたように俺を見上げたけれど、されるがままに付いてくる。
俺達は一番近くで誇らしげに咲いていた、真紅の薔薇の前で足を止めた。
「名前ちゃん」
俺は彼女の手を取り、その白く繊細な指先を、そっと薔薇の花弁に触れさせた。
「……今は、触れるでしょ?」
名前ちゃんの瞳が、僅かに見開かれる。彼女はこくりと小さく頷いた。
「走れるでしょ?」
「……うん」
「俺と、"ゲスの白馬に乗った王子様ごっこ"だって、できたでしょ?」
俺が悪戯っぽく笑い掛けると、名前ちゃんの唇がふっと綻んだ。
「……それは、覚くんが勝手にやっていただけだよ」
「じゃあ、今度も、名前ちゃんが姫様役ね! ほら、ブランコまで競争だ!」
俺は彼女の手を引いて、駆け出した。過去の寂しい記憶を振り払うように、今、この瞬間の楽しさで上書きするように。
ブランコに辿り着くと、俺は名前ちゃんの背中を優しく押した。
ぎぃ、と懐かしい音を立てて、ブランコが揺れる。高く、もっと高く。彼女の柔らかな髪が、風にふわりと舞い上がった。
「覚くん!」
「んー?」
「……ありがとう」
振り返った彼女の顔は、逆光で見えなかった。でも、その声がどんな笑顔よりも雄弁に、名前ちゃんの気持ちを伝えてくれた。
俺は最高の笑顔で叫んだ。
「今日の俺、文句なしの120点ッ!!!」
「届かない」なんて言葉は、もう要らない。
俺が、君の手を取って、どこへだって連れていってやる。君が愛したい世界全てに、その手を届かせてやる。
だから、もう大丈夫。君はもう、人形なんかじゃないんだから。
青空の下、二人の笑い声が、いつまでも庭園に響き渡っていた。