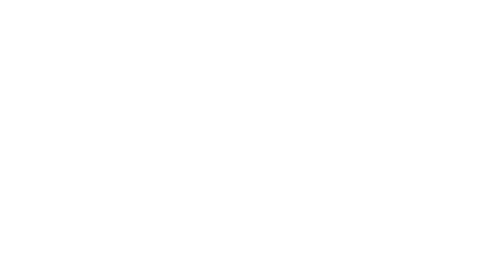朝の光に怯える彼と、触れる奇跡を信じ始めた彼女の、
静かで切実な「おはよう」の物語。
腕の中に在る温もりだけが、俺達の唯一の真実。
そう信じて眠りに就いた筈なのに、朝の光って、ほんと残酷だ。
昨夜の月光とは違う、容赦のない白色光がレースのカーテンを突き抜け、部屋の輪郭をくっきりと暴き出す。それが夢の終わりを告げる冷たい合図のようで、俺は無意識に眉を寄せた。
腕の中の名前ちゃんは、まだ静かな寝息を立てている。乱れのない髪、閉じられた瞼を縁取る長い睫毛、ほんのり開いた薄桃色の唇。何もかもが夢の中に居るみたいに綺麗で、完璧で、そして、どうしようもなく儚い。
だから、俺は名前ちゃんと一緒に迎える朝、ちょっとだけ世界に嫉妬してる。
この光が、この世界の喧騒が、俺だけの名前ちゃんを連れ去っていく気がして。
起きたらまた、俺の手からすり抜けていくんじゃないか、って。
昨夜、あれだけ確かめ合ったのに、このザマだ。そんなくだらない心配をするくらいなら、もっと寝ればいいのにって、自分でも思う。
だけど――
「……おはよう、覚くん」
耳元で囁くような声がした。
「うわっ……もう起きてたの?」
驚いて視線を落とすと、夜の海を湛えた瞳が直ぐ間近で、俺を見つめていた。いつから起きていたのか、その瞳は眠気の欠片もなく澄み切っている。
「うん。さっき、目が覚めた」
眠たげに微笑む名前ちゃんの声は、朝の弱さを溶かす魔法みたいだ。俺の心のささくれを優しく撫でてくれる。
おはようのキス、していい? って、柄にもなく許可を取ろうとした。けれど、その言葉が音になる前に、柔らかな感触が俺の唇を塞いだ。
触れるだけの、静かで温かいキス。
それなのに、心臓がぐらぐらに揺さぶられる。キスって、こんなに静かで温かくて、心をどうしようもなく掻き乱すものなんだなぁ。初めて知った時からずっと思ってるけど、名前ちゃんはそれを毎回、軽々と更新してくるから、俺は一生、彼女に勝てない気がする。
唇が離れて、名残惜しさに瞬きを一つ。
「……夢を見ていたの?」
「夢?」
「うん。寝言を言っていたよ。『ずっと居て』って」
心臓が、ドクン、と大きく跳ねた。
「……あ、それ……」
なんか、言い訳できない気がした。
いつもなら「俺の脳内の名前ちゃんが可愛過ぎた所為です!」なんて、おどけてみせて、冗談の煙幕で本心を隠せる。でも、今日だけはできなかった。朝の光が、俺の虚勢までも見透かしているみたいで。
「――名前ちゃんが、時々、消えそうに見える」
正直に口を開いたら、堰を切ったように本音が溢れた。胸が少し軽くなる。
けど、名前ちゃんの表情は変わらないままで、そこがまた、俺を不安にさせた。
「……それ、前にも言っていたよ。わたし、触れられない彫刻みたいだって」
「憶えてた?」
「当たり前でしょう。そんな悲しいこと、忘れられないよ」
そう言って、俺の左手をそっと取った。シーツの上に置いた指を、一本ずつ、確かめるように、ゆっくりと絡め取る。その指先の冷たさと、意図の読めない丁寧な仕草がやっぱりズルい。ズル過ぎて、泣きそうになる。
「わたしね、本当は、自分のことを信じていないんだ」
静かな告白だった。
「誰かに愛されるとか、大事にされるとか、壊れずに隣に居てもらえるとか……。全部、脆くて儚くて、気づいたら消えているって、ずっと思っていた」
「……」
息を詰めて、名前ちゃんの言葉の続きを待つ。ガラスの向こう側から、初めて彼女自身の声が聞こえてきた気がした。
「でも、覚くんはいつも『違う』って言ってくれる。言葉じゃなくて、態度で。寝言でも、抱き締め方でも、朝の『おはよう』でも。……それって、奇跡みたいなことだよ」
奇跡なんかじゃない。俺が、そうしたいから。俺が好きだからやってるだけ。
でも、それを口にしたら、きっとまた胸が詰まって泣きたくなってしまうから、唇をきつく噛んで黙っていた。
「わたしね――消えたいって思っていた時期がある。でも、覚くんが、わたしのこと、ちゃんと"ここに居る"って思い出させてくれるの。だから、ちゃんと信じるよ。わたしも、覚くんも、消えないって。ね?」
名前ちゃんの声はか細いけれど、真っ直ぐだった。
ああ、そうか。儚いって、壊れ易いってことじゃないんだな。
脆くて消えそうだからこそ、繋いだ手の温もりがこんなにも愛おしいんだ。
そっと手を握り返して、絡められた指先にきゅっと力を込める。
「――ありがとね」
「……なにが?」
「居てくれること、信じてくれること、俺を選んでくれたこと、全部」
言った後に、流石に重過ぎたかもって思って、ちょっと気まずくて目を逸らしたら、名前ちゃんが小さく笑う気配がした。
「それ、後で全部、お返しするね」
「えっ?」
「覚くんの好きな紅茶を淹れて、ハグして、沢山キスして、……あ、後、夜にも続きを」
俺の思考は一瞬、フリーズした。そして、理解が追いついた瞬間、とんでもない多幸感が全身を駆け巡る。
「――神?」
思わず両手を合わせて拝んだ俺を、名前ちゃんは「バカ」って言って、今度こそ声に出して笑った。
でも、その目尻がほんのり赤く潤んでいるの、俺だけじゃないって分かって、心の底から安心した。
脆くて、儚くて、消えてしまいそうでも――
それでも、こうして手を伸ばせば、ちゃんと隣に居る。
触れられる奇跡を、これからもずっと大切にしていきたい。
だから、今日も俺は言うんだ。何度でも。
「名前ちゃん、愛してるよ。超絶最上級で」
「……もう、本当にバカ。でも、わたしも。愛してる」
――消えないで。ずっと、ここに居て。
それはもう、不安な寝言じゃない。
俺の心からの、どうしようもなく切実な祈りだった。