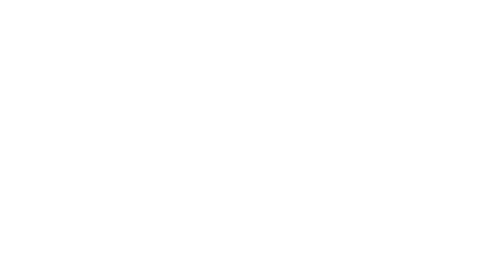ねぇ、今日の「好き」は届いてる?
あーあ。今日も名前ちゃんは、俺の知らない顔をしてる。
開け放った窓から吹き込む初夏の風が、夕陽を吸い込んだオレンジ色のカーテンをはためかせている。その乾いた布の擦れる音が好き、と彼女が呟いたのはいつだったかな。遠い記憶のようで、昨日のことのようにも思い出せる。だから、俺の部屋のカーテンは、あの日からずっとこの色だ。
名前ちゃんが零した何気ない言葉の欠片を、俺は一つ残らず拾い集めてる。自分でも引くくらい、執拗に。
なのに、名前ちゃんは多分、そのことを全然知らない。
俺が教室の窓から、校庭を横切る彼女の小さな背中を見つけては、心の奥で何回「可愛い」って叫んでたか。
バレーの練習中ですら、そうだ。セッターの指先、スパイカーの踏み込み、そのコンマ数秒の未来予測の渦の中に、ふっと名前ちゃんの顔が割り込んでくる。ブロックのタイミングを計る思考のど真ん中に、だ。ヤバ過ぎて、若利くんにも言えない。集中を乱すなと睨まれるのがオチだけど、それ以上に、こんな自分を知られるのが恥ずかしい。
……って、こういうの、全部口に出して伝えればいいのにって思うでしょ? 普通は。
でもね、それって――
「届かないから、聞かなくていい」
彼女にそう言われたことがある。
尤も、あれはまだ恋人になる前、互いの輪郭を手探りでなぞるような、もどかしくも甘い距離感で揺れていた頃の話。俺が「ねぇ、名前ちゃん、好きな人いる?」なんて、在り来たりな質問を投げ掛けた時の、彼女からの返事だった。
届かない。
彼女は自分の気持ちを、そう定義しているんだ。
いやいやいや、待て待て。今はもう正真正銘の恋人じゃん! 初めてもお互いに捧げ合っちゃった仲だし、周りも認める超仲良しカップルだし、イチャイチャだって飽きられそうな程してる。理屈では、頭では、ちゃんと分かってる。
――なのに、だ。
心の一番深い、柔らかな場所。そこだけは、名前ちゃんはまだ誰にも触れさせていない気がする。
なんて言うか……そう、美術館で、分厚いガラスの向こうに飾られた彫刻を眺めているような気分になるんだ。完璧な造形美。けれど、その表面を覆う見えないガラス一枚分の隔たりが、どうしようもなくもどかしい。指先を伸ばせば触れられそうなのに、決して届かない。ガラスに映るのは、ただ間抜けな顔をした、俺だけだ。
俺のこと、ちゃんと見てくれてる筈なのに。
名前を呼べば、夜の海を思わせる瞳が、真っ直ぐに俺を捉えるのに。
面白いことを言えば、薄桃色の唇を綻ばせて、ちゃんと笑ってくれるのに。
こうして寝る前に、腕の中で安心したようにぬくぬくしてるのに。
「……ねぇ、名前ちゃん」
ベッドの上。一日の喧騒が嘘みたいな、静かな時間。
銀色の月光がレースのカーテン越しに滑り込み、俺の腕に収まる名前ちゃんの髪を銀糸のように艶めかせている。
「なに?」
「俺のこと、好き?」
名前ちゃんはゆるりと一度瞬きをしただけで、表情は変えない。多分、俺のこの周期的な問い掛けには、もう慣れっこなんだろう。
でも、それでも、彼女はいつだって真っ直ぐに返してくれる。
「好きだよ」
事もなげに、けれど澄んだ声で。俺がこの一言にどれだけ救われ、渇望しているかなんて、まるで知らないみたいに。
「どのくらい?」
「……聞きたい?」
その問い返すような言い方がズルいんだよ。
ふっと静かに息をついた名前ちゃんは、俺の胸にぴたりと額を押し当てた。心臓の真上。
「届かないなら、聞かないで。言葉なんて、幾らでも綺麗にできるから」
彼女の声は小さくて、綺麗で、だけど、ほんの少しだけ、怒りの棘を含んでいた。
ぴしゃり、と冷たい水で頬を叩かれたような衝撃。声は囁きなのに、鼓膜を通り越して心臓に直接突き刺さる。
ああ、またやった。俺の悪い癖だ。
言葉にしてもらわないと、不安で溺れそうになる。
不安になると、それを隠すように冗談めかして訊いてしまう。
それを繰り返して、俺は何回、名前ちゃんに"本当"を強要させてきたんだろう。
「……じゃあ、届いてるって、思ってもいい?」
「それは、覚くんが決めることでしょう?」
やっぱ、名前ちゃんって、ズルい。
狡くて、優しくて、どこか冷たくて、なのにあったかくて――。
ほんと、ヤバいくらい好きだ。
俺は答えの代わりに、そのまま彼女の肩を強く抱き寄せ、そっと額に唇を押し当てる。
「でもさ、やっぱり訊いちゃうかも。心配性で、ごめん」
「ううん。覚くんだから、仕方ないと思ってる」
なんだ、それ。最高に嬉しい。やっぱりズルい。愛してる。
不安の淵から引き戻されるように、心が温かいもので満たされていく。
「ねぇ、明日、名前ちゃんちの庭園、行っていい? あそこ、名前ちゃんと歩くと、なんか童話の中みたいで楽しいんだよね」
「うん。いいよ。……でも、変なポーズで歩かないでね」
「えぇっ、じゃあ、"ゲスの白馬に乗った王子様ごっこ"は?」
「それは……してもいい。覚くんが恥ずかしくないなら」
「イエーイ! 120点ッ!!!」
「煩い。夜だよ」
「ごめんなさいィィ」
声を殺して肩を揺らし、くすくす笑い合う。こんな時間が、堪らなく好きだ。
「届いてない」なんて、俺が勝手に作り出した幻なのかもしれない。
そうだ、俺が信じなきゃいけないのは、不確かな言葉じゃなくて、腕の中に在る、確かなこの温もりなんだ。
やがて、すぅ、と規則正しい寝息が聞こえ始める。無防備に弛緩したその寝顔に、さっきまでのガラスの壁はどこにもない。俺はその小さな耳元に、祈るように言葉を落とした。
――好きだよ、世界一。
――明日も明後日も、来年も、再来年も、君がうんざりするくらい、何回でも言うからね。
――「届かない」なんて言葉、君の辞書から消し去ってやる。それくらい、しつこく、飽きる程、愛を囁き続けてやるから。
名前ちゃん、聞こえてたらいいな。
でも、もし聞こえてなくても、俺は言い続ける。
だから、今はただ、俺の腕の中で安心して眠って。この温もりだけが、俺達の唯一の真実なんだから。