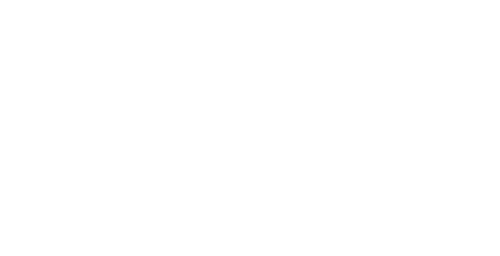「弟に嫉妬してるなんて、言えるわけないだろ」
※兄貴の登場、弟の描写が含まれます。
一年前の設定です。
午後の光は蜂蜜を煮詰めたようにとろりと甘く、リビングの床に琥珀色の四角形を描いていた。俺の背中には、窓ガラス越しの太陽が遠慮がちに寄り添い、セーターを通して、じんわりと熱を与える。その温かさは、抱き寄せた恋人の体温とよく似ていた。
「賢二郎の心臓の音、落ち着くね」
ソファに深く身を沈めた俺の胸に耳を当て、名前がぽつりと呟いた。俺の腕にすっぽりと収まった彼女の髪から、陽だまりとフローラルが混じった、世界で一番好きな匂いがする。規則正しくも、少しだけ速い俺の鼓動が、彼女の柔らかな頬に伝わっているのだろう。
「お前の匂いの方が、よっぽど落ち着く」
「ふぅん、そう。それは良かった」
短い返事と共に、名前が心地好さそうに目を細める。夜の海を溶かし込んだような瞳が、現在は穏やかな凪の状態だ。透き通る程に白い肌、僅かに開かれた薄桃色の唇。どれもが、今、俺だけのものとしてここに在る。その事実に思考が及ぶ度、腹の底からじわりと熱いものがせり上がってくるのを自覚する。全く、この身体は年頃の男子高校生らしく、実に正直だ。
「……名前」
「うん?」
「次のオフ、どこか行く? 水族館とか……お前、好きだろ」
「いいね。大きな水槽の前で、一日中、賢二郎と座っていたいな」
そんなことをしたら、俺は魚じゃなくて、名前の横顔を一日中眺めることになる。寮生活の俺にとって、名前とこうして過ごせる週末は、日頃の全てを懸けて勝ち取るべき報酬であり、生きる為のガソリンだ。この安らかな時間を、この温もりを、一秒でも長く。俺は彼女の細い肩を抱く腕に、無意識に力を込めた。
その時だった。
「そう云えばね、賢二郎」
ふと顔を上げた名前が、何でもないことのように爆弾を投下した。
「最近、弟がよく白鳥沢の話をするんだよ」
弟。苗字弟。名前の弟で、姉に似て人形めいた顔立ちをした、生意気なクソガキ。俺のことを呼び捨てにする癖に、時々、妙に懐いてくる、扱い辛い未来の義弟候補。
あいつが、白鳥沢の?
「……あいつ、来年受験だろ。まさか」
「うん。進路の一つに考えているみたい。賢二郎が居るから、心強いでしょう? って、わたしが勧めておいたんだ」
悪戯っぽく笑う名前の顔が、やけにスローモーションで見えた。
勧めた? お前が?
俺の脳内で、警報がけたたましく鳴り響く。苗字弟が、白鳥沢に? 俺のテリトリーに?
いや、それだけじゃない。あいつは、名前と血の繋がった弟だ。俺が部活で必死にバレーに打ち込んでいる間、あいつは当たり前のように、名前の隣に居る。もし白鳥沢に入学でもしたら、今よりもっと「賢二郎は知らねーだろうけど」なんて枕詞付きの、俺の知らない名前と弟の共通の話題が増えるんじゃないのか。
「……そうか」
自分でも聞き慣れない程に低く、硬質な声になった。腕の中に居た名前の体温が、急に遠くなった気がする。背中を温めていた筈の太陽が、いつの間にか分厚い雲に覆われたように、部屋の光量がふっと下がった。ソファの肘掛けに落ちる俺の影が、濃く、長くなった。
「賢二郎? どうしたの、疲れてる?」
俺の胸から頬を離し、不思議そうにこちらを見上げる名前の双眸に、俺の無表情が映っている。違う。そんな顔がしたいわけじゃない。只、黒く渦巻く感情の波に、どうやって蓋をすればいいのか分からなかった。彼女の弟に嫉妬するなんて、余りに馬鹿げていて、ガキ染みている。プライドが邪魔をして、素直な言葉が出てこない。
「……別に」
最悪の返事だった。唇から滑り落ちたその一言は、俺と名前の間に透明な冷たい壁を作るには充分過ぎた。名前の瞳が、ほんの少しだけ揺らぐ。その小さな変化に気づき、自己嫌悪で胸が軋んだ。
ああ、クソ。どうして、俺はこんな時まで可愛げのない男なんだ。瀬見さん辺りが見ていたら、「ほんっと、お前は可愛くねーな!」と怒鳴られているに違いない。
違う、違うんだ、名前。お前の弟がどうとかじゃなく、俺が、只、お前を取られたくないだけで。お前の世界で、俺が一番じゃなくなったらどうしようって、下らない不安に駆られてるだけで。
言える筈もなかった。黙り込んだ俺を、名前はじっと見つめている。その静かな視線が、今は少しだけ痛かった。
 賢二郎の心音が、不意にリズムを変えた。
それまで、一定のテンポで安心させてくれた音が、少しだけ速く、硬くなった。わたしが、弟の話をした、ほんの数秒後のことだ。
胸に当てていた耳をそっと離し、賢二郎の顔を見上げる。ミルクティー色の前髪の下で、普段は強い光を宿している瞳が、今はどこか遠くを見ているようだった。
「賢二郎? どうしたの、疲れてる?」
わたしの問いに、彼は一拍遅れて焦点を合わせた。けれど、その唇から零れたのは、素っ気ない「別に」と云う一言。
その瞬間、ぽかぽかと暖かかった部屋の空気が、急にひやりと肌を撫でた気がした。窓の外では、太陽が雲の切れ間に隠れ、世界から彩度が一段階失われている。賢二郎の纏う雰囲気も、その雲のように翳りを帯びていた。
何がいけなかったのだろう。
わたしの頭の中が、高速で回転を始める。弟の話? 白鳥沢? それとも、わたしが勧めた、と云う部分?
賢二郎は、余り自分の感情を表に出す方ではない。でも、わたしと二人きりの時は、存外分かり易かった。嬉しい時は、少しだけ口角が上がるし、楽しい時は目がきらきらと輝く。そして、今の彼は、明らかにそのどちらでもなかった。寧ろ、何かを我慢しているような、苦しそうな顔色。
わたしは、賢二郎が苦しむ姿を見るのが、一番嫌いだ。
賢二郎の腕の中からそっと抜け出し、ソファの上で、彼と向き合うように座り直す。
「賢二郎」
名前を呼ぶと、彼は居心地が悪そうに視線を逸らした。その仕草が迷子の子供のようで、胸の奥がきゅっと締め付けられる。
「わたし、何か、賢二郎が嫌なことを言ったかな」
「……いや」
「嘘だよ。さっきまで、笑っていたでしょう?」
「…………」
「教えてくれないの」
わたしの声が、自分で思うよりも寂しげに響いたのかもしれない。賢二郎は一度固く唇を結ぶと、観念したように大きな溜息を一つ吐いた。
その時だった。
「おや、どうしたんだい、二人共。まるで、〆切前の俺と、担当編集者のような緊張感じゃないか」
リビングのドアが開き、ひょっこりと顔を出したのは、兄貴兄さんだった。胸元に『人生、山あり谷あり〆切あり』と書かれたスウェットを着ている。また変な服を。
「兄貴さん。こんにちは」
「こんにちは、賢二郎くん。……さては、君達。ぽかぽかと背中を温めていた太陽が、丁度、陰ったところかな?」
作家特有の言い回しで、兄さんは的確に状況を表現する。そして、賢二郎の硬い表情と、わたしの困惑した様子を交互に見比べると、合点がいったようにポンと手を打った。
「ふむ、さては、弟の話かい? あの子は昔から、名前にべったりだからね。賢二郎くんの気持ちも、分からなくはないよ」
兄さんの推測に、賢二郎の肩がぴくりと跳ねる。
わたしは漸く全てのピースが繋がった気がした。
弟。弟。べったり。……嫉妬?
まさか。賢二郎が? わたしの弟に?
「……本当に、弟のこと?」
わたしが尋ねると、賢二郎は気まずそうに顔を伏せてしまった。ミルクティー色の前髪がさらりと揺れて、彼の表情を隠す。その沈黙が、何より雄弁な肯定だった。
途端に、わたしの心の中に、温かくて擽ったい感情が泉のように湧き上がる。
ああ、なんだ。そうだったの。
「賢二郎、わたしの弟に嫉妬したの? ……ふふ、可愛いね」
思わず笑みが零れた。すると、賢二郎は俯けていた顔を勢いよく上げ、耳まで真っ赤に染めながら、わたしを睨んだ。
「っ、可愛くねぇ!」
「ううん、可愛いよ。凄く」
わたしは彼の傍へにじり寄り、綺麗な形の頭をよしよしと撫でた。最初は抵抗していた賢二郎も、やがて諦めたように、その手を甘んじて受け入れる。
「わたしが一番好きなのは、賢二郎だよ。弟は大切な弟。それだけ。それにね、もし、弟が白鳥沢のバレー部に入ったら、賢二郎の話を沢山聞けるから、わたしは嬉しいなと思っていたんだ。賢二郎が練習を頑張っている話とか、試合で活躍した話とか。わたしの知らない、部活での賢二郎のことを、弟が教えてくれるでしょう?」
わたしの考えを、賢二郎は黙って聞いていた。その瞳の揺れが、少しずつ収まっていくのが分かる。翳りを帯びていた彼の世界に、再び光が射し込んだようだ。
「……悪かった」
「ううん。賢二郎が、わたしのことを、それだけ想ってくれているってことだよね? 嬉しいよ、本当に」
雲の切れ間から太陽が顔を出し、オレンジ色に染まった陽光が室内に溶け込み始めた。それは、賢二郎の心の雪解けを祝福しているかのようだった。
賢二郎は黙ったままだけれど、先程よりもずっと優しい力で、わたしを抱き締めてくれた。彼の首に腕を回すと、とくん、とくん、と、もう迷いのない、力強い心音が聞こえてくる。
「……名前」
「なぁに、賢二郎」
「……好きだ」
耳元で囁かれた掠れ声に、わたしの心臓も大きく跳ねる。
「わたしもだよ」
「おっと、若人の邪魔はしない主義でね」と、兄さんが静かにリビングを出ていく気配がした。
夕日が作り出す二つの長い影が、床の上でぴったりと一つに重なっている。陰ってしまった太陽も、こうしてまた顔を覗かせてくれるのなら悪くない。寧ろ、その光の有難みを、より深く感じられるのかもしれない。
賢二郎の背中をぽんぽんと軽く叩きながら、わたしは思う。
この不器用で、独占欲が強くて、最高に可愛い恋人との日常は、どんな名作小説よりも、わたしの心を揺さぶるのだ、と。
今度、弟に会ったら、賢二郎が嫉妬していたことをこっそり教えてあげようか。きっと面白い反応をするに違いない。……でも、それはまた、賢二郎を拗ねさせてしまうかな。
わたしは一人、くすりと笑って、愛しい人の腕の中で、静かに瞼を閉じた。
賢二郎の心音が、不意にリズムを変えた。
それまで、一定のテンポで安心させてくれた音が、少しだけ速く、硬くなった。わたしが、弟の話をした、ほんの数秒後のことだ。
胸に当てていた耳をそっと離し、賢二郎の顔を見上げる。ミルクティー色の前髪の下で、普段は強い光を宿している瞳が、今はどこか遠くを見ているようだった。
「賢二郎? どうしたの、疲れてる?」
わたしの問いに、彼は一拍遅れて焦点を合わせた。けれど、その唇から零れたのは、素っ気ない「別に」と云う一言。
その瞬間、ぽかぽかと暖かかった部屋の空気が、急にひやりと肌を撫でた気がした。窓の外では、太陽が雲の切れ間に隠れ、世界から彩度が一段階失われている。賢二郎の纏う雰囲気も、その雲のように翳りを帯びていた。
何がいけなかったのだろう。
わたしの頭の中が、高速で回転を始める。弟の話? 白鳥沢? それとも、わたしが勧めた、と云う部分?
賢二郎は、余り自分の感情を表に出す方ではない。でも、わたしと二人きりの時は、存外分かり易かった。嬉しい時は、少しだけ口角が上がるし、楽しい時は目がきらきらと輝く。そして、今の彼は、明らかにそのどちらでもなかった。寧ろ、何かを我慢しているような、苦しそうな顔色。
わたしは、賢二郎が苦しむ姿を見るのが、一番嫌いだ。
賢二郎の腕の中からそっと抜け出し、ソファの上で、彼と向き合うように座り直す。
「賢二郎」
名前を呼ぶと、彼は居心地が悪そうに視線を逸らした。その仕草が迷子の子供のようで、胸の奥がきゅっと締め付けられる。
「わたし、何か、賢二郎が嫌なことを言ったかな」
「……いや」
「嘘だよ。さっきまで、笑っていたでしょう?」
「…………」
「教えてくれないの」
わたしの声が、自分で思うよりも寂しげに響いたのかもしれない。賢二郎は一度固く唇を結ぶと、観念したように大きな溜息を一つ吐いた。
その時だった。
「おや、どうしたんだい、二人共。まるで、〆切前の俺と、担当編集者のような緊張感じゃないか」
リビングのドアが開き、ひょっこりと顔を出したのは、兄貴兄さんだった。胸元に『人生、山あり谷あり〆切あり』と書かれたスウェットを着ている。また変な服を。
「兄貴さん。こんにちは」
「こんにちは、賢二郎くん。……さては、君達。ぽかぽかと背中を温めていた太陽が、丁度、陰ったところかな?」
作家特有の言い回しで、兄さんは的確に状況を表現する。そして、賢二郎の硬い表情と、わたしの困惑した様子を交互に見比べると、合点がいったようにポンと手を打った。
「ふむ、さては、弟の話かい? あの子は昔から、名前にべったりだからね。賢二郎くんの気持ちも、分からなくはないよ」
兄さんの推測に、賢二郎の肩がぴくりと跳ねる。
わたしは漸く全てのピースが繋がった気がした。
弟。弟。べったり。……嫉妬?
まさか。賢二郎が? わたしの弟に?
「……本当に、弟のこと?」
わたしが尋ねると、賢二郎は気まずそうに顔を伏せてしまった。ミルクティー色の前髪がさらりと揺れて、彼の表情を隠す。その沈黙が、何より雄弁な肯定だった。
途端に、わたしの心の中に、温かくて擽ったい感情が泉のように湧き上がる。
ああ、なんだ。そうだったの。
「賢二郎、わたしの弟に嫉妬したの? ……ふふ、可愛いね」
思わず笑みが零れた。すると、賢二郎は俯けていた顔を勢いよく上げ、耳まで真っ赤に染めながら、わたしを睨んだ。
「っ、可愛くねぇ!」
「ううん、可愛いよ。凄く」
わたしは彼の傍へにじり寄り、綺麗な形の頭をよしよしと撫でた。最初は抵抗していた賢二郎も、やがて諦めたように、その手を甘んじて受け入れる。
「わたしが一番好きなのは、賢二郎だよ。弟は大切な弟。それだけ。それにね、もし、弟が白鳥沢のバレー部に入ったら、賢二郎の話を沢山聞けるから、わたしは嬉しいなと思っていたんだ。賢二郎が練習を頑張っている話とか、試合で活躍した話とか。わたしの知らない、部活での賢二郎のことを、弟が教えてくれるでしょう?」
わたしの考えを、賢二郎は黙って聞いていた。その瞳の揺れが、少しずつ収まっていくのが分かる。翳りを帯びていた彼の世界に、再び光が射し込んだようだ。
「……悪かった」
「ううん。賢二郎が、わたしのことを、それだけ想ってくれているってことだよね? 嬉しいよ、本当に」
雲の切れ間から太陽が顔を出し、オレンジ色に染まった陽光が室内に溶け込み始めた。それは、賢二郎の心の雪解けを祝福しているかのようだった。
賢二郎は黙ったままだけれど、先程よりもずっと優しい力で、わたしを抱き締めてくれた。彼の首に腕を回すと、とくん、とくん、と、もう迷いのない、力強い心音が聞こえてくる。
「……名前」
「なぁに、賢二郎」
「……好きだ」
耳元で囁かれた掠れ声に、わたしの心臓も大きく跳ねる。
「わたしもだよ」
「おっと、若人の邪魔はしない主義でね」と、兄さんが静かにリビングを出ていく気配がした。
夕日が作り出す二つの長い影が、床の上でぴったりと一つに重なっている。陰ってしまった太陽も、こうしてまた顔を覗かせてくれるのなら悪くない。寧ろ、その光の有難みを、より深く感じられるのかもしれない。
賢二郎の背中をぽんぽんと軽く叩きながら、わたしは思う。
この不器用で、独占欲が強くて、最高に可愛い恋人との日常は、どんな名作小説よりも、わたしの心を揺さぶるのだ、と。
今度、弟に会ったら、賢二郎が嫉妬していたことをこっそり教えてあげようか。きっと面白い反応をするに違いない。……でも、それはまた、賢二郎を拗ねさせてしまうかな。
わたしは一人、くすりと笑って、愛しい人の腕の中で、静かに瞼を閉じた。