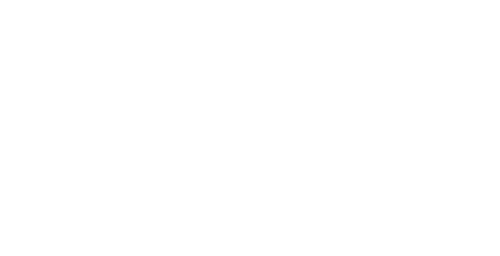しゅわしゅわの恋。
※弟の描写が含まれます。
俺と苗字名前の関係性は、時として、咽喉を焼く程に冷えた炭酸飲料と似ている。甘やかな液体が舌を喜ばせた次の瞬間には、無数の気泡が弾け、ちりちりと小気味良い痛みを与える。先週、俺が彼女の弟に抱いた見苦しい嫉妬は、正に予期せぬ刺激だった。あの疼くような感覚は、まだ胸の奥で微かに燻っている。
約束の日。水族館の入口を潜ると、世界は瞬く間に紺碧の深海へと姿を変えた。頭上を覆うアーチ状の水槽内を、光を弾く魚の群れが、銀色の竜巻となって駆け抜ける。外界の喧騒から隔絶された静謐な空間で、水の揺らぎが壁や床に、絶えず変化する光彩の模様を描き出していた。
「……凄いな」
知らず漏れた感嘆の声に、隣を歩く名前が縦に頷いた。青い光耀に染め上げられた彼女の横顔は、この世のものとは思えない程に神秘的な美しさを湛えている。色素の薄い肌は陶器のように滑らかで、深い海底の色を映した双眸は好奇心に満ち、きらきらと輝いていた。非現実的なまでの存在感に、俺はそっとその指先に触れた。彼女の隣に居ると云う事実を、今、確かめたかったのかもしれない。ひやりとした指が、俺の熱を帯びた指に絡み付く。
順路に沿って進むと、軈て大小様々な水槽が並ぶエリアに出た。俺達はゆらゆらと傘を揺らしながら漂うクラゲの前で、足を止める。照明に包まれて淡い光を放つ姿は、夜空に浮かぶ幽霊のようだ。
「賢二郎のトスみたいだね」
「……ハァ?」
唐突な名前の感想に、俺は図らずも素っ頓狂な声を上げた。俺のトスが、クラゲ? 意味が分からず眉根を寄せると、彼女は飼育槽から視線を外さないまま、落ち着いた声音で続けた。
「静かで、正確で、無駄がない。意思があるような、ないような、でも、ちゃんと目的地を知っている。スパイカーが一番打ち易い最高の場所に、いつの間にか届いてる。この子達を見ていると、それを思い出すんだ」
予想の斜め上を行く賞詞に、俺は返す言葉を失った。俺のプレーを、そんな風に見てくれていたのか。俺が、コート上で信条とする"目立たないこと"の本質を的確に言い当てられた気がして、心臓が大きく脈打つ。気恥ずかしさと、それを遥かに上回る喜びが、じわりと胸に広がった。
「……お前、時々、ワケ分かんねぇこと言うな」
照れ隠しにそう吐き捨てれば、名前は悪戯っぽく笑い、俺の腕に自身の両腕を絡ませた。ジャケット越しに伝わる柔らかな感触と、フローラルな甘い香りに、俺の思考は再び正常な働きを停止させる。全く、こいつは。
次に訪れたペンギンのコーナーは、家族連れで賑わっていた。陸上でのぎこちない動きとは裏腹に、水中を弾丸めいた速度で泳ぎ回るジェンツーペンギンの姿に、名前は感心したように目を丸くしている。
「あのペンギン、弟にちょっと似ているね。一人だけ違う方向に行こうとして、結局、皆の所に慌てて戻っていくところが」
出た。その名前。
脳内で、瞬時に警報が鳴り響く。先週の醜態がフラッシュバックし、口許が引き攣るのを感じた。俺が内心で身構えていることなど露知らず、名前は無邪気に話し続ける。
「賢二郎はイルカかな。賢くて、クールに見えるけれど、本当は凄く情熱的。仲間との連携も完璧だし」
「……そうかよ」
どうやら、今日は何でも生き物に例える日らしい。一瞬、弟の名前にざらついた心が、イルカと云う評価で僅かに浮上する。我ながら、単純なものだ。そんな俺の機微を正確に読み取ったかのように、名前は繋いだ手にきゅっと力を込めた。
「わたしは、賢二郎と云うイルカを独り占めできる、世界で一番幸せな飼育員だね」
「……飼育員かよ」
自然と零れた苦笑は、先程までのささくれ立った感情を綺麗に洗い流してくれた。甘い言葉を囁いたかと思えば、突如として突き放すような刺激を与える。矢張り、こいつは炭酸飲料そのものだ。抗い難く、癖になる。
 館内を一通り巡った後、俺達は当初の目的だった大水槽前に辿り着いた。視界いっぱいに広がる巨大なアクリルの向こう側で、雄大なジンベエザメがゆったりと泳ぎ、銀色の魚群が光のカーテンみたいに煌めいている。備え付けのベンチに並んで座り、眼前の壮大な光景を眺めていると、自らも海中に溶け込んでしまったかのような錯覚に陥った。
暫く、無言の時間が流れる。この静寂が、俺は嫌いではなかった。言葉を交わさなくても、隣に名前の体温を感じられるだけで満たされていた。
「ねぇ、賢二郎」
不意に、名前が深閑を破った。
「わたし、賢二郎が嫉妬してくれて、本当に、少し嬉しかったんだよ」
その科白に、俺は息を呑んだ。心臓を見透かされた心地がして、名前に視線を向けることができない。ジンベエザメの影が、俺達の足許を悠々と横切る。
「だって、それだけ、わたしのことを想ってくれているってことでしょう? わたしもね、賢二郎が女の子と親しげに話していたら、きっと凄く嫌な気持ちになる。心臓が縮こまると思う」
名前は、俺の顔を覗き込むようにして、少しだけ身を乗り出した。深い海の瞳が、俺を真っ直ぐに射抜いている。
「賢二郎は、わたしだけのものだから」
余りにも率直な独占欲の告白に、俺は完全に思考を奪われた。カッと顔面に熱が集まり、耳の端が燃えるように熱くなる。
なんだ、こいつは。こんな殺し文句を、こんな場所で、平然と口にするのか。
「……お前、そう云うこと、よく平気で言えるな」
絞り出した声は、自分の聴力を疑う程に掠れていた。名前は心底可笑しそうに、くすりと喉を鳴らして笑った。
「本当のことだから。賢二郎は、ただ甘いだけじゃない。時々、しゅわしゅわして、ちょっとだけ、ぴりっとする。でも、わたしはそんな賢二郎が一番好きだよ」
ああ、クソ。完敗だ。
俺は二の句が継げなくなり、名前の薄い肩をぐいと引き寄せ、淡い桃色の唇を塞ぐことで、反撃の代わりとした。俄かに見開かれた双眸が、とろりと蕩ける様子を間近で見つめる。水槽の青い光源が、二人だけの世界を優しく照らしていた。
帰り際、併設された『Blue Fin Cafe』で、『雫とヒレのクリームソーダ』を頼んだ。鮮やかな緑色のソーダは浅瀬で、バニラアイスは水面に浮かぶ白いヒレをイメージしているらしい。弾ける炭酸の泡と溶け合う甘さは、まるで、俺達のようだと思った。
「……んぶっ」
ストローを勢いよく吸い込んだ所為で、炭酸の刺激に咽てしまう。げほげほと派手に咳き込む俺を見て、名前が楽しそうに笑っている。
「ふふ、可愛いね、賢二郎」
「……可愛くねぇ」
悪態をつきながらも、声には刺々しさがない。差し出されたナプキンを素直に受け取り、口許を拭う。
甘くて、少しだけ辛くて、どうしようもなく愛おしい日常。この場所に胸を張って帰る為にも、俺は明日からもコートの上で戦い続ける。
カフェを出て、夕暮れの道を並んで歩く。繋いだ手は、先程よりもずっと温かかった。
「……名前」
「うん?」
「次のオフは、どこにも行かない」
「そう。偶には、ゆっくり休息する日も必要だね」
「違う。一日中、お前を離さないって意味だ」
俺の否定に、名前はきょとんと目を瞬かせた後、幸せそうに微笑んだ。その表情を見ているだけで、腹の底から熱いものが込み上げる。
甘くて辛い、炭酸飲料のような恋人に、俺は一生翻弄され続けるのだろう。それも悪くない。いや、それがいい。
館内を一通り巡った後、俺達は当初の目的だった大水槽前に辿り着いた。視界いっぱいに広がる巨大なアクリルの向こう側で、雄大なジンベエザメがゆったりと泳ぎ、銀色の魚群が光のカーテンみたいに煌めいている。備え付けのベンチに並んで座り、眼前の壮大な光景を眺めていると、自らも海中に溶け込んでしまったかのような錯覚に陥った。
暫く、無言の時間が流れる。この静寂が、俺は嫌いではなかった。言葉を交わさなくても、隣に名前の体温を感じられるだけで満たされていた。
「ねぇ、賢二郎」
不意に、名前が深閑を破った。
「わたし、賢二郎が嫉妬してくれて、本当に、少し嬉しかったんだよ」
その科白に、俺は息を呑んだ。心臓を見透かされた心地がして、名前に視線を向けることができない。ジンベエザメの影が、俺達の足許を悠々と横切る。
「だって、それだけ、わたしのことを想ってくれているってことでしょう? わたしもね、賢二郎が女の子と親しげに話していたら、きっと凄く嫌な気持ちになる。心臓が縮こまると思う」
名前は、俺の顔を覗き込むようにして、少しだけ身を乗り出した。深い海の瞳が、俺を真っ直ぐに射抜いている。
「賢二郎は、わたしだけのものだから」
余りにも率直な独占欲の告白に、俺は完全に思考を奪われた。カッと顔面に熱が集まり、耳の端が燃えるように熱くなる。
なんだ、こいつは。こんな殺し文句を、こんな場所で、平然と口にするのか。
「……お前、そう云うこと、よく平気で言えるな」
絞り出した声は、自分の聴力を疑う程に掠れていた。名前は心底可笑しそうに、くすりと喉を鳴らして笑った。
「本当のことだから。賢二郎は、ただ甘いだけじゃない。時々、しゅわしゅわして、ちょっとだけ、ぴりっとする。でも、わたしはそんな賢二郎が一番好きだよ」
ああ、クソ。完敗だ。
俺は二の句が継げなくなり、名前の薄い肩をぐいと引き寄せ、淡い桃色の唇を塞ぐことで、反撃の代わりとした。俄かに見開かれた双眸が、とろりと蕩ける様子を間近で見つめる。水槽の青い光源が、二人だけの世界を優しく照らしていた。
帰り際、併設された『Blue Fin Cafe』で、『雫とヒレのクリームソーダ』を頼んだ。鮮やかな緑色のソーダは浅瀬で、バニラアイスは水面に浮かぶ白いヒレをイメージしているらしい。弾ける炭酸の泡と溶け合う甘さは、まるで、俺達のようだと思った。
「……んぶっ」
ストローを勢いよく吸い込んだ所為で、炭酸の刺激に咽てしまう。げほげほと派手に咳き込む俺を見て、名前が楽しそうに笑っている。
「ふふ、可愛いね、賢二郎」
「……可愛くねぇ」
悪態をつきながらも、声には刺々しさがない。差し出されたナプキンを素直に受け取り、口許を拭う。
甘くて、少しだけ辛くて、どうしようもなく愛おしい日常。この場所に胸を張って帰る為にも、俺は明日からもコートの上で戦い続ける。
カフェを出て、夕暮れの道を並んで歩く。繋いだ手は、先程よりもずっと温かかった。
「……名前」
「うん?」
「次のオフは、どこにも行かない」
「そう。偶には、ゆっくり休息する日も必要だね」
「違う。一日中、お前を離さないって意味だ」
俺の否定に、名前はきょとんと目を瞬かせた後、幸せそうに微笑んだ。その表情を見ているだけで、腹の底から熱いものが込み上げる。
甘くて辛い、炭酸飲料のような恋人に、俺は一生翻弄され続けるのだろう。それも悪くない。いや、それがいい。