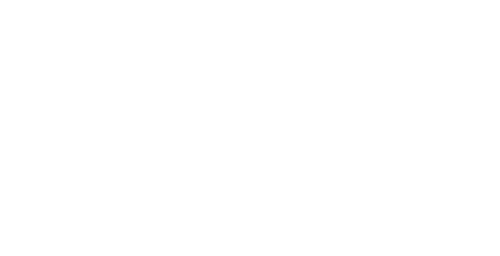苦手な筈の香りに包まれながら、
白布は彼女の"嘘"すら愛そうとする。
白布賢二郎は、薔薇の香りが苦手だった。
けれど、それが彼女の部屋に漂う匂いなら、話は別だった。
重厚な遮光カーテンの隙間から、午後の蜂蜜色の光が細く差し込むマンションの一室。ソファに深く腰掛けた苗字名前は、いつものように静謐な微笑みを湛えていた。その薄桃色の唇が緩やかに弧を描く度、白布は己の心臓が確かに一つ、大きく脈打つのを感じた。
ふわりと、微かな薔薇の香りを纏った風が窓から流れ込み、彼女の艶やかな髪を揺らす。夜の海の底に沈んだ秘宝を覗き込むような、深く暗い双眸が、ゆっくりとこちらを向いた。その瞳は、感情の揺らぎを容易には見せない。
「賢二郎、黙って見ていると、何を考えているのか、全部伝わってくるんだよ」
「……そう?」
返す声は、自分でも気づく程、微かに掠れていた。風邪ではない。問題は思考の方だ。名前と共に居ると、白布は常の冷静さを保つのが難しい。
隣に居るだけで、彼女の柔らかな体温が、甘く悩ましい香りが、静かな呼吸の一つひとつが、白布の中の何かをじわじわと、確実に満たしていく。
こんなにも穏やかに見える彼女が、昨夜、熱に浮かされたように腕を絡めて、名を何度も呼んだのだ。まだ喉の奥に、あの時の掠れた声の余韻が残っている気がした。
それでも――昼間の名前は別人みたいに涼やかな顔をしている。そのギャップがまた、白布を掻き乱す。
「ねえ、賢二郎」
「ん?」
「……"好き"って言葉は、嘘にも使えると思う?」
瞬間、心臓が鷲掴みにされたように跳ねた。
彼女は窓際から、その吸い込まれそうな瞳でこちらを見据えている。その目には悪戯の色はなく、真剣と言うよりも、ただ只管に静かで、どこか無垢な光を宿していた。
「まあ……使おうと思えば、使えるんじゃないか」
答えながら、白布は無意識に眉を顰めた。こういう抽象的な問い掛けは苦手だ。けれど、名前が望むのなら、逃げるという選択肢は彼の中にはなかった。
「使ったこと、ある?」
「ない」
即答だった。嘘偽りなく。
名前は「そう」とだけ小さく呟くと、白い陶器のような指先で、ローテーブルに飾られた一輪挿しの薔薇の花弁をそっと撫でながら、何かを深く考えているようだった。
やがて、ぽつりと呟く。
「わたしね、昨日、兄貴兄さんに聞かれたの。『どうして、賢二郎くんを好きなの?』って」
白布の指が、ぴくりと止まる。
それは……尋問か、或いは面接か。いや、あの独特な感性を持つ名前の兄ならば、どちらでも有り得そうだ。
「答えたの?」
「うん。『一緒に居ると、ちょっとだけ心が騒がしくなるの』って」
囁くような、小さな声だった。
その言葉は、白布にとっては答えになっていないくらい曖昧で、けれど、どうしようもなく胸を打つものだった。彼女の中に、自分という存在が何か特別な感情を、微細な波紋を生み出している。それが、名前の世界の中で、他の誰にも許されない、自分だけの特別な領域だったとしたら――。
「俺も……偶に、思うことある」
白布は慎重に言葉を選びながら口を開いた。
「お前が、俺を好きだって言ってくれるのは、本当なんだろうけど……俺が、その事実が嬉し過ぎて、時々、信じられなくなることがある」
名前は小さく、吐息のように笑った。
「それは、わたしの言葉を"偽り"だと思うってこと?」
「違う。……違うけど、」
白布は、名前の顔を真っ直ぐに見つめた。彼女の眼差しの奥に、静まり返った水面のようなものが揺らめいているのが見えた。
「例えば、天使が目の前に現れて『愛してる』って囁いたとして、そいつがもし悪魔だったらどうしよう、って思うのに似てる。そんな感じだ」
「ふぅん……詩的だね」
「いや、全然、そんなつもりじゃ……」
言い掛けて、白布は言葉を飲み込んだ。
名前が音もなく近づいてきた。まるで幻のように、芳しい薔薇の香りと共に、すぐ目の前にその姿を現す。
彼女の白く細い手が、そっと彼の頬に添えられた。ひんやりとした指先が、擽るように肌を撫でる。
「じゃあ、"天使のフリをした悪魔"でも、いいかな」
「え……」
「"偽り"の言葉を吐いてでも、賢二郎に触れていたいって思うくらい、わたしの愛は深いんだ」
それは囁きだった。
音量ではない。その質の問題だ。鼓膜を震わせるのではなく、直接、心臓に届くような、そんな声。
白布は一瞬、目を閉じた。息が詰まりそうになる。思春期特有の熱っぽい反応も、今や、ただの抗えない物理的な証拠でしかなかった。
「……お前、ズルいよ」
絞り出すような声だった。
「そう?」
「でももう、何言われても、俺は信用してる」
「うん。それでいい」
ふわりと花が綻ぶように微笑んで、名前は彼の膝の上に軽やかに腰を下ろした。スカートの裾が優雅に舞い、滑らかな太腿の冷たさが、熱を帯びた肌にじわりと伝わる。
そのまま、白布の肩口に額を預ける。
「偽りだと知っていても、信じたい言葉って、あるんだよ」
「それを言うなら、俺も――」
けれど、それ以上、白布は何も言葉を紡ぐことができなかった。
彼女の薄桃色の唇が、彼の首筋に、そっと触れたからだ。
天使が囁いたのだ。例え、それが偽りの愛の言葉だったとしても。
それでも、白布は全身全霊で、その甘美な毒を受け止めた。
――なあ、名前。お前が天使であろうと悪魔であろうと、俺にとっては、もうそんなことは関係ないんだよ。
そんなことを胸の内で呟きながら、白布は華奢な背中にそっと腕を回した。
窓の外では、薔薇の花が、そろそろその花びらを散らし始める季節だった。