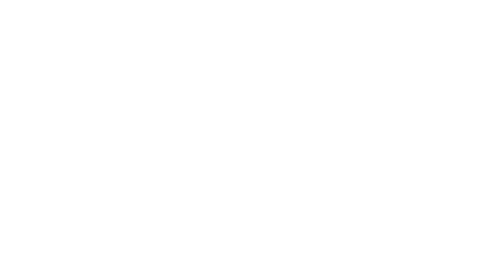Past Episode.
"例外"と云う言葉でしか表現できない、俺だけの特別。
※兄貴と弟が登場します。
練習後の体育館に漂う、汗と熱気が混じり合った、噎せ返るような空気。それを肺の奥まで吸い込んでしまわぬよう、俺は足早に部室へと向かう。床に散らばったボール、無造作に脱ぎ捨てられたビブス、誰かが飲み残したスポーツドリンクのスクイズボトル。視界に入るもの全てが、俺の定めた衛生基準値を軽々と逸脱していく。
「佐久早、今日はこの後、どうすんの? ラーメン、食いに行かね?」
背後から掛けられた、古森の能天気な声に、俺は振り返りもせずに答える。
「行かない。お前、その手で麺を啜るのか」
「ちゃんと洗うって! つーか、お前のその言い草、俺に失礼だろ!」
喧しい。そもそも、不特定多数の人間が出入りし、油が飛散するような空間に、自ら進んで身を置くこと自体が理解不能だ。俺はロッカーから手早く荷物を取り出すと、さっさと着替えを済ませ、新品のマスクを装着した。フィルター越しに吸う空気は、僅かにマシに感じられる。
「じゃあな」
「あ、おい、佐久早! ちょっと待てって!」
古森の制止を無視して部室を出ると、校門の傍ら、夕暮れの茜色に染まる桜並木の下に、その姿はあった。
苗字名前。
他の生徒達の喧騒も、舞い散る埃も、彼女を中心とした不可視の結界に阻まれているかのように、その一角だけが凛とした静寂を保っている。俺の気配に気づくと、夜の湖面を思わせる瞳が、僅かに和らいだ。
「臣くん、お疲れ様」
「……うん。待たせた?」
「ううん。今、来たところ。行こうか」
並んで歩き出す。名前の隣は、俺にとって唯一の安全地帯だ。俺の世界を脅かすあらゆるノイズが、彼女の存在によって遮断され、濾過される。この心地良さを知ってしまったから、俺はもう一人ではいられなくなった。
名前の住むマンションは、今日も要塞の如き静けさで、俺達を迎えた。外界の雑菌と喧騒から、完全に隔離された空間。エレベーターのボタンを押す彼女の指先は、寸分の躊躇いもなく、その動き一つ取っても育ちの良さが窺える。
リビングのドアを開けると、ソファに寝そべってゲームをしていた弟が、こちらを一瞥した。
「あ、来たのか。潔癖」
「……こんにちは、弟くん」
「姉さん、こいつ、腹減ってるって。なんか作ってやったら?」
「臣くん、何か食べる?」
「いや、いい」
俺が答えると同時に、奥の書斎と思われる部屋から、ひょっこりと顔が覗いた。名前の兄、苗字兄貴さん。その貌立ちは、弟の弟や妹の名前と同じく、神が精魂込めて作り上げた芸術品のように整っている。だが、その美貌を台無しにする、致命的な欠点があった。
「やあ、清潔くん! 待っていたよ!」
兄貴さんが身に纏っていたのは、胸元に黒のゴシック体で、こうプリントされたTシャツだった。
――『〆切 is デッドライン』
……なんだ、それは。英語と日本語の重複表現だ。デッドラインは〆切だろう。その程度のことも分からずに、よく作家が務まるものだ。俺の眉間の皺が、無意識の内に深くなる。
「兄貴兄さん、今日はご機嫌だね」
「ああ、名前! 新しい物語のプロットが、今まさに天から降ってきたんだ!」
そう言って、兄貴さんは芝居がかった仕草で天を仰ぐと、きらきらと瞳を輝かせながら、俺と名前を交互に見た。その視線が、獲物を見定める肉食獣のようで、俺は僅かに身構える。
「テーマはね、『名付け得ぬ感情』だ!」
「……名付け得ぬ、感情?」
「そう! 例えば、君たち二人を見ていると、俺の脳内に無数の言葉が浮かんでくる。純愛、共依存、或いは聖域と侵略者……。だが、どれもしっくり来ない。この、既存の言葉では定義できない、二人だけの関係性。それに名前を付けるとしたら、一体、どんな言葉が相応しいのか。それを探求する物語だ!」
得意満面に語る兄貴さんに、俺は返す言葉を失った。この男は、俺と名前の関係を、己の創作のネタにしようとしている。しかも、その考察が妙に的を射ていて、反論し辛いのが腹立たしい。
「……そうですか」
「どうだい、清潔くん! 君なら、この感情にどんな名前を付ける?」
無茶振りにも程がある。俺は黙り込んだまま、隣の名前に助けを求めるように視線を送った。彼女は悪戯っぽく微笑むと、俺の袖を軽く引いた。
「兄さん、その話はまた今度。臣くんが困っているでしょう」
「おっと、そうだった。すまないね、清潔くん。創作の神が降りてくると、つい我を忘れてしまうんだ」
兄貴さんはそう言ってあっさりと引き下がったが、その瞳の奥には、未だ尽きぬ好奇の色が揺らめいていた。この兄妹は揃いも揃って、俺の心の壁をいとも容易く乗り越えてくる。
 兄から解放され、わたしの部屋へと移動するなり、臣くんは大きな溜め息と共にベッドの縁に腰を下ろした。あからさまに不機嫌を露わにしている。その理由が、わたしの兄にあると思うと、少し申し訳ないような、面白いような、複雑な気持ちになる。
「……あの人、いつもあんな調子なのか」
「うん。インスピレーションが湧くと、周りが見えなくなるから」
「〆切 is デッドライン、ってなんだ。意味が重複してるけど」
「ふふ、きっと、それくらい切羽詰まっていると云うことだよ」
几帳面な臣くんらしい指摘に、思わず笑みが零れた。彼はむっとした顔でわたしを一瞥すると、視線を逸らしてぽつりと呟く。
「……名付け得ぬ、感情、か」
どうやら、兄の言葉が心に引っ掛かっているらしい。わたしは彼の隣にそっと腰を下ろし、その横顔を見つめた。マスクで半分以上が隠れているけれど、眉間に刻まれた皺と、僅かに尖った眼差しが、臣くんの不満を雄弁に物語っている。
「臣くんにとって、わたしとの関係は、名前を付けられないようなもの?」
問い掛けると、彼は少しの間を置いた後、逡巡するように口を開いた。
「……分からない。ただ、お前は、俺のルールの、唯一の例外だ」
その返答は、臣くんがくれるどんな甘い科白よりも、わたしの心を震わせた。
潔癖で、神経質で、自分の中に揺るぎない秩序を築いて生きている彼。その完璧に構築された世界の中で、わたしだけが「例外」として存在することを許されている。それは、どれ程に特別なことだろう。
「それに名前を付けるなら、なんだろうね」
わたしは独り言のように呟きながら、臣くんの手に、自分の手をそっと重ねた。バレーボールを叩き付ける、大きくて節くれ立った指。その指が驚いたようにぴくりと震え、けれど、振り払われることはない。
「恋、とか、愛、とか。そう云う、誰でも使える有り触れた言葉じゃ、しっくり来ない気がするんだ」
「……」
「臣くんとわたしの間にだけ流れている、この空気。この気持ち。他の誰にも理解されなくていい。二人だけの、特別な名前があったら、素敵だと思わない?」
見上げると、マスクの上にある彼の瞳が、深く、静かにわたしを捉えていた。その黒曜石のような瞳の奥で、様々な感情が渦巻いているのが分かる。戸惑い、苛立ち、そして、それらを遥かに凌駕する、抗い難い程の愛おしさ。
やがて、臣くんは諦めたように息を吐くと、わたしの手を力強く握り返した。
「……そんなもの、必要ない」
低く、掠れた声。
「名前なんて、どうでもいい。お前が、俺の隣に居る。……それだけで、いい」
不器用で飾り気のない、臣くんの世界の全てが詰まった言葉。
ああ、もう。
わたしは、この人がどうしようもなく好きだ。
わたしは衝動のままに身を乗り出し、臣くんのマスクに指を掛けた。彼は一瞬だけ抵抗するように眉を寄せたけれど、次第にその力を抜き、わたしに全てを委ねてくれる。露わになった端正な顔立ち。その唇に、自分のそれを重ねた。
最初はただ触れるだけだった口づけは、すぐに熱を帯びて深くなる。彼の腕が、わたしの腰を強く抱き寄せ、ベッドの上へと引き倒した。視界が反転し、天井の白い照明が映る。その光を遮るように、臣くんがわたしに覆い被さった。
「……っ、臣、くん」
「……お前の所為だ」
息も絶え絶えに名を呼ぶと、耳元で囁く掠れた声が、わたしの理性を溶かしていく。
そうだね。全部、わたしの所為。
臣くんの完璧な世界を乱すのも、臣くんの心をこんなにも掻き乱すのも、全部、わたしの所為だよ。
名付けられない感情。
もし、それにどうしても名前を付けなければならないのなら、きっと、それは。
――佐久早聖臣。
臣くんの名前、そのものなのかもしれない。
わたしは彼の首に腕を回し、その答えを伝える代わりに、もっと深いキスを強請った。窓の外では、いつの間にか、夜の帳が下り始めていた。
兄から解放され、わたしの部屋へと移動するなり、臣くんは大きな溜め息と共にベッドの縁に腰を下ろした。あからさまに不機嫌を露わにしている。その理由が、わたしの兄にあると思うと、少し申し訳ないような、面白いような、複雑な気持ちになる。
「……あの人、いつもあんな調子なのか」
「うん。インスピレーションが湧くと、周りが見えなくなるから」
「〆切 is デッドライン、ってなんだ。意味が重複してるけど」
「ふふ、きっと、それくらい切羽詰まっていると云うことだよ」
几帳面な臣くんらしい指摘に、思わず笑みが零れた。彼はむっとした顔でわたしを一瞥すると、視線を逸らしてぽつりと呟く。
「……名付け得ぬ、感情、か」
どうやら、兄の言葉が心に引っ掛かっているらしい。わたしは彼の隣にそっと腰を下ろし、その横顔を見つめた。マスクで半分以上が隠れているけれど、眉間に刻まれた皺と、僅かに尖った眼差しが、臣くんの不満を雄弁に物語っている。
「臣くんにとって、わたしとの関係は、名前を付けられないようなもの?」
問い掛けると、彼は少しの間を置いた後、逡巡するように口を開いた。
「……分からない。ただ、お前は、俺のルールの、唯一の例外だ」
その返答は、臣くんがくれるどんな甘い科白よりも、わたしの心を震わせた。
潔癖で、神経質で、自分の中に揺るぎない秩序を築いて生きている彼。その完璧に構築された世界の中で、わたしだけが「例外」として存在することを許されている。それは、どれ程に特別なことだろう。
「それに名前を付けるなら、なんだろうね」
わたしは独り言のように呟きながら、臣くんの手に、自分の手をそっと重ねた。バレーボールを叩き付ける、大きくて節くれ立った指。その指が驚いたようにぴくりと震え、けれど、振り払われることはない。
「恋、とか、愛、とか。そう云う、誰でも使える有り触れた言葉じゃ、しっくり来ない気がするんだ」
「……」
「臣くんとわたしの間にだけ流れている、この空気。この気持ち。他の誰にも理解されなくていい。二人だけの、特別な名前があったら、素敵だと思わない?」
見上げると、マスクの上にある彼の瞳が、深く、静かにわたしを捉えていた。その黒曜石のような瞳の奥で、様々な感情が渦巻いているのが分かる。戸惑い、苛立ち、そして、それらを遥かに凌駕する、抗い難い程の愛おしさ。
やがて、臣くんは諦めたように息を吐くと、わたしの手を力強く握り返した。
「……そんなもの、必要ない」
低く、掠れた声。
「名前なんて、どうでもいい。お前が、俺の隣に居る。……それだけで、いい」
不器用で飾り気のない、臣くんの世界の全てが詰まった言葉。
ああ、もう。
わたしは、この人がどうしようもなく好きだ。
わたしは衝動のままに身を乗り出し、臣くんのマスクに指を掛けた。彼は一瞬だけ抵抗するように眉を寄せたけれど、次第にその力を抜き、わたしに全てを委ねてくれる。露わになった端正な顔立ち。その唇に、自分のそれを重ねた。
最初はただ触れるだけだった口づけは、すぐに熱を帯びて深くなる。彼の腕が、わたしの腰を強く抱き寄せ、ベッドの上へと引き倒した。視界が反転し、天井の白い照明が映る。その光を遮るように、臣くんがわたしに覆い被さった。
「……っ、臣、くん」
「……お前の所為だ」
息も絶え絶えに名を呼ぶと、耳元で囁く掠れた声が、わたしの理性を溶かしていく。
そうだね。全部、わたしの所為。
臣くんの完璧な世界を乱すのも、臣くんの心をこんなにも掻き乱すのも、全部、わたしの所為だよ。
名付けられない感情。
もし、それにどうしても名前を付けなければならないのなら、きっと、それは。
――佐久早聖臣。
臣くんの名前、そのものなのかもしれない。
わたしは彼の首に腕を回し、その答えを伝える代わりに、もっと深いキスを強請った。窓の外では、いつの間にか、夜の帳が下り始めていた。