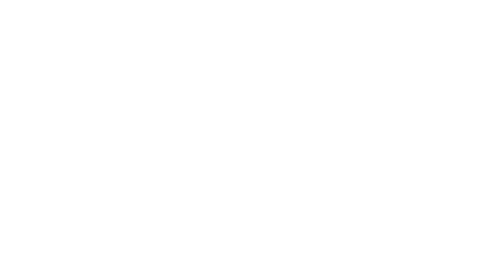Past Episode.
※兄貴と弟が登場します。
部活後のルーティン。汗と埃に塗れた体育館から脱出し、全身の湿気をタオルで徹底的に拭き取る。新品のマスクを装着し、外界からの侵略を遮断する。ここまでは、俺が俺のコンディションを正常に保つ為の、至極当然の儀式だ。
だが、その儀式にはいつからか、不可欠な続きが生まれた。
校門の傍らで待つ、唯一の例外。俺の世界の厳格な秩序を、肯定的且つ根底から破壊する存在。
苗字名前。
彼女と出逢う前の自分が、一体、どうやって息をしていたのか、時々本気で分からなくなる。
その日、俺達は特に約束を交わしたわけでもなく、ごく自然な流れで、苗字家のマンションへと向かっていた。俺にとって、あの外界から隔離された静謐な空間は、自宅よりも遥かに安息できる聖域となりつつあった。
エレベーターを降り、重厚なリビングのドアを開ける。その瞬間、俺の眉間に、無意識の力が籠もった。
ソファに陣取り、悪意を剥き出しにして、こちらを睨み付ける存在。
苗字弟。名前の一つ下の弟。
姉に似た芸術品のような造形美を、無駄に歪ませた不機嫌な表情。その双眸から放たれる敵意は、未熟な獣が己の縄張りを主張する、幼稚な威嚇みたいだ。
「……姉さん、なんで、こいつが居るんだよ」
低い声には、隠しもしない敵愾心が滲んでいる。
「弟。そんな言い方はやめて。臣くんは、わたしの大切なお客さんだよ」
名前が窘める口調は、普段の透き通るような響きとは裏腹に、僅かに困惑の色を帯びていた。それが、俺の不快指数を更に上昇させる。
この小生意気なガキは、俺と名前の関係にまだ気づいていない。或いは薄々感づきながらも、認めたくないだけか。どちらにせよ、その無知と抵抗が、名前を困らせていると云う事実が、俺の神経をヤスリ掛けのように削った。
俺がソファの空きスペースに腰を下ろそうとすると、弟が牽制するように素早く身動ぎした。
「そこ、姉さんがいつも座る場所」
「……」
俺は無言で立ち止まり、少し離れた一人掛けの椅子へと進路を変える。一々反応するのも馬鹿らしい。雑菌の集合体が意思を持って喋っていると思えば、腹も立たない。そう自己暗示を掛けるが、名前が淹れてくれた紅茶をサイドテーブルに置いた瞬間、再び横槍が入った。
「……そのティーカップ、姉さんのお気に入りなのに」
ぼそりと呟かれた言葉は、明らかに、俺に向けられたものだ。その執拗なまでのマーキング行為に、俺は内心で深く舌打ちした。面倒だ。実に面倒臭い。
その時、書斎のドアが開き、救世主なのか疫病神なのか、判然としない男が現れた。
「やあ、清潔くん! 名前! 丁度良いところに帰ってきたね!」
苗字兄貴。名前の兄。今日のTシャツには、黒の明朝体で『主語が行方不明』とだけ、潔くプリントされている。……また、意味の分からない服を着ている。
「兄貴兄さん。また、何か閃いたの?」
「その通りだ、我が妹よ! 今、俺の脳内宇宙に、新たな物語のビッグバンが起きたんだ!」
大袈裟な身振りで語り始めた兄貴さんは、俺と弟の弟を意味あり気に見比べた。
「テーマは『Iの消失』だ」
Iの消失。
その一言が、妙に耳にこびり付いた。
「例えば、だ。或る少年が居たとする。彼の世界は『僕と姉さん』と云う、絶対的に強固な関係性で成り立っていた。彼の自我、つまり、"I"は『姉さんの特別な弟である僕』と云う一点において、その存在を保証されている。だが、或る日、姉さんの隣に、別の男が現れる」
兄貴さんの視線が的を絞るように、弟を射抜く。弟は居心地悪そうに俯き、固く握った自分の拳を見つめている。
「『僕の姉さん』が、いつしか『彼の恋人』へと変わる。その時、少年の世界から、主語が消えるんだ。拠り所を失った"I"は希薄になり、やがて世界から消えてしまう……。どうだい? この、アイデンティティの崩壊と再生を描く物語! 文壇が震撼するだろう!?」
興奮気味に語る兄に、名前が困ったように微笑んだ。
「兄さん。その話、弟が可哀想だよ」
「おっと、これは失敬。だが、創作とは時に、残酷な現実を抉り出すものだからね」
リビングに気まずい沈黙が落ちる。
弟は唇をきつく結び、微かに身体を震わせていた。その小さな抵抗が滑稽で、少しだけ哀れに見えた。
「行こう、臣くん。わたしの部屋へ」
名前が、俺の袖を引いた、その時だった。
「待てよ、姉さん!」
今まで黙り込んでいた弟が、堰を切ったように声を上げた。語尾は揺れ、切羽詰まった響きを帯びている。
弟はソファから勢いよく立ち上がると、俺の真正面に立ちはだかった。俺の首までしか届かない背丈で、必死に睨み付けてくる。
「お前ら、一体、どう云う関係なんだよ」
その問いは、俺ではなく、名前に向けられたものだった。縋るような、最後の望みを託すような、そんな悲痛な色をしていた。
俺は口を挟むつもりがなかった。これは、俺が介入すべき問題ではない。どう応えるかは全て、名前に委ねられている。そして、彼女がどんな答えを選ぶのか、俺は疑いようもなく確信していた。
沈黙が部屋の空気を極限まで張り詰めさせる。
やがて、名前が静かに唇を開いた。その声はどこまでも澄んでいて、一片の揺らぎもなかった。
「弟」
名前は弟の名前を呼び、続けた。
「臣くんは、わたしの恋人だよ」
――空気が浄化された。
俺の脳内で、そんな感覚が過る。名前の凛とした一言は、この家に充満していた鬱陶しい湿気と、纏わり付く敵意を、一瞬で蒸発させたかのようだった。
弟の顔から、急速に血の気が引いていくのが分かった。見開かれた双眸は信じられないものを見たかのように揺れ、焦点を失う。彼が必死に守ろうとしていた『僕と姉さん』と云う脆弱な聖域が、今、音を立てて崩壊したのだ。
何かを言おうと、弟の唇が微かに動く。だが、そこから音は生まれなかった。言葉を、主語を、"I"を失った彼の世界は、完全な無音に包まれたのだろう。
俺は、その呆然とする姿を静かに見下ろしていた。優越感と云うよりは、寧ろ安堵に近い。俺と名前の世界が、漸く誰にも邪魔されない万全なものになった。それは、至極当然の帰結だった。
宝石が誰のものなのか。聖域の中心に居るのが、誰なのか。その答えが、今や明確に示された。名前は最初から、俺だけの光だったのだ。
弟は糸が切れた操り人形のように、ソファへと崩れ落ちた。
名前は一瞬だけ、弟に悲憫の眼差しを向けたが、すぐに向き直ると、その白い指で、俺の袖を再び摘まんだ。
「行こう」
その声に促され、俺達はリビングを後にする。背後で、兄貴さんが「おお……傑作の予感がする……」と恍惚の吐息を漏らしていたが、もうどうでもよかった。
名前の部屋に入るなり、彼女は申し訳なさそうに眉を下げた。
「ごめんね、臣くん。弟、まだ子供だから」
「別に」
俺は短く答えると、名前の華奢な身体を引き寄せ、強く抱き締めた。マスク越しに、清潔な花の香りが肺を満たす。
「あいつの世界から、お前が消えただけだ」
俺は、名前の耳元で囁く。
「俺の世界には、最初から、お前しかいない」
腕の中で、名前がふふ、と小さく笑う気配がした。
「……わたしの世界からも、"わたし"が消えてしまいそうだよ」
顔を上げた彼女が、潤んだ瞳で、俺を見つめる。
「臣くんに溶かされて」
その言葉が引き金だった。
俺はマスクを引き下げると、名前の挑発的な口唇を貪るように塞いだ。
もう、俺達を邪魔するノイズは、何一つない。
弟が失った"I"の代わりに、俺達は一個の存在として、どこまでも深く混じり合っていく。
窓の外が夕闇に染まる頃、俺は漸く、この完璧な静寂を手に入れたことに、満足の溜息を漏らした。
唇を離せば、互いの熱っぽい吐息が交差する。俺の胸元で、名前は心地好さそうに目を細めていたが、ふと、その表情に微かな翳りが落ちた。
「……弟、大丈夫かな」
ぽつりと零された呟きに、俺の眉間に皺が集まる。
「どうでもいい。あいつの世界の問題だ」
「そうだね。でも、わたしの弟なんだ。わたしにとっては、弟も大切な世界の構成要素の一つだよ」
静かだが、有無を言わさぬ響きを持つ言葉。それが、俺の安全な無菌室の壁に、小さな罅を入れた。名前の世界には、俺以外にも「大切」と定義されるものが存在する。当たり前の事実だが、実際に彼女自身の口から聞かされると、胸の奥に微細な棘が刺さるような、無視できない不快感を伴った。
名前は、俺の腕からそっと抜け出すと、ドアノブに手を掛けた。
「少し、様子を見てくる」
俺は舌打ちしたい衝動を抑え、渋々、名前の後に続いた。このまま一人で部屋に残される方が、余程落ち着かない。
リビングに戻ると、浄化された筈の空気が一段と重くなっていた。澱んでいる。
弟はソファの隅で膝を抱え、顔を埋めている。その姿は、兄貴さんの物語に出てきた『拠り所を失った"I"』そのものだった。兄貴さん本人は、そんな弟の様子を興味深そうに観察しながら、手許のノートに何事かを書き殴っている。……この兄、本当にどうかしている。
名前は音もなく、弟の隣に腰を下ろし、その背中を優しく撫でた。
「弟。夕飯はどうする? 何か食べたいものはある?」
返されたのは、くぐもった、拒絶の声だった。
「……要らない」
姉弟のやり取りを眺めながらも、俺はこの重苦しい空気に早く終止符を打ちたかった。他人の感情の機微に付き合うのは、俺の専門外だ。特に、こんな風に湿度を上げる状況は、コンディションを乱す要因でしかない。
帰る、と口を開き掛けた、その時だった。
ローテーブルの隅に置かれた、見覚えのあるロゴの入った紙袋が、俺の視界の端に映った。都内でも有名なパティスリーのものだ。常に行列が出来ており、俺のような人混みを嫌う人間にとっては、ウイルスと雑菌の巣窟にしか見えない場所。
俺の視線に気づいたのか、兄貴さんが芝居がかった口調で言った。
「おや、それは、弟が買ってきたケーキじゃないか。名前の好きな、季節限定のモンブランだ。姉さんの為に、態々、あの行列に並んで買ってきたものだね」
その言葉に、弟がびくりと肩を震わせる。そして、慌てて紙袋を背後に隠そうとした。
「……べ、別に、姉さんの為じゃない! 自分で食いたかっただけだ!」
虚勢を張る声は、情けなく上擦っている。
俺は一連の動きを無感動に眺めていた。
行列に並ぶ。姉の好物を買う。その行為自体は、俺の価値観からすれば、非合理的で理解不能だ。だが、根底にある動機――名前を喜ばせたい、と云う一点集中の目的意識。それだけは奇妙な程、鮮明に理解できた。
このガキは、俺とは違う方法で、名前と云う存在に執着している。手段は幼稚で遠回りだが、その純度において、手を抜くことを知らない。
それは、俺がバレーボールに向き合う姿勢や、己のコンディションを管理する徹底主義と、どこか似ている気がした。
こいつは、只の雑菌の集合体ではないのかもしれない。俺の聖域を脅かす不純物ではあるが、その核に在る想いだけは、或いは清浄な部類に属するのかもしれない。
俺は無言でキッチンに向かい、冷蔵庫から私物のミネラルウォーターを取り出した。そのボトルを、弟の目の前のローテーブルに、ことり、と置く。
「……飲め。脱水になる」
我ながら、不愛想でぶっきら棒な声だった。だが、体調管理ができない奴は嫌いだ。それは、この小生意気なガキ相手であっても揺るがない、俺のルールだった。
弟が顔を上げる。その瞳には、驚きと困惑が浮かんでいた。敵意を剥き出しにしていた対象からの、予想外の行動だったのだろう。名前と兄貴さんも、興味深げにこちらを見ている。
俺は構わず続けた。
「……そのケーキ、俺にも寄越せ」
弟の眉が、俄かに吊り上がる。
「名前が好きなものを、不味く食われるのは気分が悪い」
それは、俺なりの最大限の歩み寄りだった。お前の存在を認めるわけではない。だが、お前が名前の為に用意したものを、俺も共有してやる。それは、俺達の間に存在する、唯一の共通項に対する、最低限の敬意だった。
弟は暫く呆然としていたが、やがて諦めたように、むすっとした顔のまま、紙袋から箱を取り出した。
「……やるよ。全部食え、潔癖」
呼び方は変わらない。だが、その声から、先程までの刺々しい響きは消えていた。
結局、四人でケーキを囲むことになった。
名前が慣れた手つきで配ったモンブランを、俺は黙って口に運ぶ。濃厚なマロンクリームと、上品な甘さの生クリーム。確かに美味い。
隣では、弟がまだ不機嫌そうにフォークを動かしている。だが、その横顔には、もう先程までの絶望の色はなかった。
「……おい、弟くん」
俺が呼び掛けると、びくっと反応された。
「……なんだよ」
「次からは、保冷剤を二つにしてもらえ。この時期、一つじゃ足りない。クリームが緩む」
「はぁ!? なんで、お前にそんな指図されなきゃなんねーんだよ!」
「品質管理の問題だ。文句があるのか」
「あるに決まってんだろ、この潔癖野郎!」
ぎゃあぎゃあと噛み付く弟を無視し、俺は名前に視線を移す。彼女は、俺達の不毛なやり取りを、心底楽しそうに微笑んで見ていた。
その笑顔。
俺のコンディションを正常に保つ為に不可欠な、唯一無二の抗ウイルス剤。
この幸せを守る代償としてなら、俺の世界に多少のノイズが混入するのも、悪くないのかもしれない。
俺はそう結論付けた。