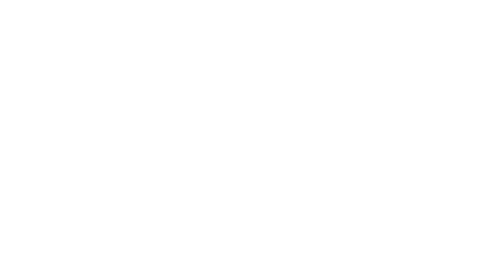※兄貴と弟が登場します。
俺の世界は、常に目に見えない脅威に満ちている。
教室と云う閉鎖空間は、謂わば培養実験のシャーレだ。咳一つで飛散する無数のウイルス、手洗いもそこそこに教科書を捲る指先に付着した雑菌、休み時間の度に無駄に上昇する湿度と二酸化炭素濃度。それら全てが、俺の神経をヤスリ掛けのように削り、苛立たせた。全く、集団生活などと云うものは、愚鈍と不潔を煮詰めて固めたような代物だ。
だから、俺は常にマスクと云う物理的な防壁で、外界と自らを隔てている。それは、俺が俺のコンディションを正常に保つ為の、至極当然の生存戦略に過ぎない。古森は「超ッッッ絶ネガティブ」などと軽々しく口にするが、断じて違う。俺はネガティブじゃない。慎重なんだ。この世に蔓延るありとあらゆるリスクを、ただ人より正確に認識しているだけだ。
「……」
そんな菌の温床たる教室で、俺の視線は自然と、左隣の席へと吸い寄せられる。
苗字名前。
彼女だけが、この澱んだ空気の中で、異質な程に清浄な領域を保っていた。春の柔らかな陽光が窓ガラスを透過して、彼女に降り注ぐ。絹糸のような髪がきらきらと光の粒子を散らし、白いブラウスの襟元から覗く首筋は、非の打ち所がない白磁のように滑らかだ。彼女が存在する半径一メートルだけが、高圧蒸気滅菌でも施されたかのように清らかで、澄み渡っている。
俺だけの聖域。
不意に、彼女がこちらを向いた。
夜の海を溶かし込んだような、どこまでも深く、静かな瞳。その吸い込まれそうな双眸に、俺の姿が映り込んだ瞬間、腹の底で何かが燻り始める。じわりと熱を帯び、心臓が不規則なビートを刻む。思春期特有の、この馬鹿げた生理現象はいつだって、名前と云う唯一つの原因によって引き起こされるのだ。
「臣くん、今日の部活はいつもより、少し早く終わるでしょう?」
「……うん。明日の練習試合の調整だけだから」
「なら、わたしの家に寄っていかない? 兄貴兄さんが、新しい絵本のラフが出来たから、見てほしい、って」
「……」
名前の兄、苗字兄貴。職業、作家。独創的と云う言葉では生温い、奇想天外な物語を紡ぐ男だ。重度のシスコンであり、何故か、俺のことを「清潔くん」と呼んで気に入っている。彼が着用している珍妙な文字入りTシャツを思い出し、俺は僅かに眉根を寄せた。確か、この前会った時は、「〆切 is デッドライン」と書かれたものを着ていた。
「……分かった」
しかし、断る選択肢はない。名前からの誘いを、俺が拒めるワケがないのだから。
約束通り、俺はいつもより早く部活を終え、校門で名前と合流した。並んで歩き出すと、彼女の纏う清潔な花の香りが、マスク越しにでもふわりと鼻腔を擽る。それだけで、練習で火照った身体の芯が、別の種類の熱を帯びていくのが分かった。
その時だった。
「あ、苗字さん! 良かったら、この後……」
背後から聞こえたのは、クラスの男子生徒の軽薄な声。名前はよく知らない。たった今、憶える価値もなくなった。そいつはヘラヘラと下卑た笑みを浮かべ、馴れ馴れしく名前の肩に手を伸ばそうとした。
――殺菌。
俺の脳内で、瞬時に警報が最大音量で鳴り響いた。その汚れた指で、名前に触れるな。一ミクロンたりとも。
俺がその腕を叩き落とすよりも早く、名前は蝶が舞うようにひらりと身を躱した。汚泥が跳ねるのを避けるかのように、優雅に。
「ごめんなさい。大切な先約があるので」
抑揚のない、凛として透き通る声。名前はそう言うと、俺の制服の袖を、白い指できゅっと掴んだ。
「行こう、臣くん」
俺の袖を引く名前に、男は呆然と立ち尽くしている。その滑稽な様を視界の端に捉え、俺は内心で嘲笑した。身の程を知れ。
俺は男に一瞥もくれず、名前に導かれるまま歩き出す。袖に触れた彼女の指先から、清らかな何かが流れ込んでくるようだった。俺の中に渦巻いていた不快指数と、或る種の殺意にも似た激情が、見る見るうちに浄化されていく。彼女は俺にとって、唯一の消毒液であり、抗ウイルス剤だ。
「……あんな奴に、声を掛けさせるな」
人通りの少ない裏道を選びながら、俺は不機嫌を隠さずに言った。
「仕方ないでしょう。口は誰にでも付いているから」
「不用意に近寄らせるなと言ってる」
「ふふ、臣くんは心配性だね」
名前は楽しそうに笑う。その声が、俺の苛立ちを少しずつ溶かしていく。
「心配性じゃない。慎重なんだ」
「そうだね。とても慎重な臣くんが、わたしには無防備なのが嬉しいよ」
「……っ」
不意打ちの言葉に、心臓が跳ねた。こうして、彼女は時折、俺の心の壁をいとも容易く飛び越えてくる。俺の潔癖症が、この慎重過ぎる性格が、名前の前でだけは形無しになることを、誰よりもよく知っている。
名前の住むマンションは、相変わらず要塞のように静かで、外界の喧騒とは無縁だった。管理人以外は苗字兄妹しか住んでいないと云う、常識外れの住環境。エントランスの表札が全て無記名なのも、兄である兄貴さんの「プライバシーの結界だ」と云う謎理論に因るものらしい。
リビングのドアを開けると、ソファで漫画を読んでいた弟が顔を上げた。名前の一つ下の弟。姉に似て整った顔立ちをしているが、口を開けば生意気なことしか言わない。
「あ、潔癖。来たのか」
「……弟くん。こんにちは」
「姉さん、こいつ、腹減ってんじゃないの? なんか食わせてやれば」
「臣くん、お腹は空いている?」
「いや、別に……」
「そうか。じゃあ、俺が腹減った。姉さん、なんか作って」
全く、相変わらずな弟だ。だが、俺が名前の彼氏だと知ってから、あからさまな敵意が消え、今のような小生意気な態度に軟化しただけマシか。
「やあ、清潔くん! よく来たね!」
奥の部屋から現れたのは、兄の兄貴さんだった。今日のTシャツは、胸に大きく『俺の妹が世界遺産』とプリントされている。……どうかしている。
「兄貴兄さん、絵本のラフが出来たんでしょう?」
「そうなんだよ、名前! 今回の物語はね、潔癖症のハリネズミが、世界で唯一触れるタンポポの綿毛ちゃんと、恋に落ちる話なんだ!」
そう言って、彼は得意気に、俺と名前を交互に見た。……俺達のことじゃないか。
「ハリネズミは、その繊細な心故に、いつも針を逆立てて、世界を拒絶している。だが、綿毛ちゃんの無垢な優しさに触れた時、初めて針を収めることを覚えるんだ。どうだい? 泣けるだろう?」
「……素敵なお話だね、兄さん」
「だろう!? 主人公の名前は『サクサク』だ!」
「……帰る」
俺が立ち上がろうとすると、名前が腕を掴んで制止した。
「待って、臣くん。兄の創作意欲の源は、いつだって身近な愛なの」
「……勘弁してほしい」
兄貴さんの絵本談義から解放され、俺達は名前の部屋へ移動した。名前の自室は、彼女自身を体現したような空間だ。無駄なものが一切なく、本棚には古今東西の書物が整然と並び、窓辺には丁寧に手入れされた観葉植物が置かれている。空気清浄機が静かに稼働し、微かにラベンダーの香りがした。俺の家より、よほど清潔で落ち着く。
俺はベッドの縁に腰掛けると、先程の校門での出来事を思い出して、再び眉間に皺を寄せた。
「……やっぱり、気に食わない」
「例の、彼のこと?」
「あんな屑が、お前と同じ空気を吸っていることすら不快だ」
俺の口から漏れたのは、紛れもない本心だった。ああ云う不用意で無頓着な存在が、俺は心底嫌いだ。
名前は静かに隣に座ると、俺の顔をじっと覗き込んだ。その静謐な瞳に見つめられると、俺の内のどす黒い感情が、全て見透かされているような気分になる。
「臣くんにとって、世界は屑だらけなんでしょう?」
核心を突く言葉に、俺は息を呑んだ。
……そうだ。俺の基準に満たない、不用意で無神経な人間。無意味な会話。不衛生な環境。それら全てが、俺のコンディションを乱すノイズでしかない。そして、残念なことに、世界はそんなノイズで満ち溢れている。
名前は、俺の心を掌で転がすように続けた。
「その中で、わたしだけが宝石なら、凄く嬉しいな」
夜の海底のような瞳が、悪戯っぽく、慈しむように細められる。
――やられた。
完全に不意を突かれた。
屑に埋れた宝石。
いや、違う。俺にとっての世界は、屑とそうでないものに、明確に区分されている。俺が定めた厳格な基準と、揺るぎない理屈で構築された、秩序ある世界。そこには一切の不純物も、曖昧な感情も入り込む余地はない筈だった。
だが、苗字名前。お前だけが、その全ての法則を超えて存在する。
俺の完璧な秩序の中で、唯一の例外であり、絶対的な中心。
俺の無菌室のような世界に咲いた、ただ一輪の花。傷一つなく、清浄な光を放ち続ける、唯一無二の宝石なんだ。
俺は衝動のままにマスクを引き下げ、床に放り投げた。そして、名前の華奢な肩を掴み、その薄桃色の唇を、貪るように塞いだ。
驚きに見開かれた瞳が、すぐに心地好さそうに細められ、白い腕が、俺の首に回される。
菌なんて、もうどうでもよかった。
彼女がくれるものなら、どんなウイルスだって、甘んじて受け入れよう。
この宝石が、俺だけのものであると云う証明になるのなら。
無数のノイズに満ちた世界で、漸く見つけた、俺だけの宝物。
誰にも触れさせない。誰にも汚させない。
この腕の中に閉じ込めて、永遠に俺だけのものにしておきたい。
唇を離すと、熱っぽい吐息が混じり合う。名前は潤んだ双眸で俺を見上げ、幸せそうに微笑んだ。
「臣くんの宝石は、ここに居るよ」
その言葉が、俺の世界の全てだった。
俺はもう一度、その輝きを確かめるように、深く、彼女に口づけた。