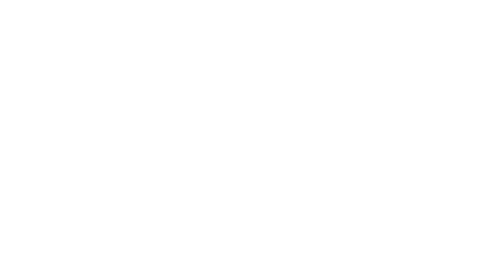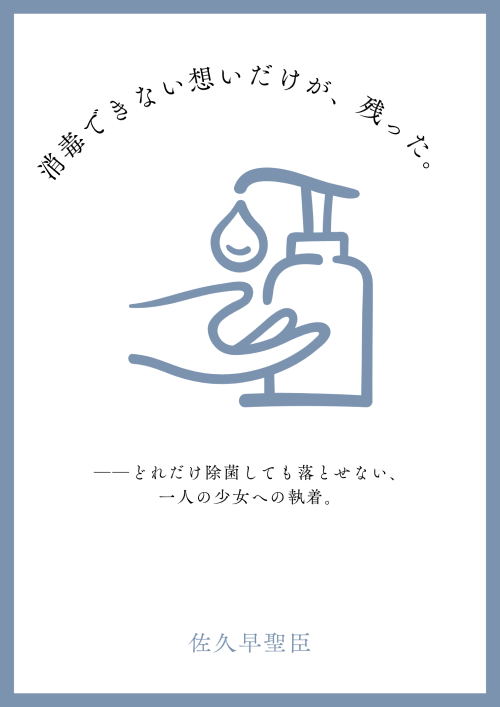
――どれだけ除菌しても落とせない、一人の少女への執着。
春の残照が夏の夜明けに溶け込もうとする、そんな曖昧な季節の変わり目。東京の朝は纏わり付くような湿気を孕み、駅の階段の手摺りには無数の他人の気配が粘り付いているようで、佐久早聖臣はマスクの内側で深く息を吐いた。今日もまた、見えない敵との戦いが始まる。
「……菌、菌菌菌……忌々しい」
無意識に漏れる呟きは、佐久早の日常のテーマソングだ。アスファルトを蹴る足取りは自ずと速くなる。すれ違う顔見知りのクラスメイトからの「おはよう」と言う声にも、彼は無言で頷きを返すのみ。声帯の振動すら、喉に付着する雑菌の温床に思えてならない。彼の世界は、常に目に見えない脅威に満ちている。
だが――
「……おはよう、臣くん」
その澄んだ声だけは、いつも彼の思考の奔流をぴたりと止める。まるで時が止まったかのように、佐久早自身の靴音も途絶えるのを、彼はどこか他人事のように感じていた。
反射的に振り返れば、そこに苗字名前が立っていた。朝の柔らかな光が彼女の柔らかな髪を透かし、繊細な輪郭を際立たせている。影を落としたその横顔は、静謐な水面に映る月のように儚く、そして美しかった。彼の網膜に焼き付く、特別な光景。
「うん……おはよう、名前」
マスク越しに、恐らく笑顔と呼べるであろう形に口元を歪めて応じる。彼女の前でだけは、この息苦しいマスクを外し、無防備な自分を晒しても良いのではないか、そんな危険な考えが頭を過る。彼女に触れたいという衝動は、彼の潔癖な信条さえも揺るがすのだ。
ずっと昔から、佐久早の世界は彼一人で完結していた。そこに、名前はまるで気配を消した猫のように、音もなく忍び込んできた。クラスの誰よりも物静かで、それでいて誰よりも強烈な個性を放つ彼女。
初めて言葉を交わした日のことを、佐久早は鮮明に記憶している。
「佐久早くん、手首が柔らかいね。死体みたい」
常人ならば眉を顰めるであろうその言葉を、彼女は夜の海のように深い瞳で淡々と告げた。その瞬間、佐久早は理解したのだ。彼女は常識という窮屈な枠組みから解き放たれ、自らの感性という宇宙で誇り高く生きているのだと。その特異な美意識は、彼の心を捉えて離さなかった。
そんな名前が、自分の恋人になった――その事実は、佐久早の世界の均衡を心地よく揺るがし、色彩を与えた。
しかし、最近の佐久早は微かな、しかし、無視できない苛立ちを抱えていた。
好き過ぎる。名前のことを考えると、胸の奥が甘く疼き、思考が全て彼女で飽和する。
考え過ぎる。彼女の一挙手一投足、言葉の欠片まで反芻し、その意味を探ろうとしてしまう。
触れ過ぎた。一度知ってしまった温もり、肌の滑らかさ、甘い香り。その記憶は鮮烈で、彼の自制心を容赦なく蝕む。
そして、今は――離れ過ぎている。
進学、練習、合宿、試合――バレーボールは、彼の時間と情熱の全てを貪欲に吸い上げていく。コートに立てば、他の何もかもが霞む。それが彼の選んだ道であり、誇りでもある。
けれど、どれ程ボールに集中しようとも、佐久早の心の奥底、最も柔らかな場所には、常に名前の影が揺らめいていた。
本当は何度も電話を掛けようとした。合宿先の消灯後の静寂の中、自宅のベッドで眠れぬ夜、遠征へ向かうバスの窓に凭れながら。だが、指が通話ボタンに触れる寸前で、いつも彼はその衝動を押し殺した。「また会える?」――その言葉が喉まで出掛かり、しかし、決して声にはならなかった。
何故なら、その問いを発した瞬間、もし、それが叶わなかった場合の自分を想像すると、立っていられなくなるからだ。彼の慎重過ぎる性格、或いは古森が言うところの「超ッッッ絶ネガティブ」な側面が、最悪の可能性を執拗に囁き掛ける。もし、名前に「また会えたね」と微笑み掛けられるその日が永遠に来なかったら、自分は一体、どうなってしまうのだろうか。その恐怖は、彼の行動を縛る見えない鎖だった。
――それでも、今日は。
校門を潜り抜けた瞬間、生温い風がふわりと頬を撫でた。それが春の残り香なのか、夏の訪れを告げるものなのか、彼には判別がつかない。ただ、その風に名前の髪が柔らかく流れた時――佐久早の胸に抗い難い衝動が突き上げてきた。
(今、言わなければ。きっと、もう二度と言えなくなる)
「名前」
佐久早の声に、彼女がゆっくりと振り向く。吸い込まれそうな、夜の海の色をした双眸。
降り注ぎ始めた陽射しが、彼女の透けるように白い肌に淡い光の筋を描き、精巧な美術品のような陰影を作り出している。手のひらを伸ばせば触れられそうな、その危ういまでの存在感に、彼は喉の奥から言葉を絞り出した。
「また……また会える?」
一瞬、名前の大きな瞳が驚いたように見開かれた。それは、佐久早にとっても意外な反応だった。彼女なら、もっと飄々と、或いは全てを見透かしたように応じると思っていたからだ。
一拍の、しかし、永遠にも感じられる沈黙の後、彼女はそれが世界の真理であるかのように、静かに、しかし、はっきりと告げた。
「勿論。また会える。でも……」
風が止んだ。周囲の喧騒が遠退き、世界が名前と自分だけになったような錯覚。
その先の言葉を、佐久早は息を詰めて待っていた。なのに――
「……その先は、まだ言えない」
そう言って、名前はふわりと踵を返し、歩き出してしまった。制服のスカートが、彼女の軽やかな動きに合わせて優雅に揺れる。
置いていかれる――その感覚に、佐久早は無意識に一歩を踏み出していた。
「……は?」
思わず漏れた声は困惑そのものだった。
くるりと振り返った名前の表情は、ほんの少しだけ照れているようにも見えたが、その瞳には確かな光が宿っていた。それは、佐久早の心の奥底まで届く、温かく、そして力強い光。
「"また会えたね"は、まだ言えないの。だって、ちゃんと……まだ、会えていないから」
(まだ――会えてない、か)
その言葉の真意は、すぐには掴めなかった。物理的には、今、こうして会っている。では、彼女の言う「ちゃんと会う」とは、一体、何を意味するのだろう。
それは、佐久早にとって、解き明かしたい、そして解き明かさなければならない、とても大切な謎だった。名前の言葉は複雑な暗号のようで、彼の心を強く惹き付けてやまない。
だから、佐久早は今日も、彼女の背中を目で追う。
彼らしい、清潔過ぎる程の距離を保ちながら、しかし、確実に心の全てを彼女に向けて。
マスクの下で、知らず識らずの内に口元が綻んでいた。多分、それは紛れもない笑顔だったのだろう。
また会える。
その言葉を、今、彼は心の底から信じることができた。
何故なら、彼女がそう言ったから。そして何より――彼女が今、ここに、彼の目の前に存在しているという、それ以上ない確かな理由があったからだ。その事実は、彼の潔癖な世界に差し込む、唯一無二の光だった。