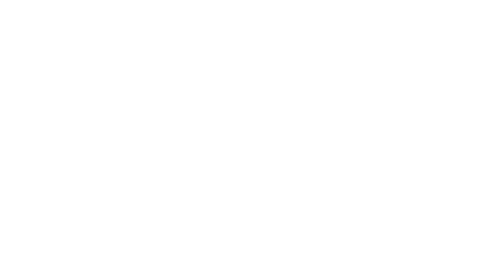不器用な音が奏でるのは、
言葉よりも真っ直ぐな「赦して」の気持ち。
鉄朗くんから、彼の秘密の宝物だった複音ハーモニカを譲り受けてからというもの、わたしの日常には新しい隠し事が一つ増えた。
──鉄朗くんの為だけに、曲を練習する。
それは、あのスリリングな尾行とはまた違う、甘やかで真剣なミッションだった。自室の机に向かい、夕陽に透ける銀色の楽器をそっと手に取る。ひんやりとした金属の感触が、あの日の公園の空気と、彼の少し照れたような横顔を思い出させた。
「……難しい」
ぽつりと零れた独り言は、誰に聞かれるでもなく部屋の空気に溶けていく。オーボエのように繊細な息のコントロールを求められるわけでも、ピアノのように複雑な指の動きが必要なわけでもない。ただ二列に並んだ小さな穴へ、均等に、真っ直ぐに息を吹き込む。たったそれだけのことが、これ程までに奥深いなんて。
吸う音と吹く音。唇の形を僅かに変えるだけで、和音の響きはガラリと表情を変える。少しでも力が入り過ぎれば音は濁り、弱過ぎれば掠れてしまう。気難しい生き物を手懐けるような作業だった。
「随分と熱心だね、名前。その小さな楽器が、恋のキューピッドにでも見えるのかい?」
不意に背後から声を掛けられ、肩が小さく跳ねた。いつの間に入って来たのか、兄貴兄さんが面白そうにこちらを覗き込んでいる。今日のTシャツには、達者な筆文字で『神出鬼没』と書かれていた。成る程、その通りだ。
「……兄さん。ノックくらいして」
「おや、すまない。余りにも真剣な横顔だったから、新しい物語の女神が舞い降りたのかと思ってね。そのハーモニカ、鉄朗くんから貰ったものだろう? 彼を驚かせたい、という訳か。実に、名前らしい健気さだ」
兄の言葉に、わたしは何も答えずにハーモニカへ視線を戻す。健気、という言葉が自分に当て嵌まるのかは分からない。ただ、あの時、「俺の知らない曲、聴かせてくれよ」と笑った彼の顔が忘れられないだけだ。わたしが奏でる音で、鉄朗くんの心を揺らしてみたい。わたしの知らない彼の顔を、もっと引き出してみたい。その一心だった。
学校では、練習のことはおくびにも出さない。昼休み、教室で彼と他愛ない話をする時も、部活終わりの彼を待って一緒に帰る時も、わたしは完璧なポーカーフェイスを保っていた。
「名前、最近、なんか楽しそうだな。良いことでもあったのか?」
或る日の帰り道、不意にそう言われて心臓が跳ねた。隠し事をしているスリルが、あの尾行の時と同じように、わたしの心を静かに高揚させる。
「そうかな。鉄朗くんと一緒に居られるから、毎日が楽しいだけだよ」
「……お前、偶に素でそういうこと言うよな」
頭をがしがしと掻きながら、照れたように視線を逸らす彼。その反応の一つひとつが、わたしの練習への意欲を更に掻き立てる燃料となった。
けれど、情熱だけでは越えられない壁もある。或る有名なバラード曲の、一番美しい筈のフレーズが、どうしても上手く吹けないのだ。音が震え、和音が濁り、旋律は無様に途切れる。何度も、何度も。繰り返す内に、焦りと苛立ちが胸の内に渦巻き始めた。
わたしは溜め息と共にハーモニカを唇から離し、手の平の上で転がした。鉄朗くんの大切な宝物だったのに。わたしが持っていた方が喜ぶ、なんて言ってくれたのに。こんな下手糞な音しか鳴らせないなんて。
「……ごめんね」
思わず、銀色のプレートにそう囁き掛ける。すると、まるで応えるかのように、机に置いていたスマートフォンが震えた。鉄朗くんからのメッセージだった。
『明日、部活早く終わるから、駅前のカフェで待ち合わせしねぇ?』
その短い文面を見た瞬間、わたしは決意した。明日こそ、この曲を完璧にしてみせる。そして、もし上手く吹けたら、彼にこの秘密を打ち明けよう、と。
翌日。わたしは学校から帰ると、脇目も振らずに自室に籠った。昨日まで苦戦していたフレーズに全神経を集中させる。吸って、吐いて。息の流れを、細い絹糸を紡ぐようにコントロールする。
──ピィ、と澄んだ和音が響いた。
できた。昨日までの濁った音が嘘のように、美しく、切ないメロディが部屋を満たす。嬉しさの余り、わたしは時間を忘れて何度も何度もその曲を繰り返し練習した。もっと、もっと美しく。鉄朗くんが息を呑むくらいに。
夢中だった。窓の外が茜色から深い藍色に変わっていくことにも、壁の時計の針が約束の時間を疾うに過ぎていることにも、全く気づいていなかった。ふと我に返り、スマートフォンの画面を点灯させた瞬間、血の気が引いた。
約束の時間から、一時間も過ぎている。着信履歴には、彼の名前が幾つも並んでいた。
「……拙い」
慌てて『ごめん、今から行く』とメッセージを送る。心臓が早鐘を打ち、指先が冷たくなっていく。どうしよう。鉄朗くんを怒らせてしまったかもしれない。
わたしはハーモニカをケースに仕舞い、バッグを掴んで部屋を飛び出した。どうか赦してくれますように。そんな祈りにも似た想いを胸に。
 「……遅ぇな」
俺は駅前のカフェの窓際席で、とっくに氷が溶けて薄くなったアイスコーヒーのグラスを指でなぞりながら、何度目かの溜め息を吐いた。名前から『ごめん、今から行く』というメッセージが届いてから、更に三十分が経過している。
怒っている、と言うよりは心配が勝っていた。あいつのことだ、また何か突拍子もない好奇心に火が点いて、時間を忘れているのかもしれない。この間の尾行騒動を思い出して、思わず苦笑が漏れる。
けれど、着信にも出なかったのは初めてだ。事故か事件にでも遭ったんじゃないか。そんな最悪の可能性が頭を過り、じっとしていられなくなった。俺は伝票を掴んで席を立つと、カフェを飛び出し、名前の住むマンションへと足を速めた。
マンションのエントランスに入った、その時だった。オートロックの向こうから、ひょっこりと見慣れた長身の男が出てくる。名前の兄さん、兄貴さんだ。
「やあ、鉄朗くんじゃないか。奇遇だね」
「あ、どうも。あの、名前は……」
「ああ、妹なら、今し方、血相を変えて飛び出していったよ。『鉄朗くんを怒らせてしまったかもしれない』と、この世の終わりのような顔でね」
そう言って、兄貴さんは悪戯っぽく笑う。その言葉に、一先ず安堵の息を吐いた。どうやら、無事ではあるらしい。
「そうでしたか。じゃあ、俺もカフェに戻って……」
「いや、その必要はないだろう。どうせ、君とは入れ違いだ。ほら、噂をすれば」
兄貴さんが顎で示したエントランスの向こう側。マンションの出入り口に見慣れたシルエットが現れた。世界の終わりみたいにしょげ返って、とぼとぼと歩いてくる名前だった。兄貴さんに腕を引っ張られ、俺達は咄嗟に非常口の影に身を隠す。
名前は俺達の存在に全く気づくことなくオートロックを解除し、力なくエレベーターのボタンを押すと、静かに乗り込んでいった。その背中がどうしようもなく小さく見える。
「ふむ。見事にすれ違ってしまったようだね」
非常口の影から顔を出すと、兄貴さんが面白そうに口の端を上げた。
「さて、どうする? このまま追い駆けるのも野暮というものだ。彼女が一体、何に夢中になって、君との約束を忘れてしまったのか、知りたくはないかい?」
有無を言わさぬ口調で手招きされ、俺は半信半疑のまま、兄貴さんの後に続いた。この兄妹は、俺を本当に面白がらせてくれる。エレベーターで最上階へ上がり、案内された部屋の前に立つ。兄貴さんは静かにドアノブに手を掛け、音を立てずに僅かな隙間を作った。
「……ん?」
その隙間から、何かが散らかった部屋の様子が窺える。楽譜らしき紙が床に散乱し、机の上には教本のようなものが何冊も開かれている。まるで、何かの研究に没頭する学者の部屋のようだ。
「わたしの馬鹿……。折角、上手く吹けるようになったのに……」
部屋の奥から、名前のしょんぼりした声が聞こえた。がっくりと肩を落とし、彼女は机の上の小さな銀色の楽器を手に取る。俺があげた、あの複音ハーモニカだった。
そういうことか。あいつ、この為に……。
俺の心臓が、ぎゅう、と鷲掴みにされたような衝撃に襲われる。名前はハーモニカをそっと唇に当てると、瞳を閉じた。そして、息を吹き込む。
途端に澄み切った、けれど、どうしようもなく切ないメロディが流れ出した。俺が知っている、有名なバラード曲。だけど、彼女が奏でる音は、オリジナルとは全く違う響きを持っていた。拙さはある。でも、一音一音に込められた想いが、感情が、痛い程に伝わってくる。俺の為にこの曲を選んで、こんなになるまで練習してくれていたのか。
曲が終わり、静寂が戻る。名前はハーモニカを胸に抱き締め、深々と溜め息をついた。
「聴いてほしかったな……ごめんね、鉄朗くん……」
そのか細い声に、限界が訪れた。俺はドアを静かに開け、部屋の中へと一歩踏み出す。
「俺は、ここに居るけど?」
「わぁっ!?」
名前の肩が、この間の尾行の時みたいに盛大に跳ねた。勢いよく振り返った彼女の瞳が、驚きと困惑で大きく見開かれる。
「て、鉄朗くん!? どうして……いつから……!」
「ついさっき。最高の演奏だったぜ」
呆然と立ち尽くす彼女の元へ歩み寄り、その華奢な身体を腕の中に閉じ込めた。驚きで強張っていた身体が、俺の腕の中で少しずつ力を抜いていく。
「ごめん……こんな、下手なところ、見せて……」
「謝んな。俺の為に、部屋をこんなにしてまで頑張ってくれてたんだろ。それだけで、世界で一番上手い演奏だよ」
ぎゅっと抱き締めると、名前は俺の胸に顔を埋めて、くぐもった声で言った。
「でも、約束を破ってしまった……しかも、迷って……待たせて、ごめんね……」
「いいって。最高の言い訳じゃねぇか。だから、もう『ごめん』は終わり。な? 赦してやるから、顔上げろよ」
促されるままに顔を上げた彼女の瞳は、潤んでキラキラと輝いていた。その表情が愛おし過ぎて、俺は堪らず彼女の唇に自分のそれを重ねた。
「……なあ、もう一回聴かせてくれよ。今度は、俺一人の為の特別アンコール」
悪戯っぽく囁くと、名前は真っ赤な顔でこくりと頷いた。そして、少し震える手で、再びハーモニカを口元へ運ぶ。
二人きりの部屋に響く、不器用だけれど、有りっ丈の愛が込められたセレナーデ。俺は静かに目を閉じ、その一音一音を心に刻み付けた。
この掴みどころのない、最高に愛おしい恋人の為なら。何度だって、心を掻き乱されて、その甘美な音色に酔い痴れてやろう。それこそが、俺達だけの、極上の日常なのだから。
「……遅ぇな」
俺は駅前のカフェの窓際席で、とっくに氷が溶けて薄くなったアイスコーヒーのグラスを指でなぞりながら、何度目かの溜め息を吐いた。名前から『ごめん、今から行く』というメッセージが届いてから、更に三十分が経過している。
怒っている、と言うよりは心配が勝っていた。あいつのことだ、また何か突拍子もない好奇心に火が点いて、時間を忘れているのかもしれない。この間の尾行騒動を思い出して、思わず苦笑が漏れる。
けれど、着信にも出なかったのは初めてだ。事故か事件にでも遭ったんじゃないか。そんな最悪の可能性が頭を過り、じっとしていられなくなった。俺は伝票を掴んで席を立つと、カフェを飛び出し、名前の住むマンションへと足を速めた。
マンションのエントランスに入った、その時だった。オートロックの向こうから、ひょっこりと見慣れた長身の男が出てくる。名前の兄さん、兄貴さんだ。
「やあ、鉄朗くんじゃないか。奇遇だね」
「あ、どうも。あの、名前は……」
「ああ、妹なら、今し方、血相を変えて飛び出していったよ。『鉄朗くんを怒らせてしまったかもしれない』と、この世の終わりのような顔でね」
そう言って、兄貴さんは悪戯っぽく笑う。その言葉に、一先ず安堵の息を吐いた。どうやら、無事ではあるらしい。
「そうでしたか。じゃあ、俺もカフェに戻って……」
「いや、その必要はないだろう。どうせ、君とは入れ違いだ。ほら、噂をすれば」
兄貴さんが顎で示したエントランスの向こう側。マンションの出入り口に見慣れたシルエットが現れた。世界の終わりみたいにしょげ返って、とぼとぼと歩いてくる名前だった。兄貴さんに腕を引っ張られ、俺達は咄嗟に非常口の影に身を隠す。
名前は俺達の存在に全く気づくことなくオートロックを解除し、力なくエレベーターのボタンを押すと、静かに乗り込んでいった。その背中がどうしようもなく小さく見える。
「ふむ。見事にすれ違ってしまったようだね」
非常口の影から顔を出すと、兄貴さんが面白そうに口の端を上げた。
「さて、どうする? このまま追い駆けるのも野暮というものだ。彼女が一体、何に夢中になって、君との約束を忘れてしまったのか、知りたくはないかい?」
有無を言わさぬ口調で手招きされ、俺は半信半疑のまま、兄貴さんの後に続いた。この兄妹は、俺を本当に面白がらせてくれる。エレベーターで最上階へ上がり、案内された部屋の前に立つ。兄貴さんは静かにドアノブに手を掛け、音を立てずに僅かな隙間を作った。
「……ん?」
その隙間から、何かが散らかった部屋の様子が窺える。楽譜らしき紙が床に散乱し、机の上には教本のようなものが何冊も開かれている。まるで、何かの研究に没頭する学者の部屋のようだ。
「わたしの馬鹿……。折角、上手く吹けるようになったのに……」
部屋の奥から、名前のしょんぼりした声が聞こえた。がっくりと肩を落とし、彼女は机の上の小さな銀色の楽器を手に取る。俺があげた、あの複音ハーモニカだった。
そういうことか。あいつ、この為に……。
俺の心臓が、ぎゅう、と鷲掴みにされたような衝撃に襲われる。名前はハーモニカをそっと唇に当てると、瞳を閉じた。そして、息を吹き込む。
途端に澄み切った、けれど、どうしようもなく切ないメロディが流れ出した。俺が知っている、有名なバラード曲。だけど、彼女が奏でる音は、オリジナルとは全く違う響きを持っていた。拙さはある。でも、一音一音に込められた想いが、感情が、痛い程に伝わってくる。俺の為にこの曲を選んで、こんなになるまで練習してくれていたのか。
曲が終わり、静寂が戻る。名前はハーモニカを胸に抱き締め、深々と溜め息をついた。
「聴いてほしかったな……ごめんね、鉄朗くん……」
そのか細い声に、限界が訪れた。俺はドアを静かに開け、部屋の中へと一歩踏み出す。
「俺は、ここに居るけど?」
「わぁっ!?」
名前の肩が、この間の尾行の時みたいに盛大に跳ねた。勢いよく振り返った彼女の瞳が、驚きと困惑で大きく見開かれる。
「て、鉄朗くん!? どうして……いつから……!」
「ついさっき。最高の演奏だったぜ」
呆然と立ち尽くす彼女の元へ歩み寄り、その華奢な身体を腕の中に閉じ込めた。驚きで強張っていた身体が、俺の腕の中で少しずつ力を抜いていく。
「ごめん……こんな、下手なところ、見せて……」
「謝んな。俺の為に、部屋をこんなにしてまで頑張ってくれてたんだろ。それだけで、世界で一番上手い演奏だよ」
ぎゅっと抱き締めると、名前は俺の胸に顔を埋めて、くぐもった声で言った。
「でも、約束を破ってしまった……しかも、迷って……待たせて、ごめんね……」
「いいって。最高の言い訳じゃねぇか。だから、もう『ごめん』は終わり。な? 赦してやるから、顔上げろよ」
促されるままに顔を上げた彼女の瞳は、潤んでキラキラと輝いていた。その表情が愛おし過ぎて、俺は堪らず彼女の唇に自分のそれを重ねた。
「……なあ、もう一回聴かせてくれよ。今度は、俺一人の為の特別アンコール」
悪戯っぽく囁くと、名前は真っ赤な顔でこくりと頷いた。そして、少し震える手で、再びハーモニカを口元へ運ぶ。
二人きりの部屋に響く、不器用だけれど、有りっ丈の愛が込められたセレナーデ。俺は静かに目を閉じ、その一音一音を心に刻み付けた。
この掴みどころのない、最高に愛おしい恋人の為なら。何度だって、心を掻き乱されて、その甘美な音色に酔い痴れてやろう。それこそが、俺達だけの、極上の日常なのだから。