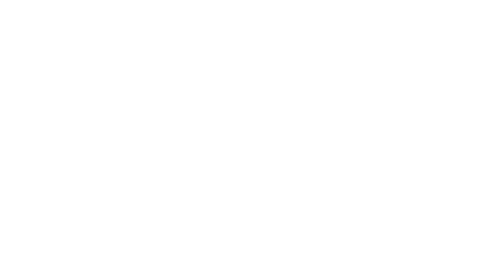※名前の祖父が登場します。
雨が鍵を開けた、見えない気持ちの交信記。
「おい、研磨ァ! 傘、忘れてんぞ!」
部室の窓から、グラウンドへ向かう幼馴染の背中に声を張り上げるも、そいつはイヤホンと云う現代の耳栓によって、外界の音をシャットアウトし、猫のように軽やかな足取りで、さっさと昇降口へ消えていった。ちっ、あいつめ。まあ、研磨のことだ、どうせ駅までダッシュするなり、俺が迎えに来るのを待つなりするんだろう。
「クロさーん! お先っス!」
「お疲れ様でしたー!」
後輩達の元気な声を見送り、俺は部室の戸締りの確認を終える。湿気を含んだ空気が、制服越しに肌へじっとりと纏わり付く。天気の神様は本日、大変ご機嫌斜めらしく、空は今にも泣き出しそうな鈍色に染まっていた。
「やれやれ、こりゃ一本取られたな」
誰に、とは述べない独り言を零し、自分の傘を手に、部室棟の階段を下りる。校舎の出口で空を見上げると、ぽつ、ぽつ、とアスファルトに黒い染みが生まれ始めた。それが瞬く間に数を増やし、サーッと云う優しい音色を奏で始める。
俺は雨傘を開こうとして、ふと足を止めた。
昇降口の庇の下、俺が出てくるのを待っていたかのように、一人の少女が佇んでいた。
苗字名前。
俺の恋人だ。
片手にスケッチブックを抱え、空模様を恨めしげに見上げるでもなく、ただ静かに雨粒が地面を叩く様を眺めている。その横顔は、印象派の絵画から抜け出してきたみたいに、淡い光と影の中で儚げな輪郭を描いていた。
「名前」
声を掛けると、彼女の肩が小さく跳ねる。ゆっくりとこちらを振り返った大きな瞳が、俺の姿を捉え、ふわりと花の蕾が綻ぶように和らいだ。
「鉄朗くん。お疲れ様」
「おう、お疲れ。待ってたのか?」
「うん。雨が降りそうだったから」
そう首肯して、名前は自分の持っていた小さな折り畳み傘を、少しだけ持ち上げてみせる。……いや、どう考えても、身長187.7cmの男子高校生と、その隣に立つ女子高生が二人で入るには、余りにも心許ないサイズだ。こいつ、本当にそれで相合傘をするつもりなのか?
「……お前、それ、本気か?」
「え? うん。鉄朗くんが濡れてしまうのは、困るから」
きょとんとした顔で、さも当然のように言う。どこまでも純粋で、ちょっとネジの外れた思考回路。この底知れない天然さに、何度、調子を狂わされてきたことか。
「あのな、俺の傘、デカいから。こっち入りなさい」
俺はバサリと音を立てて、自分の大きな傘を開き、名前の肩をぐっと引き寄せた。途端に、シャンプーと、雨と、彼女自身の甘い匂いが混じり合った、くらりとするような香りが鼻腔を擽る。肩が触れ合う距離。密着した腕から伝わる柔らかな感触と体温に、心臓が馬鹿みたいに跳ね上がる。おいおい、理性。仕事しろ、仕事。お前は音駒の主将だろうが。
「わ、ありがとう」
素直に頷き、俺の腕の中にすっぽりと収まる名前。心臓の音、聞こえてないだろうな。雨音に紛れてくれ、頼むから。
「でも、私の傘、どうしよう」
「畳んで、カバン入れとけ」
「そうだね」
二人で一つの傘に身を寄せ、ゆっくりと歩き出す。雨は次第に強まり、ポリエステルを叩く音が、オーケストラの打楽器のように重厚なリズムを刻み始めた。街灯がぼんやりと光の輪を滲ませ、世界から色彩が洗い流されていくようだ。
「……ねぇ、鉄朗くん」
「ん?」
「さっき、研磨くんが走って駅に向かっていたよ」
「だろうな。あいつは傘より、ゲームのセーブデータが大事なんだよ」
「ふふ、そうなんだ」
楽しそうに笑う名前の声は、雨音の中でも不思議とクリアに届く。その声を聞いているだけで、部活の疲労がじんわりと溶けていく気がした。
と、その時だった。名前がふと足を止め、俺の顔をじっと見上げた。傘から落ちる雫が、彼女の長い睫毛をきらりと濡らす。
「どうした?」
「鉄朗くんの髪、今日のトサカはいつもより、少しだけ右に傾いてるね」
「……は?」
なんだ、そのピンポイント過ぎる指摘は。俺の寝癖は生き物か何かか?
「それに、左の眉が、ほんの少し上がってる。何か、面白いことでも考えているの?」
「いや、別に何も……」
嘘だ。めちゃくちゃ考えてる。お前が可愛過ぎてどうにかなりそうだとか、このままどっかに連れ去っちまいたいとか、その他諸々、とてもじゃないが、口には出せない思春期丸出しの煩悩が、脳内でサンバを踊っている。
名前は、ふぅん、と小さく息を吐くと、また前を向いて歩き出した。
「鉄朗くんって、時々、何を考えているのか、見えなくなる時がある」
「……そりゃ、お互い様だろ」
俺だって、お前が何を考えているのか、さっぱり分からない時がある。今みたいに、俺の寝癖の角度を真剣に分析してる時とかな。
「そうかな。私は、分かり易いと思うけれど」
「どこがだよ」
「でもね」
名前は繋いでいない方の手で、俺の制服のブレザーの裾を、きゅ、と小さく掴んだ。
「見えなくても、鉄朗くんがここに居るのは、ちゃんと分かるよ。匂いとか、音とか、この温かさとかで」
――――ドクンッ。
心臓が喉から飛び出しそうだった。
やめろ。そう云う、無自覚の爆弾を投下するのはやめてくれ。俺の男子高校生レベルの耐久力では、受け止め切れない。
「……そ、そうかよ」
「うん。だから、大丈夫」
何が大丈夫なのかはさっぱり分からないが、名前の確信に満ちた声に、俺はもう降参するしかなかった。見えないもの。ああ、確かにそうだ。俺がお前を好きな気持ちも、お前が俺を想ってくれているであろうその心も、目には見えない。だけど、こうして触れ合う肌の温かさや、裾を掴む指先の力、隣で聞こえる呼吸の音、その全てが、見えない筈の"それ"が実在していると、雄弁に物語っていた。
「……なぁ、名前」
「なに?」
「この雨、止みそうにねえな」
「そうだね」
「お前のじいちゃんの店、寄ってかねえか? 雨の日しか、やってねえし」
「! うん。鉄朗くん、来てくれるの?」
ぱあっと顔を輝かせ、期待に満ちた瞳で、俺を見上げる。その反応が堪らなく愛しくて、口許が自然と弛んだ。
「当たり前だろ。あの店の『雨の日パフェ』、食いたくなった」
そうだ、あそこなら、この鳴り止まない雨音も、喧しい心臓の音も、心地好いBGMに変えてくれる筈だ。
路地裏にひっそりと佇む、その風変わりなブックカフェの看板が見えてくる。
『雨滴文庫』
雨の雫だけが、その扉を開く鍵だった。
 私の祖父が道楽で営む『雨滴文庫』は、私の家であり、私の世界そのものだ。
木の扉を開けると、カランコロン、と澄んだベルの音が鳴り、古書の匂いと、焙煎された珈琲豆の香ばしいアロマが、私達をふわりと包み込んだ。
「おや、名前。それに、鉄朗くんも。いらっしゃい」
カウンターの奥から、柔和な笑顔で迎えてくれたのは、私の祖父だった。銀縁眼鏡の奥の瞳が、優しく細められる。
「ただいま、お祖父ちゃん」
「こんにちは、お邪魔します」
鉄朗くんが少しだけ頭を下げると、祖父は「はいはい」と嬉しそうに頷いた。
「鉄朗くんは、いつもの『ジュークボックス・ブレンド』でいいかい? 名前は、今日はどうする?」
「あ、俺、今日は『雨の日パフェ』で」
「おや、珍しい。分かったよ。名前は?」
「私は、温かいミルクティーをお願い」
窓際のカウンター席に、二人で並んで腰を下ろす。見慣れた場所。見慣れた窓の外の景色。でも、隣に鉄朗くんが居るだけで、いつもの風景が、初めて観る映画のワンシーンみたいに、特別にきらきらして見えるから不思議だ。
私は鞄からスケッチブックを取り出した。別に、誰かに見せるわけではない。ただ、描いていると落ち着くのだ。特に、私の世界に居る、鉄朗くんの姿を。
鉛筆を握り、向かいの出窓の小物に視線を移す振りをしながら、隣に座る鉄朗くんを盗み見る。
窓の外を眺める、彼の横顔。雨粒に濡れた髪が、店内のオレンジ色の照明を浴びて、艶やかに光っている。僅かに開かれた唇。長い指が、カウンターの木目をゆっくりと撫でている。
鉄朗くんの、そう云う何気ない仕草の一つひとつが、私の心を掴んで離さない。
バレーをしている時の、鋭い獣のような眼差しも好き。
仲間と巫山戯合っている時の、少年みたいなくしゃっとした笑顔も好き。
でも、こうして、私の世界に溶け込んで、リラックスしている彼を見ているのが、一番好きかもしれない。
鉄朗くんの全てを、この紙の上に写し取れたらいいのに。
そうすれば、会えない時も、彼の存在を直ぐ傍に感じられるから。
線の練習、なんて、ただの口実だ。本当は、鉄朗くんの輪郭を、骨格を、筋肉の付き方を、この指先に記憶させたいだけ。彼の"存在"そのものを、自分のものにしてしまいたいと云う、独占欲なのかもしれない。
先程、彼が私のことを「分からない」と言った時、少しだけ胸がちくりと痛んだ。
分かり易いと思うのだけれど。
鉄朗くんが隣に居ると、心臓がふわふわして、温かいお日様の下で微睡んでいるような気持ちになること。彼の声を聞くと、安心すること。彼に触れられると、溶けてしまいそうになること。
全部、顔に出てしまっていると思っていた。
でも、そうか。鉄朗くんには、見えていないのか。
私のこの気持ちも、彼が私に向けてくれる優しい気持ちも、目には見えない。
それは、少しだけ、もどかしい。
「はい、お待ちどう。鉄朗くんの『雨の日パフェ』と、名前のミルクティー。それと、これ。新作の『吐息のガトーショコラ』だ。名前、ちょっと味見してくれるかい?」
「わぁ、うん。頂きます」
目の前に置かれたのは、濃厚なチョコレートの香りがする、小さなケーキ。フォークを入れると、しっとりとした感触が伝わる。一口食べれば、ビターな甘さが口いっぱいに広がって、本当に吐息が出そうなくらい、美味しかった。
「……美味しい」
「そりゃ良かった」
祖父が嬉しそうに笑う。ちらり、と隣を見ると、鉄朗くんがパフェのスプーンを咥えたまま、じっと、私のことを見ていた。その視線に気づいて、心臓が、とくん、と跳ねる。
「……なに?」
「いや。美味そうに食うなって」
「鉄朗くんも、食べる?」
「ん。一口」
私がフォークで切り分けた小さな一欠けらを、彼は大きな口でぱくりと食べた。
「……うまっ」と、少しだけ目を見開く。その表情が可愛くて、私はくすくすと笑ってしまった。
見えなくても、いいのかもしれない。
鉄朗くんの考えていること、全てが見えなくても。私の考えていること、全てが伝わらなくても。
こうして、同じものを「美味しい」と感じて、同じ空間で、同じ音を聞いている。
鉄朗くんがパフェを食べるスプーンの動きが、ほんの少しだけぎこちないことに、私は気づいている。
彼の視線が、私の唇に一瞬だけ注がれたことに、私は気づいている。
見えないけれど、確かにそこに在るもの。
それは不安の種にもなるけれど、同時に宝探しみたいで、一寸だけ、わくわくもする。
私はスケッチブックを閉じた。
そして、カウンターの下で、鉄朗くんの大きな手に、自分の指をそっと絡めた。
ぴくり、と彼の肩が揺れるのが、繋いだ手を通して伝わる。
見上げると、鉄朗くんは僅かに目を見開いて、それから、どうしようもなく優しい顔で笑った。
その表情に、答えが全部、書いてあった。
「……鉄朗くん」
「ん?」
「好きだよ」
雨音とジャズのメロディと、祖父が食器を片付ける音に紛れてしまいそうな、小さな声。
でも、この私の世界でなら、きっと素直に言える。
彼には、ちゃんと届いたみたいだ。
「……知ってる。俺も」
鉄朗くんは些か照れ臭そうにそう返して、絡めた指を、ぎゅっと強く握り返した。
その温かさと強さが、見えない筈の彼の心を、何よりもはっきりと伝えてくれる。
窓の外では、いつの間にか雨が上がっていた。
雲の切れ間から差し込む西日が、濡れた世界を金色に染め上げていく。
見えないけれど、確かに存在している。
それはきっと、この世界の、一番素敵な魔法なのだと思う。
私の祖父が道楽で営む『雨滴文庫』は、私の家であり、私の世界そのものだ。
木の扉を開けると、カランコロン、と澄んだベルの音が鳴り、古書の匂いと、焙煎された珈琲豆の香ばしいアロマが、私達をふわりと包み込んだ。
「おや、名前。それに、鉄朗くんも。いらっしゃい」
カウンターの奥から、柔和な笑顔で迎えてくれたのは、私の祖父だった。銀縁眼鏡の奥の瞳が、優しく細められる。
「ただいま、お祖父ちゃん」
「こんにちは、お邪魔します」
鉄朗くんが少しだけ頭を下げると、祖父は「はいはい」と嬉しそうに頷いた。
「鉄朗くんは、いつもの『ジュークボックス・ブレンド』でいいかい? 名前は、今日はどうする?」
「あ、俺、今日は『雨の日パフェ』で」
「おや、珍しい。分かったよ。名前は?」
「私は、温かいミルクティーをお願い」
窓際のカウンター席に、二人で並んで腰を下ろす。見慣れた場所。見慣れた窓の外の景色。でも、隣に鉄朗くんが居るだけで、いつもの風景が、初めて観る映画のワンシーンみたいに、特別にきらきらして見えるから不思議だ。
私は鞄からスケッチブックを取り出した。別に、誰かに見せるわけではない。ただ、描いていると落ち着くのだ。特に、私の世界に居る、鉄朗くんの姿を。
鉛筆を握り、向かいの出窓の小物に視線を移す振りをしながら、隣に座る鉄朗くんを盗み見る。
窓の外を眺める、彼の横顔。雨粒に濡れた髪が、店内のオレンジ色の照明を浴びて、艶やかに光っている。僅かに開かれた唇。長い指が、カウンターの木目をゆっくりと撫でている。
鉄朗くんの、そう云う何気ない仕草の一つひとつが、私の心を掴んで離さない。
バレーをしている時の、鋭い獣のような眼差しも好き。
仲間と巫山戯合っている時の、少年みたいなくしゃっとした笑顔も好き。
でも、こうして、私の世界に溶け込んで、リラックスしている彼を見ているのが、一番好きかもしれない。
鉄朗くんの全てを、この紙の上に写し取れたらいいのに。
そうすれば、会えない時も、彼の存在を直ぐ傍に感じられるから。
線の練習、なんて、ただの口実だ。本当は、鉄朗くんの輪郭を、骨格を、筋肉の付き方を、この指先に記憶させたいだけ。彼の"存在"そのものを、自分のものにしてしまいたいと云う、独占欲なのかもしれない。
先程、彼が私のことを「分からない」と言った時、少しだけ胸がちくりと痛んだ。
分かり易いと思うのだけれど。
鉄朗くんが隣に居ると、心臓がふわふわして、温かいお日様の下で微睡んでいるような気持ちになること。彼の声を聞くと、安心すること。彼に触れられると、溶けてしまいそうになること。
全部、顔に出てしまっていると思っていた。
でも、そうか。鉄朗くんには、見えていないのか。
私のこの気持ちも、彼が私に向けてくれる優しい気持ちも、目には見えない。
それは、少しだけ、もどかしい。
「はい、お待ちどう。鉄朗くんの『雨の日パフェ』と、名前のミルクティー。それと、これ。新作の『吐息のガトーショコラ』だ。名前、ちょっと味見してくれるかい?」
「わぁ、うん。頂きます」
目の前に置かれたのは、濃厚なチョコレートの香りがする、小さなケーキ。フォークを入れると、しっとりとした感触が伝わる。一口食べれば、ビターな甘さが口いっぱいに広がって、本当に吐息が出そうなくらい、美味しかった。
「……美味しい」
「そりゃ良かった」
祖父が嬉しそうに笑う。ちらり、と隣を見ると、鉄朗くんがパフェのスプーンを咥えたまま、じっと、私のことを見ていた。その視線に気づいて、心臓が、とくん、と跳ねる。
「……なに?」
「いや。美味そうに食うなって」
「鉄朗くんも、食べる?」
「ん。一口」
私がフォークで切り分けた小さな一欠けらを、彼は大きな口でぱくりと食べた。
「……うまっ」と、少しだけ目を見開く。その表情が可愛くて、私はくすくすと笑ってしまった。
見えなくても、いいのかもしれない。
鉄朗くんの考えていること、全てが見えなくても。私の考えていること、全てが伝わらなくても。
こうして、同じものを「美味しい」と感じて、同じ空間で、同じ音を聞いている。
鉄朗くんがパフェを食べるスプーンの動きが、ほんの少しだけぎこちないことに、私は気づいている。
彼の視線が、私の唇に一瞬だけ注がれたことに、私は気づいている。
見えないけれど、確かにそこに在るもの。
それは不安の種にもなるけれど、同時に宝探しみたいで、一寸だけ、わくわくもする。
私はスケッチブックを閉じた。
そして、カウンターの下で、鉄朗くんの大きな手に、自分の指をそっと絡めた。
ぴくり、と彼の肩が揺れるのが、繋いだ手を通して伝わる。
見上げると、鉄朗くんは僅かに目を見開いて、それから、どうしようもなく優しい顔で笑った。
その表情に、答えが全部、書いてあった。
「……鉄朗くん」
「ん?」
「好きだよ」
雨音とジャズのメロディと、祖父が食器を片付ける音に紛れてしまいそうな、小さな声。
でも、この私の世界でなら、きっと素直に言える。
彼には、ちゃんと届いたみたいだ。
「……知ってる。俺も」
鉄朗くんは些か照れ臭そうにそう返して、絡めた指を、ぎゅっと強く握り返した。
その温かさと強さが、見えない筈の彼の心を、何よりもはっきりと伝えてくれる。
窓の外では、いつの間にか雨が上がっていた。
雲の切れ間から差し込む西日が、濡れた世界を金色に染め上げていく。
見えないけれど、確かに存在している。
それはきっと、この世界の、一番素敵な魔法なのだと思う。