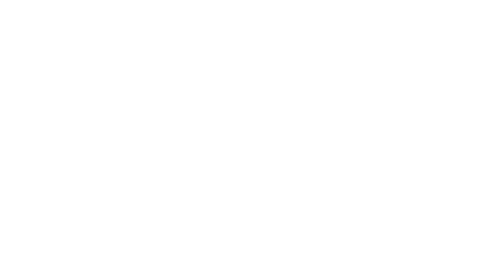何気ない放課後、公園に響いた二つの音が、
恋の温度をそっと上げていく。
尾行騒動から数日後の放課後。わたしの突飛な好奇心に最後まで付き合ってくれた恋人との約束を果たすべく、二人で連れ立って例のコンビニへと向かっていた。喧騒が遠ざかり始めた通学路を、夕陽が橙色の絵の具で塗り潰していく。隣を歩く鉄朗くんの長い影が、わたしの影に時折重なっては離れていった。
「本当に面白かったよ、この間の尾行。鉄朗くん、全然気づいていないフリをするのが上手だったね」
「そりゃどうも。心臓に悪いから、もう勘弁してほしいけどな」
呆れたように言いながらも、彼の口元は楽しげに綻んでいる。あの日のことを思い出すと、今でも胸の奥が擽ったい。スリルと背徳感に満ちた甘美なゲーム。そして、最後に彼に捕まえられた瞬間の、あのどうしようもない高揚感。わたしの仕掛けた悪戯に、鉄朗くんが完璧な形で乗ってくれたことが、何よりも嬉しかった。
「でも、お陰で、わたしの知らない鉄朗くんを沢山見られたよ。リエーフくんを心配する主将の顔も、研磨くんと居る時のリラックスした顔も。そして、わたしを揶揄う時の、意地の悪い顔も」
「おい、最後のは余計だろ」
軽口を叩き合いながら、コンビニの自動ドアを潜る。むわりと漂う独特の匂い。わたし達は迷うことなく、あの日の彼と同じように中華まんの保温ケースの前へ向かう。
「肉まん、二つください」
鉄朗くんが店員さんに告げる声は、部活の時とは違う、少しだけ気の抜けた穏やかな響きを持っている。湯気の立つ温かな包みを二つ受け取ると、彼は一つをわたしに手渡した。中身の詰まった重みと熱が、指先からじんわりと伝わる。
「どこで食べようか。近くの公園、空いているかな」
「ああ、行ってみるか」
コンビニを出て、駅とは反対方向にある小さな公園を目指す。ブランコと滑り台、そして、ぽつんと置かれたベンチだけの、何の変哲もない場所。けれど、今のわたし達にとっては、世界で一番特別な場所に思えた。
ベンチに並んで腰掛け、早速、ほかほかの肉まんを頬張る。もちりとした皮の中から、ジューシーな肉餡の旨味がじゅわりと溢れ出した。
「……美味しい」
「だろ? 部活終わりの空きっ腹に染みるんだよ、これが」
満足気に目を細める彼の横顔を盗み見る。学校でも、二人きりの部屋でもない、こんな風に外で他愛ない時間を過ごすのは、何だか新鮮で、少しだけ照れ臭い。夕暮れの公園は静かで、時折、遠くを走る電車の音や、カラスの鳴き声が聞こえてくるだけだった。
その時だ。どこからともなく、素朴で、けれど、どこか郷愁を誘うような音色が風に乗って届いたのは。震えるような、二つの音が重なり合って生まれる独特の響き。
「……ハーモニカ?」
わたしが知っているオーボエやピアノの音とは全く違う、温かみのある音色だった。公園の隅にある東屋で、年配の男性が一人、小さな楽器を手に夕陽へ向かって吹いているのが見えた。トレモロ奏法と言うのだろうか、その優しい調べは茜色に染まる空気に溶けて、わたしの心の琴線にそっと触れた。
「複音ハーモニカ、だな。二列の穴があって、同時に吹くと音が少しずれて、あんな風に震えるように聞こえるんだ」
鉄朗くんが事もなげに説明する。わたしの知らないことを、彼は沢山知っている。その度に、心臓の辺りがぎゅっとなる。
「ばあちゃんが昔、少しだけ吹いてたんだよ。懐かしい音だ」
そう言って微笑む彼の表情は、とても優しかった。わたしはその音色と、彼の横顔から目が離せなくなる。もっと聴いていたい。もっと知りたい。その純粋な好奇心が、わたしの口を動かした。
「鉄朗くんは吹けるの?」
「俺? いや、全然。難しくてさ」
彼はそう言って苦笑すると、何故か自分のスクールバッグをごそごそと漁り始めた。そして、中から取り出したのは、使い込まれて些か色褪せた、赤いレザーケースだった。パチン、と留め具を外すと、中から現れたのは、あの男性が持っていたのと同じ、銀色に輝く複音ハーモニカだった。
「……どうして、鉄朗くんが持っているの?」
驚きに目を見開くわたしに、彼は少しだけバツが悪そうに視線を逸らした。
「ばあちゃんに、昔貰ったヤツ。吹けたら格好良いかな、なんて思ったけど……まあ、見ての通り、ただのお飾りだよ」
夕陽の光を反射して、きらりと光るハーモニカ。それはまるで、鉄朗くんの秘密の宝物のように見えた。
 やっちまった、と内心で舌打ちする。名前が音楽を愛しているのは知っていたから、いつかこの古びたハーモニカを見せたいとは思っていた。けれど、オーボエやピアノを完璧に弾き熟す彼女の前で、ドレミも覚束ない俺の腕前を披露するなんて、羞恥以外の何物でもない。だから、ずっと鞄の底に眠らせていたのに。
公園に響くあの音色に、名前がうっとりと耳を澄ませるものだから。その澄んだ瞳が、余りにも綺麗だったから。つい、見栄を張るみたいに取り出してしまった。
「吹いてみて」
ほら、来た。純粋な好奇心に満ちた、悪意なきリクエスト。断れるワケがない。俺は観念して、ハーモニカをそっと口に当てた。ばあちゃんに教わった通り、息を吸ったり吐いたりしてみるが、唇から漏れるのは間抜けで単調な音ばかり。和音なんて、夢のまた夢だ。
「……ほら、な? 全然だろ」
自嘲気味に笑ってみせると、名前は首を横に振った。馬鹿にするでもなく、呆れるでもなく、ただ真摯な眼差しで、俺の手元を見つめている。
「ううん。鉄朗くんの音がする」
「は……?」
「不器用で、少しだけ強がりで、でも、とても優しい音。わたしは好きだよ」
その言葉に、心臓が大きく跳ねた。夕陽の所為ではなく、顔に熱が集まるのが分かる。俺の彼女は時々、こういう、こちらの心臓を鷲掴みにするような台詞を、何の気なしに口にする。
「……わたしにも、少しだけ吹かせてくれないかな」
小首を傾げる仕草に抗える筈もなく、俺は恐る恐るハーモニカを手渡した。名前はそれを受け取ると、壊れ物を扱うかのように両手でそっと包み込む。そして、オーボエのリードを咥える時のように、ゆっくりと、優雅な仕草で銀色のプレートに薄桃色の唇を寄せた。
その光景に、息を呑む。
俺がさっきまで口を付けていた場所に、彼女の唇が触れている。間接キス、なんて陳腐な言葉が頭を過ったが、そんな思考は直ぐに吹き飛んだ。
ふぅ、と彼女が息を吹き込む。すると、どうだろう。俺が出したのとは比べ物にならないくらい、澄み切った、清らかな和音が公園の空気に響き渡った。拙さはある。けれど、音の一つひとつに芯があって、命が宿っているようだった。
「……凄いな、お前」
「息を二つの穴に、均等に、真っ直ぐ入れるのが難しいね。でも、面白い。オーボエとは違う、身体全体で音を鳴らす感覚がある」
真剣な顔で分析する彼女の横顔を、夕陽が黄金色に縁取っていた。長い睫毛が落とす影、ハーモニカに映る真剣な瞳、そして、微かに開かれた唇。その全てが芸術品のように美しくて、俺はもうどうしようもなかった。
「……名前」
「ん?」
「それ、やるよ」
「え?」
きょとん、と目を丸くする彼女に、俺はもう一度繰り返した。
「お前が持ってた方が、こいつも喜ぶだろ。俺が持ってても、ただのガラクタだしな」
本当は、ばあちゃんから貰った大切なものだ。でも、このハーモニカが名前の唇に触れて、あんなにも美しい音を奏でた瞬間、これはもう彼女のものだ、と直感的に思った。俺の宝物は、彼女がもっと輝かせてくれる筈だ。
「……ありがとう、鉄朗くん。嬉しい。大切にする」
ふわりと花が綻ぶように、名前が微笑んだ。彼女はハーモニカをそっと胸に抱き締める。その仕草が、どうしようもなく愛おしい。
日が落ち、公園の照明がぼんやりと灯り始める。俺は立ち上がり、彼女に手を差し出した。
「今度はそのハーモニカで、俺の知らない曲、聴かせてくれよ」
「うん。鉄朗くんの為だけに、練習するね」
その約束だけで、胸がいっぱいになる。繋いだ手は、さっき食べた肉まんみたいに温かかった。
地を這うようなスリリングな追い駆けっこも悪くない。けれど、こんな風に何でもない日常の中で、彼女の新しい一面を発見し、俺の欠片を分かち合う。そんな穏やかな時間こそが、何よりの宝物なのかもしれない。
隣で時々、ハーモニカを鞄から取り出しては愛おしそうに眺めている恋人を見ながら、俺は静かに思う。この掴みどころのない、最高に愛しい彼女の為なら。何度だって、心を掻き乱されてやろう。それもまた、俺と彼女だけの、極上の物語なのだから。
やっちまった、と内心で舌打ちする。名前が音楽を愛しているのは知っていたから、いつかこの古びたハーモニカを見せたいとは思っていた。けれど、オーボエやピアノを完璧に弾き熟す彼女の前で、ドレミも覚束ない俺の腕前を披露するなんて、羞恥以外の何物でもない。だから、ずっと鞄の底に眠らせていたのに。
公園に響くあの音色に、名前がうっとりと耳を澄ませるものだから。その澄んだ瞳が、余りにも綺麗だったから。つい、見栄を張るみたいに取り出してしまった。
「吹いてみて」
ほら、来た。純粋な好奇心に満ちた、悪意なきリクエスト。断れるワケがない。俺は観念して、ハーモニカをそっと口に当てた。ばあちゃんに教わった通り、息を吸ったり吐いたりしてみるが、唇から漏れるのは間抜けで単調な音ばかり。和音なんて、夢のまた夢だ。
「……ほら、な? 全然だろ」
自嘲気味に笑ってみせると、名前は首を横に振った。馬鹿にするでもなく、呆れるでもなく、ただ真摯な眼差しで、俺の手元を見つめている。
「ううん。鉄朗くんの音がする」
「は……?」
「不器用で、少しだけ強がりで、でも、とても優しい音。わたしは好きだよ」
その言葉に、心臓が大きく跳ねた。夕陽の所為ではなく、顔に熱が集まるのが分かる。俺の彼女は時々、こういう、こちらの心臓を鷲掴みにするような台詞を、何の気なしに口にする。
「……わたしにも、少しだけ吹かせてくれないかな」
小首を傾げる仕草に抗える筈もなく、俺は恐る恐るハーモニカを手渡した。名前はそれを受け取ると、壊れ物を扱うかのように両手でそっと包み込む。そして、オーボエのリードを咥える時のように、ゆっくりと、優雅な仕草で銀色のプレートに薄桃色の唇を寄せた。
その光景に、息を呑む。
俺がさっきまで口を付けていた場所に、彼女の唇が触れている。間接キス、なんて陳腐な言葉が頭を過ったが、そんな思考は直ぐに吹き飛んだ。
ふぅ、と彼女が息を吹き込む。すると、どうだろう。俺が出したのとは比べ物にならないくらい、澄み切った、清らかな和音が公園の空気に響き渡った。拙さはある。けれど、音の一つひとつに芯があって、命が宿っているようだった。
「……凄いな、お前」
「息を二つの穴に、均等に、真っ直ぐ入れるのが難しいね。でも、面白い。オーボエとは違う、身体全体で音を鳴らす感覚がある」
真剣な顔で分析する彼女の横顔を、夕陽が黄金色に縁取っていた。長い睫毛が落とす影、ハーモニカに映る真剣な瞳、そして、微かに開かれた唇。その全てが芸術品のように美しくて、俺はもうどうしようもなかった。
「……名前」
「ん?」
「それ、やるよ」
「え?」
きょとん、と目を丸くする彼女に、俺はもう一度繰り返した。
「お前が持ってた方が、こいつも喜ぶだろ。俺が持ってても、ただのガラクタだしな」
本当は、ばあちゃんから貰った大切なものだ。でも、このハーモニカが名前の唇に触れて、あんなにも美しい音を奏でた瞬間、これはもう彼女のものだ、と直感的に思った。俺の宝物は、彼女がもっと輝かせてくれる筈だ。
「……ありがとう、鉄朗くん。嬉しい。大切にする」
ふわりと花が綻ぶように、名前が微笑んだ。彼女はハーモニカをそっと胸に抱き締める。その仕草が、どうしようもなく愛おしい。
日が落ち、公園の照明がぼんやりと灯り始める。俺は立ち上がり、彼女に手を差し出した。
「今度はそのハーモニカで、俺の知らない曲、聴かせてくれよ」
「うん。鉄朗くんの為だけに、練習するね」
その約束だけで、胸がいっぱいになる。繋いだ手は、さっき食べた肉まんみたいに温かかった。
地を這うようなスリリングな追い駆けっこも悪くない。けれど、こんな風に何でもない日常の中で、彼女の新しい一面を発見し、俺の欠片を分かち合う。そんな穏やかな時間こそが、何よりの宝物なのかもしれない。
隣で時々、ハーモニカを鞄から取り出しては愛おしそうに眺めている恋人を見ながら、俺は静かに思う。この掴みどころのない、最高に愛しい彼女の為なら。何度だって、心を掻き乱されてやろう。それもまた、俺と彼女だけの、極上の物語なのだから。