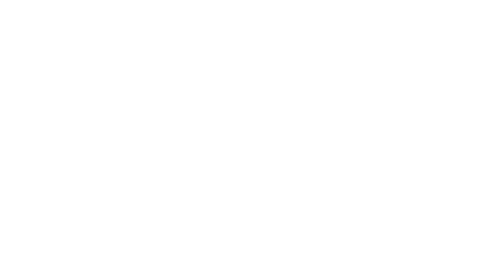事の発端は、兄の書斎で見つけた一冊の古い探偵小説だった。主人公は恋人の素行を疑い、巧みな変装で七日七晩に渡る尾行の末、彼女が自分への誕生日プレゼントを選ぶ為に奔走していただけだと知る。感動的な結末ではあったけれど、わたしの心に引っ掛かったのは別の部分だった。
──恋人を尾行する。
それは一体、どれ程にスリリングで、心躍る経験なのだろう。
「兄貴兄さん。わたし、鉄朗くんを尾行してみようと思う」
「ほう」
リビングのソファで、新作の構想を練っていた兄──苗字兄貴は、奇妙な象形文字がプリントされた黒いTシャツ姿で顔を上げた。妹の突拍子もない宣言に、彼は眉一つ動かさない。それどころか、漆黒の瞳を面白そうに細めた。
「それは素晴らしい着眼点だ、名前。動機は? 彼の浮気を疑っているのかい?」
「ううん、そういうことじゃないよ。ただ、わたしの知らない鉄朗くんが、どんな顔で、どんな風に世界を見ているのか、こっそり覗いてみたくなっただけ。鉄朗くんが、わたし以外に見せる顔を内緒で知る、という状況に興味がある」
「成る程。独占欲の新しい形か。実に、名前らしい。いいじゃないか、やってみるといい。きっと新しい物語の種が見つかる」
兄のお墨付きを得たわたしは、早速、計画を実行に移すことにした。決行は明日、放課後。音駒高校排球部の練習終わりを狙う。
自室に戻り、クローゼットの奥から引っ張り出したのは、兄がどこかで見つけてきては「面白いだろう」と押し付けてくる、変な文字入りTシャツの一枚。墨痕鮮やかに『隠密』と書かれたそれを着込み、その上からチャコールグレーのパーカーを羽織る。黒いパンツに、髪は低い位置で一つに束ね、深めのキャップを被れば、我ながら完璧な変装に思えた。鏡に映る自分は、どこにでも居る、少しだけ挙動不審な若者だ。うん、これなら、鉄朗くんにも気づかれないだろう。
翌日。夕暮れの気配が色濃くなってきた頃、わたしは音駒高校の校門が見える電信柱の影に身を潜めていた。心臓がオーボエのソロパートを前にした時みたいに、静かに高鳴っている。やがて、賑やかな声が聞こえてきて、排球部の面々がぞろぞろと姿を現した。
居た。長身に、あの特徴的なトサカヘッド。間違いない、わたしの恋人、黒尾鉄朗くんだ。
彼の隣には、プリン頭がトレードマークの孤爪研磨くんが歩いている。二人は何やら言葉を交わしながら、駅の方向へ歩き出した。わたしは電信柱からそっと身を乗り出し、慎重に距離を保ちながら後を追う。これぞ正しく、地を這うような前進。心の中で、わたしは探偵小説の主人公になり切っていた。
「今日のリエーフ、最後の自主練で顔面レシーブ三回はしてたよな」
「クロが扱き過ぎなんだよ……」
風に乗って、そんな会話が聞こえてくる。わたしの知らない、部活での鉄朗くん。後輩を厳しくも愛情を持って指導する主将の顔。それだけで、胸の奥がじんわりと温かくなる。
二人がふらりと吸い込まれていったのは、駅前のコンビニだった。わたしも何食わぬ顔で入店し、お菓子コーナーに陣取って、棚の影から二人を観察する。鉄朗くんは迷うことなく中華まんのケースへ向かい、店員さんに「肉まんください」と告げた。そうか、彼は肉まんが好きなんだ。また一つ、彼の秘密を知ってしまった。そんな些細なことが堪らなく嬉しい。
コンビニを出ても、二人は別れる素振りを見せない。そうだった。二人は家が隣同士で、一緒に電車で帰るんだった。わたしは慌てて距離を取り直し、二人が向かう駅の改札へと足を速める。
同じ車両に乗り込むのはリスクが高い。わたしは一つ隣の車両に乗り込み、連結部分の窓からそっと彼らの様子を窺った。夕方の帰宅ラッシュで混み合う車内。吊革に掴まる鉄朗くんと、その隣でスマートフォンを覗き込む研磨くん。二人の世界は騒がしい車内から切り離されたように穏やかだ。
ガタン、ゴトン、と規則的な揺れが、わたしの高揚感を更に煽る。窓ガラスに映る鉄朗くんの横顔。学校で見せる顔とも、わたしと二人きりの時の顔とも違う、幼馴染と過ごすリラックスした表情。それを盗み見ているという背徳感が堪らない。
やがて電車が目的の駅に到着し、ホームに降り立った二人。けれど、彼らは別れない。当然だ、家が隣同士なのだから。ここからが最大の難関。どうやって、鉄朗くんだけに尾行を明かそう。わたしが思考を巡らせていると、二人は並んで改札を出て、住宅街へと歩き始めた。
研磨くんの家の前まで来れば、彼は家に入って、鉄朗くんは一人になる筈。そこからが本番だ。人通りも少なくなってくる。わたしは彼の視界に入らないよう、駐車してある車の陰に隠れたり、塀にぴったりと身を寄せたり、宛らスパイ映画の主人公のように動いた。我ながら見事なステルス性能だ。
その時だった。
「……ん?」
鉄朗くんが、ぴたりと足を止めた。そして、ゆっくりとこちらを振り返る。
拙い。
心臓が喉から飛び出そうになるのを必死で押さえた。わたしは咄嗟に身を屈め、植え込みの影に完全に同化する。彼の視線が、辺りを訝しむように彷徨っているのが気配で分かった。お願い、気づかないで。見つかったら、この甘美なゲームが終わってしまう。
沈黙が支配する。どうしよう。何か、何かで誤魔化さないと。その瞬間、わたしの口から意味不明な音が飛び出した。
「……にゃーん」
絞り出した声は思ったよりもか細く、そして下手糞だった。けれど、効果はあったらしい。
「……なんだ、猫か」
鉄朗くんはそう呟くと、何事もなかったかのように前を向いて歩き出した。
わたしは植え込みの中で、安堵の息を漏らした。危なかった。けれど、スリルが堪らない。このドキドキは、彼が直ぐ近くに居るから? それとも、悪いことをしている背徳感から? きっと、その両方だ。わたしはキャップを整え直し、再び慎重に愛しい獲物の後を追い始めた。地を這うように、一歩、また一歩と。
 「……なんだ、猫か」
俺はそう呟き、笑いを堪えるのに必死になりながら歩き出した。肩が震えるのを誤魔かす為に、態と大きく腕を振る。
いや、猫じゃねぇだろ。どう考えても。あんな覇気のない、か細い「にゃーん」が猫であって堪るか。
と言うか、そもそも気づいてないフリをするのだって、もう限界に近かった。
俺が彼女──苗字名前の珍妙な尾行に気づいたのは、校門を出て直ぐのことだ。なんか視線を感じるな、と思って目だけで確認したら、電信柱の影からキャップにパーカーのフードを被った不審人物がこっちを覗いている。一瞬、誰かのストーカーか? と身構えたが、その独特な気配と、隠し切れていない華奢なシルエットに見覚えがあり過ぎた。
……名前だ。
なんで? どうして? 何してんの、あいつ。
疑問符が頭の中を乱舞したが、次の瞬間、猛烈な面白さが込み上げてきた。隣を歩く研磨にバレないように口元を引き締め、俺は一つの結論に至る。
──乗ってやろう、この奇妙なゲームに。
「今日のリエーフ、最後の自主練で顔面レシーブ三回はしてたよな」
敢えて、少しだけ大きな声で研磨に話し掛ける。案の定、背後で微かな衣擦れの音がした。付いてきてる、付いてきてる。
コンビニに入った時も、お菓子コーナーの棚の影からこっちを凝視している名前を、俺は店内の防犯ミラー越しに確りと確認済みだ。あの真剣な眼差し。俺が肉まんを買うだけなのに、国家機密でも目撃したかのような集中力。
……可愛過ぎんだろ、俺の彼女。
普段はミステリアスで、何を考えているか分からない時もある。けれど、一度好奇心に火が点くと、こうして突拍子もないことを仕出かす。そんなところが、どうしようもなく愛おしい。
コンビニを出て、駅へ向かう。勿論、背後には『隠密』行動中の彼女。研磨はゲームに夢中で、周囲への関心はゼロだ。好都合過ぎる。
改札を抜け、ホームで電車を待つ間も、名前は柱の影からこちらを窺っている。電車に乗り込めば、律儀に隣の車両へ。連結部の窓から覗く、キャップのツバと真剣な眼差し。おいおい、そんなに見つめたらバレるっての。俺は吹き出しそうになるのを堪え、窓の外の景色を眺める振りをして口元を隠した。
最寄り駅に着き、改札を出る。家まで、あと数分。研磨と二人、いつもの道を歩く。俺の家の隣が、研磨の家だ。つまり、このゲームは、研磨が家に入るまで続くことになる。どうやって、この状況を面白くしてやろうか。
「なあ、研磨。今日、うちでアップルパイ食ってかねぇ? ばあちゃんが美味そうなの買ってきたって言ってたぜ」
俺は態と大きな声で、研磨を誘った。背後で、名前が息を呑む気配がする。
「……え、でも、おれ、今日の分のクエストが……」
「いいじゃねぇか、偶には。じいちゃん達も喜ぶって」
「……んー、じゃあ、少しだけ」
よし、乗った。これで、名前の計画は大きく狂った筈だ。どうする、名前? 俺は口の端が上がるのを隠せない。
研磨の家の前を通り過ぎ、俺は自宅の玄関のドアに手を掛けた。さあ、ここからが第二ラウンドだ。研磨を家に上げて、俺は直ぐに郵便受けのチェックを忘れたフリをして、外に出よう。そこを、名前がどうするか。
「どうしよう……」
俺達が玄関に入ったのを確認し、角から出てきた名前が困惑したような声を上げるのが聞こえる。キャップの下で、彼女が不安気に唇を噛んでいるのが目に浮かぶようだ。
よし、今だ。
俺は音を立てずに玄関のドアを少しだけ開け、その隙間から彼女の背後へ回り込み、耳元でそっと囁いた。
「おーい、こんなとこで何してんの?」
「わぁっ!」
名前の肩が面白い程にビクンと跳ねた。勢いよく振り返った拍子にキャップがズレ、驚きに見開かれた瞳と目が合う。
その表情が余りにも素で、可愛くて。俺は、もう限界だった。
「ぶはっ! あはははは! お前さぁ……!」
堪え切れずに噴き出すと、俺は腹を抱えてその場にしゃがみ込んだ。涙が出る程に笑ったのは久し振りだ。
「て、鉄朗くん……? どうして……分かったの? 完璧だった筈なのに」
きょとんとした顔で、心底不思議そうに首を傾げる名前。その無自覚さが本当に、俺の心をどうしようもなく掻き乱す。
「完璧なワケねぇだろ! 校門出た時から丸分かりだよ!」
笑い涙を拭いながら立ち上がると、俺はまだ状況が飲み込めていない様子の彼女を腕の中に閉じ込めた。チャコールグレーのパーカー越しに、華奢な身体がすっぽりと収まる。
「地を這ってまで、俺のこと追い駆けてくんの、可愛過ぎ」
ぎゅっと抱き締めると、腕の中でぽつりと言った。
「……鉄朗くんの反応が、見たかっただけ」
「はっ、そうかい。で、俺の反応はどうだった?」
悪戯っぽく笑い掛けてやると、名前は俺の胸に顔を埋めたまま、満足気にこくりと頷いた。
「うん。とても面白かった。わたしの勝ちだね」
「はいはい、お前の勝ちでいいよ、もう……」
降参だ。こんな奇想天外な恋人には、到底敵わない。俺は彼女の柔らかな髪を優しく撫でた。
「次は、もっと上手くやるから」
「頼むから、もうやめてくれ。俺の心臓が保たない」
懇願する俺に、名前はくすくすと楽しそうに笑う。その笑顔が見られるなら、まあ、偶にはこんなスリリングな放課後も悪くないのかもしれない。
二人で手を繋ぎ、夕焼けに染まる道を歩く。隣で「今度、一緒に肉まんを食べようね」なんて言っている彼女を見ながら、俺は心の中で静かに誓う。
この掴みどころがなくて、最高に愛おしい恋人の為なら。
何度だって、地を這う彼女に追い駆けられてやろう、と。それもまた、悪くない日常だ。
「……なんだ、猫か」
俺はそう呟き、笑いを堪えるのに必死になりながら歩き出した。肩が震えるのを誤魔かす為に、態と大きく腕を振る。
いや、猫じゃねぇだろ。どう考えても。あんな覇気のない、か細い「にゃーん」が猫であって堪るか。
と言うか、そもそも気づいてないフリをするのだって、もう限界に近かった。
俺が彼女──苗字名前の珍妙な尾行に気づいたのは、校門を出て直ぐのことだ。なんか視線を感じるな、と思って目だけで確認したら、電信柱の影からキャップにパーカーのフードを被った不審人物がこっちを覗いている。一瞬、誰かのストーカーか? と身構えたが、その独特な気配と、隠し切れていない華奢なシルエットに見覚えがあり過ぎた。
……名前だ。
なんで? どうして? 何してんの、あいつ。
疑問符が頭の中を乱舞したが、次の瞬間、猛烈な面白さが込み上げてきた。隣を歩く研磨にバレないように口元を引き締め、俺は一つの結論に至る。
──乗ってやろう、この奇妙なゲームに。
「今日のリエーフ、最後の自主練で顔面レシーブ三回はしてたよな」
敢えて、少しだけ大きな声で研磨に話し掛ける。案の定、背後で微かな衣擦れの音がした。付いてきてる、付いてきてる。
コンビニに入った時も、お菓子コーナーの棚の影からこっちを凝視している名前を、俺は店内の防犯ミラー越しに確りと確認済みだ。あの真剣な眼差し。俺が肉まんを買うだけなのに、国家機密でも目撃したかのような集中力。
……可愛過ぎんだろ、俺の彼女。
普段はミステリアスで、何を考えているか分からない時もある。けれど、一度好奇心に火が点くと、こうして突拍子もないことを仕出かす。そんなところが、どうしようもなく愛おしい。
コンビニを出て、駅へ向かう。勿論、背後には『隠密』行動中の彼女。研磨はゲームに夢中で、周囲への関心はゼロだ。好都合過ぎる。
改札を抜け、ホームで電車を待つ間も、名前は柱の影からこちらを窺っている。電車に乗り込めば、律儀に隣の車両へ。連結部の窓から覗く、キャップのツバと真剣な眼差し。おいおい、そんなに見つめたらバレるっての。俺は吹き出しそうになるのを堪え、窓の外の景色を眺める振りをして口元を隠した。
最寄り駅に着き、改札を出る。家まで、あと数分。研磨と二人、いつもの道を歩く。俺の家の隣が、研磨の家だ。つまり、このゲームは、研磨が家に入るまで続くことになる。どうやって、この状況を面白くしてやろうか。
「なあ、研磨。今日、うちでアップルパイ食ってかねぇ? ばあちゃんが美味そうなの買ってきたって言ってたぜ」
俺は態と大きな声で、研磨を誘った。背後で、名前が息を呑む気配がする。
「……え、でも、おれ、今日の分のクエストが……」
「いいじゃねぇか、偶には。じいちゃん達も喜ぶって」
「……んー、じゃあ、少しだけ」
よし、乗った。これで、名前の計画は大きく狂った筈だ。どうする、名前? 俺は口の端が上がるのを隠せない。
研磨の家の前を通り過ぎ、俺は自宅の玄関のドアに手を掛けた。さあ、ここからが第二ラウンドだ。研磨を家に上げて、俺は直ぐに郵便受けのチェックを忘れたフリをして、外に出よう。そこを、名前がどうするか。
「どうしよう……」
俺達が玄関に入ったのを確認し、角から出てきた名前が困惑したような声を上げるのが聞こえる。キャップの下で、彼女が不安気に唇を噛んでいるのが目に浮かぶようだ。
よし、今だ。
俺は音を立てずに玄関のドアを少しだけ開け、その隙間から彼女の背後へ回り込み、耳元でそっと囁いた。
「おーい、こんなとこで何してんの?」
「わぁっ!」
名前の肩が面白い程にビクンと跳ねた。勢いよく振り返った拍子にキャップがズレ、驚きに見開かれた瞳と目が合う。
その表情が余りにも素で、可愛くて。俺は、もう限界だった。
「ぶはっ! あはははは! お前さぁ……!」
堪え切れずに噴き出すと、俺は腹を抱えてその場にしゃがみ込んだ。涙が出る程に笑ったのは久し振りだ。
「て、鉄朗くん……? どうして……分かったの? 完璧だった筈なのに」
きょとんとした顔で、心底不思議そうに首を傾げる名前。その無自覚さが本当に、俺の心をどうしようもなく掻き乱す。
「完璧なワケねぇだろ! 校門出た時から丸分かりだよ!」
笑い涙を拭いながら立ち上がると、俺はまだ状況が飲み込めていない様子の彼女を腕の中に閉じ込めた。チャコールグレーのパーカー越しに、華奢な身体がすっぽりと収まる。
「地を這ってまで、俺のこと追い駆けてくんの、可愛過ぎ」
ぎゅっと抱き締めると、腕の中でぽつりと言った。
「……鉄朗くんの反応が、見たかっただけ」
「はっ、そうかい。で、俺の反応はどうだった?」
悪戯っぽく笑い掛けてやると、名前は俺の胸に顔を埋めたまま、満足気にこくりと頷いた。
「うん。とても面白かった。わたしの勝ちだね」
「はいはい、お前の勝ちでいいよ、もう……」
降参だ。こんな奇想天外な恋人には、到底敵わない。俺は彼女の柔らかな髪を優しく撫でた。
「次は、もっと上手くやるから」
「頼むから、もうやめてくれ。俺の心臓が保たない」
懇願する俺に、名前はくすくすと楽しそうに笑う。その笑顔が見られるなら、まあ、偶にはこんなスリリングな放課後も悪くないのかもしれない。
二人で手を繋ぎ、夕焼けに染まる道を歩く。隣で「今度、一緒に肉まんを食べようね」なんて言っている彼女を見ながら、俺は心の中で静かに誓う。
この掴みどころがなくて、最高に愛おしい恋人の為なら。
何度だって、地を這う彼女に追い駆けられてやろう、と。それもまた、悪くない日常だ。