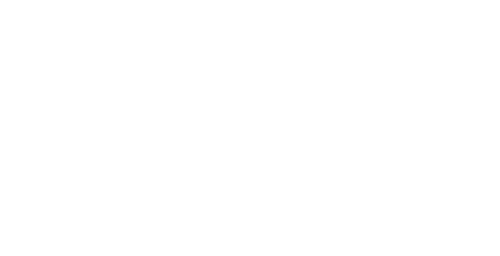彼女の静かな報復は、ラッキョウの瓶と嫉妬の余韻と共に、
俺の心をじわじわと支配した。
授業終了を告げるチャイムの音は、俺にとって一日の内で最も幸福な音の一つだ。気怠い身体を机に預けたまま、ゆっくりと顔を上げる。窓の外は、既にオレンジ色に染まり始めていた。今日の授業も殆ど意識の彼方にあったな、なんてぼんやり考えていると、ふと隣の席からの視線に気づいた。
「……なに」
俺の彼女、苗字名前は、夜の海の底を思わせるような深い瞳で、じっと俺を見つめていた。その表情からは何も読み取れない。いつものことではあるが、ここ数日、この無言の視線を浴びる頻度が格段に増えている気がする。
「英くん、顔に跡が付いているよ」
「あー……うん」
名前はそう言って、白く細い指を伸ばし、俺の頬に触れた。ひんやりとした指先が肌を撫でる。その仕草はひどく優雅で、貴重な美術品に触れるかのようだ。けれど、その瞳の奥に揺らめく光は、いつもの穏やかなそれとは少し違う種類のものだった。何かを値踏みするような、或いは何かを確かめるような、そんな光。
「名前……最近、なんか変じゃないか?」
「そう? わたしはいつも通りだよ」
彼女は小さく首を傾げ、ふわりと微笑む。その完璧な笑顔の前では、こちらの疑念など些細なことのように思えてしまう。結局、俺は「そっか」と短く返すことしかできなかった。これが、全ての始まりだった。彼女が仕掛けた、甘くて執拗な報復の序曲だったなんて、この時の俺は知る由もなかった。
 部活を終え、体育館の熱気と汗の匂いを背に帰路に就く。自販機で買ったスポーツドリンクを呷りながら、金田一の「今日の及川さん、サーブ練、えぐかったよな」なんていう、分かり切った感想を適当に聞き流していた時だった。
「あの、国見くん!」
背後から掛けられた、聞き慣れない女子の声。振り返ると、同じクラスの、確か……名前も曖昧な女子生徒が数人、頬を染めて立っていた。面倒臭い、というのが第一印象だ。
「次の小テストの範囲、ノート見せてもらえないかなって……」
「あー……」
俺は気のない返事をしながら、鞄からノートを取り出して渡す。彼女達の「ありがとう!」「国見くんって、意外と優しいんだね!」なんていう浮かれた声が、やけに耳障りだった。正直、一秒でも早く帰って寝たい。その一心で「別に。じゃあ」と素っ気なく背を向けた。
その時、校舎の影が一瞬、揺れた気がした。黒い、長い髪。見間違いか、と思った。名前はいつも、俺が終わるのを待たずに先に帰る。彼女は人混みが好きじゃないし、部活の喧騒も得意ではないからだ。だから、気のせいだろう。俺はそう結論づけて、金田一と共に駅へと向かった。この些細な油断が、後に自分の首を絞めることになるとも知らずに。
翌日から、名前の奇妙な"報復"は始まった。
昼休み、いつものように購買で買った塩キャラメルパンを齧ろうとした、その瞬間。どこからともなく現れた名前が、俺の手からパンをそっと抜き取った。
「英くん」
「……なに」
「糖分の過剰摂取は、午後のパフォーマンスを下げる原因になるそうだよ」
そう言って、名前が代わりに差し出したのは、小さなガラス瓶。中には、白く艶やかな塊が幾つか入っている。……らっきょう?
「……要らない」
「そう。残念だよ」
名前は心底無念そうな顔で小瓶を仕舞うと、俺から奪ったパンを半分に千切り、片方を「はい」と差し出した。
「半分なら、許してあげる」
「……どうも」
俺は釈然としないまま、それを受け取る。何故、俺の好物である塩キャラメルパンが、名前の嫌いなラッキョウとトレードされ掛けたのか。そして、何故、彼女に摂取量を管理されなければならないのか。謎は深まるばかりだった。
その日の放課後、部活へ向かう廊下で、まただ。名前が俺の腕に、自分の腕をすっと絡めてきた。普段、人前でこれ見よがしにスキンシップを取ってくることは滅多にない。どちらかと言えば、二人きりの空間で、甘えるように寄り添ってくるタイプだ。
「名前……?」
「行こう、英くん。部活に遅れてしまうよ」
彼女は俺の戸惑いなど意に介さず、ぴたりと身体を寄せたまま歩き出す。すれ違う生徒達の好奇の視線が痛い。特に女子からの視線が。まるで「この人は、わたしのものだから」と無言の牽制をしているかのような行動に、俺の頭の中はクエスチョンマークで埋め尽くされた。嬉しい、筈なのに、どこか落ち着かない。これは一体、誰へのアピールなんだ?
極め付けは、金田一との関係だった。
「金田一くん」
「へっ!? あ、はい! 苗字さん!」
部活の休憩中、名前がマネージャーでもないのに、当たり前のように体育館の入り口に現れた。その手には、スポーツドリンクのボトルが二本。そして、彼女が話し掛けたのは、俺ではなく金田一だった。
「いつも、英くんがお世話になっているね。これ、良かったら」
「え、あ、あざっす……!」
金田一は普段、女子と話す機会が少ない所為か、名前を前にしてガチガチに緊張している。ラッキョウ頭が茹で蛸みたいに赤い。面白い光景ではあるが、俺の心は全く面白くなかった。
「英くんのこと、一番よく知っているのは金田一くんでしょう? 今度の練習試合、わたしも応援に行こうと思っているのだけれど、何か気を付けることはあるかな」
「え、えっと……国見は、その……後半に強いんで、最初、静かでも心配しなくて大丈夫っす!」
「ふぅん、後半にね。ありがとう、参考にするよ」
俺をダシにして、金田一と親しげに話す名前。俺は壁に寄り掛かったまま、その光景をただ黙って見つめていた。胸の奥が、チリチリと焦げるような感覚。なんだ、これ。嫉妬、か。俺が、金田一に? 違う。名前のあの態度にだ。俺という存在を直ぐ隣に置きながら、態と他の男と親密な雰囲気を作る、その意図の読めなさに、どうしようもなく苛立っていた。
部活を終え、体育館の熱気と汗の匂いを背に帰路に就く。自販機で買ったスポーツドリンクを呷りながら、金田一の「今日の及川さん、サーブ練、えぐかったよな」なんていう、分かり切った感想を適当に聞き流していた時だった。
「あの、国見くん!」
背後から掛けられた、聞き慣れない女子の声。振り返ると、同じクラスの、確か……名前も曖昧な女子生徒が数人、頬を染めて立っていた。面倒臭い、というのが第一印象だ。
「次の小テストの範囲、ノート見せてもらえないかなって……」
「あー……」
俺は気のない返事をしながら、鞄からノートを取り出して渡す。彼女達の「ありがとう!」「国見くんって、意外と優しいんだね!」なんていう浮かれた声が、やけに耳障りだった。正直、一秒でも早く帰って寝たい。その一心で「別に。じゃあ」と素っ気なく背を向けた。
その時、校舎の影が一瞬、揺れた気がした。黒い、長い髪。見間違いか、と思った。名前はいつも、俺が終わるのを待たずに先に帰る。彼女は人混みが好きじゃないし、部活の喧騒も得意ではないからだ。だから、気のせいだろう。俺はそう結論づけて、金田一と共に駅へと向かった。この些細な油断が、後に自分の首を絞めることになるとも知らずに。
翌日から、名前の奇妙な"報復"は始まった。
昼休み、いつものように購買で買った塩キャラメルパンを齧ろうとした、その瞬間。どこからともなく現れた名前が、俺の手からパンをそっと抜き取った。
「英くん」
「……なに」
「糖分の過剰摂取は、午後のパフォーマンスを下げる原因になるそうだよ」
そう言って、名前が代わりに差し出したのは、小さなガラス瓶。中には、白く艶やかな塊が幾つか入っている。……らっきょう?
「……要らない」
「そう。残念だよ」
名前は心底無念そうな顔で小瓶を仕舞うと、俺から奪ったパンを半分に千切り、片方を「はい」と差し出した。
「半分なら、許してあげる」
「……どうも」
俺は釈然としないまま、それを受け取る。何故、俺の好物である塩キャラメルパンが、名前の嫌いなラッキョウとトレードされ掛けたのか。そして、何故、彼女に摂取量を管理されなければならないのか。謎は深まるばかりだった。
その日の放課後、部活へ向かう廊下で、まただ。名前が俺の腕に、自分の腕をすっと絡めてきた。普段、人前でこれ見よがしにスキンシップを取ってくることは滅多にない。どちらかと言えば、二人きりの空間で、甘えるように寄り添ってくるタイプだ。
「名前……?」
「行こう、英くん。部活に遅れてしまうよ」
彼女は俺の戸惑いなど意に介さず、ぴたりと身体を寄せたまま歩き出す。すれ違う生徒達の好奇の視線が痛い。特に女子からの視線が。まるで「この人は、わたしのものだから」と無言の牽制をしているかのような行動に、俺の頭の中はクエスチョンマークで埋め尽くされた。嬉しい、筈なのに、どこか落ち着かない。これは一体、誰へのアピールなんだ?
極め付けは、金田一との関係だった。
「金田一くん」
「へっ!? あ、はい! 苗字さん!」
部活の休憩中、名前がマネージャーでもないのに、当たり前のように体育館の入り口に現れた。その手には、スポーツドリンクのボトルが二本。そして、彼女が話し掛けたのは、俺ではなく金田一だった。
「いつも、英くんがお世話になっているね。これ、良かったら」
「え、あ、あざっす……!」
金田一は普段、女子と話す機会が少ない所為か、名前を前にしてガチガチに緊張している。ラッキョウ頭が茹で蛸みたいに赤い。面白い光景ではあるが、俺の心は全く面白くなかった。
「英くんのこと、一番よく知っているのは金田一くんでしょう? 今度の練習試合、わたしも応援に行こうと思っているのだけれど、何か気を付けることはあるかな」
「え、えっと……国見は、その……後半に強いんで、最初、静かでも心配しなくて大丈夫っす!」
「ふぅん、後半にね。ありがとう、参考にするよ」
俺をダシにして、金田一と親しげに話す名前。俺は壁に寄り掛かったまま、その光景をただ黙って見つめていた。胸の奥が、チリチリと焦げるような感覚。なんだ、これ。嫉妬、か。俺が、金田一に? 違う。名前のあの態度にだ。俺という存在を直ぐ隣に置きながら、態と他の男と親密な雰囲気を作る、その意図の読めなさに、どうしようもなく苛立っていた。
 そして、部活がオフの月曜日。俺達は名前の父が用意したという、だだっ広いマンションの一室で、ソファに並んで座っていた。名前が選んだ、やたらと芸術性の高いフランス映画がスクリーンに映し出されているが、内容は全く頭に入ってこない。
俺の思考は、ここ数日の彼女の不可解な行動で飽和状態だった。塩キャラメル制限、過剰なスキンシップ、そして、金田一への接近。一つひとつは些細なことかもしれない。だが、それらが連続して起こることで、俺の心は確実に掻き乱されていた。
沈黙に耐え切れず、俺はリモコンで映画を止めた。
「……名前」
「……なにかな、英くん。今、良いところだったのだけれど」
スクリーンから視線を外さずに、彼女が静かに言う。その横顔は相変わらず美しく、そして冷たい。
「お前、最近、マジでどうしたんだよ。俺、何かした?」
もう我慢の限界だった。誤魔化し続ける彼女に、真正面から問い質すしかない。すると、名前は漸くゆっくりとこちらを向いた。その夜色の瞳が、俺を真っ直ぐに捉える。
「何かした、という自覚がないことが、問題なんだよ」
「……は?」
「誤魔化し続けたでしょう、英くん」
その言葉に、どきりとする。誤魔化した? 俺が? 一体、何を。
俺が答えに窮していると、彼女は静かに続けた。
「先週の金曜日。部活の帰り、校門の前で、クラスの女子と話していたね」
「……あ」
脳裏に、あの日の光景が蘇る。ノートを貸した、ただそれだけのこと。だが、確かに、俺はそれを見ていたかもしれない名前の気配を「気のせいだ」と片付けた。そして、彼女から「最近、何か変わったことはない?」と探るように聞かれた時も、「別に、何もない」と答えてしまった。だって、本当に、俺にとっては「何もない」に等しい出来事だったから。
「見て、たのか」
「うん。見ていたよ。英くんが、わたしには見せないような、少し困ったような、でも、面倒見のいい先輩みたいな顔で、笑っていた」
「笑ってねえよ。て言うか、あれはただ……」
「ただ、何? 英くんにとっては、取るに足らないことだったのかもしれない。だけどね」
名前はすっと立ち上がると、俺の目の前に来て、その場にしゃがみ込んだ。ソファに座る俺と、床に膝を突く彼女の視線が、同じ高さで交差する。
「わたしにとっては、取るに足らなくなんかない。英くんの知らない一面を、他の誰かが見ている。その事実を、英くんがわたしに隠そうとした。それが、わたしはとても嫌だった」
静かな、確固たる意志を宿した声。その瞳の奥には、今まで見たことのないような剥き出しの独占欲と、ほんの少しの不安が揺らめいていた。ああ、そうか。こいつは怒っていたのか。嫉妬して、不安になって、その気持ちをどう処理していいか分からなくて、あんな奇妙な行動に出ていたのか。
「だから、報復することにしたんだ」
「報復……」
「英くんが、わたしの心を乱したように、わたしも英くんの心を、少しだけ乱してあげようって。英くんが好きな塩キャラメルを制限して、わたしの存在を他の人に見せ付けて、英くんが一番心を許しているであろう金田一くんに近づいてみた。……どうだった? 少しは、わたしの気持ち、分かったかな」
悪戯っぽく、しかし、真剣な眼差しで問い掛ける名前。その言葉の全てが、すとんと胸に落ちてきた。なんて遠回しで、なんて面倒臭くて、そして、なんて愛おしい報復だろうか。
俺は思わず、吹き出してしまった。
「ははっ……なんだよ、それ……」
呆れと、安堵と、どうしようもない愛しさがごちゃ混ぜになって、笑いが止まらない。
「お前、ほんと……最高だな」
「褒め言葉として受け取っておくよ」
俺は笑うのをやめると、名前の華奢な身体をぐいと引き寄せ、腕の中に閉じ込めた。ソファから落ちそうになるのも構わずに、強く、強く抱き締める。
「分かった。俺が悪かった。もう隠さない。どんな些細なことでも、全部言う。女子に道聞かれたとか、猫に懐かれたとか、全部」
「ふふ、本当?」
「本当。だから、もう金田一に近づくな」
「それは、英くん次第かな」
腕の中で、名前がくすくすと笑う。その声が心地良い。
「報復は、まだ終わっていないからね」
「……上等だろ」
俺はそう囁くと、彼女の薄桃色の唇を塞いだ。窓の外では、いつの間にか静かな雨が降り始めている。部屋の中の暖かさと、腕の中にある確かな体温だけが、やけにリアルだった。
誤魔化し続けた報復は、どうやらまだ始まったばかりらしい。まあ、こんな甘い報復なら、幾らでも受けて立つけど。
そして、部活がオフの月曜日。俺達は名前の父が用意したという、だだっ広いマンションの一室で、ソファに並んで座っていた。名前が選んだ、やたらと芸術性の高いフランス映画がスクリーンに映し出されているが、内容は全く頭に入ってこない。
俺の思考は、ここ数日の彼女の不可解な行動で飽和状態だった。塩キャラメル制限、過剰なスキンシップ、そして、金田一への接近。一つひとつは些細なことかもしれない。だが、それらが連続して起こることで、俺の心は確実に掻き乱されていた。
沈黙に耐え切れず、俺はリモコンで映画を止めた。
「……名前」
「……なにかな、英くん。今、良いところだったのだけれど」
スクリーンから視線を外さずに、彼女が静かに言う。その横顔は相変わらず美しく、そして冷たい。
「お前、最近、マジでどうしたんだよ。俺、何かした?」
もう我慢の限界だった。誤魔化し続ける彼女に、真正面から問い質すしかない。すると、名前は漸くゆっくりとこちらを向いた。その夜色の瞳が、俺を真っ直ぐに捉える。
「何かした、という自覚がないことが、問題なんだよ」
「……は?」
「誤魔化し続けたでしょう、英くん」
その言葉に、どきりとする。誤魔化した? 俺が? 一体、何を。
俺が答えに窮していると、彼女は静かに続けた。
「先週の金曜日。部活の帰り、校門の前で、クラスの女子と話していたね」
「……あ」
脳裏に、あの日の光景が蘇る。ノートを貸した、ただそれだけのこと。だが、確かに、俺はそれを見ていたかもしれない名前の気配を「気のせいだ」と片付けた。そして、彼女から「最近、何か変わったことはない?」と探るように聞かれた時も、「別に、何もない」と答えてしまった。だって、本当に、俺にとっては「何もない」に等しい出来事だったから。
「見て、たのか」
「うん。見ていたよ。英くんが、わたしには見せないような、少し困ったような、でも、面倒見のいい先輩みたいな顔で、笑っていた」
「笑ってねえよ。て言うか、あれはただ……」
「ただ、何? 英くんにとっては、取るに足らないことだったのかもしれない。だけどね」
名前はすっと立ち上がると、俺の目の前に来て、その場にしゃがみ込んだ。ソファに座る俺と、床に膝を突く彼女の視線が、同じ高さで交差する。
「わたしにとっては、取るに足らなくなんかない。英くんの知らない一面を、他の誰かが見ている。その事実を、英くんがわたしに隠そうとした。それが、わたしはとても嫌だった」
静かな、確固たる意志を宿した声。その瞳の奥には、今まで見たことのないような剥き出しの独占欲と、ほんの少しの不安が揺らめいていた。ああ、そうか。こいつは怒っていたのか。嫉妬して、不安になって、その気持ちをどう処理していいか分からなくて、あんな奇妙な行動に出ていたのか。
「だから、報復することにしたんだ」
「報復……」
「英くんが、わたしの心を乱したように、わたしも英くんの心を、少しだけ乱してあげようって。英くんが好きな塩キャラメルを制限して、わたしの存在を他の人に見せ付けて、英くんが一番心を許しているであろう金田一くんに近づいてみた。……どうだった? 少しは、わたしの気持ち、分かったかな」
悪戯っぽく、しかし、真剣な眼差しで問い掛ける名前。その言葉の全てが、すとんと胸に落ちてきた。なんて遠回しで、なんて面倒臭くて、そして、なんて愛おしい報復だろうか。
俺は思わず、吹き出してしまった。
「ははっ……なんだよ、それ……」
呆れと、安堵と、どうしようもない愛しさがごちゃ混ぜになって、笑いが止まらない。
「お前、ほんと……最高だな」
「褒め言葉として受け取っておくよ」
俺は笑うのをやめると、名前の華奢な身体をぐいと引き寄せ、腕の中に閉じ込めた。ソファから落ちそうになるのも構わずに、強く、強く抱き締める。
「分かった。俺が悪かった。もう隠さない。どんな些細なことでも、全部言う。女子に道聞かれたとか、猫に懐かれたとか、全部」
「ふふ、本当?」
「本当。だから、もう金田一に近づくな」
「それは、英くん次第かな」
腕の中で、名前がくすくすと笑う。その声が心地良い。
「報復は、まだ終わっていないからね」
「……上等だろ」
俺はそう囁くと、彼女の薄桃色の唇を塞いだ。窓の外では、いつの間にか静かな雨が降り始めている。部屋の中の暖かさと、腕の中にある確かな体温だけが、やけにリアルだった。
誤魔化し続けた報復は、どうやらまだ始まったばかりらしい。まあ、こんな甘い報復なら、幾らでも受けて立つけど。