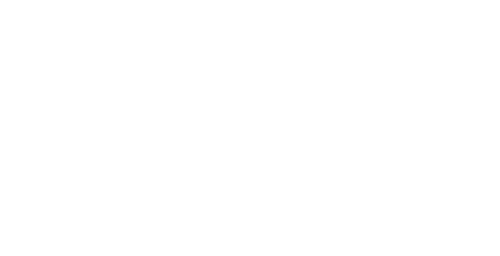- 月曜の宝石 -
月曜日の空気は、週末の喧騒が残した微熱と、これから始まる一週間の気怠さを混ぜ合わせたような、独特の匂いがする。部活がオフの英くんと並んで歩く通学路は、少しだけ世界の彩度が高く見えるから不思議だ。私の左側、半歩先を行く彼の長い影が、西日に焼かれたアスファルトの上で、ゆらゆらと揺れている。
「……あ」
思わず、小さな声が漏れた。視線の先、電信柱の根元に蹲る黒いビニール袋。どうやら街の掃除屋である烏の鋭い嘴に突かれたらしく、無惨に引き裂かれた穴から、幾つかの中身が路上に零れ落ちていた。
「どうしたんだよ、名前」
立ち止まった私を、英くんが眠たげな眼で振り返る。彼の声音は、夏の終わりの風みたいに一寸だけ乾いていて、心地良い。
「見て、英くん。宝石が落ちているよ」
私が指差した先にあるのは、恐らく誰かが捨てたであろうギフト用のラッピングリボンや、プラスチックのビーズ、銀色の包装紙の切れ端なんかだ。けれど、傾き掛けた太陽の光を乱反射するそれらは、打ち捨てられた宝箱から零れ落ちた、名もなき宝石のようにきらきらと輝いていた。
「……は? 宝石?」
英くんは心底不思議そうな表情で、わたしの指し示すガラクタと、わたしの顔を交互に見比べた。彼の大きな双眸に「こいつは何を言ってるんだ」と云う疑問が書いてある。うん、知っている。私が些か、他の人と違うものを見ていることは。
「うん。ほら、あそこの青いビーズなんて、まるでサファイアみたい。こっちの丸いのは、きっと持ち主を失くした真珠だね。可哀想に」
「……お前の言う『可哀想』は、なんか独特だよな」
呆れたような、でも、どこか面白がっている声色で、英くんが呟く。彼は『可哀想』と云う言葉が嫌いだと、いつか話していた。けれど、私が使うその言葉は、癪に障らないらしい。この事実が、胸の奥をそっと温める。
「そうかな。……でも、誰かにとってのゴミは、他の誰かにとっては、宝物になることもある。そう云うことだよ」
「ふーん。よく分かんないけど」
そう言う彼の隣に、わたしは歩みを戻した。英くんの大きな手が、わたしの手を自然に捕らえる。骨張っていて、少し冷たい、大好きな手。わたし達は再び歩き出す。塵袋から零れた宝石達は、あっと言う間に背後へと遠ざかった。
我が家である『雨滴文庫』の古びた扉を開けると、インクと古紙、珈琲豆の焙煎された香りが混じり合う、懐かしい匂いに包まれた空間が、わたし達を迎えた。今日は雨が降っていないから、雨天限定のブックカフェは静かな眠りに就いている。マスターの祖父はきっと、奥の書斎で新しいメニューでも考えていることだろう。『失恋の味を再現したブルーベリータルト』とか、『読後感すっきりミントソーダ』とか、そう云う名前の。
二階。リビングのソファに深く身を沈めた英くんは、猫みたいに一つ伸びをすると、「なぁ、名前。塩キャラメル、ない?」と徐に強請った。ここに来る目的だったみたいに。
「うん。ちょっと待っていて」
キッチンへ向かいながら、わたしは小さく笑った。冷蔵庫から取り出した塩キャラメルの箱と、冷たい麦茶。琥珀色の一粒を口に放り込んでから、小箱と二つのグラスをトレーに載せて居間へ戻ると、英くんはスケッチブックを手にしていた。ソファの前に置かれたローテーブル上に、無造作に放り出していたものだ。
「わっ、英くん、それは……!」
心臓が、きゅっと音を立てて縮こまる。わたしの慌てた声に、英くんはぱっと顔を上げた。表情は悪戯が見つかった子供のようで、どこかバツが悪そうだ。
「……別に、見てない」
「本当? 耳が赤いけれど」
「気の所為だろ」
ぷい、とそっぽを向く彼の耳は、綺麗な夕焼けみたいに染まっていた。嘘を吐くのが、下手な男の子。不器用さが堪らなく愛おしい。
わたしはトレーをローテーブルに置き、英くんの隣にそっと腰を下ろした。スケッチブックは慌てて閉じられた所為で、少しだけ歪んでいる。取り戻した頁の隙間から、鉛筆で描かれた背番号13番のユニフォームの裾が、ほんの一寸だけ覗いていた。
矢張り、知られてしまったのかもしれない。
帳面の殆どが、英くんで埋め尽くされていることを。
練習中の真剣な横顔。休憩の合間に見せる、一瞬の気の抜けた表情。わたしだけに向けてくれる、微かな笑み。眠そうな顔。怒った顔。呆れた顔。
道端に転がったガラクタを拾い集めるみたいに、こっそりと蒐集してきた、英くんの欠片達。
誰も気に留めないような、彼の一コマずつ。
わたしにとっては、それこそが世界で一番輝いて映る、たった一つの宝石だった。
「……線の、練習をしていただけだよ」
声が震える。自分でも情けない程、分かり易い言い訳だ。
英くんは黙って、只、わたしをじっと見つめていた。眠たげな双眸の奥に宿る光が、いつもよりずっと熱を帯びていることに、わたしは未だ気づけなかった。
 ヤバい。見てしまった。
名前がキッチンに立った、ほんの数分の出来心。普段、彼女が大切そうに抱えているスケッチブックに、一体、何が描かれているんだろう、なんて。軽い気持ちで開いたページに、俺は完全に動きを止めてしまった。
そこに居たのは、俺だった。
俺しか、居なかった。
練習着の俺。制服の俺。ジャージの俺。眠そうな俺。金田一と話してる俺。塩キャラメルを食ってる俺。
どれもが驚く程に精密な線で、魂を吹き込まれたかのように生き生きと描写されていた。俺、こんな顔で笑うのか。こんな目でボールを追ってるのか。俺自身でさえ認識してない俺が、沢山居た。
心臓が煩い位に鳴っている。
自分の知らないところで、こんなにも熱の籠もった視線に貫かれていたなんて。
描かれた俺の隣に、描かれてない名前が立っている気がした。
「私のことは、誰もちゃんと見てない」なんて、名前はよく言う。冗談じゃない。世界中の誰よりも、俺が一番、お前のことを見てるのに。
名前が戻ってきた気配を感じ、俺は反射的にスケッチブックを閉じた。マズい、見られた。耳に血が集まる。名前の「耳が赤い」と云う指摘に、心音が更に跳ねた。鋭いんだよ、こう云うとこだけ。
「……線の、練習をしていただけだよ」
震える声で、しどろもどろに言い訳をする名前。顔面は真っ赤で、潤んだ瞳が不安そうに揺れている。ああ、もう。なんで、こんなに可愛いんだよ。
庇護欲とか、そう云う生易しい感情じゃない。もっとどす黒くて、独占欲に満ちた激情が腹の底からせり上がる。
この視線を、他の誰にも向けさせたくない。
こいつが描くものは、全部、俺だけでいい。
俺は黙って、名前の手からスケッチブックを取り上げた。びくりと動揺する、華奢な肩。もう一度、ページを開く。
「……見てた。名前が、俺のことばっか描いてるヤツ」
観念して、白状する。名前は息を呑んで、小さな塊みたいに固まってしまった。
俺は帰り道の光景を思い出す。破れたゴミ袋と、きらきら光るガラクタ。
「さっきのゴミ袋。あれ、宝石みたいだって言ってただろ」
「……え?」
「俺にとっての宝石は、多分、これ」
そう告げて、俺はスケッチブックの紙面を指でなぞった。描かれているのは、練習で疲れ切って、タオルを頭から被っている、我ながら締まらない顔の俺だ。
「誰も見てないような、俺のどうでもいい顔。練習で疲れてるとことか、授業中、本気で眠いだけのとことか。……そう云う、そこら辺に転がってるガラクタみたいな瞬間を、名前は全部拾って、宝物みたいに描いてくれる」
名前の大きな瞳から、ぽろり、と雫が零れた。驚きと、安堵と、どうしようもない程の喜びに彩られた、美しい涙だった。
自分の観察眼が、只の趣味や自己防衛なんかじゃなく、俺にとっての宝物なんだと伝わったらしい。
「英、くん……」
「……だから、他の奴には見せないで」
気づけば、名前の華奢な身体を抱き締めていた。甘い花の香りと、鉛筆芯の匂いが混じって、くらりとする。腕の中の熱が、俺の理性をじわじわと溶かし始める。
こいつの描く俺も、こいつが見ている俺も、全部、俺達だけのものだ。常に全力じゃなくたって、燃費良くしか動けなくたって、名前が見つけてくれるなら、それでいい。
「名前の見てる俺が、本当の俺でいいよ」
少し顔を離してから、涙で濡れた頬にキスをする。そのまま唇を重ねると、俺が強請った塩キャラメルの、甘くてしょっぱい味がした。
窓の外は、もうすっかり夕暮れの色に染まっていた。ブックカフェの静かな空間に射し込むオレンジの光が、名前に残る落涙の跡をきらきらと照らし出す。まるで、本物の宝玉みたいに綺麗だった。
いや、違う。
彼女自身が、日常って云う退屈で有り触れたゴミ袋から零れ落ちた、たった一つの奇跡みたいな宝石なんだ。
「……名前」
唇を離し、強く抱き締め直しながら、耳元で囁く。
「今夜、泊まっていってもいい?」
腕の中の宝石が、小さく頷いた。その肯定だけで、俺の世界はどうしようもなく満たされる。月曜の夜は、まだ始まったばかりだ。
ヤバい。見てしまった。
名前がキッチンに立った、ほんの数分の出来心。普段、彼女が大切そうに抱えているスケッチブックに、一体、何が描かれているんだろう、なんて。軽い気持ちで開いたページに、俺は完全に動きを止めてしまった。
そこに居たのは、俺だった。
俺しか、居なかった。
練習着の俺。制服の俺。ジャージの俺。眠そうな俺。金田一と話してる俺。塩キャラメルを食ってる俺。
どれもが驚く程に精密な線で、魂を吹き込まれたかのように生き生きと描写されていた。俺、こんな顔で笑うのか。こんな目でボールを追ってるのか。俺自身でさえ認識してない俺が、沢山居た。
心臓が煩い位に鳴っている。
自分の知らないところで、こんなにも熱の籠もった視線に貫かれていたなんて。
描かれた俺の隣に、描かれてない名前が立っている気がした。
「私のことは、誰もちゃんと見てない」なんて、名前はよく言う。冗談じゃない。世界中の誰よりも、俺が一番、お前のことを見てるのに。
名前が戻ってきた気配を感じ、俺は反射的にスケッチブックを閉じた。マズい、見られた。耳に血が集まる。名前の「耳が赤い」と云う指摘に、心音が更に跳ねた。鋭いんだよ、こう云うとこだけ。
「……線の、練習をしていただけだよ」
震える声で、しどろもどろに言い訳をする名前。顔面は真っ赤で、潤んだ瞳が不安そうに揺れている。ああ、もう。なんで、こんなに可愛いんだよ。
庇護欲とか、そう云う生易しい感情じゃない。もっとどす黒くて、独占欲に満ちた激情が腹の底からせり上がる。
この視線を、他の誰にも向けさせたくない。
こいつが描くものは、全部、俺だけでいい。
俺は黙って、名前の手からスケッチブックを取り上げた。びくりと動揺する、華奢な肩。もう一度、ページを開く。
「……見てた。名前が、俺のことばっか描いてるヤツ」
観念して、白状する。名前は息を呑んで、小さな塊みたいに固まってしまった。
俺は帰り道の光景を思い出す。破れたゴミ袋と、きらきら光るガラクタ。
「さっきのゴミ袋。あれ、宝石みたいだって言ってただろ」
「……え?」
「俺にとっての宝石は、多分、これ」
そう告げて、俺はスケッチブックの紙面を指でなぞった。描かれているのは、練習で疲れ切って、タオルを頭から被っている、我ながら締まらない顔の俺だ。
「誰も見てないような、俺のどうでもいい顔。練習で疲れてるとことか、授業中、本気で眠いだけのとことか。……そう云う、そこら辺に転がってるガラクタみたいな瞬間を、名前は全部拾って、宝物みたいに描いてくれる」
名前の大きな瞳から、ぽろり、と雫が零れた。驚きと、安堵と、どうしようもない程の喜びに彩られた、美しい涙だった。
自分の観察眼が、只の趣味や自己防衛なんかじゃなく、俺にとっての宝物なんだと伝わったらしい。
「英、くん……」
「……だから、他の奴には見せないで」
気づけば、名前の華奢な身体を抱き締めていた。甘い花の香りと、鉛筆芯の匂いが混じって、くらりとする。腕の中の熱が、俺の理性をじわじわと溶かし始める。
こいつの描く俺も、こいつが見ている俺も、全部、俺達だけのものだ。常に全力じゃなくたって、燃費良くしか動けなくたって、名前が見つけてくれるなら、それでいい。
「名前の見てる俺が、本当の俺でいいよ」
少し顔を離してから、涙で濡れた頬にキスをする。そのまま唇を重ねると、俺が強請った塩キャラメルの、甘くてしょっぱい味がした。
窓の外は、もうすっかり夕暮れの色に染まっていた。ブックカフェの静かな空間に射し込むオレンジの光が、名前に残る落涙の跡をきらきらと照らし出す。まるで、本物の宝玉みたいに綺麗だった。
いや、違う。
彼女自身が、日常って云う退屈で有り触れたゴミ袋から零れ落ちた、たった一つの奇跡みたいな宝石なんだ。
「……名前」
唇を離し、強く抱き締め直しながら、耳元で囁く。
「今夜、泊まっていってもいい?」
腕の中の宝石が、小さく頷いた。その肯定だけで、俺の世界はどうしようもなく満たされる。月曜の夜は、まだ始まったばかりだ。