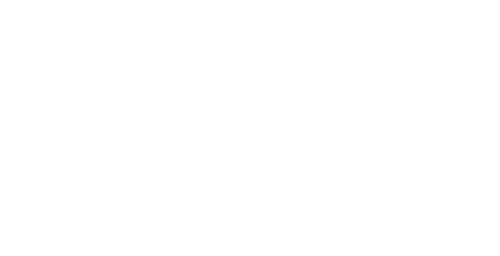もしも最後の瞬間が来た時、隣にきみが居れば、
それでいいと思えた。
わたしの恋人、孤爪研磨は、言葉の代わりに沈黙を纏うことが多い。
しなやかな三毛猫を思わせる静けさで、ふとした瞬間に、まるでゲームという異空間に精神ごと潜り込むように、こちらの声が届かなくなることがある。けれど、彼は思考を止めているわけではない。寧ろ逆だ。彼の沈黙は、言葉にならない無数の感情や思考で満たされた深い湖のようで、その水面下では誰よりも多くのものが渦巻いている。ただ、その豊穣な内面を縁取る言葉を見つけるのが、彼は人一倍苦手なだけ。いつも、あと一歩というところで、唇を引き結んでしまうのだ。
わたしは彼のそんなところが、堪らなく愛おしいのだと思う。
だから、今日も研磨が何かを言い掛けて、それを微かな喉の動きと共に奥へと押し込めた気配を、わたしは見逃さなかった。夕食の支度をするわたしの背後、リビングのソファに深く沈む彼は、スマートフォンに視線を落としている。けれど、その指先は画面をなぞると言うよりは所在なげに彷徨い、猫のように大きな瞳は、どこか遠い一点を見つめて虚空を彷徨っているのが、キッチンの磨かれた調理台に映る姿からでも見て取れた。
「……研磨」
呼び掛けると、彼の指先がぴくりと微かに震える。静寂を破る小石が水面に投げ込まれたように。
「何か、話したいことがあるの?」
一瞬の沈黙。それは、研磨が言葉を探す為の、或いは言葉にすることを躊躇う為の時間。やがて重たい硝子戸を開けるような緩慢さで、彼はこちらに視線を寄越した。その表情は「……おれのこと、また名前にバレてる」とでも言いたげで、少しだけ困ったような、それでいてどこか安堵したような、複雑な色を浮かべていた。
「……名前って、死んでも、どこにも行かない感じがする」
その言葉は何の脈絡もなく、静寂の中にぽとりと落とされた。わたしは手にしていたお玉を、カチャンと音を立ててコンロの脇に置き、ゆっくりと彼の方へ振り返る。夕暮れのオレンジ色の光が、研磨の色素の薄い髪を透かして、部屋に幻想的な陰影を落としていた。
「死ぬ予定は、今のところないけれど……それはつまり、どういう意味?」
研磨は唇の端をほんの少しだけ持ち上げた。けれど、それは微笑みとは呼べない、もっと曖昧で切ない何かだった。
「遺灰とか、残らなさそうってこと」
わたしは小さく首を傾げる。研磨の言葉は時折、迷路のように入り組んでいて、その真意に辿り着くには、慎重な道筋を辿らなくてはならない。
「それは、風に吹かれて跡形もなく消えてしまいそう、という意味? それとも、誰かに吸い込まれてしまいそう、という意味?」
後者の言葉を口にした瞬間、研磨の猫のような瞳が、ほんの僅かに見開かれた。心の奥底に隠していた秘密の扉を、わたしが偶然にも見つけてしまったかのように。
「……ならば遺灰を吸い込み、一つになろうと……とか」
研磨の声は囁くように掠れていた。
「それ、何かのゲームの台詞?」
「ううん……クロが、昨日言ってた。ちょっと厨二っぽいけど」
「良いと思う」
わたしは即座に答えた。研磨が黒尾さんの言葉を借りてまで、こんなにも突飛で、けれど切実な感情を伝えようとしてくれている。その不器用な真摯さが堪らなく愛おしい。普段、感情を表に出すことの少ない彼が、こんな台詞を覚えて口にするなんて。その意外性に、そしてその奥に隠された純粋さに、冷え性なわたしの指先まで、じんわりと熱が伝わるような、そんな温かさが胸に広がった。
「遺灰を吸い込むって……物凄く過激で、でも、とても純粋」
「うん」
研磨は小さく頷く。
「つまり、一緒になりたいってことでしょう?」
研磨は少しだけ目を伏せ、再び頷いた。長い睫毛が、彼の白い頬に幽かな影を落とす。
「ずっと、名前の傍に居たいって……考えた時に、一番強い方法が、それだった」
その言葉の重みに、わたしは息を詰める。わたしは静かに歩み寄り、彼の隣にそっと腰を下ろした。ソファが微かに軋み、研磨は一瞬だけ身を引いたけれど、すぐにわたしの肩にこてんと頭を預けた。彼の体温は、いつも少しだけ低い。それが、わたしには心地よかった。時として熱を持ち過ぎたわたしを、彼が穏やかに鎮めてくれるようで。
「研磨は、どんな風に死ぬと思う?」
静かな声で尋ねてみる。
「……ゲームしながら、かな」
研磨は少しも迷わず答えた。らしい答えに、思わず笑みが零れる。
「じゃあ、わたしは?」
「……おれの隣に居て」
「じゃあ、そうする」
静まり返った部屋に、わたし達の吐息が重なり合う微かな音だけが漂う。いつの間にか消えていたテレビの画面は、ただの黒い鏡となってわたし達を映し出し、天井のダウンライトが呼吸をするように、ゆっくりと明るさを変えていく。その光が、彼のプリン色の髪を柔らかく照らしていた。
「……研磨、わたしね」
「うん」
言葉が喉の奥でつかえる。こんなにも伝えたい想いがあるのに、それを的確に表す言葉が見つからない。
研磨は辛抱強く、わたしの次の言葉を待ってくれている。その静かな眼差しが、わたしに勇気をくれる。
「研磨のことが、初めての好きって気持ちで、胸がいっぱい」
彼は少し目を丸くした後、ふい、と視線を逸らした。白い首筋がほんのりと赤く染まっているのが見えて、愛しさが込み上げる。
「おれも……その、初めてで……名前と話す度に、心がドキドキする」
「思春期特有の?」
わたしは少し揶揄うように言った。
「……うん。名前の所為」
その言葉に、わたしはそっと研磨の頬に手を伸ばし、親指で優しく撫でた。きめ細やかな肌は陶器のように滑らかだ。
「ならば遺灰を吸い込み一つになろうと」
今度はわたしが研磨の言葉を繰り返す。
「うん……吸って」
「吸っていいの?」
「……吸って」
彼は冗談めかして言ったのかもしれない。けれど、わたしは本気だった。恋というものは、肉体という境界線をもどかしく感じさせ、その人の記憶ごと、魂ごと、全てを飲み込んでしまいたくなるような、そういう激しい渇望を伴うものだと、わたしは思っている。
唇を重ねる度に、研磨を構成する全てが境界線を溶かして、わたしの中に流れ込んでくるような錯覚を覚える。彼の低く掠れた声の響き。わたしよりも少しだけ低い、けれど確かな温もりを宿す体温。微かに甘いような、それでいてどこか切ない彼の息の味。そして、わたしに触れる指先の、隠し切れない繊細な震え。それら全てが、わたしの内側を満たし、研磨の色に染め上げていく。
わたしは、彼の少し乾いた唇に、そっと自分のそれを重ねた。最初は戸惑うように固かった唇が、やがてゆっくりと応えてくれる。わたしは囁いた。
「研磨、ずっと生きていて。わたしより、一日でも長く」
「……やだ。名前が居ない世界で生きるの、無理」
彼の声が、くぐもって聞こえる。
「じゃあ、同時に死のう」
「うん……死ぬ時も、一緒がいい」
彼の声は、ひどく掠れていた。心の一番柔らかな部分に触れられてしまったかのように、壊れてしまいそうだった。それでも、わたしは彼に触れ続ける。彼の温もりを、彼の存在を、この肌で感じていたい。
そうやって言葉にならない想いを交換し、互いの存在を確かめ合っていれば、本当に遺灰を吸い込んだりしなくても、わたし達はもうとっくに一つになっているのかもしれない。この静かな部屋で、世界でたった二人きりのように寄り添いながら、わたしはそんなことを考えていた。夕食の準備はまだ途中だったけれど、今はどうでもよかった。この、研磨と溶け合うような時間こそが、わたしにとって何よりも大切な、魂の糧なのだから。