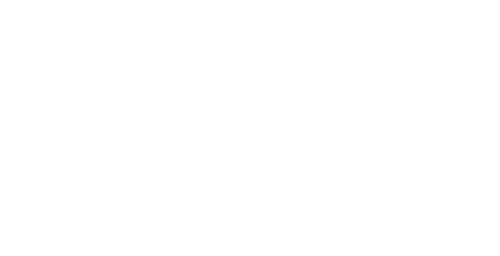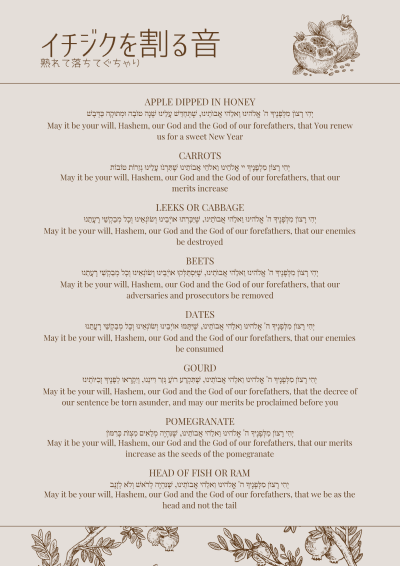
※兄貴の存在、R-15程度の性描写が含まれます。
茹だる、という表現は、こういう日の為に在るのかもしれない。
七月の半ば。梅雨明けを宣言するみたいに、空の青は目に痛い程で、アスファルトは陽炎を立ち昇らせていた。凡そ生命活動に適しているとは思えない外気温に、おれの体力ゲージはとっくに底を突いている。部活が休みで本当に良かった。もし、今日も体育館でボールを追う羽目になっていたら、おれはきっと床に溶けて染みになってた。
「……暑い……」
誰に言うでもなく呟いた声は、クーラーが低く唸る音に掻き消される。ここは、名前の部屋。正確には、名前と彼女の兄が住んでいるマンションの一室。遮光カーテンが引かれた室内は、外の灼熱地獄が嘘のような別世界だ。フローリングのひんやりとした感触が、Tシャツ越しに背中へ伝わってくるのが、唯一の救いだった。おれは床に大の字になって、天井の簡素な照明をぼんやりと見上げていた。最早、愛用の携帯ゲーム機を操作することすら億劫で、ただ無為に時間を溶かしている。
「研磨は、夏が苦手だね」
凛、と涼やかな声が降ってきた。目の向きだけを動かすと、窓辺の椅子に腰掛けた名前が、こちらを見て小さく微笑んでいた。彼女は白いノースリーブのワンピースを着ていて、その姿はこの灼熱の世界で、彼女の周りだけ、気温が五度程も低いみたいに清涼感がある。夜の海を溶かし込んだような双眸が、気怠げなおれを静かに映していた。
「……夏は暑いし、冬は寒いから」
「ふふ、そうだね。生き物泣かせの季節だ」
事もなげに言って、名前は再び手元に視線を落とした。彼女が手にしているのは、ずしりと分厚いハードカバーの本。彼女の趣味は多岐に渡るけれど、こうして黙々と読書に耽っている様子は、精巧に作られた人形のようで、時々、息をしているのかと不安になる。だけど、その白い頬に薄っすらと朱が差したり、薄桃色の唇が微かに綻んだりするのを見ると、ちゃんと彼女の世界がそこに在るのだと分かって、少しだけ安心する。
おれは寝返りを打って、うつ伏せになった。頬に触れる床の冷たさが心地良い。名前のワンピースから伸びる、すらりとした白い脚が視界に入る。華奢な足首。丁寧に切り揃えられた爪。そんな些細な部分にまで、彼女の育ちの良さが滲んでいる気がした。
付き合い始めて、もう随分経つ。お互いが初めてで、何もかもが手探りで。それでも、この静かで満たされた時間が、おれは嫌いじゃなかった。寧ろ、好ましいとさえ思っている。虎みたいに騒がしくないし、リエーフみたいに面倒でもない。ただ、名前がそこに居る。それだけで、おれの世界は完成されている。
「……名前」
「うん?」
「……なんでもない」
「そう」
特に意味もなく名前を呼んで、すぐに取り消す。名前は気にした風もなく、ページを捲る乾いた音だけが室内に響いた。
……ああ、駄目だ。まだ暑さで頭がぼーっとして、思考が纏まらない。このまま眠ってしまおうか。そんなことを考えていた、その時だった。
「あ」
不意に、名前が小さな声を上げた。本を閉じて立ち上がると、彼女はするりとした動きで、ベランダに繋がる窓を開ける。むわり、と生温かい風が流れ込んできて、おれは顔を顰めた。
名前はスペースにずらりと並んだ、鉢植えの一部を覗き込んでいる。園芸も彼女の趣味の一つで、この空間には季節の花や、ちょっとした野菜が植えられていた。
「研磨、見て」
手招きされて、おれは億劫な身体をのろのろと起こした。床に肘を突いて上半身だけ持ち上げると、名前が手にしているものが見える。
それは一つの果実だった。黒みがかった濃い紫色で、西洋梨のような、ぷっくりとした雫の形。
「……イチジク?」
「うん。食べ頃みたいだね。もう、はち切れそう」
名前はそう言うと、瑞々しい果実を愛おしげに指でなぞった。その言葉と仕草が、やけに扇情的に見えて、おれの喉がごくりと鳴る。
名前は熟れたイチジクを丁寧に枝から切り取ると、部屋に戻ってきた。そして、おれの目の前に、軽やかにしゃがみ込む。ふわり、と彼女の髪から甘い香りがした。
「見て。熟れて、落ちそうだったから」
名前はにこりと笑って、そのイチジクを両手でゆっくりと二つに割った。ぱかり、と開いた果実の内側は、花の集合体だというその構造をありありと見せ付けるように、深紅の粒が密集している。とろり、と透明な蜜が溢れ、彼女の白い指先を濡らした。
熟れて、落ちそうだった。
その言葉が、頭の中で奇妙な反響を起こす。名前の濡れた手指。割れた果実の、余りにも生々しい断面。そして、おれを見つめる彼女の、感情の読めない暗い瞳。
全部が緩やかに、おれの理性を侵食していく。
「研磨、あーん」
無邪気な声で、名前が裂いたイチジクの片割れを、おれの口元に差し出した。
夏の暑さの所為じゃない。クーラーが効いている筈のこの部屋で、おれの身体の芯だけが、じりじりと熱を帯びていくのが分かった。下腹部の辺りが、きゅう、と疼く。マズい。これは、いつもの"思春期特有の現象"の中でも、かなり危険なヤツだ。
おれは与えられたイチジクを食べる振りをして、彼女の指先に、そっと唇を寄せた。甘い蜜の味と一緒に、名前の指の柔らかな感触が伝わる。ちゅ、と軽く吸い付けば、名前の肩がぴくりと跳ねた。
「……っ、けんま?」
戸惑いが滲む声。その声が、最後のストッパーを外した。
気づいた時には、おれは彼女の細い腕を掴んで、自分の方へと引き寄せていた。バランスを崩した名前の身体が、おれの上に倒れ込む。彼女の手から滑り落ちたイチジクが、フローリングの床に転がった。
ぐちゃり。
熟れ過ぎた果実が、自重で潰れる鈍い音。木目に赤い果肉と蜜が、無残な染みを作った。
でも、そんなことはもう、どうでもよかった。
「……名前が、美味しそう」
掠れた声でそう告げると、腕の中に居る名前の双眸が、驚きに見開かれる。だけど、そこに拒絶の色はなかった。寧ろ、どこかそれを待っていたとでも言うように、深々と昏く揺らめいている。
おれは彼女の薄桃色の唇に、自分のそれを重ねた。最初は触れるだけ。やがて、もっと深くを求めるように角度を変える。口唇の隙間から舌を差し入れると、イチジクの濃厚な甘さと、名前自身の甘さが混じり合って、頭が痺れるような味がした。
「ん……っふ……」
名前の小さな抵抗は、すぐに力を失っていく。彼女のワンピースの肩紐に指を掛け、ゆっくりと引き下ろした。現れた真っ白い肌は、クーラーで冷えている筈なのに、おれの指先が触れた場所から熱を帯びていくのが分かる。面積の少ない、黒いレースの下着が、彼女の素肌とのコントラストで、やけに目に焼き付いた。
名前の趣味を、おれは知っている。知っていて、その度にどうしようもなく煽られていることも、彼女はきっと、知っている。
「……ねぇ、研磨」
「……なに」
「床、汚してしまったね」
「……後で拭けばいい」
「そうだね」
息も絶え絶えな会話。どちらの心臓の音か分からないくらい、激しい鼓動が耳元で鳴り響いている。
おれは名前を抱きかかえると、数歩先のベッドへと運んだ。シーツの上にそっと降ろしても、絡めた唇は離さない。
熟れて。
落ちて。
ぐちゃり。
あのイチジクみたいに、このまま名前と混ざり合って、ぐちゃぐちゃになってしまえたらいい。思考も、理性も、何もかも溶かして、ただこの熱だけを感じていたい。
西日が差し込み始めた窓の外で、遠くからひぐらしの鳴く声が聞こえる。
夏場は暑くて、面倒で、嫌いだ。
だけど、こんな風に、どうしようもなく熱くなる夏が在るのなら。
……まあ、それも悪くないのかもしれない、なんて。
そんなことを火照った頭の片隅で、ぼんやりと考えていた。