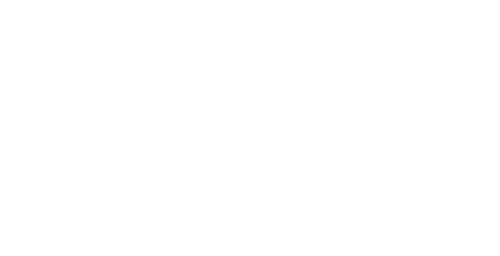証拠隠滅が間に合わない――でも、それでいいかもしれない。
夜の東京は、レンダリングが追いつかないゲームの背景みたいだった。無数の光の粒子が滲んで、街の輪郭を曖昧に溶かしている。アスファルトを濡らす気配もない乾いた空気の中、信号が変わる度にヘッドライトが神経質に瞬き、高架を渡る電車の重低音が、腹の底に響くように低く、長く唸っていた。駅前のコンビニエンスストアからは、自動ドアが開く軽い圧縮空気の音と共に、誰かが慌ただしく現実世界に吐き出されていく。
そんな巨大な都市の片隅で、おれは自室のデスクに向かっていた。プラスチックの筐体が軋む音に混じって、カタカタカタッ――タンッ、と。しん、と静まり返った部屋では、無機質なキーボードの打鍵音だけが、水面に落ちる雫のように、やけに大きく響く。モニターには、目に痛い程の真っ白なテキストエディタ。その空白の上で、カーソルが生命体のように規則正しく点滅する度に、まるで同期するように、おれの心臓がぎこちなく跳ねた。
画面に並ぶのは、数分前に自分の指が生み出した文字列。
『好き。好きで、どうしようもない』
『息をする度に、彼女を思い出す。朝、意識が浮上する瞬間も、夜、瞼の裏に彼女を描いて眠りに落ちる時も、頭の中は名前でいっぱいだ』
『この感情がどこから来て、どこへ行こうとしているのか、もう自分でも制御できない』
……ちょっと、待って。なにこれ。
おれは一体、どんな思考回路でこんなものをタイプしてる? 指先がじんわりと冷えていくような感覚。
カタカタカタカタ――タンッ!
バックスペースキーを、不具合を起こした機械みたいに神経質に連打する。画面から文字が、犯行の証拠が消去されるように、一文字ずつ後退していく。
マズい。これは本当にマズい。
自分で打ち込んでおきながら、全身の肌が粟立つような強烈な羞恥心に襲われる。誰が言うんだよ、こんな砂糖菓子を煮詰めたみたいに甘ったるいセリフ。ラブレター? それにしたって、余りにも……余りにもストレート過ぎて、陳腐だ。
長く、重い溜め息を吐き出して、椅子の背にぐったりと体重を預けた。軋むキャスターの音が、静寂を僅かに破る。画面には、ただ無慈悲に点滅を続けるカーソルだけが残っている。打つべき言葉なんて、どこにも見つからない。指先が頼りなく宙を掻く。
――これから、どうすればいい? この持て余した感情を、どう処理すればいい?
『……研磨?』
不意に静寂を破って、スマホのスピーカーから鼓膜を震わせたのは、夜の空気に溶けるような、それでいて芯のある透き通った声だった。心臓が驚きで大きく跳ねる。
「……あ、うん」
作業通話の相手は、名前。
おれの彼女。この世界で、たぶん一番大切で、一番好きな人。
そして、今まさにこの部屋で、おれを内側から静かに破壊しつつある、厄介な問題の発生源。
『何をしていたの?』
その声色は、どこまでも穏やかだ。
「……んー……」
言えるわけがない。数分前まで、キーボードを叩き割らんばかりの勢いで、読んだら赤面必至のポエムを生成していたなんて。天地が引っ繰り返っても、絶対に言えない。
「……ゲーム」
絞り出した声は、自分でも驚くほど平坦で、感情が抜け落ちていた。
『本当?』
探るような響き。それは疑念と言うより、もっと深い何か――確信に近いような、静かな圧力を伴っていた。
「……うん」
『ふぅん』
名前の声には、何かを見透かしているような、それでいて楽しんでいるような、不思議な響きがあった。おれは無意識に椅子のキャスターを僅かに軋ませ、実際には何も起動していないゲームランチャーの画面を、意味もなく見つめるフリをした。背中に嫌な汗が滲む。
『研磨』
「……なに?」
『わたしのこと、考えていた?』
空気が一瞬で密度を増した気がした。部屋の温度が数度下がったような錯覚。
「っ……」
ドクン、と喉の奥で心臓が暴れる音が聞こえる。いや、違う。落ち着け、おれ。これは多分、彼女特有の野生動物みたいな鋭い勘だ。さっきのポエムを読まれたわけじゃない。絶対に。物理的に読まれる筈がないんだ。
それでも、どう答える? 肯定も否定も、どちらも巧妙な罠のような気がしてならない。
「別に……何も」
我ながら、ひどく曖昧で最低な返事だと思った。
『そう』
一拍置いて、通話越しにもわかるくらい、ふわりと柔らかく笑った気配がした。その笑みに、何故か追い詰められるような感覚を覚える。
『じゃあ、今からそっちに行ったら、迷惑かな?』
「え?」
『だって、研磨がゲームをしているなら、隣で見ていてもいいでしょう?』
背筋に冷たいものが走る。血の気が引くって、こういう感覚か。
無理。絶対に無理。
おれのデスクの上には、ディスプレイの青白い光を薄っすら反射して、さっき書き殴ったポエムの残骸が印刷されたコピー用紙が無防備に転がっている。こんなものを見られたら、社会的に死ぬ。いや、それ以上に、精神的に再起不能になる。
「今、ちょっと……部屋、散らかってるから」
声が上擦る。
『気にしないよ』
あっさりと、名前は言う。
「いや、気にして。凄く」
必死さが滲む。
『しないってば』
譲る気配は微塵もない。
「……」
言葉を失う。静かな、しかし決定的な絶望が、じわじわと胸の中に広がっていく。ゆっくりと潮が満ちるように。
『じゃあ、今から向かうね』
悪戯っぽい響きを含んだ、宣告。
「え、ちょ、本気で?」
『うん。もう家を出てしまった』
「っ……!!」
反射的に椅子から立ち上がる。その勢いで椅子が後ろに倒れそうになり、慌てて手で支えた。部屋を見渡す――と言うより、絶望的な視線がデスク周りの惨状を彷徨う。
PCの電源を落とさなきゃ。エディタを完全に閉じないと。それからコピー用紙! あの致命的なコピーを隠滅しないと! 証拠を完全に抹消しなきゃ!
焦る余り、殆ど無意識に机上のコピー用紙へ手を伸ばした、その瞬間――
ガタンッ!!
鈍い衝撃音と共に、視界の端で黒い物体が床に落下した。
――キーボードが、無残に床に叩き付けられていた。
「……あ」
間の抜けた声が、自分の口から漏れた。
『研磨? 今の、何の音? 大丈夫?』
名前の声に、僅かに心配の色が混じる。
「……いや、なんでもない。ちょっと、物が落ちただけ」
嘘を重ねる。心臓が早鐘を打っている。
『……?』
名前は訝しむような短い息遣いを漏らしたが、幸い、それ以上は追及してこなかった。おれは床に転がったキーボードを慌てて拾い上げる。逆さまになったそれをデスクに戻しながら、キートップが幾つか外れていないか確認する余裕すらなかった。
……落ち着け、おれ。大丈夫。まだ時間は、ある筈。彼女がここに着くまでに、全ての証拠を完全に隠滅すればいい。あのポエムさえ見られなければ、それで……それで、何とかなる筈。
でも――
スマホの向こうで、名前がふっと息を吐く気配がした。それは諦めとも、或いは慈しみともつかない、不思議な静けさを含んだ響きだった。
『……研磨』
「……うん」
『好きだよ』
静寂を切り裂くように、その言葉は真っ直ぐに届いた。
「っ……」
まただ。心臓が大きく、強く脈打つ。鷲掴みにされたような衝撃。
名前の声は驚くほど平坦で、感情の抑揚すら殆どない。なのに、その飾らない真っ直ぐさが、まるで物理的な力を持って、おれの胸の中心を正確に貫くようだった。
たった四文字。それだけなのに、全身の動きが、思考までもが、一瞬フリーズする。逃げ場なんて、どこにもない。彼女の言葉の前では、どんな防御も意味を成さない。
「……おれも」
掠れた声で、漸くそれだけを返すのが精一杯だった。喉が渇いて、上手く声が出ない。
『うん。知ってる』
悪戯っぽく、でもどこか全てを包み込むような優しさで、名前はくすりと笑った。
……ああ、そっか。
そうだよね。
おれはもう一度、ゆっくりとキーボードに指を置いた。冷えたキートップの感触が、妙にリアルだ。さっき消した、あの赤面もののポエムの続きを書くべきか、一瞬だけ迷う。
でも――
カタカタカタカタ――タンッ。
次の瞬間、おれの指は新しい文章を打ち始めていた。さっきとは違う、もっと確かな衝動に突き動かされて。
『好き。どうしようもなく、好きだ』
『だから、今すぐ会いたい』
多分、もう誤魔化す必要なんてなかったんだ。最初から。
おれがどれだけ名前のことばかり考えているかなんて、彼女にはとっくに全部、バレていたのかもしれない。お見通しだったのかもしれない。
だから、今度は、もっと素直な言葉で。飾らない、ありのままの気持ちを。
おれは、さっきとは違う意味で、キーボードを叩き壊してしまいそうな衝動に駆られながら、ただ只管に、今、この瞬間に感じている、世界で一番好きな人のことを綴り始めた。
窓の外では、東京の夜が、まだぼんやりとした光の粒を瞬かせていた。