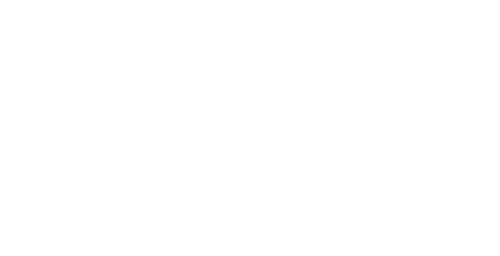※死を連想させる表現が含まれます。(Not.死ネタ)
結末は救済的ですが、苦手な方はご注意ください。
絶望も、過去も、君への想いで上書きしたい。
『研磨、そろそろ着くよ』
たった一言、スマホのスピーカー越しに伝えられたその音声が、おれの意識を現実へと叩き付けた。さっきまで無数の文字が渦巻くデジタルの深海に沈んでいた脳が、急激に浮上を開始する。水圧から解放されたみたいに、ぐわんと世界が歪む感覚。喉の奥が、熱い砂でも飲み込んだかのように、じりじりと焼け付く。肋骨の内側で、心臓が焦げ付きそうな勢いで暴れ出す。逃れようもなく、余りにも確かなこの身体的な反応――ああ、これは間違いなく、"好き"っていう感情の副作用だ。それ以外に、説明がつかない。
「あ……うん」
掠れた声で、短く返事する。指先が妙に冷たい。本当は、まだ心の準備どころか、物理的な準備すら整っていない。この部屋には、名前の目に触れさせてはいけない"痕跡"――おれの弱さや、制御できない感情の残骸が、まだそこかしこに散らばっている。書き掛けで放置された、ラブレターみたいなポエムの断片。落ちた時の衝撃でキーボードから抜けてしまった、転がったままのキートップ。集中できずに投げ出した、ゲームの攻略メモが書かれたコピー用紙の山。全部、隠さなきゃ。いつもなら、そう思う筈なのに。
でも、何故か足はもう、玄関へと向かっていた。薄暗く、しんとした廊下を抜ける。冷たい金属の感触を確かめるように、玄関ドアのチェーンを外しながら、指先が微かに震えているのに気づいた。さっきまで気にしていた筈の部屋の惨状なんて、もうどうでもよくなっていた。それより、もっと圧倒的な何かが、おれの思考を支配している。
「……好きなんだよ、おれ、ほんとに」
誰に言うでもなく、ぽつりと呟いた言葉が、静かな空間に吸い込まれて消える。そのまま、冷たいドアに軽く額を押し当てた。ひんやりとした感触が、火照った思考を少しだけ落ち着かせてくれる気がした。
その、瞬間だった。
ピンポン。
抑制された、けれどクリアなチャイムの音が、東京の無機質な夜気の中に、静かに、だけど確かに響き渡った。まるで、おれの心臓の鼓動とシンクロするように。
「研磨、開けて」
ドア越しに聞こえた声は、物理的な隔たりがある筈なのに、すぐ耳元で囁かれたかのように鮮明だった。息が詰まる。
ゆっくりと、ドアを開ける。そこに立っていたのは、夜の闇をそのまま纏ったような、黒いコートに身を包んだ名前だった。冷たい冬の空気に晒された滑らかな髪が、外灯の頼りない光を受けて、柔らかく揺れている。白い頬は、寒さか、それとも別の理由か、ほんのりと上気していた。そして、その大きな瞳は、吸い込まれそうなほど真っ直ぐに、おれだけを見つめていた。
「……寒かった?」
やっとのことで絞り出した声は、自分でも驚く程に掠れていた。
「ううん、全然。研磨に会えると思ったら、心臓がドキドキして、寧ろ温かくなった」
悪戯っぽく笑う名前のその一言で、おれの心臓はまた、鷲掴みにされたみたいに強く脈打った。どうして、この子はいつもこうも簡単に、おれの防御壁を打ち破ってくるんだろう。
「……入って」
促すと、名前は小さく頷いて、するりと部屋の中に入ってきた。その拍子に、彼女の冷えた指先が、おれの手にそっと重なる。驚くほど自然に、まるで最初からそこにあるべきだったみたいに。その瞬間、強張っていた肩の力がふっと抜け、浅かった呼吸が少しだけ深くなるのを感じた。彼女の体温が、じんわりと伝わってくる。それは心地よくて、安心する温かさだった。ずっと息を止めていた水底から、漸く水面に顔を出して、呼吸を取り戻したような、そんな解放感があった。この冷たくて複雑な世界に、ちゃんと帰ってこられたような感覚。
名前はおれの部屋に入るなり、真っ直ぐに机の上のPCモニターに視線を向けた。他には目もくれない。そこには、彼女が来る直前まで格闘していた、たった一文が、白いテキストエディタの画面に、告白のように浮かんでいる。
『好き。どうしようもなく、好きだ』
それを見た名前が、ほんの少しだけ、慈しむように瞳を細めたのがわかった。何も言わない。けれど、その静かな眼差しは、おれの混乱も、焦りも、そして、この抑え切れない感情も、多分、全部お見通しなんだろう。
「研磨」
おれの名前を呼ぶ声は、いつもより少しだけ低く、深みを帯びていた。心の奥底から湧き上がってくる熱い何かを、必死に抑え込もうとしているかのような、そんな響きがあった。
「わたしね――」
名前はゆっくりと口を開く。
「ん」
息を詰めて、次の言葉を待つ。
「生きるって、少しだけ面倒だなって、ずっと思っていたの」
余りにもさらりと、まるで天気の話でもするように、名前は言った。その言葉の持つ重さに、部屋の空気が一瞬で張り詰める。
「希望とか、未来とか、そういうキラキラしたもの、余りピンと来なくて。ただ、流されているだけみたいな毎日で」
名前は続ける。視線はモニターの文字に注がれたままだ。
「だけど、どうしようもなく苦しくて、首でも括ってしまおうかって考えた、そんな絶望の夜にね、ふと、研磨の手に触れた時のことを思い出したんだ」
ゲームをしている時、隣で何気なく触れた、おれの手。
「その手が、凄く温かかったこと。その時、思ったの。もし、この息苦しい世界から消えるなら、誰かに殺されるっていう終わり方があるなら……わたしは、研磨の手がいいなって」
おれの呼吸が完全に止まった。脳が理解を拒む。けれど、名前の言葉は恐ろしいほど真っ直ぐに、おれの鼓膜を貫いた。
「それくらい、好き。……ねぇ、研磨は?」
答えを促すように、名前の視線がおれに戻される。そして、その冷えていた筈の手が、そっと、おれの頬に触れた。驚く程に温かい。まるで、小さな太陽みたいに。焼け付くような、それでいて、どうしようもなく救われるような、矛盾した熱。
「……おれも」
絞り出した声は、自分でも情けない程に震えていた。
「おれも、多分、同じこと考えてた」
視界が滲む。
「生きるのって、正直、あんまり得意じゃない。面倒なことばっかりだし、意味なんて、よくわかんないし。……でも、名前が居るなら。名前が隣に居てくれるなら、死ぬのは、ちょっと、勿体ないかなって思う」
「……そうだね」
名前が、ふわりと微笑む。その笑顔は夜明けの光みたいだった。
二人の間の距離が、音もなくゼロになる。どちらからともなく、引き寄せられるように。世界から切り離されたような、濃密な静けさの中、名前の唇が、おれの唇に、そっと重ねられた。
温くて、柔らかくて、でもどこか切実で、確りとしたその感触。
それは足を踏み外して、真っ暗な崖から落ちていく寸前に、誰かに力強く手を掴まれたような感覚だった。奈落の底に引き摺り込まれる代わりに、確かな温もりに引き上げられるような。
この息苦しい夜を生きて、迷って、足掻いて、今、この瞬間に辿り着けて、本当に心の底から、良かったと思った。
もう、ポエムを書いてもいい気がした。恥ずかしい言葉を、幾ら連ねてもいい。
それを見られたとしても、きっと、もう大丈夫だと思った。
だって――
「名前が居るなら、おれ、全部、どんなに恥ずかしくても、それでいい」
掠れた声で告げると、彼女の瞳の奥に、おれの言葉が真っ直ぐに吸い込まれていくのが見えた。揺らがない、確かな光がそこにあった。
そして、おれの頬に添えられていた彼女の手は、いつの間にか、おれの首の後ろに回されていた。それは、決して絞め殺す為の手つきではなく、ただただ温かく、優しく、おれをこの場所――この現実へと、しっかりと繋ぎ止めてくれている。
ああ、そうか。
おれの命綱は、きっと、この子の両手なんだ。
この温もりがある限り、おれはどんな面倒な世界でも、彼女と一緒に生きていける。