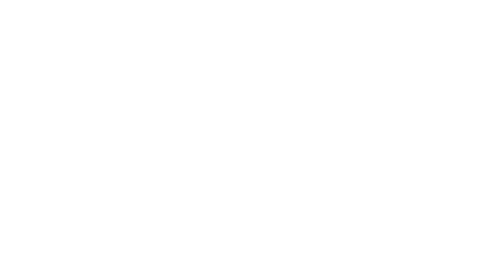慣れねぇんだよ、全部。
※兄貴の描写が含まれます。
纏わり付くような、少し温い風だった。
春の名残と夏の気配が混じり合う、どっちつかずの空気。それが部活で火照った首筋を緩やかに撫でていく。練習後の、まだ昂ぶりが残る身体から、張り詰めていたものがふっと溶けていくような感覚があった。悪くない。寧ろ、心地いいくらいだ。
「……飛雄くん、今、こっちを見たよね?」
不意に隣から聞こえた、名前の声。静かだが、妙に芯のある響きが鼓膜を揺らし、心臓がドクン、と妙な音を立てた。なんで、こいつの声はいつもこうなんだ。
すぐ隣を歩いているだけ。それなのに、こいつはいつも、俺の心の壁を易々とすり抜けるような視線を向けてくる。水底を覗き込むような、静かで、どこか全てを見透かしているような目。ガラス一枚隔てた向こう側から、じっと観察されている気分になる。
「見てねぇし」
「本当? わたしはちゃんと見ていたよ、飛雄くんのこと」
「……は?」
見てたのはどっちだよ、と思ったけど、口には出さない。出せない。
こいつ相手だと、どうしてか言葉が上手く形にならない。反論しようとしても、その前にこいつのペースに巻き込まれている気がする。
なんかもう、こいつの言葉は一つひとつに裏がある気がして落ち着かない。ただの会話の筈なのに、どこかに仕掛けがあるんじゃないかと勘繰ってしまう。付き合ってるんだ。正真正銘、俺の、恋人。だったら、もっとこう、慣れてもいい筈なのに、一向に心臓がこの状況に慣れてくれない。
「ずっと見ていたよ。飛雄くん、黙っているのに耳まで真っ赤だった」
「……ボゲェ……っ」
反射的に悪態が口を衝いた。意味わかんねぇ。なんで、そんな細かいとこまで気づくんだよ。
ていうか、耳? そんなとこまで観察されてんのか、俺は。クソッ、練習試合中に敵セッターの動きを読むより、よっぽど集中して俺を見てやがる……! バレーの時より神経使わされてどうすんだ。
思考がぐるぐる回っている内に、足は勝手に、名前の住むマンションのエントランスへと辿り着いていた。
磨き上げられたような白い外壁に、青々とした蔦が見事に絡んでいる。手入れが行き届いているそれは、古い洋館か、どこかの城塞のようにも見えた。普通の女子高生が住むには、ちょっと、いや、かなり立派過ぎるだろ、これ。何度来ても場違いな気がして、少しだけ身が縮こまる。こんなとこに住んでる女子高生、他に居ねぇだろ。
自動ドアを抜けて、ひんやりとした空気が漂うロビーへ。エレベーターを待つ、ほんの数秒。それが、やけに長く感じる。名前の隣で、妙な沈黙が重たい。さっきの「耳まで赤い」発言が、まだ頭の中で反響している。
「ねぇ、飛雄くん」
「……なんだよ」
「もういっそ、飛雄くんの心臓の音を、直接聴いてみようかな」
殆ど吐息のような声が、耳元の直ぐ近くで、さらりと紡がれた。
ぞわっ、と粟立つような感覚。背筋を駆け下りた汗は、夏の試合終盤の、あの嫌な冷たさとは比べ物にならない程、芯から凍えるような冷たさだった。なんだ、今の、反則だろ。
「おま、お前、何言って……っ!」
「だって、凄くドキドキしているのが、こっちまで聞こえてきそうなくらいだったから。わたしのことが好き過ぎて、心臓が爆発しそうなんだね?」
悪戯っぽく笑う気配。カッ、と顔中の血液が沸騰するような熱さを感じた。
なんだ、それ。怖い。いや、怖いって言うか……こいつ、こういうとこが妙に可愛いと言うか……でも、やっぱり怖い。なんだ、この感情のジェットコースター。可愛いのに怖いってなんなんだ。
それに、核心を突かれているのが、また猛烈に悔しい。くっそ……なんでバレてんだよ……。
思考が完全に停止し掛けた、正にその時。『チン』という軽やかな到着音と共に、目の前の扉が静かに開いた。磨かれた金属の内壁が、俺たち二人だけを映している。誰も乗っていない、密室。
先に乗り込んだ俺の隣に、名前がすっと並ぶ。唇の端に揶揄うような、でも、どこか満足そうな、小さな笑みが浮かんでいた。その表情がまた、俺の心臓を無駄に煽る。
「……爆発すんのは、名前だって、同じだろ?」
意地だった。完全に意地だ。ここで黙ってたら、負けな気がした。こんな時ぐらい、俺だって攻めていい筈だ。そうだろ。
「そうかもね」
「うぇ?」
余りにもあっさり肯定されて、不意に心臓が大きく、痛い程に跳ね上がった。受け止め切れねぇ。なんだよ、今の返事は。肯定かよ。
「飛雄くんの声を聞くだけで、息が止まりそうになる。毎日、こうして一緒に居ても、全然、慣れないんだよ」
自分の制服の胸元を軽く押さえながら、名前がぽつりと言った。その声には、いつもの揶揄うような響きは欠片もなかった。
笑ってない。その目は冗談じゃなく、真剣だった。俺の声が? こいつの中で、そんな風に響いてるのか? 信じられないような、でも、胸の奥がじわりと熱くなるような感覚。こいつが俺に向ける感情の、その一端に触れた気がした。
「……じゃあ、もういっそ……」
自分でも、何を言おうとしているのか、よくわかっていなかった。ただ、衝動、としか言いようがない。口が勝手に動いていた。
でも、もし、あのまま何も言わなかったら、多分、俺は後悔してた。絶対に。
「同じ家、住めばいいだろ」
しん、とエレベーターの中に濃密な沈黙が落ちた。上昇していく機械音だけが、やけに大きく響く。
静か過ぎて、ドクドクと脈打つ音が耳の奥で鳴っているのがわかる。自分の心臓か? それとも、隣に立つ、こいつのか? 区別がつかない程、空気が張り詰めている。息をすることさえ忘れていた。
「……え?」
名前が漸く絞り出したような、小さな声を漏らす。
「だから……俺んちでも、ここでもいい。毎日一緒に居るとか、そういうのじゃなくて……もっと、その……上手く言えねぇけど、ずっと、一緒に……」
しどろもどろになりながら、必死で言葉を繋ぐ。一瞬、鳩が豆鉄砲を食ったような顔をして、それから、何かを吟味するように、名前が小さく首を傾けた。理解したような、まだ戸惑っているような、複雑な表情。頼むから、変なこと言われたとか思うなよ。
「……じゃあ、わたし、間取りから考えていい?」
予想外過ぎる角度からの返答。
「えっ、いいのかよ!?」
「うん。いいよ。……でも、その前に、兄貴兄さんには、飛雄くんがちゃんと直談判してね?」
悪戯な光が、名前の瞳に戻っていた。
「うっ……!」
あの兄貴か……! 名前の兄貴である、あの無駄に掴みどころのない人を説得するのか……想像しただけで胃がキリキリする。だが、引けない。引きたくない。もう、逃げ場なんてなくていい。
あの人にどんな突飛な試練を課されようが、訳の分からない創作論で翻弄されようが、なんだっていい。こいつの隣に、ずっと居られるなら、もうそれでいいと思った。覚悟は、できた。……多分。
再び『チン』と音がして扉が開く。外には、カーペットが敷かれた静謐な廊下が続いていた。目的の階だ。
部屋に向かって歩き出す。その流れで、少しだけ躊躇いながら名前の手に触れると、指がするりと絡んできた。繋いだその手は驚く程に小さく、温かかった。そして、微かに震えていた。
俺の声を聞くだけで息が止まりそうになる、と言ったこいつ。その言葉が決して嘘じゃないと伝わってくる、その正直な震えがどうしようもなく、俺の心を掴んで、嬉しくて仕方なかった。