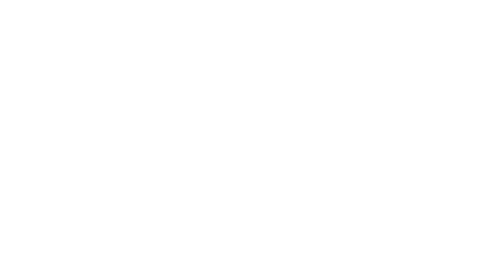夏の午後、俺は沸騰した。
※兄貴と弟が登場します。
アスファルトが陽炎を吐き出す。じりじりと肌を焼く八月の太陽は、容赦と云うものを知らないらしい。体育館での猛練習を終えた身体は、まるで燃え殻のようで、一歩踏み出す毎に汗が塩の結晶となり、首筋をちりつかせた。スポーツドリンクのボトルはとっくに空で、咽喉の奥は干上がった砂漠みたいだ。
早く、冷たいもんが飲みてぇ。
その一心だけで、俺、影山飛雄は歩道を行く。向かう先は、俺の家じゃない。いつからか練習後の足が、当然の如く向かうようになった、苗字家のマンションだ。
エントランスの自動ドアを抜けると、むわりとした熱気が嘘のように断ち切られ、冷房の効いた空気が火照った身体を優しく撫でた。何度来ても慣れないのは、集合ポストにも、玄関のドアにも、一切の表札がないことだ。建物全体が、世界から隔絶された秘密の箱庭みたいで、中心には、名前が居る。
最上階に到達し、苗字家のチャイムを鳴らすと、直ぐに聞き慣れた声が応えた。
『はーい、どうぞ』
鍵の開く音と共に、ドアノブに手を掛ける。
「お邪魔します」
「やあ、未来の全日本司令塔殿。今日もバレーボールと云う名の球体と戯れてきたようだね」
俺を出迎えたのは、名前の兄さん、兄貴さんだった。今日のTシャツの胸元には、達筆な明朝体で『人生の伏線、未回収』と書かれている。相変わらず意味は分からないが、この人らしい。
「……ウス」
「そんなに汗だくで。宛ら、滝行を終えた修行僧のようだね。さあ、中へ。我が妹が、君を待っているよ」
ひらひらと手を振りながら、リビングへ消えていく兄貴さんの背中を見送り、靴を揃えた直後だった。廊下の奥から、ぱたぱたと軽い足音が近づいてくる。
「飛雄くん、いらっしゃい」
現れた名前は、薄水色の涼しげなワンピースを着ていた。普段は制服姿しか見てないから、その格好は妙に新鮮で、心臓がトクン、と一つ大きく跳ねる。柔らかな髪が、窓から差し込む西日を吸い込んで、淡い蜂蜜色に煌めいていた。
「……おぅ」
「凄い汗だね。先ずはシャワーを浴びる? それとも、何か冷たいものが飲みたい?」
静かな湖面を思わせる双眸が、俺を真っ直ぐに捉える。こいつに見つめられると、いつも調子が狂う。頭の中の思考が、全部、ぐちゃぐちゃに掻き混ぜられるような感覚。
「……冷たい、もん」
辛うじて、それだけを絞り出すと、名前は小さく頷いて、「じゃあ、こっちへ」と俺の手を引いた。触れた指先は、夏を忘れるくらいひんやりとしていて、心地良かった。
キッチンは生活感と云うものが見当たらない程、整然としていた。その一角に鎮座しているのは、飲食店にでもありそうな、バカデカい業務用の冷蔵庫だ。
「好きなもの、選んでいいよ」
名前に促され、重いステンレスの把手を握る。観音開きの扉を開けると、ぶわりと冷気が滝のように溢れ出し、汗ばんだ顔を撫でた。
「うおっ……」
中には、麦茶、スポーツドリンク、牛乳、野菜ジュース、炭酸水が、軍隊のように整列している。奥には、ガラスの器に入れられた、オレンジ色の夕焼けみたいなゼリーが幾つか並んでいる。キラキラと光を反射して、やけに美味そうだ。
無意識に、その一つに手を伸ばした時だった。
ふわり、と。
背中に柔らかくて温かいものが押し当てられた。
甘い石鹸と、名前自身の匂いが鼻腔を擽る。振り返るより先に、細い腕が腹に回された。
「……っ、先頭文字、名前……?」
「飛雄くん、お疲れ様」
首筋近くで囁かれた声に、背筋がぞくりと粟立つ。背部に感じる、控え目だが確かな膨らみと、とくとくと脈打つ心音。家電製品で冷やされていた筈の身体が、一瞬で沸騰した。
なんだこれ。なんだこれ。ボゲェ、俺の心臓、うるせぇ!
冷蔵庫の中は、こんなに冷てぇのに、なんで、こいつはこんなに……温かいんだ。
思考が完全に停止する。目の前のゼリーも、喉の渇きも、何もかもが吹っ飛んだ。只、背に感じる名前の体温だけが、俺の世界の全てになった。
「……飛雄くん?」
固まっている俺を不思議に思ったのか、名前が脇からひょこりと顔を覗き込む。近過ぎる距離に息が止まる。透き通るような白い肌。ほんのりと色付いた唇。長い睫毛に縁取られた瞳が、心配そうに俺を映している。
「顔、真っ赤だよ。茹蛸みたい」
くすくすと、鈴を転がすような声で笑われた。
「ちがっ……これはその、暑いからだ、ボゲェ!」
「ふふ、そう。でも、クーラーは効いているけどね」
悪戯っぽく細められた目に、心臓を鷲掴みにされる。駄目だ。こいつには勝てねぇ。
俺がしどろもどろになっていると、リビングの方から呆れたような声が飛んできた。
「うわ、またやってる。姉さん、そいつ、熱中症で頭やられてるから、早く離してやれよ」
ひょっこりと現れたのは、名前の弟、弟だった。夏用の、薄手のカーディガンを羽織っている。
「俺は正常だ!」
「正常な奴が、冷蔵庫の前で茹蛸みてぇな顔するかよ。あ、もしかして、姉さんの面積少ない下着のことでも想像した?」
「なっ……! てめぇ、ぶっ飛ばす!」
「やれるもんならやってみろよ、この単細胞!」
俺と弟がギャンギャンと吠え合っていると、いつの間にか背後から離れていた名前が、ぽつりと零した。
「わたしの下着は、飛雄くんしか見ちゃ駄目」
「「えっ」」
俺と弟の声が、綺麗にハモった。
名前は何を言ったのか全く分かってないような、きょとんとした表情で、俺達を見比べている。この天然さが、一番タチが悪い。
キッチンに流れる、気まずい沈黙。それを破ったのは、リビングから聞こえてきた、兄貴さんの呑気な言葉だった。
「いいねぇ、青春だ。よし、次の絵本のタイトルは『パンツとオレンジゼリーとぼく』にしよう。きっと、子供達に夢と希望を与えられる」
「「絶対、やめ(ろ)てください!!」」
またしても、俺と弟の声がハモった。
結局、俺達はリビングの大きなソファに並んで、オレンジゼリーを食べることになった。
兄貴さんが新作の突拍子もない粗筋を語り、弟が的確なツッコミを入れている。賑やかな会話をBGMに、俺はスプーンでゼリーを掬った。
ひんやりとした感触が舌に広がり、甘酸っぱいオレンジの香りが鼻に抜ける。渇き切った身体に、冷たさが染み渡るようだった。
「……美味い」
ぽつりと呟くと、隣に座っている名前が、嬉しそうに微笑んだ。
「うん。良かった」
その時、ガラスの器を持つ俺の手に、名前の指先がそっと触れた。ほんの一瞬。だけど、爪先から伝わる熱が、電流みたいに全身を駆け巡った。
ひんやりしたゼリーと、名前の体温。
二つの滅茶苦茶な温度差が、どうしようもなく心地好くて、胸の奥が締め付けられる。
バレーのこと、次の試合のこと、日向の奴に負けたくねぇこと。いつも頭の中はそればっかりだ。
でも、今は。
この甘くて冷やかな味と、隣に在る柔らかな熱さだけで、脳内がいっぱいだった。
冷蔵庫の中身は冷たい。でも、その扉を一緒に開けて、中身を分け合える相手が居る。その温もりがきっと、俺を強くする。
そんな、柄にもないことを思った。
「飛雄くん、口の端にゼリーが付いてる」
名前が細い指で、俺の口許をそっと拭う。自然な仕種に、また顔面に熱が集まる。
「……バッ! 自分でやる!」
俺が慌てて顔を背けると、名前はまた楽しそうに、くすくすと笑った。
揶揄われるのは、破滅的に苦手な筈なのに。
こいつがやると、なんでこんなに、夏の太陽みたいに眩しいんだ。
茹だるような夏期の午後。
俺は、冷蔵庫の中身よりも甘くて、誰かの体温よりもずっと熱い、そんな感情の正体を、まだ名前も付けられずに持て余していた。