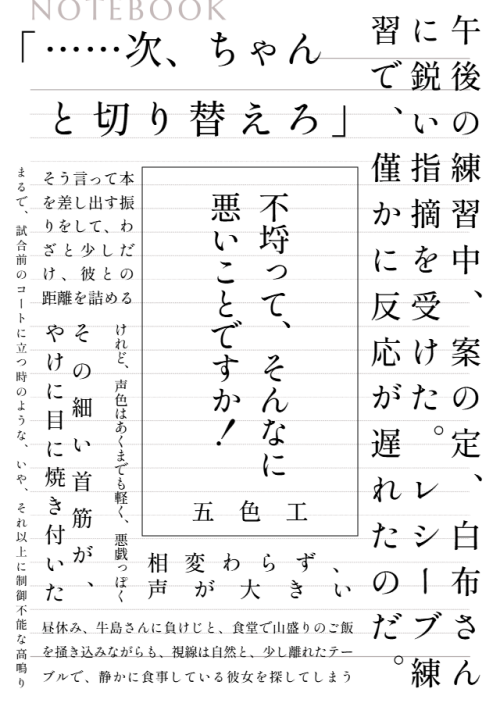
一途で純情な次期エースが、
恋とバレーの間で右往左往するお話。
雨上がりの空気は妙に澄んでいて、昨夜の出来事を鮮明に思い出させた。
苗字さんの、あの最後の笑顔。「嬉しかった」と言った時の、ふわりと綻んだ唇と、柔らかく細められた瞳。あの残像が授業中も、飯を食っている時も、ふとした瞬間に脳裏を過り、その度に、俺の心臓は律儀に跳ね上がるのだ。まるで、試合前のコートに立つ時のような、いや、それ以上に制御不能な高鳴り。
(……嬉しかった、か)
その言葉を反芻するだけで、顔が熱くなる。耳までジンジンと痺れるようだ。彼女が、俺を家に招き入れたこと、二人きりで紅茶を飲んだこと、そして、あの核心に迫るような質問――「五色くんになら、何回言ったら伝わる?」。あれは一体、どういう意味だったのか。考えれば考える程、頭の中がぐちゃぐちゃになる。
数学の授業中、ノートを取る手が止まる。気づけば、シャーペンの先が、無関係な余白の上を彷徨っていた。危うく、彼女の名前を書きそうになって、慌てて手を引く。何をやっているんだ、俺は。集中しろ。エースたるもの、常に冷静沈着でなければ。
ちらり、と斜め前の席に座る苗字さんの背中に視線を送ってしまう。柔らかな髪がブラウスの襟に掛かっている。その細い首筋が、やけに目に焼き付いた。彼女がふと何かを思い付いたように小さく頷く仕草や、教科書のページを捲る指先の白さ。その一つひとつがスローモーションのように見えて、俺の思考を奪っていく。
(……不埒だ)
そう思った。授業中に女子のことばかり考えているなんて、不埒極まりない。バレーのこと、次の試合のこと、もっと鋭いクロスを打つにはどうすればいいか、考えるべきことは山ほどある筈なのに。なのに、俺の頭の中の大部分は、苗字名前という存在に占拠されつつあった。
いや、違う。不埒なのは、俺の思考そのものだ。
時折、本当に一瞬だけ、彼女の隣に座りたいとか、あの滑らかな髪に触れてみたいとか、もっと言えば、あの雨の日、傘の下で触れそうになった距離よりも、もっと近くに……そんな、凡そ健全とは言えない、エースにあるまじき邪念が頭を過るのだ。その度に、俺は心の中で「違う! 断じて違う!」と叫び、ぶんぶんと頭を振って妄想を追い払おうとする。だが、一度芽生えたそれは、コートに深く突き刺さったスパイクのように、簡単には消えてくれない。
昼休み、牛島さんに負けじと、食堂で山盛りのご飯を掻き込みながらも、視線は自然と、少し離れたテーブルで、静かに食事している苗字さんを探してしまう。声を掛けたい。昨日の礼をちゃんと、もう一度言いたい。あわよくば、少しでも話したい。けれど、いざ彼女の姿を捉えると、途端に心臓が煩くなり、足が竦む。結局、今日も遠くから見つめるだけで終わってしまった。情けない。
「おい五色、今日、いつも以上に変だぞ。ぼーっとしてんじゃねぇ」
午後の練習中、案の定、白布さんに鋭い指摘を受けた。レシーブ練習で、僅かに反応が遅れたのだ。
「す、すみませんっ!」
「……次、ちゃんと切り替えろ」
意外にも、それ以上の追求はなかった。けれど、見透かされているような気がして、余計に背筋が伸びる。そうだ、俺は白鳥沢の次期エース。こんなことで浮かれている場合じゃない。もっと強く、もっと上手くならなければ。牛島さんを超える存在になる為に。
そう自分に言い聞かせ、練習に打ち込む。ボールを追い、汗を流している間だけは、少しだけ、彼女のことを忘れられた。けれど、練習が終わり、寮の自室に戻ると、再び苗字さんのことが頭を擡げてくる。
ベッドに倒れ込み、天井を見上げる。
あの部屋の静かな空気。紅茶の香り。壁一面の本棚。そして、俺を見つめていた、深い海の底のような瞳。
(……やっぱり、分かんねぇ)
苗字さんの考えていることは、まるで複雑なサインプレーのようだ。一つひとつの仕草や言葉に意味があるような気がするけれど、その真意を読み解くことができない。
(でも……)
あの笑顔は嘘じゃなかった筈だ。「嬉しかった」という言葉も。
だとしたら、俺は……どうすればいい?
この胸の中で燻り続ける恋。それはただの憧れを超えた、彼女への想いだと気づいてしまった。どうしたら、この気持ちを伝えられる?
(もういっそ、とか、そういう逃げじゃなくて……)
ちゃんと向き合わなければいけないのかもしれない。この「不埒」な感情にも、そして、苗字名前という存在にも。
だが、具体的にどうすればいいのか、皆目見当がつかない。ただ、ベッドの上で悶々としながら、夜は更けていくばかりだった。
 五色くんが嵐のように帰っていった後、わたしはリビングのソファに座り直し、温くなった紅茶をゆっくりと口に含んだ。彼の慌てふためく様子、真っ赤になった耳、必死に何かを堪えているような表情。その一つひとつを思い出すと、自然と口元が緩む。
(……可愛い)
真っ直ぐで、一生懸命で、そして、驚く程に不器用。バレーをしている時の、自信に満ち溢れたエースの顔とは全く違う、年相応の、いや、それ以上に純粋な反応。それがどうしようもなく、わたしの心を惹き付ける。
「なかなか面白い子じゃないか、あの五色くん」
いつの間にか、リビングに戻ってきていた兄貴兄さんが、買ってきたばかりの"打倒! ラスボス"Tシャツを満足げに眺めながら言った。
「うん。とても素直で、見ていて飽きない」
「ほう? 名前がそこまで言うとは珍しい。……もしかして、例の『好きな子』って、彼のことかい?」
兄の言葉に、わたしは答えず、ただ静かに紅茶のカップを傾けた。肯定も否定もしない。それが、わたしの答えだと、兄は理解しただろう。
「ふぅん。成る程ねぇ……。確かに、彼なら名前の隣に居ても、悪くないかもしれないね。あの、絵に描いたような生真面目さと、時折見せる隙だらけな表情のギャップは、物語の主人公にしたくなる魅力がある」
「……わたしの五色くんだけれど」
ぽつり、と呟いた言葉は、自分でも驚く程の独占欲に満ちていた。兄は少し目を丸くした後、くつくつと喉の奥で笑った。
「はいはい、分かっているよ。お兄ちゃんは手を出さないから、安心しなさい」
昨日の、「好きって、何回言ったら伝わる?」という問い。あれは、半分は本心で、半分は彼を試すような気持ちだった。わたしなりに、少しだけ踏み込んでみたのだ。五色くんの心を揺さぶりたい、もっとわたしを意識してほしい。そんな、ちょっと意地悪な、――そう、"不埒"な願望から。
彼の反応は予想通り、いや、予想以上に可愛らしかったけれど、核心には届かなかった。彼はまだ、自分の気持ちにも、わたしの気持ちにも、確信が持てていないのだろう。
(もう少し、待ってあげようかな)
そう思う反面、このじれったい状況を早く終わらせたい気持ちもある。彼の真っ直ぐな好意は、言葉にしなくても伝わってくる。けれど、わたしは彼の口から、はっきりと聞きたいのだ。「好きだ」と。
次の日、わたしは小さな決意を胸に教室へ向かった。
自分の席に着く前、少しだけ遠回りをして、五色くんの机の隣に立つ。彼は窓の外を眺めていたけれど、わたしの気配に気づいて、びくりと肩を揺らした。
「おはよう、五色くん」
「お、おはよう、苗字さんっ!」
相変わらず、声が大きい。そして、緊張しているのが手に取るように分かる。
わたしは、彼が昨日、話題にした時に忘れていった文庫本を取り出した。
「これ、忘れ物」
そう言って本を差し出す振りをして、わざと少しだけ、彼との距離を詰める。五色くんの腕に、わたしの腕が軽く触れた。彼は息を呑んで、身体を硬直させる。
(……分かり易い)
その反応が、また愛おしい。
そして、わたしは少しだけ身を屈め、五色くんの耳元に顔を寄せた。吐息が掛かるくらいの、ぎりぎりの距離で。
「ねぇ、五色くん」
囁くような声で呼び掛ける。彼は驚いて、顔をこちらに向けようとしたけれど、余りの近さに動きを止めた。真っ赤になっている彼の耳が、視界の端に入る。
「昨日の……続き、聞いてもいい?」
核心の質問。けれど、声色はあくまでも軽く、悪戯っぽく。
五色くんの喉が、ごくりと鳴るのが聞こえた。答えられないのは分かっている。それでも、こうして彼の心を乱すのが、今は少しだけ楽しいのだ。
(不埒、かな)
好きな相手を困らせて楽しむなんて。けれど、五色くんがわたしに向ける、戸惑いと、熱の籠もった視線は、わたしの中の独占欲を静かに満たしていく。
わたしは、ふっと彼から身を離し、何事もなかったかのように自分の席へと向かった。背中に突き刺さる、彼の熱っぽい視線を感じながら。
(もう少し、このままでもいいかな)
この、甘くて、じれったい時間。五色くんが自分の気持ちに気づいて、勇気を出して、わたしに伝えに来てくれるまで。
でも、
(早く、わたしのものに、全部)
心の中で囁く、もう一人のわたしの声。それはとても静かで、けれど抗い難い程に強い、「不埒」な本音。
彼の全てを、この手の中に収めたい。そんな欲求が静かに、けれど確実に、わたしの内側で育っているのを感じていた。雨上がりの空気が、まだ少し湿り気を帯びているように。
五色くんが嵐のように帰っていった後、わたしはリビングのソファに座り直し、温くなった紅茶をゆっくりと口に含んだ。彼の慌てふためく様子、真っ赤になった耳、必死に何かを堪えているような表情。その一つひとつを思い出すと、自然と口元が緩む。
(……可愛い)
真っ直ぐで、一生懸命で、そして、驚く程に不器用。バレーをしている時の、自信に満ち溢れたエースの顔とは全く違う、年相応の、いや、それ以上に純粋な反応。それがどうしようもなく、わたしの心を惹き付ける。
「なかなか面白い子じゃないか、あの五色くん」
いつの間にか、リビングに戻ってきていた兄貴兄さんが、買ってきたばかりの"打倒! ラスボス"Tシャツを満足げに眺めながら言った。
「うん。とても素直で、見ていて飽きない」
「ほう? 名前がそこまで言うとは珍しい。……もしかして、例の『好きな子』って、彼のことかい?」
兄の言葉に、わたしは答えず、ただ静かに紅茶のカップを傾けた。肯定も否定もしない。それが、わたしの答えだと、兄は理解しただろう。
「ふぅん。成る程ねぇ……。確かに、彼なら名前の隣に居ても、悪くないかもしれないね。あの、絵に描いたような生真面目さと、時折見せる隙だらけな表情のギャップは、物語の主人公にしたくなる魅力がある」
「……わたしの五色くんだけれど」
ぽつり、と呟いた言葉は、自分でも驚く程の独占欲に満ちていた。兄は少し目を丸くした後、くつくつと喉の奥で笑った。
「はいはい、分かっているよ。お兄ちゃんは手を出さないから、安心しなさい」
昨日の、「好きって、何回言ったら伝わる?」という問い。あれは、半分は本心で、半分は彼を試すような気持ちだった。わたしなりに、少しだけ踏み込んでみたのだ。五色くんの心を揺さぶりたい、もっとわたしを意識してほしい。そんな、ちょっと意地悪な、――そう、"不埒"な願望から。
彼の反応は予想通り、いや、予想以上に可愛らしかったけれど、核心には届かなかった。彼はまだ、自分の気持ちにも、わたしの気持ちにも、確信が持てていないのだろう。
(もう少し、待ってあげようかな)
そう思う反面、このじれったい状況を早く終わらせたい気持ちもある。彼の真っ直ぐな好意は、言葉にしなくても伝わってくる。けれど、わたしは彼の口から、はっきりと聞きたいのだ。「好きだ」と。
次の日、わたしは小さな決意を胸に教室へ向かった。
自分の席に着く前、少しだけ遠回りをして、五色くんの机の隣に立つ。彼は窓の外を眺めていたけれど、わたしの気配に気づいて、びくりと肩を揺らした。
「おはよう、五色くん」
「お、おはよう、苗字さんっ!」
相変わらず、声が大きい。そして、緊張しているのが手に取るように分かる。
わたしは、彼が昨日、話題にした時に忘れていった文庫本を取り出した。
「これ、忘れ物」
そう言って本を差し出す振りをして、わざと少しだけ、彼との距離を詰める。五色くんの腕に、わたしの腕が軽く触れた。彼は息を呑んで、身体を硬直させる。
(……分かり易い)
その反応が、また愛おしい。
そして、わたしは少しだけ身を屈め、五色くんの耳元に顔を寄せた。吐息が掛かるくらいの、ぎりぎりの距離で。
「ねぇ、五色くん」
囁くような声で呼び掛ける。彼は驚いて、顔をこちらに向けようとしたけれど、余りの近さに動きを止めた。真っ赤になっている彼の耳が、視界の端に入る。
「昨日の……続き、聞いてもいい?」
核心の質問。けれど、声色はあくまでも軽く、悪戯っぽく。
五色くんの喉が、ごくりと鳴るのが聞こえた。答えられないのは分かっている。それでも、こうして彼の心を乱すのが、今は少しだけ楽しいのだ。
(不埒、かな)
好きな相手を困らせて楽しむなんて。けれど、五色くんがわたしに向ける、戸惑いと、熱の籠もった視線は、わたしの中の独占欲を静かに満たしていく。
わたしは、ふっと彼から身を離し、何事もなかったかのように自分の席へと向かった。背中に突き刺さる、彼の熱っぽい視線を感じながら。
(もう少し、このままでもいいかな)
この、甘くて、じれったい時間。五色くんが自分の気持ちに気づいて、勇気を出して、わたしに伝えに来てくれるまで。
でも、
(早く、わたしのものに、全部)
心の中で囁く、もう一人のわたしの声。それはとても静かで、けれど抗い難い程に強い、「不埒」な本音。
彼の全てを、この手の中に収めたい。そんな欲求が静かに、けれど確実に、わたしの内側で育っているのを感じていた。雨上がりの空気が、まだ少し湿り気を帯びているように。

