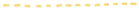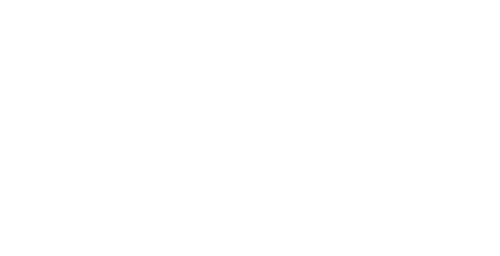首筋の朱を巡る二人の攻防戦は、
午後の部屋に溶けるように、甘く、柔らかく。
十二月の午後の陽光は、どこか遠慮がちだ。窓ガラスを透かして射し込むそれは、部屋の隅々に淡い琥珀色の化粧を施し、舞い上がる埃さえもキラキラと輝かせる魔法のようだった。
わたしの恋人、赤葦京治くんの部屋は、彼自身を映したかのように整然としている。本棚にはバレーボール関連の専門書や文芸書が背表紙を揃えて並び、机の上には書き掛けのレポートと数本のペンが行儀良く置かれている。その静謐な空間で、わたしは彼のベッドに腰掛け、買ったばかりの文庫本のページを捲っていた。傍らでは、京治くんが床に座り込み、熱心にタブレット端末を覗き込んでいる。画面の中では小さな選手達がコートを縦横無尽に駆け回り、ボールを繋いでいた。
「……」
時折、京治くんが「成る程」とか「このタイミングか」とか、小さな声で分析を呟く。その真剣な横顔を盗み見るのは、わたしの密かな楽しみの一つだ。切れ長の涼やかな目元、すっと通った鼻筋、きゅっと結ばれた薄い唇。普段は冷静沈着という言葉がぴたりと当て嵌まる彼が、バレーのことになると途端に熱を帯びる。そのギャップが堪らなく愛おしい。
ふと、彼の首筋に視線が吸い寄せられた。
健康的な肌の上に、ぽつりと落とされた朱色の点。それは雪の上に零れた木苺の果汁のようで、妙に艶めかしく目に映った。
見覚えがある。と言うより、忘れる筈がない。昨夜、この部屋で二人きりの甘い時間の中、わたしが彼の所有権を主張するかのようにそっと唇で刻んだ印なのだから。
「ねぇ、京治くん」
わたしの声に、彼の動きがぴたりと止まる。画面に集中していた深い色の瞳が、ゆっくりとこちらを向いた。
「名前、どうかした?」
「首、どうしたの?」
わたしは努めて無垢な声色を装い、小首を傾げてみせた。彼の首筋を指差しながら。
京治くんは一瞬、きょとんとした顔でわたしを見つめ、それから自分の首に触れた。指先が例の場所に触れた瞬間、彼の表情が凍り付くのが分かった。普段、0.5秒で幾千もの思考を巡らせる彼の脳が、この時ばかりは完全にフリーズしているように見えた。
「……あ」
彼は慌てて立ち上がると、姿見の前に走り、食い入るように鏡を覗き込んでいる。その背中が明らかに動揺を物語っていた。強気なトスを上げるセッターも、木兎さんのような猛禽を手懐ける副主将も、今はそこに居ない。ただの、恋人が付けた小さな痕に狼狽える、十七歳の男の子が居るだけだ。
その姿がどうしようもなく可愛らしいと思ってしまうのは、わたしの性格が悪いからだろうか。
「……虫、かな」
鏡の中の自分と睨めっこした末、京治くんが絞り出したのは、余りにも苦しい言い訳だった。
「ふぅん。虫刺されにしては、随分、情熱的な虫だね」
わたしがそう言うと、京治くんの肩がびくりと揺れる。
「それか……どこかにぶつけた、とか」
「ぶつけたのなら、青くなるんじゃないかな。これは綺麗な赤色で……とても見覚えがあるような気がするのだけれど」
追い打ちを掛けるように言葉を重ねると、彼は観念したように深い溜め息をついた。ゆっくりとこちらを振り向いたその顔は、耳の先まで林檎のように赤く染まっている。その深い色の瞳が、困惑と羞恥と、ほんの少しの期待を滲ませて、わたしを捉えた。
誤魔化そうとしている。明日からの部活動、チームメイト達の目、特に、木兎さんや木葉さん、それに他校の黒尾さん辺りに見つかった時のことを瞬時に計算しているのだろう。彼のその思考回路が透けて見えて、自然と口元が緩んでしまう。
「……わたしが付けたのに、京治くんは忘れてしまったの?」
些か声色を落とし、寂しさを滲ませてみる。これは意地悪な駆け引きなんかじゃない。もし本当に忘れられていたら、それはそれで少し、いや、かなり悲しい。
すると、彼は数歩で距離を詰め、わたしの隣にどさりと腰を下ろした。そして、大きな手で、わたしの手をそっと握り締める。
「忘れるワケ、ないだろう」
低い、掠れた声。その声色だけで、彼の羞恥心が限界に達していることが伝わってくる。わたしはこの冷静な恋人が、わたしの所為で冷静でいられなくなる瞬間が世界で一番好きだった。
「だったら、どうして隠そうとするの?」
「……それは、その……」
言葉に詰まる彼を見て、わたしはくすくすと笑った。京治くんの困った顔はどんな芸術品よりも、わたしの心を惹き付けてやまない。
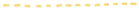 名前に指摘された瞬間、俺の頭の中では警報が鳴り響いていた。
拙い。これは非常に拙い。
脳内シミュレーションが0.1秒で開始される。
パターンA:明日の朝練で、木兎さんに発見される。「あかーし! 首、どうしたんだ!? なんか赤いぞ! 虫か!? すげー吸血虫だな!!」と体育館中に響き渡る大声で叫ばれ、全員の視線が集中。木葉さん辺りに「おーおー、赤葦くんも隅に置けないねぇ」とニヤニヤされる。最悪だ。
パターンB:練習試合で、黒尾さんに発見される。「おや、赤葦くん。随分、情熱的なマーキングされてんじゃん。うちの研磨にも見習わせたいねぇ」などと、ねっとりとした口調で揶揄われる。想像しただけで鳥肌が立つ。
パターンC:名前の弟、弟くんに見つかる。「うわ、赤葦、だっせ。名前に首輪付けられてんじゃん」と蔑んだ目で見られる。まあ、これはいつものことだからいい。いや、良くない。
パターンD:名前の兄、兄貴さんに見つかる。「ふむ、我が妹ながら、実に情熱的だ。京治くん、名前を泣かせたら、俺の次の新作の主人公は君になるから、覚悟しておくように」と笑顔で脅される。それはそれで少し読んでみたい気もするが、間違いなく悲劇だろう。
結論、どのパターンも回避したい。その為には、これを"誤魔化す為の"何かが必要だ。絆創膏? 不自然過ぎる。湿布? 首に? 余計に目立つ。ファンデーション? そんなもの、持っているワケがない。
思考の渦の中、名前の「わたしが付けたのに、京治くんは忘れてしまったの?」と言う声が、俺の心臓を直接掴んだ。
違う。忘れるワケがない。昨夜の、彼女の熱い吐息も、しがみ付いてきた細い指の力も、何もかも鮮明に憶えている。この痕は、彼女が俺に残してくれた、甘美な所有の証だ。それを「虫刺され」などという無粋な言葉で片付けようとした自分自身に腹が立つ。
だが、しかし。現実問題として、これをどうにかしなければならない。羞恥心と、部活での副主将としての体面。それらが彼女への愛おしさや独占欲と、頭の中で激しい試合を繰り広げている。
「だったら、どうして隠そうとするの?」
彼女のどこまでも澄んだ声が、俺の葛藤を貫いた。
そうだ。俺は何故、これを隠したいんだ? 他人の揶揄から自分を守る為? それはこの痕を付けてくれた彼女の行為を否定することにならないか?
いや、寧ろ見せ付けたいくらいの気持ちもある。苗字名前は、俺の恋人なのだと世界中に知らしめたい。だが、それを実行するには、俺はまだ青過ぎた。
「……それは、その……」
俺が言葉に詰まっていると、名前は楽しそうに笑った。その悪戯っぽい笑みを見て、腹が決まった。
もういい。誤魔化すのは止めだ。
俺は彼女の手を引いて、自分の膝の上に向かい合わせになるように座らせた。驚いて見開かれた深海のような瞳が、俺を映す。
「……名前の所為だから」
拗ねたように呟くと、自分でも驚く程に甘えた声が出た。
「え?」
「全部、名前がしたことだろう。だから、責任、取ってくれるよね?」
普段の俺なら、絶対に言わないであろう台詞がいとも容易く口から滑り落ちる。彼女の前では、俺の冷静さなど脆いガラス細工同然だ。
名前は一瞬目を丸くしたが、やがて状況を理解したのか、花が綻ぶようにふわりと微笑んだ。
「うん。勿論。どうやって責任を取ればいい?」
その問いに、俺の中にあった羞恥心という名のダムが完全に決壊した。
「……もっと、付けて」
囁くような声だった。
「隠せないくらい。誤魔化しようがないくらい。俺が、君のものだって、誰が見ても分かるように」
これはもう、ヤケクソに近い告白だ。羞恥心を通り越した、俺なりの最大の愛情表現であり、独占欲の表明だった。他人にどう見られるかなんて、もうどうでもいい。この瞬間の、目の前の彼女が全てだった。
名前の瞳が、愛おしいものを見るように優しく細められる。彼女はそっと身を乗り出すと、俺の耳元に唇を寄せた。
「うん。わたしの京治くん」
その声と同時に、昨夜とは比べ物にならないくらい、はっきりと強く、俺の首筋に彼女の唇が押し当てられた。
「これで、もう誰にも誤魔化せないね」
悪戯に成功した子供のように笑う彼女を見て、俺はもう抵抗するのをやめた。
誤魔化す為の言い訳を考えるより、彼女に愛されていると実感する方がよっぽど有意義だ。
翌日、案の定、体育館で木兎さんの絶叫が響き渡った。
「あかーし! 首、どうしたんだ!? 真っ赤だぞ!? どんな虫に集られてんだ!!」
「……ええ、まあ。昨夜、強力なのが大量発生したみたいで」
俺は平静を装ってそう答えながら、自分の首筋に刻まれた、幾つもの愛の証をそっと撫でた。
誤魔化すことを諦めた首筋は、少しだけ誇らしかった。
名前に指摘された瞬間、俺の頭の中では警報が鳴り響いていた。
拙い。これは非常に拙い。
脳内シミュレーションが0.1秒で開始される。
パターンA:明日の朝練で、木兎さんに発見される。「あかーし! 首、どうしたんだ!? なんか赤いぞ! 虫か!? すげー吸血虫だな!!」と体育館中に響き渡る大声で叫ばれ、全員の視線が集中。木葉さん辺りに「おーおー、赤葦くんも隅に置けないねぇ」とニヤニヤされる。最悪だ。
パターンB:練習試合で、黒尾さんに発見される。「おや、赤葦くん。随分、情熱的なマーキングされてんじゃん。うちの研磨にも見習わせたいねぇ」などと、ねっとりとした口調で揶揄われる。想像しただけで鳥肌が立つ。
パターンC:名前の弟、弟くんに見つかる。「うわ、赤葦、だっせ。名前に首輪付けられてんじゃん」と蔑んだ目で見られる。まあ、これはいつものことだからいい。いや、良くない。
パターンD:名前の兄、兄貴さんに見つかる。「ふむ、我が妹ながら、実に情熱的だ。京治くん、名前を泣かせたら、俺の次の新作の主人公は君になるから、覚悟しておくように」と笑顔で脅される。それはそれで少し読んでみたい気もするが、間違いなく悲劇だろう。
結論、どのパターンも回避したい。その為には、これを"誤魔化す為の"何かが必要だ。絆創膏? 不自然過ぎる。湿布? 首に? 余計に目立つ。ファンデーション? そんなもの、持っているワケがない。
思考の渦の中、名前の「わたしが付けたのに、京治くんは忘れてしまったの?」と言う声が、俺の心臓を直接掴んだ。
違う。忘れるワケがない。昨夜の、彼女の熱い吐息も、しがみ付いてきた細い指の力も、何もかも鮮明に憶えている。この痕は、彼女が俺に残してくれた、甘美な所有の証だ。それを「虫刺され」などという無粋な言葉で片付けようとした自分自身に腹が立つ。
だが、しかし。現実問題として、これをどうにかしなければならない。羞恥心と、部活での副主将としての体面。それらが彼女への愛おしさや独占欲と、頭の中で激しい試合を繰り広げている。
「だったら、どうして隠そうとするの?」
彼女のどこまでも澄んだ声が、俺の葛藤を貫いた。
そうだ。俺は何故、これを隠したいんだ? 他人の揶揄から自分を守る為? それはこの痕を付けてくれた彼女の行為を否定することにならないか?
いや、寧ろ見せ付けたいくらいの気持ちもある。苗字名前は、俺の恋人なのだと世界中に知らしめたい。だが、それを実行するには、俺はまだ青過ぎた。
「……それは、その……」
俺が言葉に詰まっていると、名前は楽しそうに笑った。その悪戯っぽい笑みを見て、腹が決まった。
もういい。誤魔化すのは止めだ。
俺は彼女の手を引いて、自分の膝の上に向かい合わせになるように座らせた。驚いて見開かれた深海のような瞳が、俺を映す。
「……名前の所為だから」
拗ねたように呟くと、自分でも驚く程に甘えた声が出た。
「え?」
「全部、名前がしたことだろう。だから、責任、取ってくれるよね?」
普段の俺なら、絶対に言わないであろう台詞がいとも容易く口から滑り落ちる。彼女の前では、俺の冷静さなど脆いガラス細工同然だ。
名前は一瞬目を丸くしたが、やがて状況を理解したのか、花が綻ぶようにふわりと微笑んだ。
「うん。勿論。どうやって責任を取ればいい?」
その問いに、俺の中にあった羞恥心という名のダムが完全に決壊した。
「……もっと、付けて」
囁くような声だった。
「隠せないくらい。誤魔化しようがないくらい。俺が、君のものだって、誰が見ても分かるように」
これはもう、ヤケクソに近い告白だ。羞恥心を通り越した、俺なりの最大の愛情表現であり、独占欲の表明だった。他人にどう見られるかなんて、もうどうでもいい。この瞬間の、目の前の彼女が全てだった。
名前の瞳が、愛おしいものを見るように優しく細められる。彼女はそっと身を乗り出すと、俺の耳元に唇を寄せた。
「うん。わたしの京治くん」
その声と同時に、昨夜とは比べ物にならないくらい、はっきりと強く、俺の首筋に彼女の唇が押し当てられた。
「これで、もう誰にも誤魔化せないね」
悪戯に成功した子供のように笑う彼女を見て、俺はもう抵抗するのをやめた。
誤魔化す為の言い訳を考えるより、彼女に愛されていると実感する方がよっぽど有意義だ。
翌日、案の定、体育館で木兎さんの絶叫が響き渡った。
「あかーし! 首、どうしたんだ!? 真っ赤だぞ!? どんな虫に集られてんだ!!」
「……ええ、まあ。昨夜、強力なのが大量発生したみたいで」
俺は平静を装ってそう答えながら、自分の首筋に刻まれた、幾つもの愛の証をそっと撫でた。
誤魔化すことを諦めた首筋は、少しだけ誇らしかった。