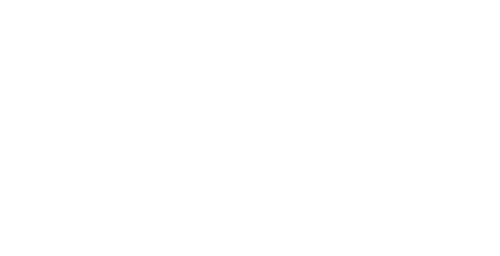※赤葦のセンスを捏造しています。
- 海と心臓と指先 -
八月の末、暦の上では、秋の気配が囁かれ始めると云うのに、アスファルトは未だ陽炎を立ち昇らせ、世界は巨大な鉄板の上でじりじりと焼かれているようだった。そんな猛暑の午後、私達は電車を乗り継ぎ、都心から離れた海辺に来ていた。
「……海は呼吸しているみたいだね」
サンダルの爪先で、寄せては返す波の縁をなぞりながら呟くと、隣を歩く京治くんが「そうだね」と静かに相槌を打った。彼の声は、真夏の太陽の下でも不思議と涼やかで、火照った耳に心地好い。
ざあ、と白波が砂を攫っていく。それは、巨大な生き物が深く息を吸い込む音のようで、潮頭は安堵の溜息に似ていた。吸って、吐いて。その一定のリズムが、心臓の鼓動と静かに共鳴する。
「大きな生き物の、お腹の中に居るみたい。私達は、プランクトンなのかもしれないね」
「……随分、壮大な話になってきたな。俺達がプランクトンだとすると、木兎さん辺りは巨大なクジラか何かなのか」
「ふふ、そうかも。時々、潮を吹いて、周りをびしょ濡れにするけれど、憎めない感じ」
「的確な分析、ありがとう。本人に伝えたら、喜びそうだ」
呆れ混じりの、どこか楽しそうな声色で、京治くんが言う。私は彼の横顔を盗み見た。黒曜石の瞳が、水平線の先を穏やかに見つめている。癖のある黒髪が、潮風にふわふわと揺れていた。バレーボールを操る、長くて綺麗な指。日に焼けたしなやかな首筋。練習時に付いたであろう、腕の小さな擦り傷。その全てをスケッチブックに描き留めたい衝動に駆られる。いつからだろう。私の描く線の練習は、いつだって彼の輪郭をなぞるようになっていた。
シートを敷いた浜辺に腰を下ろして、持参した冷たい麦茶を飲む。京治くんは、私の隣で静かに砂の城……と云うには、余りに前衛的で、立方体を組み合わせたような、奇妙なオブジェを作り始めていた。彼のこう云う独特なセンスが、私は堪らなく好きだった。
「ねぇ、京治くん」
「ん?」
「京治くんは、深海魚みたい」
「……それは、褒められてる?」
「うん。凄く褒めてる。静かで、賢くて、目が綺麗。それに、誰も知らない海の底で、たった一人、凄いことを考えている感じがするから」
私の返答に、彼は真砂を固める手をぴたりと止めた。ゆっくりとこちらを向く。その瞳からは、何を考えているのか読み取れなくて、一寸だけ不安になる。変なことを言ってしまっただろうか。人の弱味を探すのが癖になっているけれど、それはあくまで自己防衛の為で、誰かを傷付けたいわけではない。それでも、私の言葉は時々、意図しない刃を持ってしまうことがある。
「……名前」
「……うん」
「俺は、君が思っている程、一人じゃない」
静かな声音だった。だけど、その響きには、確かな熱が込められていた。京治くんは、私の手を取り、指をそっと絡める。彼の掌はバレーボールに触れることで、少し硬くなっているけれど、温かくて、大きくて、どうしようもなく安心する。
「それに、考えてることも、そんなに凄くない。最近の悩みは、もうちょっとパワーを付けたい、とか。今日の晩ご飯は何だろう、とか」
「……菜の花の辛子和え?」
「はは、よく分かったね。まあ、今は夏だから、難しいけど」
京治くんが、滅多に見せない柔らかな笑顔を浮かべる。その笑顔を見る度に、胸の奥がきゅう、と甘く締め付けられる。この人は、梟谷バレー部の副主将で、冷静沈着な司令塔で、沢山のチームメイトに囲まれて、大きな体育館の眩しいライトの下で戦っている人。私の知らない顔を、いっぱい持っている人。
ふと、心に小さな影が落ちる。
試合中の彼は、私の知らない表情をする。厳しい眼差しでコートを見渡し、0.5秒の間に膨大な情報を処理して、最適なトスを上げる。ニヤリと不敵に笑うこともあれば、苛立ちを滲ませることもある。その全てが格好良くて、誇らしくて、同時に、少しだけ寂しくなる。私の知らない世界で、京治くんは生きている。私の知らない言語で、仲間と笑い合っている。
「……私のことは、誰もちゃんと見てない」
ぽつり、と。自分でも意図しない内に、心の奥底に沈殿していた澱のような塊が、唇から零れ落ちていた。しまった、と思ったけれど、一度吐き出した言葉はもう取り消せない。京治くんの顔色が、僅かに曇ったのが分かった。
「名前?」
彼の優しい声が、却って胸に刺さる。違うの、そんなつもりじゃ。京治くんが、私をちゃんと見てくれているのは、誰よりも理解している。これは、私の昔からの、根深い臆病さだ。
夕日が、海をオレンジゴールドに染め上げていた。世界が終わってしまうのではないかと思うくらい、美しい光景だった。それなのに、私の心だけが、凪いだ海に取り残された小舟のように、心細く揺れていた。