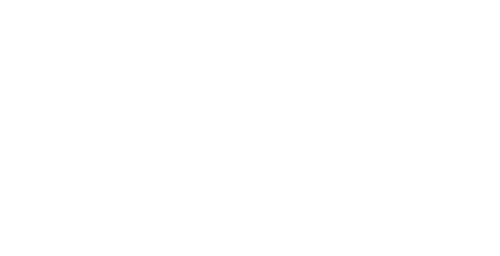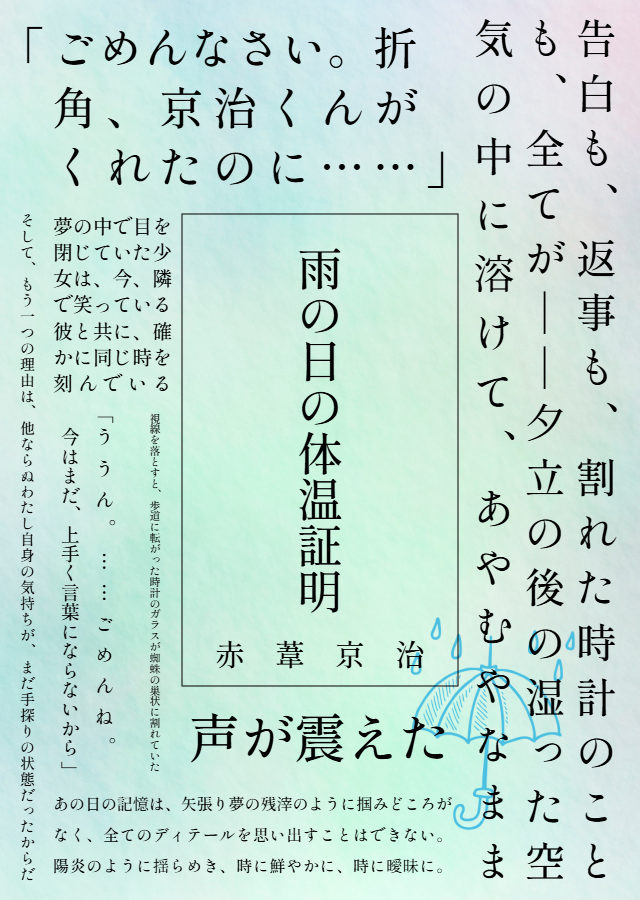
あの文化祭の午後の記憶は、まるで古い映画のフィルムみたいだ。不意に脳裏で回り出すと、焼き付くように鮮明な光を放つコマがある一方で、大部分は真夏の陽炎のように揺らめき、色も音も輪郭も溶け合って滲んでいる。都合の悪い記憶だけを選んで、無意識がフィルターを掛けているのかもしれない。それでも――あの日のわたしが何を考え、何を感じていたのか。その核心だけは、歳月を経た今だからこそ、確かな輪郭を持って掴める気がする。
文化祭最終日。体育館から漏れ聞こえる放送部の感傷的な閉会式の挨拶が、午後の気怠い空気に溶けていく中、わたしは校舎の裏手――屋上へと続く、錆びた手摺りの外階段に居た。普段は陽の当たらない、少し埃っぽいその場所に。
その少し前、教室の喧騒の中で、京治くんが「少しだけ、付き合ってくれませんか」と、真剣な眼差しで言ってきた時、わたしの心臓がどれほど跳ね上がったか。今思い出しても頬が熱くなるし、その馬鹿正直な反応に笑ってしまう。彼は、わたしが人生で初めて"ちゃんと好きになった"と自覚した相手だった。巷で言う"初恋"という、少し気恥ずかしい響きの言葉以外に、この感情を表す術をわたしは知らなかった。
階段の踊り場。そこは校舎の影になり、祭りの熱気から切り離されたような静寂が支配していた。彼が制服のポケットからそっと取り出したのは、鈍い銀色の光を放つ懐中時計だった。手のひらに乗せられた瞬間、ずしりとした重みと、ひんやりとした金属の感触が伝わってきた。それがただ時を刻むだけの道具ではない、特別な意味を孕んだものであることを、わたしは言葉もなく察していた。
表面には、誰かの手で慈しむように磨かれたであろう滑らかな光沢があり、縁には細く優雅なリボンが通されている。そして、蓋の内側には――息を呑んだ――小さな便箋が、まるで秘密を隠すように一枚、折り畳まれて挟まっていた。
けれど――わたしはその手紙を、その場で開くことができなかった。
理由は、幾つかあった。
一つは、どうしようもなく、怖かったからだ。
この人の"本当の気持ち"が、飾りのない言葉として、この薄い紙の上に凝縮されているのだと悟った瞬間、わたしは心の内側を全て剥き出しにして、強い光の下に立たされるような、途方もない羞恥と恐怖に襲われた。いつもは冷静沈着で、けれど時折、ふとした瞬間に子供のような不器用さを見せる彼が、一体、どんな言葉でわたしという存在を捉え、見つめてくれていたのか――それを知るのが、怖くて堪らなかったのだ。
そして、もう一つの理由は、他ならぬわたし自身の気持ちが、まだ手探りの状態だったからだ。
彼が好きだった。それは確かだ。
優しくて、どこまでも真面目で、時々、意地悪く揶揄ってみたくなるくらい生真面目で可愛いところもあって。
けれど、その想いは、指の間からすり抜けていく煙のように実体がなく、ふわふわと漂っているばかりで、まだ「付き合ってください」という言葉に、迷いなく頷ける程の確信にはなっていなかったのだ。
「はい」とも「いいえ」とも言えず、わたしはただ、彼の想いが託されたであろう時計を、そっと両手で包み込むことしかできなかった。冷たい筈の金属が、わたしの手のひらの中で少しずつ熱を帯びていくような気がした。
「……返事、聞いてもいいですか?」
彼の声が、午後の気怠い光の中に、静かに、けれど確かに響いた。期待と不安が入り混じったような、微かな震えを帯びて。
耳の奥がじんと熱くなり、わたしは息を呑んだまま、返すべき言葉を探した。けれど、喉の奥でつかえて、どうしても形にならなかった。ただ、心臓の音がやけに大きく聞こえるだけだった。
「ううん。……ごめんね。今はまだ、上手く言葉にならないから」
あれは嘘偽りのない本心だった。本当に、言葉にできなかったのだ。
けれど同時に――あれは、彼の差し出してくれた勇気を踏み躙るような、残酷な響きを持った言葉でもあったのだと思う。彼の表情が一瞬、翳ったのを、わたしは見ない振りをした。
そして、帰り道。わたし達の曖昧な心模様を映すかのように、空気を冷やしながら夕立が降り出した。アスファルトを叩く雨音だけが響く中、事件は起きた。開きっぱなしだった鞄の口から、あの銀色の懐中時計が滑り落ちる瞬間が、今でもスローモーションのように再生される。
"カシャン"――硬質で、どこか絶望的な響きを伴った音。
視線を落とすと、歩道に転がった時計のガラスが蜘蛛の巣状に割れていた。容赦なく降り注ぐ雨粒が、その傷口を濡らしていく。
「ごめんなさい。折角、京治くんがくれたのに……」
声が震えた。雨に濡れながら、それを拾い上げた彼の指先が微かに揺らいでいたのを、見ない振りはできなかった。その揺らぎが、わたしの胸を締め付けた。
わたしは、矢張り怖かったのだ。もし、あの場で軽率に「はい」と答えてしまっていたら、自分の心がその一言に追いつけなくなるのではないか、という確信めいた予感が。いつか、この時計のように、わたし達の関係も壊れてしまうのではないかと。だから、わたしは――あの瞬間、夢の中で危険から目を逸らすように、答えることから逃げてしまった。
けれど、そんな不誠実なわたしを、京治くんは責めなかった。
ただ、雨に打たれ、ずぶ濡れになりながら、わたしの手をそっと握ってくれた。その濡れた手のひらの温かさと、伝わってくる微かな震え。わたしはそれに気づかない振りをした。彼の優しさが、余計にわたしの罪悪感を抉った。
そして、その日、全ては曖昧なまま終わった。
告白も、返事も、割れた時計のことも、全てが――夕立の後の湿った空気の中に溶けて、あやむやなまま。
けれど、あの夜、一人きりになった自室の静寂の中で、わたしは時計の蓋の内側からそっと便箋を取り出した。指先に触れる、薄く、けれど確かな存在感。インクの匂いが微かにした。
『好きです。多分、ずっと前から。
でも、この気持ちを言葉にしようとすると、なんだか輪郭がぼやけて、大切なものが全部、零れ落ちてしまいそうだから。
代わりに、これに俺の"時間"を預けます。
いつか、貴方の時間と、静かに重なってくれるといい。』
涙は流れなかった。けれど、心の奥深くで、何かが静かに、しかしはっきりと"カチリ"と音を立てて嵌まったような感覚があった。止まっていた歯車が、ゆっくりと動き出すような。
この人と――きっと、わたしはこれから先の時間を、一緒に過ごしていくのだろう。そう、強く思った。
返事は結局、あの時には伝えられなかった。
けれど、わたしはあの手紙を読んだ瞬間、確かに心を決めたのだ。
「そういえば、読んだんですか、あの時の手紙」
数年後。夫婦になったわたし達が、デリバリーピザの湯気が立ち上るダイニングで、他愛ない話をしている時、彼がふと、そんなことを問い掛けた。香ばしいチーズの匂いの中で。
わたしは一瞬、遠い日の文化祭の光景に目を細め、それから悪戯っぽく肩を竦めてみせた。
「さぁ、どうだったかな。あれは、わたしの中でも、まだちょっと"あやむや"なままの、秘密の領域なんだよ」
そう言いながら、あの日と同じように、ただ目の前の現実――今は伸びるチーズの糸――を見つめる。
彼が少し残念そうな、それでいてどこか嬉しそうな複雑な表情をしているのを見て、わたしはそっと付け加える。
「でも、今、こうして京治くんと夫婦になって、一緒にピザを食べているということは……多分、ちゃんと読んだということでしょう?」
彼は小さく頷き、眼鏡のブリッジを指で押し上げて、柔らかく笑った。あの頃と変わらない、優しい笑顔で。
あの日の記憶は、矢張り夢の残滓のように掴みどころがなく、全てのディテールを思い出すことはできない。陽炎のように揺らめき、時に鮮やかに、時に曖昧に。
でも、わたし達は確かにあの階段の踊り場から、あの雨の帰り道から、一歩を踏み出したのだ。
夢の中で目を閉じていた少女は、今、隣で笑っている彼と共に、確かに同じ時を刻んでいる。
そして、あの時、割れてしまった懐中時計は――ガラスの傷跡もそのままに、今はわたし達のダイニングテーブルの上で、これから先も続いていく二人の未来を、静かに、確かに見守り続けている。