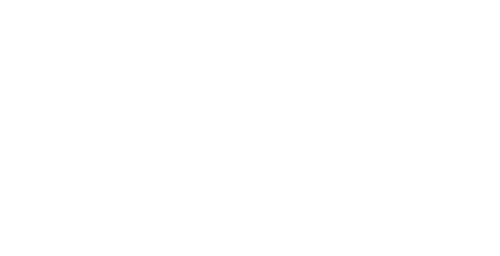ピザの箱を片付けた後のキッチンには、まだ確かな温もりの残り香が漂っていた。チーズと、少しだけ焦げた生地の匂い。満たされた胃の心地よさが、部屋の空気そのものに溶け込んでいるようだった。
窓の外では、巨大な生き物のように息衝く都会の夜が、更にその深さを増していく。家路を急ぐ車のテールランプが遠ざかり、高層ビルの窓の灯りが、瞬きながら一つ、また一つと闇に吸い込まれていく。その静かな消失を眺めていると、世界から切り離されたような、不思議な安堵感があった。
ダイニングテーブルの上では、ガラスに罅の入った懐中時計が、かすかな音を立てて時を刻み続けている。チク、タク、チク、タク……。それだけが、流転する時間の法則から取り残された孤島の住人のように、律儀に、そして頑固に"今"この瞬間を告げているのだった。壊れているのに動き続けるその姿は、どこか痛々しく、同時に強い意志を持っているようにも見えた。
「お風呂、先にどうぞ」
不意に掛けられた声に、窓の外へ向いていた意識が引き戻される。京治くんはそう言って、わたしの使い終えた皿をシンクで洗いながら、濡れた手で器用に蛇口を捻り、ちらりとこちらを振り返った。水の跳ねる音と、彼の穏やかな声が、静かな空間に優しく響く。
眼鏡のレンズ越しに見える、彼の横顔。少し伏せられた睫毛、真剣な眼差しで皿の汚れを見つめる時の、きゅっと結ばれた唇。それはいつだって変わらず優しく、そして、他の誰にも見せない、わたしだけの知る、わたしの最も好きな表情だった。
わたしは小さく頷いて、音を立てないように椅子から立ち上がる。床を踏むカーペットの柔らかな感触。バスルームへ向かう短い廊下を歩きながら、ふと、背中に彼の視線を感じた気がした。見ているわけではないのかもしれない。けれど、わたしの動きを、気配を、彼がいつも意識してくれていることは知っている。その事実に気づいて、自然と口元が緩んだ。くすりと、小さな笑い声が漏れる。
――この人は、本当に変わらない。
出会った頃からずっと、わたしという存在を丸ごと尊重し、繊細なガラス細工でも扱うかのように、丁寧に、大切に扱ってくれる。
それが堪らなく嬉しくて、胸の奥が温かくなる。それと同時に、時折、ほんの少しだけ、その完璧な優しさを揺らしてみたくなる。意地悪、と言うには可愛らしい、ささやかな悪戯心がむくむくと顔を出すのだ。
湯船にゆっくりと身を沈めると、じんわりと熱が身体の芯まで染み渡っていく。浴室に満ちる湯気は現実の輪郭を曖昧に暈し、思考を自由にした。目を閉じれば、自然と思い出すのは、あの文化祭の、雨に煙る午後のこと。
古びた外階段の湿った空気の中で交わされた、告白とも、返事ともつかない、曖昧な言葉達。濡れた制服の冷たさと、高鳴る心臓の熱さが混じり合った、鮮烈な記憶。
それでも、あの夜、震える指で開いた彼からの手紙を読んで――便箋の向こうの言葉にならない想いを確かに受け取って――わたしは、はっきりと"心を決めた"のだった。
あの時、未来への不安と期待の中で、ぎゅっと目を閉じていた少女は、今、ここに居る。
不確かだった想いは、いつしか温かく、確かな愛の形を成して、この両手に収まっている。彼と同じ部屋の空気を吸い、同じ食卓を囲み、そして、同じ未来の景色を見つめている。それは、あの日のわたしには想像もできなかった、奇跡のような現実だ。
風呂上がり、まだほんのり湿った肌にネグリジェを纏い、脱衣所からリビングへと戻る。柔らかな間接照明が照らす空間で、京治くんはソファに深く腰を下ろし、静かに本を読んでいた。ページを繰る指先の動きが、夜の静寂に溶け込んでいる。
けれど、わたしの足音、或いは気配に気づいたのだろう、彼はすぐに本から顔を上げた。眼鏡の奥の切れ長の目元が、ふわりと優しく緩む。その一瞬の変化を見逃さなかったことに、小さな達成感を覚えた。
「……ずっと見られていると照れますよ」
少し困ったような、それでいて嬉しそうな響きを含んだ声で、彼は言った。そして、読んでいたページに栞を挟み、ぱたりと本を閉じた。その一連の動作が余りにも自然で、優しくて、わたしの心臓を不意打ちのように掴む。じわりと胸が熱くなる。
「見ていたいんだよ、京治くんのこと」
わたしはソファに近づきながら、素直な言葉を口にした。
「きっと、わたしはあの文化祭の日から、ずっとずっと、貴方のことを見続けているんだと思う」
わたしの言葉に、彼の眉がほんの僅かに、ぴくりと動いた。
自分の感情を表に出すことを良しとしない彼が、それでも隠し切れずに、こうして偶に見せてくれる"動揺"の欠片が、どうしようもなく愛しくて堪らなくなる。
「……あの日から、ですか」
彼の声は、僅かに掠れていた。
「うん。わたし、あの時……京治くんのことばかり考えながら、夢の中みたいに目を閉じた。でもね、今は違うの」
わたしは彼の隣に腰を下ろし、その瞳を真っ直ぐに見つめた。
「今は――目を開けたら、いつも隣に京治くんが居るんだ。……それが、わたしにとっては、他のどんなものにも代えられない、一番の幸せ」
言葉が、ぽろりと零れ落ちた後、しんとした沈黙がリビングを満たした。
けれど、その沈黙は少しも気まずくなく、寧ろ心地よい。夜の深い静寂を優しく包み込む、柔らかな毛布のように、わたしたち二人をそっとくるんでいた。
次の瞬間、ソファからすっと立ち上がった京治くんが、迷いのない足取りで、わたしの目の前に立った。そして、そっとわたしの髪糸に指を添えた。まだ少し湿り気を帯びた髪の一房を掬い上げ、慈しむように耳の後ろに掻き上げる。壊れ物に触れるかのように、彼の指先は驚くほど丁寧に、わたしの肌を滑った。
「……名前」
低く、囁くように名前を呼ばれるだけで、胸の奥が甘く、きゅうっと締め付けられるように揺れる。
彼の手が、わたしの頬をそっと包み込み、親指が顎のラインを優しく撫でた。
その眼差しは深く、吸い込まれそうだった。
唇と唇が触れ合うまでの一瞬が、スローモーションのように、永遠にも似て長く感じられた。
そして、遂に触れ合った瞬間――わたしの呼吸が、すうっと深く、そして少しだけ重くなった。
キスは最初、触れるだけの淡雪のようだった。けれど、すぐに確かな熱を帯び始めた。
優しく、けれど疑いようのない確かな意思を持って、わたしの唇を、気持ちを、存在そのものを、丸ごと包み込もうとしてくる。彼の体温が、熱が、わたしの中に流れ込んでくるようだった。
いつからだろう。
この人の触れる温度が、この人の与えてくれる温もりが、わたしの世界の絶対的な基準になったのは。
リビングのオレンジ色の灯りが、ふっと落とされる。彼が壁のスイッチに手を伸ばしたのだろう。
窓の向こうでは、あれほど煌めいていたビル群の灯りも、今はもう疎らになり、世界全体が深い静寂に包まれていく時間だった。
その夜――わたし達は多くを語らなかった。
言葉はもう必要なかった。
ただ、触れ合いの中で、視線の交錯の中で、繰り返されるキスの中で、確かに互いの想いを伝え合い、重ね合った。
ずっと目を閉じて見ていた、あの文化祭の日の夢の続きを、今、この確かな現実の中で、二人で見ていた。
眠りに落ちる直前、ベッドの中で彼の広い背中にぴったりと身を預けながら、その温もりを感じていると、彼が小さく耳元で囁いた。
「……名前さん。今も、あの懐中時計は動いていますよ」
今はサイドテーブルの上に置かれている、あの時計のことだ。
「うん、知っている。……わたし達の時間が止まらなかった、ううん、止まらないっていう証拠」
壊れていても、傷付いていても、それでも進み続ける時間。わたし達が共に歩んでいく未来の象徴のように思えた。
その言葉を最後に、わたしは満たされた気持ちで、そっと目を閉じた。彼の規則正しい寝息が心地よい子守唄になった。
――目を開けたら、朝だった。
カーテンの隙間から、新しい一日を告げる柔らかな陽光が射し込み、白いシーツの上に淡い光の模様を描き出している。部屋の空気は澄みきっていて、清々しい。
隣では、京治くんが穏やかな寝息を立てて、まだ深い眠りの中に居た。規則正しい呼吸に合わせて、肩が小さく上下している。
彼の眼鏡はサイドテーブルの上に、昨夜と同じように丁寧に置かれていた。そして、そのすぐ横には、あの懐中時計が変わらないリズムで、静かに、しかし、正確に新しい朝の時を刻み続けていた。
わたしはゆっくりと身を起こし、彼の眠りを妨げないように、そっとその時計に手を伸ばした。
ひんやりとした金属の感触が指先に伝わる。それは、あの文化祭の日、不安の中で触れた時と同じ冷たさだった。
でも、今はもう、少しも怖くない。
この時計が刻む一秒一秒が、この人と一緒に見る夢の続きなのだから。そして、その夢はこれから何度でも――こうして穏やかな朝を迎えていくのだと確信していた。わたし達は壊れた時計が刻むように、不完全でも、確かに未来へと歩んでいく。