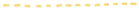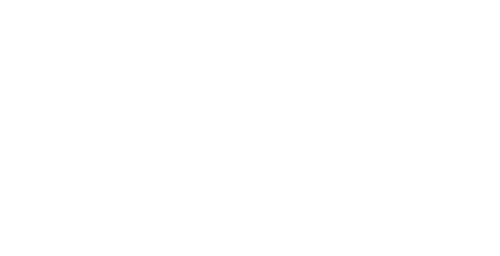あの文化祭の日のこと――正確には、あの日の午後の、或る一連の出来事について、実は、俺は今でも、全てを鮮明な輪郭で思い出すことはできない。
記憶というのは厄介なもので、忘れたいことは妙に生々しく、大切にしたい瞬間ほど、まるで陽炎のように揺らめいて、掴もうとすると指の間からすり抜けていってしまう。
それでも、断片は残っている。網膜に焼き付いた、幾つかのスナップショットのように。
校舎全体を包み込んでいた、どこか浮かれた祭囃子にも似た喧騒の響き。ソースと油が混じり合い、甘く香ばしく鼻腔を擽った、模擬店の焼きそばの匂い。そして、何故かやけに印象に残っている、クラスの出し物の看板を直していた木兎さんが、楽しげに笑いながら制服の袖にべったりとペンキを付けていた、あの顔。
そして――あの時の、名前の横顔。
ついさっきまで抜けるように晴れていた筈の空が、薄墨を流したように、見る見るうちに灰色に染まり掛けていた、あの午後の、湿り気を帯びた空気の中で。
文化祭の最終日。閉会式も終わり、後片付けが始まる前の、妙に感傷的で、それでいてどこか弛緩した時間。
俺は、ブレザーの内ポケットに忍ばせた小さな硬い感触を、何度も指先で確かめていた。懐中時計。それを、今日、彼女に渡すと決めていた。
元々、彼女が小さくて精巧な古いものが好きだと知っていたから。偶然にも、俺の父が若い頃に使っていたという銀の懐中時計が、家の引き出しの奥で眠っているのを見つけたのは、幸運だったのかもしれない。ずっしりとした重みと、細やかな装飾。それを時間を掛けて磨き上げ、アンティークショップで見つけた細いシルクのリボンを通した。そして、そっと蓋を開け、その裏側に折り畳んだ小さな便箋を滑り込ませた。
『好きです。多分、ずっと前から。
でも、この気持ちを言葉にしようとすると、なんだか輪郭がぼやけて、大切なものが全部、零れ落ちてしまいそうだから。
代わりに、これに俺の"時間"を預けます。
いつか、貴方の時間と、静かに重なってくれるといい』
……今読み返せば、顔から火が出るほど中二病じみた、気障な文章だと自覚している。赤面せずにはいられない。
けれど、高校生の、不器用な俺にとっては、あれが精一杯の表現だったのだ。それ以上に"確か"で、自分の気持ちにしっくり来る言葉が、どうしても見つけられなかった。
苗字名前という存在は、俺にとって、どうにか言葉の網で捕まえようとしても、いつもするりと抜け落ちてしまう、定義できない何かだった。
彼女は、手のひらに掬った水のようだった。光を受けてきらきらと輝き、指の隙間を静かに流れ落ちていく。触れようとすれば形を変え、掴もうとすれば、ただ濡れた感触だけを残して消えてしまう。そんな、捉えどころのない、けれど抗い難い魅力を持っていた。
それでも、その日――俺は、ありったけの勇気を振り絞って、「付き合ってください」という、月並みで、けれど最も直接的な言葉と共に、その懐中時計を彼女の手に渡したのだ。
場所は、確か美術室の裏手にある、古びた外階段だったと思う。
屋上へと続いているが、普段は殆ど誰も使わない、ひっそりとした場所。壁に貼られていた手作りの装飾は既に取り払われ、祭りの後の気怠い静けさが漂っていた。コンクリートの壁には、色褪せた文化祭のポスターが数枚残っていて、吹き抜ける夕方の風に、その端をぱたぱたと頼りなく揺らしていた。日常へと戻る準備を始めた校舎は、どこか寂しげに見えた。
「これは、何?」
小さな銀色の塊を受け取った名前は、不思議そうに小首を傾げ、それからゆっくりと、繊細な動きで蓋を開けた。
中の手紙を読んだのかどうか。それは、俺には分からなかった。彼女の表情は、いつものように淡く、凪いだ湖面のようで、感情の揺らぎを読み取ることは難しい。ただ、受け取った時計を、壊れ物を扱うように、そっと両手で包み込むように抱えた。その仕草が、やけに印象に残っている。
「……返事、聞いてもいいですか?」
絞り出すように、そう訊ねた俺の声は、自分でも驚くほど上擦っていた。心臓が、耳元で鳴っているかのように煩い。
名前はほんの少しだけ、長い睫毛を伏せて、それからふわりと、困ったような、それでいて優しいような、曖昧な微笑みを浮かべた。
「ううん。……ごめんね。今はまだ、上手く言葉にならないから」
多分、あれが――俺の初恋の、着地点だったのだろう。明確な答えのない、どこか宙ぶらりんで、あやむやな結末。喜びでもなく、悲しみでもない、ただ、胸の中にぽっかりと空いたような、奇妙な感覚だけが残った。
そして、その帰り道のことだ。俺達の心情を映すかのように、空は本格的に泣き出し、激しい夕立が降り始めた。
駅までの道を歩きながら、俺は自分の折り畳み傘を無理矢理彼女に押し付け、自分は走って帰ろうとした。その時だった。名前が、咄嗟に俺の濡れたブレザーの袖を掴んで、引き止めたのだ。
「……傘、いいよ。わたし、京治くんとなら、濡れても平気だから」
雨音に混じって聞こえたその言葉は、あの時の彼女なりの"返事"だったのかもしれない。そうであってほしい、と願った。
けれど、俺にはそれを聞き返す勇気はなかった。言葉で確認してしまえば、この壊れそうなほど繊細で、曖昧なままの優しさが、ガラス細工のように粉々に砕けてしまいそうで、怖かったのだ。
その、直後だった。
開いていた彼女の通学鞄の口から、あの懐中時計が滑り落ちたのは。
アスファルトに叩き付けられる、カシャン、という鋭く、乾いた音。俺の心臓が、嫌な音を立てて跳ねた。
反射的に拾い上げた時計の蓋には、衝撃の中心から放射状に、蜘蛛の巣のような亀裂が無数に走っていた。銀色の表面にも、痛々しい傷が刻まれている。
「……ごめんなさい。折角、京治くんがくれたのに……」
雨に打たれながら、名前が本当に申し訳なさそうに、小さな声で呟いた。その声が、雨音に掻き消されそうに儚かった。
俺は、ただ黙って首を横に振ることしかできなかった。どんな言葉も、喉の奥でつかえて出てこなかった。
傷付いたのは、果たしてこの懐中時計だけだったのだろうか。それとも、この時計に託した俺の不器用な気持ちそのものだったのか。その判断すら、つかなかった。ただ、目の前の現実が、やけに重く感じられた。
けれど、その日、俺達はどちらからともなく手を繋ぎ、激しい雨に打たれながら、びしょ濡れになって駅までの道を歩いた。傘は、どちらも差さなかった。
そして結局、肝心なことは何一つはっきりさせないまま、告白も、返事も、壊れた時計のことも、全てが雨に流されるように、あやむやで、曖昧なまま、その日はお終いになったのだ。
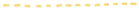 けれど、今となっては、それで良かったのだと、心からそう思う。
あの日の割れた懐中時計は、今も俺達の家のダイニングテーブルの上で、他のどんな置物よりも確かな存在感を放ちながら、静かに時を刻んでいる。
蓋のガラスは、あの日と変わらず、痛々しい亀裂が入ったままだし、俺が選んだシルクのリボンも、少し色褪せて、草臥れている。
けれど、その心臓部であるムーブメントは、驚くほど正確に、そしてどこか頑固なまでに、一日も休むことなく時を刻み続けているのだ。あの日の出来事など、些細なことだと言わんばかりに。
そして、蓋の裏に仕込んだあの手紙は、今もまだ、そこに挟まれたままだ。
名前がそれを読んだのか、読んでいないのか。俺は、未だにその答えを知らないし、彼女も教えてはくれない。
「そういえば、読んだんですか、あの時の手紙」
届けられたピザを頬張りながら、ふと長年の疑問を口にしてみると、名前は一切れを持ち上げたまま、一瞬だけ遠い目をして考え込み、それから悪戯っぽく肩を竦めて答えた。
「さぁ、どうだったかな。あれは、わたしの中でも、まだちょっと"あやむや"なままの、秘密の領域なんだよ」
「……そうですか」
俺が少しだけ残念そうな顔をしたのを見て取ったのか、名前はチーズを伸ばしながら、ふふ、と笑う。
「でも、今、こうして京治くんと夫婦になって、一緒にピザを食べているということは……多分、ちゃんと読んだということでしょう?」
「……まあ、そうでしょうね。そうでなければ、辻褄が合いません」
二人で顔を見合わせて、どちらからともなく笑い声が零れた。
もう、それでいいのだ。明確な"答え"なんて、なくてもいい。過去の全ての疑問に、白黒つける必要なんてないのかもしれない。
何よりも大事なのは、"それでも俺達は、止まることなく、今日まで一緒に歩んできた"という、揺るぎない事実なのだから。
ガラスが割れても。
言葉にできなくても。
全てがあやふやで、輪郭のぼやけた、曖昧な記憶のままでも――時間は止まることなく流れ続け、想いは確かに繋がり、育まれていった。
その何よりの証として、あの日の割れた懐中時計は、今も――俺達のすぐ傍で、過去と現在、そして未来へと続く時間を、確かに、静かに、刻み続けている。
けれど、今となっては、それで良かったのだと、心からそう思う。
あの日の割れた懐中時計は、今も俺達の家のダイニングテーブルの上で、他のどんな置物よりも確かな存在感を放ちながら、静かに時を刻んでいる。
蓋のガラスは、あの日と変わらず、痛々しい亀裂が入ったままだし、俺が選んだシルクのリボンも、少し色褪せて、草臥れている。
けれど、その心臓部であるムーブメントは、驚くほど正確に、そしてどこか頑固なまでに、一日も休むことなく時を刻み続けているのだ。あの日の出来事など、些細なことだと言わんばかりに。
そして、蓋の裏に仕込んだあの手紙は、今もまだ、そこに挟まれたままだ。
名前がそれを読んだのか、読んでいないのか。俺は、未だにその答えを知らないし、彼女も教えてはくれない。
「そういえば、読んだんですか、あの時の手紙」
届けられたピザを頬張りながら、ふと長年の疑問を口にしてみると、名前は一切れを持ち上げたまま、一瞬だけ遠い目をして考え込み、それから悪戯っぽく肩を竦めて答えた。
「さぁ、どうだったかな。あれは、わたしの中でも、まだちょっと"あやむや"なままの、秘密の領域なんだよ」
「……そうですか」
俺が少しだけ残念そうな顔をしたのを見て取ったのか、名前はチーズを伸ばしながら、ふふ、と笑う。
「でも、今、こうして京治くんと夫婦になって、一緒にピザを食べているということは……多分、ちゃんと読んだということでしょう?」
「……まあ、そうでしょうね。そうでなければ、辻褄が合いません」
二人で顔を見合わせて、どちらからともなく笑い声が零れた。
もう、それでいいのだ。明確な"答え"なんて、なくてもいい。過去の全ての疑問に、白黒つける必要なんてないのかもしれない。
何よりも大事なのは、"それでも俺達は、止まることなく、今日まで一緒に歩んできた"という、揺るぎない事実なのだから。
ガラスが割れても。
言葉にできなくても。
全てがあやふやで、輪郭のぼやけた、曖昧な記憶のままでも――時間は止まることなく流れ続け、想いは確かに繋がり、育まれていった。
その何よりの証として、あの日の割れた懐中時計は、今も――俺達のすぐ傍で、過去と現在、そして未来へと続く時間を、確かに、静かに、刻み続けている。