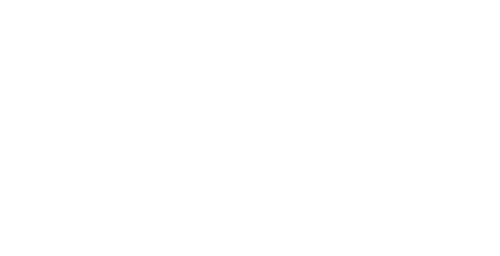ピザが届いたのは、思いのほか早かった。チャイムが鳴るまでの、あの独特の期待感に満ちた静寂は、呆気なく破られた。
箱を受け取り、温もりが残るそれをダイニングへ運ぶ。途端に、濃厚なチーズの匂いと食欲を掻き立てるガーリックの香りが解き放たれ、部屋の空気が一瞬にして弛緩する。まるで、「今夜は全ての鎧を脱ぎ捨て、心ゆくまでだらけてもいいのだ」と、空間そのものが囁き掛けてくるようで、甘美な許可が下りたかのようだ。
デリバリー特有の、少し歪んだ段ボールの箱を開けると、湯気と共に現れたピザは、トッピングのサラミやピーマンが片側へ雪崩を起こしていた。けれど、その不完全さが、不思議と俺の心を和ませる。完璧に整えられた料理よりも、こうして少し崩れている方が、どこか不器用で、それでも愛しい俺達の関係そのものを映しているようで、妙にしっくり来るのだ。
「ねぇ、見て。京治くん。このチーズ、どこまでも伸びて、なかなか切れてくれない」
テーブルの向こうで、名前が一切れを持ち上げたまま、小首を僅かに傾けている。その真剣な眼差しは、空中に引かれた黄金色の糸――チーズの運命――を、静かに見守る古代の司祭のようだ。厳粛さすら漂うその横顔に、俺は堪え切れずに噴き出しそうになるのを、必死で飲み込んだ。
「名前さん、それは……ピザという食べ物の、或る種の宿命みたいなものですよ」
「そうなんだ。……これはもう、断ち切られる運命じゃなかったんだね。……ふふ、わたしと京治くんの縁みたい」
そう言って、悪戯っぽく笑う名前。その突拍子もない、けれど彼女らしい発想に、俺は一瞬言葉を失う。けれど、すぐに温かいものが胸の奥から込み上げてくるのを感じた。
"わたしと京治くんの縁"
言葉にしてしまえば、それはありふれた比喩に過ぎないのかもしれない。それでも、俺達の間には、確かに幾度ものすれ違いと、その度に互いへと伸ばされた不器用な手があった。遠回りをして、時に傷付きながらも手繰り寄せたその縁が、今、"夫婦"という確かな形を結んでいる。その事実を噛み締める度、陽だまりに居るかのような、穏やかな幸福感に包まれるのだ。
「ところで、京治くん。さっきね、引き出しの奥を整理していたら、こんなものが出てきた」
名前は、ピザの油で指先を艶やかに光らせながらも、それを丁寧にナプキンで拭うと、テーブルの隅にそっと小さな布包みを置いた。年代を感じさせる、少し色褪せた更紗の布だ。
彼女がその結び目を解き、中身が現れた瞬間、俺は思わず息を飲んだ。
そこにあったのは、割れた懐中時計だった。
古びた銀製のそれは、長い年月を経た証として、表面に細かな傷が無数に刻まれている。蓋を覆うガラスは、右下の部分が衝撃の中心だったのだろう、蜘蛛の巣状に繊細な亀裂が走り、痛々しい。
だが、目を凝らせば、秒針は――音こそ立てないものの、静かに、しかし揺るぎない意志を持って、"時"を刻み続けていた。
「これ、憶えている? 高校生の頃。あの忘れられない文化祭の後、わたしが落として割ってしまったもの」
「……憶えています。俺が、初めて名前さんにプレゼントした、あの日の帰り道ですよね。確か、急に激しい夕立が降ってきて……」
「うん。あっと言う間にびしょ濡れになった制服のわたしに、京治くんが自分の傘を差し出してくれて。でも、慌てていたから、わたしの鞄の口が開いていて……地面に落ちて、カシャン、って、嫌な音がした」
俺は、懐中時計の文字盤の上を滑るように進む秒針を、暫くの間、黙って見つめていた。
決して美しい状態ではない。寧ろ、傷付き、一部は砕けている。しかし、その心臓部であるムーブメントは、あの日の衝撃を乗り越え、今もなお動き続けているのだ。
どこか不格好で、痛みを抱えたその姿が、あの頃の未熟だった俺達自身と重なる気がした。ぶつかり合い、傷付け合いながらも、確かに育んでいた互いへの気持ち。その、不器用だけれど真摯だった想いを、この時計は今も静かに刻み続けてくれているのではないか。そんな気がした。
「なんで、急にこれを?」
「ねぇ、京治くん。これって、なんだか凄く、わたし達そのものみたいだと思わない?」
「と言うと?」
「だって、少し不器用で、完璧に綺麗じゃなくて、ちょっとだけ……ううん、結構、壊れている部分もある。でも、決して止まらない。止まるどころか、ほら、今もちゃんと動いているでしょう? ……そういうところが、わたし達に似ているなって」
名前の声は、夜の静寂に溶け込むように、とても穏やかだった。
部屋を満たすピザの香ばしい匂いの中に、ふと、あの日の湿った土と雨の匂いが、幻のように混ざり合った気がした。
「わたし、時々思うの。もし、あの時、あの懐中時計が完全に壊れて、動かなくなっていたら、もしかしたら、何かが少しずつ違っていたのかもしれないって。だけど、現実は違った。あれからわたし達は、色々なことがあったけれど、ちゃんと今日まで、一緒に時間を重ねることができた。止まらなかった。壊れても、動き続けていた。……わたし達が歩んできた時間も、きっと、そうなんだと思う」
胸の奥が、じんわりと熱を帯びて痛む。
けれど、その痛みは不思議なほど優しく、寧ろ愛おしさすら感じさせるものだった。過去の切なさも、今の幸せも、全てが溶け合って胸を満たす感覚。
「……名前さん」
「なに?」
「俺は、この先、俺達の間に何が起ころうとも、この時計のように時を止めない自信があります。例え、また何かにぶつかって傷付いたり、少し形が変わってしまったりしても、二人で居る限り、ずっと進み続ける。……それが、"俺達"の時間なんだと、そう思っていますから」
「うん。……わたしも、そう思っているよ、京治くん」
そう言って、名前は椅子を少し引き、俺の方へそっと身を寄せた。肩が触れ合う距離。彼女の体温が、温かく伝わってくる。
リビングの柔らかな照明が、テーブルに置かれた懐中時計の割れたガラスに反射し、乱反射した光が緩やかな模様を描き出す。それは、傷付きながらも続いていく、俺達の未来を照らす、ささやかな灯火のようだった。
「……ねぇ、京治くん。ピザ、そろそろ冷めてしまうよ」
「それは大変だ。冷たいチーズは、時に運命をも断ち切ると言いますからね」
「ふふ、なんだか名言っぽい響き」
「でしょう? どこかの偉い哲学者が言っていた気がします」
「多分、それは、京治くん」
どちらからともなく笑い声が零れ、俺達は再びピザへと手を伸ばした。少し冷め始めたチーズは、先程よりも幾分か素直に切れたけれど、その温もりはまだ充分に残っていた。
今日のこの何気ない会話の中に、明日への不安や迷いは、一欠けらも存在しなかった。
ただ、静かに時を刻み続ける"割れた懐中時計"と、それを囲む穏やかな二人の時間だけが、満ち足りた空気としてそこにあった。
そして、俺は確信している。
この小さな、傷付いた時計の針が止まらない限り、俺達の未来もまた、決して――止まることはないのだと。雨の日も、晴れの日も、こうして隣で、同じ時を刻み続けていくのだと。