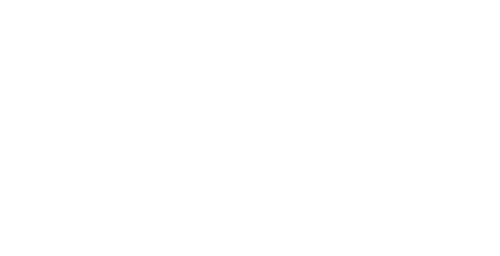会社からの帰り道、ひときわ喧騒の増す金曜日の駅ビル。その地下フロアの一角で、俺――赤葦京治は、思わず足を止めた。目に飛び込んできたのは、凡そ現実味のないキャッチコピーと、それに輪を掛けて奇妙な商品だった。"折り畳み式ハイヒール"なるものが、スポットライトを浴びて鎮座している。
何を言っているのか分からないかもしれないが、俺も最初、自分の目を疑った。ショーケースの中には、手のひらに収まる程コンパクトに折り畳まれた、鮮やかな色のヒール。その傍らのポップには、妙に力の入ったゴシック体でこう謳われている。
『働く女性の救世主! 折り畳んでスマートにポケットへIN! どんな突如の戦場にも即応可能!』
戦場、とは一体、どこのことだ。緊迫した会議室か、それとも神経を摩り減らす取引先との交渉の場か。そして何より、ポケットにハイヒールが収まったところで、それを一体いつ、どのようにして履き替えるというのか。疑問は雪だるま式に膨らんでいく。その非現実的な佇まいは、まるで現代社会が生み出したシュールな寓話のようだ。
しかし、そんな数々の疑問を置き去りにして、俺は殆ど衝動的にその商品を購入していた。理由は、ただ一つ。
――きっと、名前がこれを面白がるだろう、と。
俺の妻である彼女は、どこか風変わりなもの、日常の理から少しだけはみ出したような事象に心惹かれる性質がある。言葉の端々に、ふと意表を突くような棘を潜ませたり、感情の繊細な揺らぎを、ただ一瞥の視線だけで表現してみせたり。そういう、掴みどころがなく、どこか詩的な危うさを孕んだ一面が、俺には抗い難いほど魅力的に映るのだ。
それと同時に、彼女は日常に潜む些細な"滑稽さ"や"歪み"を見つけ出す天才でもある。だから、俺は期待せずにはいられなかった。この珍妙極まりない"折り畳み式ハイヒール"という存在が、彼女の豊かな想像力にどのような火を灯すのか、見てみたかったのだ。
「…………ポケットに?」
帰宅し、リビングのローテーブルにそっとそれを置くと、名前は暫し無言で物体を見つめた。深海の水面のように静かな瞳が、折り畳まれたままの、やや毒々しい程に真っ赤なハイヒールを、疑わしげに観察している。やがて、徐に伸ばした華奢な手の爪先で、それを軽く突っついた。
「嘘みたいに小さい。でも……ちゃんと、踵(ヒール)としての矜持は保っているみたい」
「ええ。とは言え、これをポケットに入れても、存在感があり過ぎて違和感しかないと思いますけど」
俺の冷静な指摘に、名前はくすりと笑う気配を見せる。
「そうだね。もし、弟の弟が見つけたら、きっと真顔でこう言う。『姉貴、ポケットに凶器入れて歩いてんのか』って」
「弟くん、最近、ますます語彙が辛辣になってきましたね……」
思わず苦笑が漏れる。
会話のテンポは、いつも通り、緩やかだ。急かされることも、途切れることもない、穏やかな流れ。けれど、俺の心の中は、名前と居ると常に天手古舞だ。この人と交わす、他愛もない言葉の一つひとつが、どうしようもなく愛おしくて、普段は静かな筈の心臓が、ちくちくと心地よい痛みを伴って騒ぎ出す。
「でも、折り畳みのハイヒールって、なんだか面白い発想だね。まるで、"自立することを一時的に放棄した女性"みたいじゃない?」
「……名前さん、そういう比喩、偶に核心を突き過ぎていて怖いです」
彼女の言葉は、時折、鋭利な刃物のように本質を切り裂く。
「そう? でも、わたし、京治くんの前では、そういう自立とか、強がりとか、もうどうでもいいかなって思ってる」
「え、ええ……」
不意打ちだった。ほんのりと熱を持った自身の耳を隠すように、俺は意味もなく眼鏡の位置を直す。これは、完全に反則だ。毎日同じ屋根の下で暮らし、同じ空気を吸っているというのに、こんな何気ない一言で、未だに心臓が跳ね上がるほど照れさせられるとは。
それにしても――『わたし、京治くんの前では自立とかどうでもいい』って。
それを、結婚して数年経った今、このタイミングで言うか? 余りにも、不意打ち過ぎる。
「……もし、それを会社の休憩室辺りで不意に言われたら、俺、多分驚いて鼻血を出すかもしれませんけど」
「じゃあ、今度、こっそり会社まで行って、耳元で囁いてみようかな。『京治くんの、折り畳みの妻です』って」
「頼むからやめてください。俺の理性が先に折り畳まれて機能不全に陥る」
俺の必死の懇願に、名前は漸く声を立てて笑った。その笑みは、とても静かで、けれど春の陽だまりのように底知れず優しかった。悪戯っぽい光を宿した瞳が、悪戯が成功した子供のように煌めいている。
「ねぇ、京治くん」
不意に、名前の声のトーンが少しだけ低くなる。
「ん?」
「今日ね、わたし、仕事で凄く疲れたの。頭も肩も、ずっしり重くて」
「……そうだったんですね」
気づけなかった自分を少しだけ責める。
「でも、京治くんがこんな、ちょっとどうかしているくらい面白いものをくれたから、なんだか、すうっと疲れが抜けて、元気になった」
「くだらない、とは言いませんが……まあ、実用性は未知数ですからね……」
「褒めているんだよ。最高の褒め言葉」
言いながら、名前はそっと俺の手を取った。触れた指先は少しひんやりとしていて、けれどその繊細な手のひらから伝わってくる温もりは、どこまでも確かで、俺の心をじんわりと満たしていく。
「ねぇ、京治くん。今日の夜ご飯、ピザにしよう。デリバリーで。ハイヒールも、気遣いも、何もかも脱ぎ捨てて、だらだら過ごす夜が、今のわたしには一番の贅沢だよ」
「……それ、なんだか名言みたいですね」
思わず感心して呟くと、名前は悪戯っぽく目を細めた。
「うん。でもね、本当の名言は、ピザの油で指をテカテカにさせながら言うものじゃないって、昔、誰かが言っていた気がする」
「……一体誰ですか、その人は」
「多分、わたし」
結婚して何年経っても、この人は本当に謎だらけだ。思考回路は時に迷宮のようで、発言は意表を突く変化球ばかり。
でも、それでいいのだ。
その尽きることのない謎を、一つひとつ、焦らずに解き明かしていく作業こそが、俺の愛おしい"毎日"なのだから。
そしてきっと、そうやって二人で積み重ねていく、他愛なくて、少しだけ可笑しくて、どうしようもなく温かいこの日常こそが、世間で言うところの"幸せ"ってヤツなのだろう。
俺は名前の手にそっと力を込め返し、デリバリーピザのメニューを思い浮かべながら、静かに微笑んだ。折り畳み式のハイヒールは、テーブルの上で、相変わらず奇妙な存在感を放っていた。