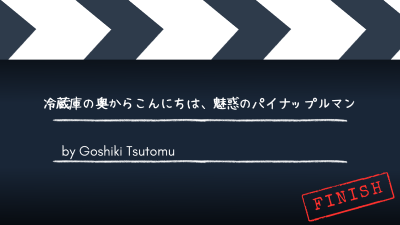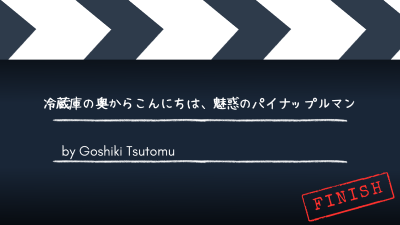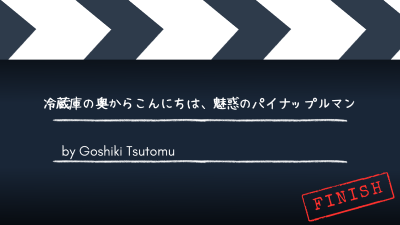
怪しい漢方と謎のクッションに導かれ、"恋のケミストリー"が暴走し始めた俺は、
気づけば彼女との距離0.5cm――これは、もはや事件だ。
Title:いけない二人
ああ、もう。
やっぱり、今日の俺の"恋愛運気"は……漢方の力があろうとなかろうと、間違いなく急上昇中だ。この胸の高鳴りは本物だ。
名前の花が綻ぶような笑顔と、「工くんが元気になってくれるなら、わたしはそれで、とっても嬉しいよ」という言葉が、俺の心臓を優しく、しかし、力強く鷲掴みにする。さっきまでの漢方薬による強制ブーストされたハイテンションとは明らかに違う。もっとずっと穏やかで、身体の芯からじんわりと温かさが込み上げてくるような、そんな本物の幸福感が胸いっぱいに広がっていく。
そんな俺の表情を見て取ったのか、
名前は耳まで真っ赤に染めながらも、俺から視線を逸らさずに、小さな、けれど、確かな声で言葉を続けた。
「……それに、その……さっきの工くんの言葉も、全然、変じゃなかった……寧ろ、ちょっと嬉しかった、から……」
う、嬉しい……だと……!?
俺の脳内で、先程までのカレイの煮付けによる味覚革命とはまた別の、もっと甘くて、もっと強烈な何かが弾けた。頭の中で、祝福のファンファーレが鳴り響いている。さっきの支離滅裂なプロポーズ紛いの絶叫も、あながち間違いじゃなかったのかもしれない、なんて、とんでもない勘違いまでしそうだ。いや、してる。確実に。
「っ、
名前……っ!」
俺は勢いよく立ち上がり、テーブルを挟んで向かい合う彼女の元へ駆け寄ろうとして――その瞬間、背後からヌッと現れた人影に、心臓が喉から飛び出そうな程に驚いた。
「ふむ。どうやら、我が秘薬、"超集中力強化用ブレンド・T10スペシャル"は、君の潜在的な恋愛力をも覚醒させてしまったようだね、工くん」
いつの間にか、例のカシミアブランケットを古代ローマのトーガのように優雅に身に纏い(下半身は相変わらず心許ないが)、頭にはどこから持ってきたのか、月桂冠もどきの葉っぱの飾りまで載せている
兄貴さんが、腕を組んで仁王立ちしていた。その姿は作家と言うより、新興宗教の教祖か何かにしか見えない。
「と、
兄貴さん!? いつの間に……て言うか、その格好は一体……!?」
「おっと、失敬。少し、我が妹と、その愛する青少年の魂の交歓が、余りにも神々しかったものでね。つい、その輝きに相応しい装いを、と思ってしまったんだよ」
全然、思ってないだろ! 絶対、面白がってるだけだろ、この人!
俺の心のツッコミも虚しく、
兄貴さんは舞台俳優のように大袈裟な手つきで、俺と
名前を交互に指差した。
「見えたよ、工くん、
名前。君達、二人の未来が! 今宵、この部屋に満ちる恋愛エネルギーは、過去最高潮に達している! これは、星々の配置、宇宙の波動、そして何より、この俺、
苗字兄貴の鋭敏なる第六感が告げているんだ!」
始まった……
兄貴さんの、謎のスピリチュアルトークが……!
名前は「また、兄さんが変なことを……」とでも言いたげな、困ったような、でもどこか慣れたような表情で小さく溜め息をついている。その顔もめちゃくちゃ可愛い。漢方の効果がまだ残っているのか、俺の語彙力は可愛い一択だ。
「い、いや、
兄貴さん、そういうのは……」
「案ずるな、工くん。これは科学的根拠に基づいた推論だ。君が口にしたT10スペシャルは、脳内の幸福物質の分泌を促進する。そして、
名前の心の籠もった手料理は、愛情という名の最強の触媒。この二つが組み合わさった時、そこに生まれるのは、正に奇跡のケミストリー! 今の君達は、謂わば歩くパワースポットであり、いけない二人! 触れ合うだけで、周囲の恋愛運すらも引き上げる、そんな存在なんだよ!」
何を言ってるのか全然分からないけど、妙な説得力だけはあるのが、
兄貴さんの凄いところだ。俺は半信半疑ながらも、心のどこかで「もしかしたら、本当に……?」なんて、淡い期待を抱き始めている自分に気づいて、顔が熱くなるのを感じた。だって、
名前との関係が進展するなら、なんだって信じたい。
「さあ、食後のデザートには、取って置きの映画を用意してある。タイトルは、確か……『冷蔵庫の奥からこんにちは、魅惑のパイナップルマン』だったかな。B級カルトの傑作と名高い作品だ。きっと、君達の高まった感受性を、更に刺激してくれることだろう」
タイトルからして、既に不穏過ぎる! パイナップルマンってなんだよ! しかも冷蔵庫からって!
俺の不安をよそに、
兄貴さんはどこか満足気に頷くと、リビングの大型スクリーンの前に、俺達を促した。
名前は「兄さんの選ぶ映画は、いつもちょっと変わっているけれど……」と小声で呟きながらも、俺の隣にちょこんと座る。その距離の近さに、心臓がまたドクンと跳ねた。
映画が始まると、予想通り、と言うか、予想を遥かに超えるカオスな映像がスクリーンに映し出された。チープな特殊メイクのパイナップル頭の怪人が、冷蔵庫からヌルリと現れては、意味不明な歌と踊りを披露し、人々を恐怖(と失笑)の渦に叩き込むという、前衛的過ぎる内容だ。
正直、映画の内容は全く頭に入ってこない。俺の意識は全て、隣に座る
名前の存在に集中していた。彼女のシャンプーの甘い香り、時折聞こえる小さな息遣い、そして、ソファの座面越しに伝わってくる、柔らかな体温。
――と、その時だった。
いつの間にか、俺の隣にふかふかとした妙な感触のクッションが置かれていた。黒地に金色の糸で、何やらごちゃごちゃとした文字が刺繍されている。よく見ると、それは……
【恋のケミストリー(当社比120%UP) ~触れ合えば、運命の歯車が加速する(かもしれない)~】
……って、書いてある――――!!
なんだ、この胡散臭いキャッチコピーは! しかも、(かもしれない)ってなんだよ!
背後を見るが、
兄貴さんはいつの間にか姿を消していた。あの人、このクッションを仕込んで、直後に退場したのか。
「……工くん、そのクッション……」
名前も気づいたようで、小さな声で呟く。彼女の頬が、薄暗い部屋の中でも分かるくらい、ほんのりと赤く染まっている。
「あ、ああ……
兄貴さんの、また新しい芸術作品……なのかな……」
俺は引き攣った笑みを浮かべるしかなかった。でも、このクッションの所為で、俺達の間の距離は、さっきよりも更に縮まっている。肩と肩が触れ合うか触れ合わないか、そんなギリギリの距離。
映画のパイナップルマンは、相変わらず意味不明な奇声を発しながら暴れ回っている。けれど、俺の耳にはもう、その騒音は殆ど届いていなかった。聞こえるのは自分の心臓の音と、
名前の小さな呼吸音だけ。
兄貴さんの言う「運命の歯車」だとか「恋のケミストリー」だとか、そんなものは正直、よく分からない。でも、このクッションがなんだか、俺達の背中をそっと押してくれているような、そんな気がしないでもなかった。
意を決して、ほんの少しだけ、
名前の方へ身体を傾けてみる。
すると、彼女の肩が、俺の肩に、こつん、と優しく触れた。
「……っ」
びくりと身体が強張る。でも、嫌な感じは全くしない。寧ろ、その温かさが心地よくて、心臓が甘く締め付けられるような感覚に襲われる。
名前も少しだけ驚いたように息を呑んだけれど、すぐに力を抜いて、俺の肩にそっと体重を預けてきた。
……ヤバい。これは本当にヤバい。
漢方の所為でも、
兄貴さんの変な占いの所為でも、この怪しいクッションの所為でもない。
俺は、今、心の底から、
名前のことが好きで、この瞬間が永遠に続けばいいと本気で願っている。
スクリーンの中では、パイナップルマンが冷蔵庫に吸い込まれていき、エンドロールが流れ始めた。けれど、俺達はどちらも動こうとしなかった。
肩越しに伝わる
名前の体温が、まるで春の陽射しのように温かくて、心地良い眠気を誘う。
これが、
兄貴さんの言っていた「いけない二人」の始まりなのだろうか。
だとしたら、俺はこの「いけない」状況を、もっともっと深く味わってみたいと、そう思ってしまった。
部屋の明かりがふわりと灯り、現実へと引き戻される。
俺はゆっくりと顔を上げ、隣の
名前を見た。彼女もまた潤んだ瞳で、俺を見つめ返してくる。その瞳の奥に揺らめくのはきっと、俺と同じ、甘くて、少しだけ背徳的な期待の色。
「……工くん」
「……
名前」
どちらからともなく、俺達は顔を近づけていた。
カレイの煮付けと、漢方薬と、B級映画と、変なクッション。
そして、何よりも大切な、
名前の笑顔。
今日の出来事全てが、俺達の「運命の歯車」を、確かに加速させてくれたのかもしれない。
――この先の展開は俺達と神様と、それから多分、
兄貴さんだけが知っている。