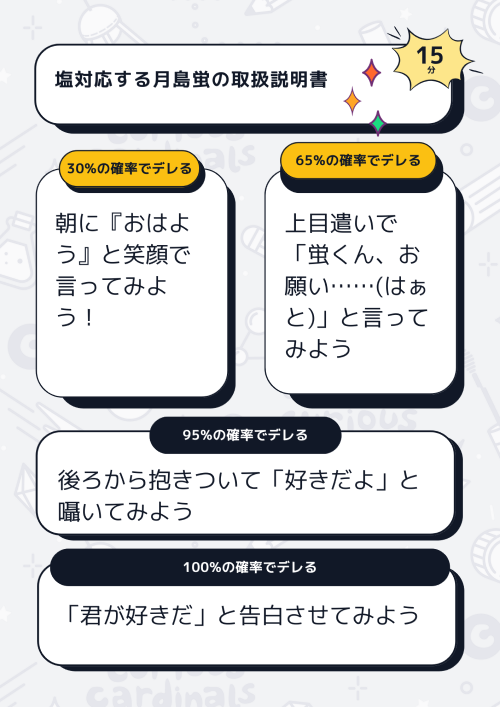君と僕の、夢物語 | 夢の続きは、君と二人で。
「……
名前、帰ったら一緒に宿題やらない?」
隣でぼそっと呟いた月島蛍の声に、わたしは顔を上げた。体育館の窓から差し込む夕陽が、彼のひよこ色の髪を琥珀色に染め上げている。黒縁の眼鏡越しに覗く瞳は普段と変わらず冷静だったけれど、その奥に微かな期待が揺れているのを見逃さなかった。
「うん、いいよ」
わたしがそう返すと、蛍くんは照れ隠しのように小さく「ありがとう」と呟き、愛用のヘッドフォンを首に掛けた。立ち上がった彼の背中は、少しだけ強張っているように見える。その仕草には何度見ても惹かれる何かがあった。
――その瞬間だった。
バチンッ――
空間が弾けるような音がして、体育館の床に不自然な光が走った。蛍くんとわたしは一瞬顔を見合わせ、彼の眉が軽く上がるのを見た。その理由はすぐに分かった。床に浮かび上がったそれは、間違いなく魔法陣だった。
「……これは何?」
わたしの声には珍しく動揺が混じっている。
「いや、僕に聞かれても……」
魔法陣は、心音に合わせるように脈打ち、明滅を繰り返していた。赤、青、金――複雑に絡み合う魔力の線が、見る者を誘い込むかのように輝き、その光は蛍くんの眼鏡に反射して、彼の表情をより神秘的に見せていた。
「これ……入ってみる?」
わたしの声には、理性よりも好奇心が先に出ていた。
「いや、入ったら戻ってこれない可能性――」
言い終えるよりも早く、わたしは蛍くんの手を掴んで魔法陣に飛び込んでいた。彼の手指の冷たさと、それに続く微かな温もりを感じる間もなく、世界が回転した。
視界が暗転した後に、わたし達が立っていたのは――
「……ダンジョン?」
そこは見慣れた烏野の体育館とはまるで別世界だった。天井は遥か彼方に霞み、壁を覆う黒々とした蔦は、生き物のように不気味に蠢いていた。足元の石畳は、罅割れ、苔生し、古の記憶を閉じ込めているかのよう。遠くで不穏な呻き声が響き、淀んだ空気が肌を這うように纏わりついてきた。
「……
名前」
蛍くんの声にはいつもの余裕がなかった。手に感じる彼の体温が少し上がっているのがわかる。
「蛍くん、これは……」
「……あれ、見える?」
蛍くんが指差した先に、鳥居が建っていた。石で出来た古い鳥居は、この場にそぐわない威厳を放っている。
その鳥居には――
『ツッキー神社』
と、何とも滑稽な文字が刻まれていた。
「……ツッキー……神社……?」
名前を口にした時、その響きの不条理さに、わたしは笑いを堪えるのに必死になった。
「何これ、悪趣味すぎる……」
蛍くんの眉間に浮かんだ皺は、彼の不快感を如実に物語っていた。それでも、わたし達は自然と鳥居の奥へと足を進めていた。
鳥居の奥には、コケに覆われた古びた祠があった。中には何かが置かれている。恐る恐る近づいてみると、それは――
大量の塩。
「……塩?」
白い結晶が祠の中で小山を作り、その形はまるで祈りを捧げているように見えた。
「何これ……お供え物?」
蛍くんの声には明らかな困惑が混じっていた。彼はメガネを直す仕草をした。緊張している時の癖だ。
その時、わたしは自分の手元に何かがあることに気がついた。どこから現れたのか、小さな冊子がわたしの手のひらに収まっている。
「……『塩対応する月島蛍の取扱説明書』……?」
「……え?」
蛍くんの顔が硬直する。
「どういうこと?」
表紙には、妙にデフォルメされた蛍くんのイラストが描かれていて、そのイラストはどこか愛嬌があった。試しにページを開いてみると、こんな項目が並んでいた。
・朝に『おはよう』と笑顔で言ってみよう! → 30%の確率でデレる
・上目遣いで「蛍くん、お願い……
」と言ってみよう → 65%の確率でデレる
・後ろから抱きついて「好きだよ」と囁いてみよう → 95%の確率でデレる
文字は古い筆文字で、インクが少し滲んでいるようだった。けれど、不思議と読み易い。
「……これは……」
「誰が書いたの、これ……」
蛍くんの声は普段の冷静さとは裏腹に、少し上擦っていた。
「試してみようか」
わたしが茶目っ気たっぷりに言うと、蛍くんの表情が更に硬くなる。
「やめて」
それでも彼の耳がほんのり赤くなっているのが見えた。心臓が少し速く鼓動する。
わたしが試しに「蛍くん、お願い……」と言おうとした瞬間――
バッ!
祠の陰から、誰かが飛び出してきた。突然の気配に、蛍くんがわたしの前に軽く立ちはだかるようにして身体を寄せる。
「……おい、蛍がデレるって聞いたんだけど!!」
馴染みのある声に、二人とも固まった。
「……兄ちゃん……」
月島明光だった。彼の顔には子供のようなはしゃぎようが見えた。
「ちょっと、今の蛍、撮っていい? デレてる蛍とか、貴重すぎる!!」
明光さんの手には、デジタルカメラが握られている。
「帰って」
蛍くんが明光さんを睨みつける。けれど、その耳が更に赤く染まっているのをわたしは見逃さなかった。肩の力が入り、普段は見せない一面が現れている。
「蛍くん……デレているの?」
わたしの言葉に、蛍くんの肩がピクリと動いた。
「デレてない」
彼の否定は少し早すぎた。
「じゃあ、これを試してみる?」
取扱説明書のページを捲ると、その最後のページには――
『「
名前が好きだ」と告白させてみよう → 100%の確率でデレる』
「蛍くん」
彼の喉元が微かに動いた。息を飲む音が聞こえた気がした。
「……」
「告白してみる?」
「……やめて」
そう漏らしながらも、蛍くんの視線はわたしの顔から離れなかった。何かを決意するような、試されているような、複雑な感情が彼の瞳に浮かんでいた。
「でも、100%デレるって――」
「わかった、言う」
蛍くんはメガネを外して、静かに深呼吸した。その仕草には、常とは違う緊張感があった。裸眼の彼の目は、どこか脆く見えて、心が揺さぶられる。
「
名前」
彼の呼びかけに、わたしの心臓が平常時よりも強く鼓動した。
「……うん」
「好きだよ」
彼の声はいつもより低くて、胸に直接響くような音だった。短い言葉なのに、その一語だけで体温が上がるのを感じた。
「デレた……!!」
明光さんが興奮気味にカメラを構える。その動きは素早かった。
「撮るな」
蛍くんは低く呟くと、無造作にわたしの手を引いた。その指にはいつもより強い力がこもっている。
「帰るよ」
「え? でも、まだ――」
「もう充分」
そう遮り、蛍くんはわたしを引き寄せて、額にそっと口づけた。その唇の触れる感覚は、余りにも鮮明で、温かかった。
「――これで満足?」
彼の問いかけは、明光さんにではなく、わたしに向けられているような気がした。
「いや、これは永久保存版……」
「帰れ!!」
「蛍、最高……!!」
そんな明光さんの叫びを背に、蛍くんはわたしを抱き寄せていた。彼の胸に耳を当てると、速い鼓動が聞こえる。
「
名前、もう……君の所為で、僕……」
言葉にならない彼の感情が、体温を通して伝わってくる。
「……ふふっ」
「笑うな」
彼の抗議は、いつもの刺々しさがなく、甘えに似ていた。
「でも、かわいいよ。蛍くん」
「……もう」
照れくさそうに顔を伏せた蛍くんの髪に、わたしはそっと指を通した。ひよこ色の髪はほんのり温かく、触れる指先に繊細な感触が残る。
「わたしも、好きだよ」
わたしの言葉に彼の腕に力が入った。
「……知ってる」
その声は、普段の冷静な蛍くんのものじゃなかった。少し震え、でも確かな感情がこもっていた。
100%デレた月島蛍は――多分、誰よりも可愛かった。
「……あれ?」
瞼の裏に、淡く光る蛍火のようなものがちらついている。それは意識の沈みゆく湖面で揺れる光のようで、一息ごとに遠ざかっていく。
重たい瞼をゆっくりと開くと、視界に飛び込んできたのは見慣れた天井の木目模様。朝の柔らかな光がカーテンを透かして、部屋の隅々まで優しく包み込んでいる。
「……夢、だったの?」
自分の手指を見つめる。魔法陣も、石畳のダンジョンも、あの奇妙なツッキー神社も、どこにも存在しない。指先には何の痕跡もなく、手の平に残るのは夢の中で感じた微かな熱だけ。蛍くんの手を掴んだ感触が、幻のように消えかけている。
「100%デレる」なんて、あり得ないほど素直だった蛍くんの姿が頭の中を過る。そして、カメラを向ける明光さんの興奮した顔。全てが鮮明すぎて、夢とは思えない。
「
名前?」
不意に、耳元で囁くような声がした。寝起きの低く掠れた声色に、心音が小さく跳ねる。
「蛍くん……?」
隣を見ると、朝日を受けたひよこ色の癖毛が微かに揺れている。琥珀色の瞳が、まだ眠気を帯びたまま瞬きを繰り返していた。メガネを掛けていない素顔は、日常の鋭さが抜け落ちて、どこか無防備な印象を与える。
「おはよ……。どうしたの?」
蛍くんは少し身を起こし、片肘をついて横向きになった。寝間着のシャツが僅かにずれて、鎖骨の線が見える。
「……ちょっと、不思議な夢を見たの」
告白するように言うと、蛍くんは軽く片眉を上げた。
「夢?」
「うん。蛍くんと一緒に異世界みたいな所に行ったの。体育館の床に魔法陣が現れて、飛び込むと、烏野が古びたダンジョンになっていて……」
言葉にする程に、夢の記憶が鮮明に蘇ってくる。蔦の絡まる壁、不気味な呻き声、そして何より――
「最後には"ツッキー神社"と祠まであったの」
「ツッキー神社?」
蛍くんの目が少し見開かれた。声のトーンが上がるのを聞き逃さない。
「うん。そこに辿り着くと、"塩対応する月島蛍の取扱説明書"なんていう本を持っていて……」
「待って」
蛍くんが眉間に皺を寄せる。朝の光が彼の横顔を優しく照らし、長い睫毛の影が頬に落ちていた。
「塩対応の僕って……何?」
「……。祠に塩がたくさん供えられていて、取扱説明書には、蛍くんをデレさせる方法が書いてあったの。上目遣いでお願いすると、65%の確率でデレるって」
「……ばかばかしい」
言葉とは裏腹に、蛍くんの耳が徐々に赤くなっていく。夢の中と同じ反応に、胸の奥が温かくなった。
「そうしたら、突然、明光さんが現れて、"蛍がデレてるって聞いたんだけど!"って」
「……は?」
「カメラまで持ってきていたよ」
「兄ちゃん、マジで……」
蛍くんは無意識に髪をかき上げ、天井を仰いだ。寝起きの蜜色の瞳が、朝の光を受けて琥珀のように輝いている。
「それで?」
「それで……蛍くんが、わたしに告白して……」
言葉が喉に詰まる。夢だと分かっていても、あの時の低い声、真っ直ぐな眼差しが記憶に焼き付いている。
「……台詞は覚えていないけれど、とても素直だったよ。照れていたけれど」
「僕が……照れた?」
「うん。それで、わたしの額に……」
全てを話すのは恥ずかしくて、言葉を飲み込んだ。けれど、蛍くんの視線は逃してくれない。そのまま黙り込むよりも、ずっと辛い。
「……キスしたんだ」
「え?」
「額に。そっと」
蛍くんの呼吸が止まったように見えた。彼の双眸は僅かに広がり、その中に驚きと別の何かが交錯している。朝の静けさの中で、二人の間に流れる時間だけが妙に緩やかに感じられた。
「……夢だったのかな」
言葉を投げかけるような問いに、蛍くんは静かに身を起こした。片手が僅かに宙を泳ぎ、やがてわたしの頬に触れる。指先は想像以上に温かく、その熱が肌から伝わってくる。
「夢に決まってるでしょ」
淡々とした声音だけれど、その指先は静かにわたしの頬の線をなぞっていた。
「でも……」
「僕がデレるなんて、そんなの絶対にありえないから」
言葉とは裏腹に、彼の指はわたしの耳朶に触れ、そっと髪を耳に掛けてくれる。
「……ふふっ」
思わず漏れた笑みに、蛍くんの眉が更に寄る。
「何がおかしいワケ?」
「今の蛍くん、夢の中と似た反応だったよ」
「……」
「でも、もし夢じゃなかったとしたら?」
蛍くんの指がわたしの頬から滑り落ち、代わりにそっと手を握った。掌と掌が重なる瞬間、電流のような小さな震えが走る。指先が絡み合うと、彼の体温がダイレクトに伝わってきて、心臓が早鐘を打ち始める。
「だったら、僕の取扱説明書を読んだ君が責任取ればいい」
蛍くんの声は低く、耳に心地良く響いた。その瞳に映るわたしの姿だけを見つめていると、彼は静かに続けた。
「夢だったら、もう一回見ればいい」
「……一緒に?」
「見れたらね」
蛍くんはそっと目を閉じる。わたしもその誘いに応じるように、ゆっくりと瞼を下ろした。彼の手の温もりが、現実と夢の境界線を曖昧に暈していく。静寂の中、二人の呼吸だけが微かに聞こえていた。
もう一度、あのダンジョンに行けるだろうか? ツッキー神社に再び辿り着けるだろうか? そして今度こそ、蛍くんの本当の気持ちを――
「もしまたその世界に行けたら、今度はゆっくり観光しよう」
蛍くんの声が、闇の中から優しく届いた。
「……うん」
二人の間に落ちる朝の静謐さが心地よく、肌に馴染んでいく。窓の外では鳥の囀りが始まり、新しい一日の訪れを告げている。
――でも、もう一度、あの夢を見られるなら。
今度はきっと、彼と手を繋いだまま。
「ツッキー神社か……」
蛍くんがぼそりと呟いた。声はまるで独り言のようで、けれどわたしの耳には確かに届いた。
「……鳥居、ちゃんと拝んでおくべきだったかな」
その言葉に、わたしは思わず微笑んだ。蛍くんもまた、あの世界を憶えているのだろうか? 夢と現実の狭間で、彼もまた何かを見ていたのだろうか?
わたしはくすりと笑いながら、蛍くんの手を握り返した。
指先から伝わる温もりは、確かに現実のもの。
けれど、心の中では既に次の冒険への期待が静かに芽生え始めていた。
――続きは、また夢の中で。
そして今度こそ、100%デレた蛍くんと共に。