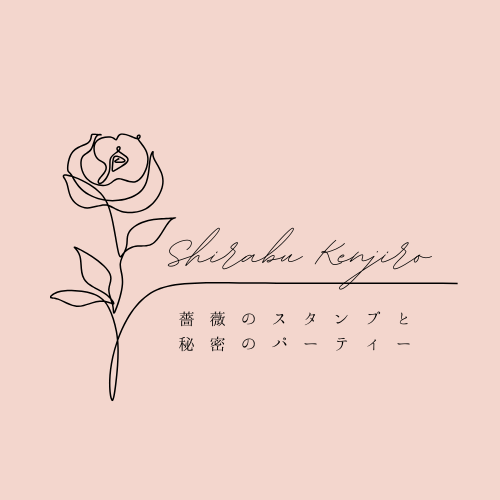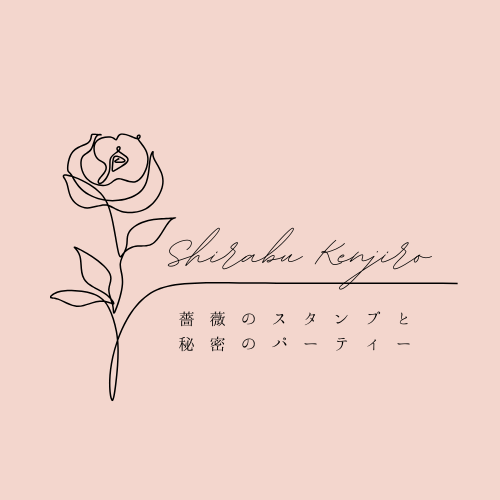薔薇のスタンプと秘密のパーティー | 二人だけの誕生祝 | Title:秘密のパーティー
春の柔らかな夕暮れが、宮城の町並みを淡い茜色に染め上げる頃。白布賢二郎は寮室のデスクライトの下、手元の白い封筒を何度目か分からないほど見つめ直していた。指先がかさりと触れる上質な紙の感触。そこには、彼にとって特別な意味を持つ名前が記されていた。
――『賢二郎へ。
今度の日曜、午後五時。わたしの部屋でささやかな秘密のパーティーを開きます。
正装で来てね。
苗字名前より』
便箋の隅には、彼女らしい控え目な、けれど印象的な小さな薔薇のスタンプが押されていた。インクの掠れ具合まで目に焼き付くようだ。筆跡は、
名前特有の静謐さを湛えた癖のある丸文字。まるで精緻な音楽の譜面のように、一文字一文字が丁寧に配置されている。そして、封を開けた瞬間からふわりと漂ってきたのは、あの忘れられない"潮の香り"――二週間前、春の陽射しが降り注ぐ町中で、白布自身が彼女の為に選び抜いた香水だった。それが彼女の日常に溶け込んでいる事実に、胸の奥が微かに温かくなる。
だが、白布はこの招待状に込められた"真実の意味"を、文面を一読した瞬間から正確に理解していた。この日曜日は――
苗字名前の誕生日。彼女はその事実を一言も、本当に一言も口にしてこなかった。それでも、白布が忘れる筈はない。カレンダーの日付に記された赤い丸。ここ数週間、練習の合間にも、帰り道にも、彼女がどんな顔で喜ぶだろうかと想像しながら、頭を悩ませ続けた贈り物の選定。その全てが、この日の為だった。
白布の鞄の奥深くには、長方形の箱が一つ。店員に頼んで、念入りに施してもらったラッピングに包まれ、静かに収まっている。中身は艶やかな木目が美しいオーボエリードケース。演奏後、唇に触れたリードを壊れ物を扱うかのように繊細な指先でそっと抜き取り、大切そうに仕舞う彼女の仕草を、白布は何度も盗み見てきた。彼女が全身全霊で愛する音楽の世界に、ほんの少しでも寄り添えるものでありたい。そんな切なる願いを込めて選んだ一品だった。
「……秘密のパーティー、ね……」
呟いた声は、自分でも驚くほど微かに震えていた。手のひらにじわりと汗が滲むのを感じ、無意識にズボンの生地で拭う。逸る心臓を落ち着かせようと深く息を吸い込み、着慣れないシャツの襟元を意味もなく指でなぞった。招待状にあった『正装』という言葉に内心戸惑いつつも、クローゼットの中から選んだのは、黒のボタンダウンシャツにネイビーのカーディガン。派手さはないが、
名前が好みそうな落ち着いた色合いとシルエットを意識したつもりだ。準備を終え、マンションのエントランスへと続く道を歩く足取りは、いつもより少しだけ重く、そして期待に満ちていた。
見慣れた、けれど、今日だけは違う空気を纏っているように感じるマンション。エントランスを抜け、エレベーターで彼女の住む階へ。目的の部屋の前に立つが、そこには矢張り、表札はなかった。それが
苗字家らしい、と白布は思う。インターホンのボタンを押し込む指先に、僅かな緊張が走る。数秒の静寂。それは永遠のようにも感じられた。やがて、内側から鍵の開く微かな金属音が響き、扉がゆっくりと外側へ開かれた。そこに立っていたのは――
「いらっしゃい、賢二郎」
――息を飲むほど美しい、ドレス姿の
名前だった。
夜空の深い青を溶かし込んだような、ミッドナイトブルーのミディアムドレス。デコルテから肩に掛けてあしらわれた繊細なレースが、彼女の白い肌を上品に縁取っている。耳元では、小振りながらも存在感を放つシルバーのピアスが、彼女が動く度に微かな光を反射して揺れていた。普段の、どちらかと言えば控え目で知的な雰囲気とは一線を画す、洗練された優雅な佇まい。そして、彼女の周囲にふわりと漂うのは、矢張り、あの"潮の香り"。白布が贈った香りが、今日の特別な彼女をより一層引き立てているように感じられた。
まるで古い物語の中から抜け出してきたかのような彼女の姿に、白布は文字通り、数秒間、呼吸を忘れていた。時が止まったかのような感覚。鼓動だけが、やけに大きく耳の奥で響く。
「……すげぇ、似合ってる」
漸く絞り出したのは、何の飾り気もない、無意識の言葉だった。それを聞いた
名前の頬が、キャンドルの灯りを映したかのように微かに、しかし、確かに紅潮する。
「ふふ……ありがとう。今日は、わたしが主催者。賢二郎は、わたしにとって一番の、特別なお客様」
悪戯っぽく微笑む彼女の、白魚のような手にそっと導かれるまま、部屋へと足を踏み入れる。目に飛び込んできたのは、二人で囲むには少しだけ広いテーブルの上に並べられた、手作りらしき温かみのある料理や、小振りながらも美しいデコレーションの施されたケーキ。壁には控え目ながらもセンスの良い飾り付け。そして、部屋全体を柔らかく照らす、幾つものキャンドルの温かい光。窓の外の夕闇が深まるにつれて、その光はより一層、幻想的な陰影を作り出していた。CDプレーヤーからは、どこか遠い時代の記憶を呼び覚ますような、優雅で懐かしいチェンバロの調べが静かに流れていた。
「……これ、本当に……ガチのパーティー……」
「だって、他の誰にも言っていないから。正真正銘"秘密"のパーティー」
名前はそう言って悪戯っぽく笑いながら、テーブルの傍らに置かれたアンティーク調のティーポットに、慣れた手つきでゆっくりとお湯を注ぎ始める。その一つひとつの所作が計算された舞踏のように滑らかで美しく、白布は自分がまるで、この世界で二人だけの為に用意された、特別な時間の舞台に招かれたような、不思議な錯覚を覚えた。
けれど、白布は知っている。今日という日が、ただの「秘密のパーティー」などではないことを。彼女がこの日の為に、どれ程の準備をしてくれたのか。そして、彼女が決して口にしなかった、本当の理由を。
「……なあ、
名前」
「ん?」
彼女が繊細な絵柄のティーカップをソーサーに乗せ、こちらへ差し出そうとした、その直前。白布は意を決して右手を伸ばし、彼女の動きを制するように軽くテーブルに置いた。そして、左手で背後の鞄を手繰り寄せ、奥に仕舞い込んでいたあの長方形の箱を取り出す。ひんやりとした滑らかな感触が、期待と不安が綯い交ぜになった感情と共に、手のひらに伝わってくる。それを彼女に手渡す、ほんの数秒の瞬間。心臓が警鐘を鳴らすかのように、ひどく煩く脈打つのを感じていた。
「……誕生日、おめでとう」
その一言を紡ぎ出すだけに、自分でも驚く程の勇気が必要だった。喉が渇き、声が掠れなかっただろうか、と内心焦る。
名前は驚いたように長い睫毛を瞬かせると、差し出された箱を壊れ物を扱うように両手でそっと受け取った。丁寧過ぎるほど慎重な手つきでリボンを解き、包装紙を開けていく。そして、現れた木製のケースを覗き込んだ瞬間、彼女は小さく息を呑んだ。
「……リードケース……木製の……わたし、こんな素敵なもの……」
手の中のそれを稀有な宝石でも見つめるかのように、食い入るように見つめている。そして、ゆっくりと顔を上げると、ふっと目を細めた。その瞳には驚きと、それ以上の深い喜びの色が浮かんでいるように見えた。
「わたし、誕生日のこと……本当に、何も言っていなかったのに」
「……憶えてるに決まってんだろ」
言葉にしようとすると、途端に照れ臭さが込み上げてきて、白布はぶっきら棒に付け加えるのが精一杯だった。視線をどこにやればいいのか分からなくなる。
「……本当に、嬉しい……。大切にする。ありがとう、賢二郎」
そう囁くように言う彼女の頬を染める紅の色は、二週間前、香水を選び終えた帰り道で見せたそれよりもずっと深くて、温かいもののように感じられた。
その後は緩やかに流れる川のように、静かな時間が過ぎていった。
二人で温かい紅茶を飲み、テーブルの料理を少しずつ分け合い、時折、どちらからともなく言葉を交わしては、小さく笑い合った。そして、また訪れる沈黙。けれど、その沈黙は決して気まずいものではなく、寧ろどこまでも心地よく、言葉よりも確かな信頼と親密さが、二人の間に満ちていることを示しているかのようだった。チェンバロの調べと、キャンドルの炎が揺らめく音だけが、静寂を優しく彩っていた。
不意に、
名前が「少し待っていて」と囁いて席を立ち、部屋の隅にあるクローゼットへと向かった。そして、戻ってきた彼女の手には、白布が贈った箱よりも一回り小さな、シンプルな白い箱が握られていた。
「……わたしも、実は、賢二郎の為に用意していたものがあるんだ」
少しだけはにかみながら、彼女が箱の蓋を開ける。白布が息を詰めて見守る中で現れたのは、淡く澄んだブルーの液体が満たされた、美しいガラスのボトルだった。手作りであろうシンプルなラベルには、見慣れた
名前の丸い文字で、こう記されていた。
――“Kenjiro's Blue”
「わたしなりに、賢二郎に似合うと思う香りを、調合してみたの。……天然の香料を少しずつ混ぜて、バランスを取って……何日も掛かったけれど……」
白布は言葉を失っていた。予想だにしなかった贈り物。それも、彼女が自分の為だけに、時間を掛けて創り出してくれた香りだなんて。
「良かったら、少し嗅いでみて?」
名前が促すように言って、ボトルの小さな蓋を捻って開ける。そして、白布の差し出された左の手の甲に、儀式のようにほんの一滴、その青い液体を慎重に乗せた。瞬間、ふわりと立ち昇った香りは、微かにあの"潮の香り"の面影を感じさせつつも、それよりもずっと涼やかで凛としていて、それでいてどこか懐かしいような、不思議な空気を纏っていた。清廉で、誠実で、けれど奥底に秘めた情熱を感じさせるような……まるで、自分自身の中にある、まだ知らない一面を不意に映し出されたかのような感覚に襲われる。
「……すげぇな……これ……」
「……これはね、"わたしから見た賢二郎"の香り。他の誰でもない、わたしだけの特別な視点で作ったつもり。……だから、これは、わたしだけの賢二郎の香り」
その言葉に含まれた、控え目ながらも確かな独占欲と真っ直ぐな想いに、喉の奥が焼けるように熱くなるのを感じた。衝動的に、白布は椅子から立ち上がっていた。そして、目の前に居る
名前の、香りを乗せてくれたばかりの右手をそっと取り、その白く繊細な指先に吸い寄せられるように唇を寄せた。触れた肌はキャンドルの熱を吸ったように温かかった。
潮風を思わせる夜に二つの香りが重なり合い、言葉にならない想いが交錯する。二人の距離はゆっくりと、けれど確実に縮まっていく。
"秘密のパーティー"は、まだ終わらない。
それは明確な恋の告白でも、未来を縛る誓いでもなかったかもしれない。けれど、二人が互いの存在を映し出した"香り"と、共有された"記憶"を慈しむように交換し合った、かけがえのない夜だった。
そして、この夜に生まれた"Kenjiro's Blue"と、彼女が纏う"潮の香り"は、これからもきっと――何度も繰り返し思い出すであろう、甘く切ない"香りの記憶"として、二人の心の中に深く、深く刻まれていくのだろう。