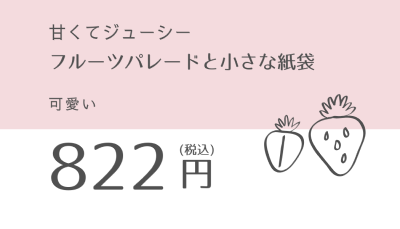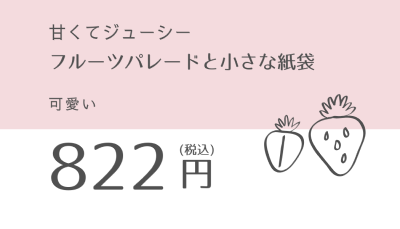フルーツパレードと小さな紙袋 | Title:可愛い
わたしも何か、彼が喜んでくれるようなものを買って帰ろうかな。
そう思い立ち、わたしはゆっくりと、先程まで五色くんが居た衛生用品の棚へと、吸い寄せられるように歩き始めた。
ほんの数分前までの小さな不安は、もう春の淡雪のようにどこかへ消え去り、胸の中は温かい期待と、ほんの少しの悪戯心で満たされている。
コンドームが並ぶ棚の前に立つと、改めてその種類の多さに驚かされた。五色くんが手に取っていたのは、確か一番オーソドックスなデザインのものだったけれど、その隣には、まるで外国のキャンディか何かと見紛うような、可愛らしいパッケージのものが沢山並んでいた。
瑞々しいフルーツのイラストが描かれたもの。淡いパステルカラーで統一された、高級な化粧品の小箱のようなデザインのもの。中には、猫の肉球のシルエットがプリントされたものまである。
「……可愛い」
思わず、ぽつりと声が漏れた。
これなら、独特の生々しさが薄れて、少しだけ抵抗感が和らぐ気がする。
わたしは苺とチェリーの絵柄が散りばめられた、ピンク色の箱をそっと手に取った。箱の裏を見ると、ほんのり甘いフルーツの香り付きで、中身も薄いピンク色をしているらしい。
「……これなら、恥ずかしくない、かな……」
誰に言うでもなく呟き、自分を納得させるように小さく頷く。五色くんはこの可愛らしい箱を見て、どんな顔をするだろう。きっと、一瞬驚いて、それから頬を真っ赤にしながらも、どこか嬉しそうな、困ったような、そんな表情をするに違いない。その顔が見たい、という純粋な期待が、胸の奥からむくむくと湧き上がってきた。
次に目に付いたのは、ハンドクリームかリップバームの容器と見間違えそうになるくらい、お洒落なチューブに入った潤滑ゼリーだった。こちらもバニラやピーチといった、甘くて優しい香りのものが幾つか並んでいる。
「これなら……部屋に置いていても、恥ずかしくない……筈」
わたしは、ふわりと甘いピーチの芳香がする、小さなチューブを選んだ。いつか、本当に五色くんに触れてもらう日が来た時、こんな甘くて幸せな匂いに包まれていたら、きっと嬉しいな、なんて。そんな、まだ見ぬ未来の光景を想像して、また顔が熱くなる。
そして、ふと視線を移した先にあったのは、今まで見たこともないような、少し特殊な形状のものが集められた一角だった。
『刺激強め!』『彼女がもっと喜ぶ!』などと、少し過激なキャッチコピーが、淡いピンクや水色の文字で書かれている。パッケージには、何やら細かい凹凸が付いていたり、波打つようなウェーブ状になっていたりするイラストが描かれていた。中には、様々な種類が少しずつ入った、アソートタイプのものもある。
「……初めて見たけれど、こういうのもあるんだ……」
好奇心に抗えず、その中の一つを恐る恐る手に取ってみる。それは、小さな突起が幾つも付いたタイプのものらしかった。パッケージに小さく書かれた『未体験の刺激を二人で』という文言が、やけに目に飛び込んできて、心臓がどきりとした。
その時、唐突に「何かお探しですか?」と、穏やかな声が掛かった。
はっと顔を上げると、にこやかな笑顔を浮かべた女性の店員さんが、すぐ傍に立っていた。拙い、見られた。
「あ、いえ、あの、大丈夫です……! ちょっと、見ていただけなので……!」
わたしの声は、自分でも驚く程に上擦り、顔から火が出そうなくらい熱くなっているのが分かった。慌ててその商品を棚に戻そうとしたけれど、何故か指先が震えて上手く掴めず、小さな音を立てて床に落としてしまった。
「わっ……!」
「あらあら、大丈夫ですよ」
店員さんは少しも慌てず、それを拾い上げ、にっこりとわたしに手渡してくれた。その優しい笑顔が、今のわたしには拷問のように感じられる。
「……ありがとうございます」
蚊の鳴くような声で礼を言い、わたしはその場から逃げるように立ち去りたかった。けれど、足が鉛のように重い。
パッケージに踊る『刺激増強』や『快感スパイラル』などという、扇情的で直接的な言葉の数々。
(うわ……でも……五色くん、こういうの……もしかしたら、喜ぶ、かも……?)
そんな考えが、心の隅を掠める。夢の中の彼は、いつもわたしに夢中で、もっともっとと求めてくれる。そんな彼が、もしこんなものを使ったら……。
想像しただけで、身体の奥が、きゅんと甘く疼くような感覚に襲われた。
でも、ダメだ。わたしは、五色くんの"添い寝フレンド"ではあるけれど、決して"セフレ"になりたい訳じゃない。この純粋な想いを、そんな汚らわしいものにしたくはない。
けれど、ほんの少しだけ、彼を驚かせて、喜ばせてみたいという、悪戯な気持ちも捨て切れなかった。
結局、わたしは最初に選んだ可愛らしいフルーツ柄のものと、お洒落なピーチの香りの潤滑ゼリー、そして、ほんの少しだけ冒険心を満たす為に、数種類が少量ずつ入ったアソートパックの中から、一番刺激の少なそうなものを選んで、レジへと向かった。
胸のドキドキは、先程よりも更に大きくなっている。
会計を済ませ、小さな紙袋を手にドラッグストアを出ると、夕暮れの空は美しい茜色に染まっていた。
五色くんに、早く会いたい。
この、どうしようもなく高鳴る気持ちを、彼にどう伝えようか。
わたしの愛用の、あの薔薇の刺繍のハンカチが、本当にふわりと香り立つみたいに、甘やかで、ちょっぴりスリリングな予感が胸いっぱいに広がっていく。
明日の夜、彼と添い寝するのが、いつもよりもずっと、ずっと楽しみになっていた。
そのことを考えると、またちょっぴり、心臓が愛おしい音を立てて騒がしくなるのだった。