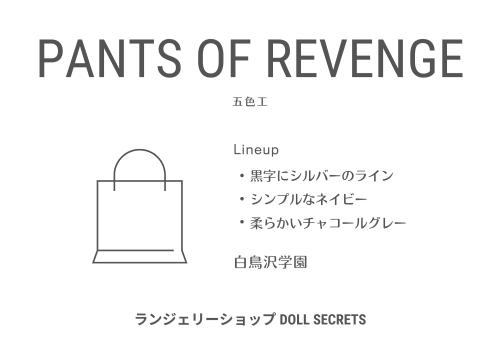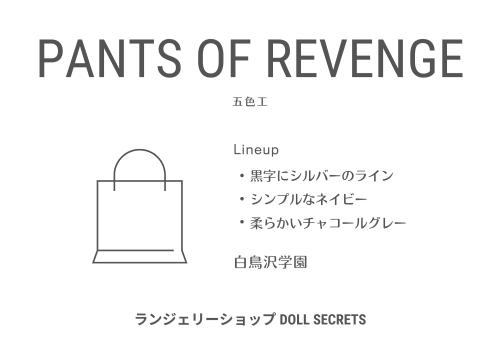パンツ・オブ・リベンジ | 指先が震える程のフィット感――選ばれた下着が暴く本音。
昼下がりの気怠い光が、薄いレースのカーテンを透かして、部屋の中に柔らかな縞模様を描き出していた。俺、五色工は、
苗字名前の部屋の、彼女の匂いが微かに残るベッドの端にちょこんと腰を下ろし、視線は意味もなく床のフローリングに落としていた。心臓が、やけに煩い。
すぐ隣には、見覚えのあるブランドロゴが入った紙袋が、まるでそこに置かれることが運命だったかのように、ぽつんと静かに存在感を主張している。その中には、あの日、
名前に半ば強引に、しかし最終的には彼女の嬉しそうな顔に絆されて受け取ってしまった、“アレ”が三着、収められている筈だ。そう、下着だ。俺の、俺がこれから穿く為の、だ。
「……っは、ずかしい……」
今更ながらに、じわじわと顔に熱が集まってくるのを感じて、思わず両手で顔を覆った。指の隙間から見える光景が歪む。
思い出すだけで、耳まで赤くなるのが分かる。あの日の下着売り場での出来事。煌びやかな照明、女性ばかりの空間、そして、楽しそうに、真剣な眼差しで俺用のパンツを選ぶ
名前。最終的に俺の手に渡されたのは、黒地にシルバーのラインが鋭く走る、見るからに攻めたデザインの一枚。それから、落ち着いた色味ながらも素材の良さが伝わるシンプルなネイビー。そして、ふわりと柔らかく、指先で触れた時の感触が忘れられないチャコールグレー。全部、全部、
名前が「工くんにはこれが似合うと思う」って選んだヤツだ。
「……結局、断り切れなくて、全部プレゼントされる形になっちゃったしな……」
自分でレジに持っていく勇気なんて、到底湧かなかった。なのに、選び終えて満足そうに微笑む
名前を見たら、「いらない」なんて言葉は喉の奥に引っ込んで、代わりに曖昧な返事しかできなかった。あの笑顔はズルい。
あれから数日が経った。紙袋はクローゼットの奥に隠していたけれど、
名前から「そろそろ、あのお礼、見せてほしいな?」なんて、悪戯っぽい光を含んだ瞳で言われてしまえば、もう逃げ道はない。
遂に今日――俺は、あの日の屈辱(と、ほんの少しの期待と好奇心)に対するリベンジを果たすべく、この部屋で覚悟を決めていたのだ。
名前に「可愛い」なんて言わせない。今日こそは、俺が主導権を握るんだ、と。
「工くん、準備できた?」
不意に、ドアの向こうから
名前の声が聞こえた。やけに明るく、弾むようなその声色が、逆説的に俺の心臓を鷲掴みにする。びくり、と肩が跳ねた。
「……っ、ちょ、ちょっと待ってくれ!」
殆ど反射的に、裏返った声で叫び返す。落ち着け、俺。深呼吸しろ。震える手で、隣の紙袋に手を伸ばした。がさがさ、と乾いた音が妙に大きく響く。
(……ど、どれにするか……)
指先が、最初にあの黒とシルバーのヤツに触れる。しかし、その余りにも大胆なデザインに気圧され、指が止まった。
あの日もそうだった。売り場で、
名前がこれを手に取った時、俺は思わず後退りした。結局、その日は一番無難に見えたネイビーも込みで買ってもらったのだ。
でも、今日は――今日こそは。
「……っ、うじうじしてても仕方ないだろ! やるしかないんだ!」
自分自身に檄を飛ばし、勢いを付けて立ち上がる。穿いていた私服の、草臥れたスウェットパンツを乱暴に脱ぎ捨て、更に普段使いの、何の変哲もない無地のボクサーパンツを引っ張って脱ぎ取る。ひやりとした午後の空気が、がら空きになった下半身の肌に直接触れ、ぶるりと小さく身震いが走った。目の前に広げられた三つの選択肢が、やけに鮮やかに、挑発的に見えた。これは気のせいじゃない、絶対に。
「……よしっ」
もう一度、短く気合を入れる。そして、震える指で、意を決して黒とシルバーの下着を取り出した。
想像していたよりも薄手で、滑らかな生地。そこに走るシルバーのラインが、光を受けて鈍く輝いている。……やっぱり、どう見ても攻めたデザインだ。これを俺が? 胸の奥がざわざわと落ち着かないのを、奥歯を噛み締めて必死に抑え込んだ。
腹を括り、えいやっ、と足を通す。するりとした感触が太腿を撫で上げ、腰まで引き上げると、驚く程ぴったりと身体にフィットした。締め付け過ぎることもなく、かと言って緩過ぎることもない。計算され尽くしたようなそのフィット感に、寧ろ違和感を覚える。布地が、まるで第二の皮膚のように肌に吸い付く感覚が、なんだか妙にそわそわして落ち着かない。柄は確かに派手だけど、サイズ感は完璧だし、案外、その……穿き心地自体は、悪くないのかもしれない……なんて、認めたくない思考が頭を過る。
恐る恐る、部屋に備え付けられた姿見の前に立つ。そこに映っていたのは、いつもより少しだけ大人びて見える、自分でも知らないような自分の姿だった。黒が肌の色を引き締め、シルバーのラインが妙な色気を醸し出しているような……気がする。
(……あれ? なんか、思ってたより……悪くない、かも?)
そう思った、正にその瞬間だった。
ガチャリ、と控えめな音を立てて、部屋の扉が不意に開いた。
「工くん、まだ? 遅いよ――」
能天気な響きすら含んだ
名前の声と共に、彼女がひょっこりと顔を覗かせた。
「っ!!」
振り向いた俺の視線が、ドアの隙間から覗く
名前の視線と、真正面から交差した。時間が、止まった気がした。
「……!」
名前の大きな瞳が、驚きに見開かれる。次の瞬間、その表情が見る見るうちに変化し、ふわりと、花が咲くような、それでいて全てを見透かしたような、柔らかな笑みが浮かんだ。
「……ふふ、やっと、穿いてくれたんだね」
その声は、砂糖菓子のように甘く、優しく、でも、ほんの少しだけ意地悪な響きが隠し味のように混じっていた。
「な、なな、なんで許可なく入ってくるんだよ!」
羞恥心と動揺で、声が盛大に裏返る。俺は咄嗟に近くにあったクッションを拾い上げ、慌てて腰元を隠した。しかし、その狼狽した俺の仕草が余計に面白かったのか、
名前はくすくすと、楽しそうな忍び笑いを漏らした。
「だって、待てなかったから。呼んでもなかなか返事がなくて、心配で」
悪びれる様子もなく、堂々と言い放ちながら、
名前はするりとしなやかな動きで部屋に入ってくる。そして、ゆっくりと、俺の方へ近づいてくる。一歩、また一歩と縮まる距離に、俺は後退りしたくてもできない。
「うん、凄く似合ってる。……やっぱり、工くんはカッコいいね」
すぐ傍まで来た
名前が、俺の耳元に顔を寄せて囁いた。吐息が耳に掛かる。その声が、やけに艶っぽく鼓膜を震わせ、心臓が早鐘のように打ち鳴らされる。
「か、カッコいいとか……そういうこと、言うなよ!」
顔が熱い。絶対に真っ赤になっている。
「どうして? 本当のことなのに」
悪戯っぽく笑いながら、
名前はさらりと言ってのける。その圧倒的な余裕に、俺はどう反応すればいいのか全く分からず、視線を彷徨わせることしかできなかった。クッションを持つ手に力が入る。
「ねぇ、工くん」
不意に、
名前がすっと手を伸ばし、その冷たい指先が俺の熱い頬にそっと触れた。ひんやりとした感触に、びくりと身体が震える。
「……折角、わたしにリベンジしようとしてくれているのに」
名前の指が、慈しむように俺の頬を撫でる。
「そんなに顔を真っ赤にしていたら、台無しだよ?」
「っ……!」
見抜かれてる。俺がリベンジしようとしていたことも、その為にこの下着を選んだことも、そして、今、完全に動揺してしまっていることも。全部、全部、
名前にはお見通しだった。悔しさが、喉の奥から込み上げてくる。
「じゃあ、今度はわたしからも、リベンジしていい?」
唐突に、
名前がそんなことを言い出した。え? と聞き返す間もなく、彼女は再び俺の耳元に唇を寄せた。さっきよりも近く、吐息が直接耳朶を擽る。
「――今日の工くん、最高に可愛い」
一瞬、思考が完全に停止した。頭の中が真っ白になる。耳元で、自分の心臓の音がどくどくと、狂ったように鳴り響いているのが聞こえる。理性のタガが、音を立てて外れそうになるのを感じた。
「……っ、な、なにが可愛いんだよ!」
反射的に、殆ど叫ぶように反論する。だが、
名前は意に介した様子もなく、ただ楽しそうに笑って、俺の汗で少し湿った髪を、優しい手つきでそっと撫でた。
「そういうところ。一生懸命、頑張って強がろうとしているところが、とっても可愛い」
どこまでも甘く、蕩けるような
名前の声が、部屋の空気に溶けていく。その声に、その仕草に、心が、抗いようもなく解きほぐされていくのを感じる。
(……ダメだ。結局、また……俺の、負けだ……)
リベンジなんて、とんでもない。完全に、彼女の手のひらの上で転がされている。それが悔しくて堪らない。
けれど、その悔しさよりも、隣に居る
名前の存在が、彼女の温もりが、どうしようもなく心地よくて。
「……もう、いいや」
諦めにも似た感情と共に、ぽつりと囁きが漏れた。
名前が、きょとんとした、子猫のような顔で俺を見上げてくる。
「やっぱり俺、
名前には……勝てねぇよ」
情けない声だったかもしれない。でも、それが今の正直な気持ちだった。
「ふふ、知ってる。そんな工くんも、わたしは大好きだよ」
名前はそう言うと、細い腕で俺の身体を優しく、しかし確りと抱き締めた。彼女の柔らかな肢体の感触と、甘い香りに包まれる。悔しさで燻っていた筈の心の中に、じんわりと温かい、別の小さな炎が灯るのを感じた。
いつかきっと、必ず。今日とは違う形で、俺が彼女を驚かせて、赤面させてやる――
そう胸の中で固く誓いつつも、今はまだ、この甘美な敗北に身を委ねていたいと思った。
心地よい温もりに包まれながら、窓から差し込む午後の光の中で、俺達の影が、ゆっくりと一つに重なり合っていくのを、ただ感じていた。