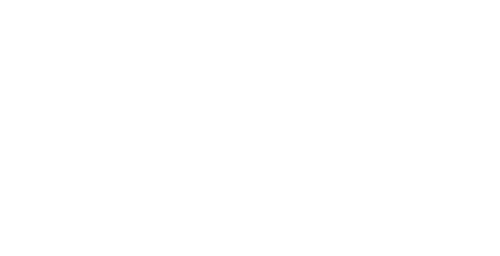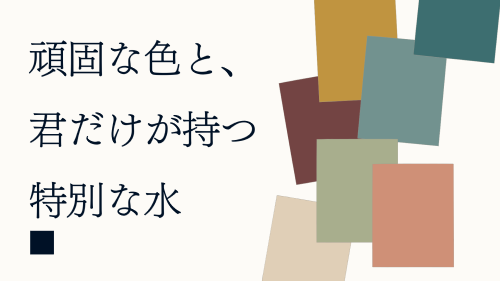
机の上に無造作に放り出された、アクリル製の透明なパレット。その窪みの中で、且て鮮やかだった筈の絵の具は、冬の湖面のようにかちこちに凍り付き、その役目を放棄していた。鮮烈な赤も、深い青も、希望を思わせる黄色すらも、どの色も等しく精彩を欠き、表面には無数の細かい亀裂が走っている。長い間、忘れ去られた感情の化石のようだ。そして、そのパレットと同じくらい、いや、それ以上に冷たく固まっているように感じられるのは――
「……名前、もしかして怒ってる?」
僕の問い掛けは、午後の静かな部屋に吸い込まれて消えた。返事はない。代わりに返ってきたのは、言葉よりも雄弁な、部屋の空気全体を通して肌に伝わる、じんわりとした、しかし確かな冷たさだった。まるで、彼女の不機嫌が室温を物理的に下げているかのようだ。
週末の午後。僕は名前の部屋で、半ば恒例となりつつある『芸術的センスに対する精神的拷問』とでも呼ぶべき、彼女の絵画課題の手伝いに駆り出されていた。彼女はオーボエとピアノに関しては、僕が口を挟む余地もない程の才能を持ち合わせているし、その読書量や映画に対する造詣の深さには、時折舌を巻く。庭で育てているハーブや花々は、彼女の指先から魔法が掛かったかのように生き生きとしている。なのに、こと美術、特に絵画に関しては、どういうわけか壊滅的なのだ。そのギャップが、まあ、面白いと言えなくもないけれど。
「……っていうか、この絵の具、完全に固まってるんだけど。これ、いつのヤツ?」
僕は罅割れた絵の具の表面を指でつつきながら、呆れ半分で尋ねる。
「……多分、二年前の」
漸く声がした。けれど、それは窓の外を眺めている名前の背中越しに発せられたもので、僕の方を向こうとはしない。声のトーンも、いつもより数段低い。
「いや、普通に考えて捨てるでしょ、二年物の固まった絵の具なんて」
「でも、色が綺麗だったから。なんだか、勿体なくて」
その理屈は、僕には到底理解できない。けれど、いかにも彼女らしい、モノに対する独特の執着や感性だとは思った。使えなくなったものでも、そこに"美しさ"を見出してしまうのなら、彼女にとっては捨てられないのだろう。
今日の名前は、朝、僕がこの部屋のドアを開けた時から、妙に静かだった。勿論、名前が静かなのはデフォルトだ。けれど、彼女の静けさには二種類ある。内側まで凪いだ湖面のように穏やかな"中が静か"な時と、表面は静かでも水面下で複雑な感情が渦巻いている"外だけが静か"な時。その差は、付き合いの長い僕にはもう、空気の匂いでわかる。
そして、今日は明らかに後者。つまり、何かに腹を立てているか、拗ねているか、その両方か。
原因は……十中八九、昨日の放課後のことだろう。
部活が終わり、教室に忘れ物を取りに戻ると、体調不良で授業を休んでいたクラスメイトの女子に呼び止められた。今日のノートをコピーさせてほしい、と。まあ、それ自体は別に構わない。ただ、なんとなくその流れで、少しだけ教室で話し込んでしまったのだ。他愛もない、当たり障りのない会話を。その時、廊下を通り掛かった名前が、一瞬だけ僕らの姿を視界に入れたのを、僕は見逃さなかった。彼女は僕と目を合わせることもなく、そのまま静かに昇降口の方へ歩き去っていった。あの時の、一瞬だけ硬直したように見えた背中が、妙に記憶に残っている。
「……もしかして、嫉妬、したの?」
僕は固まった絵の具のチューブのキャップを、力を込めて捻り開けながら、努めて平静を装って訊いてみた。
答えはない。けれど、その代わりに部屋の空気が一瞬だけ、ピンと張り詰めたような濃密な静寂に包まれた。これは、図星のサインだ。僕のこの問いが、彼女の心の壁に小さな亀裂を入れた証拠。
「僕が、あんな子と少し話してたからって、君の代わりになるわけないじゃん」
敢えて、少しだけ意地悪く言ってみる。
「……本当に、そう思っている?」
「じゃなきゃ、態々、君の拷問みたいな課題を手伝いに、休日にここまで来てない」
僕がそう言うと、名前はゆっくりと、本当にゆっくりと、こちらを振り返った。
窓からの逆光を受けて、彼女の輪郭が柔らかく光る。そして、その中に浮かぶ双眸は、嵐の前の夜の海を湛えたように、深く、濃く、そして少しだけ揺れていた。その視線に射抜かれると、僕はいつも少しだけ動揺する。
「……わたし、凄く醜いと思う。こんなことで、すぐに、心がざわざわして、嫉妬してしまうから」
俯きがちに、名前が呟く。その声には、自己嫌悪の色が滲んでいた。
「うん、まあ、醜いと言えば醜いかもね」
「……肯定するんだ」
僕の素直過ぎる返答に、彼女は僅かに目を見開いた後、ふっと息を吐くように小さく笑った。そして、漸く僕の隣の椅子に、音もなく腰を下ろす。艶やかな髪が、白いブラウスの肩からさらりと滑り落ちた。その何気ない仕草の一つひとつが、計算されたかのように美しくて、スローモーションが掛かった映像作品の一場面を見ているような気にさせられる。全く、狡い。
僕は固まった絵の具が並ぶパレットをそっと持ち上げて、廊下の隅にある小さな洗面所へと向かった。蛇口を捻り、冷たい水をパレットに注ぐ。固く閉ざされていた絵の具達が、水の浸食を受けて、じわじわとその頑なさを解きほぐしていくのを、僕は暫く黙って眺めていた。
嫉妬なんて、正直、面倒臭い感情だ。理解できない行動だし、非合理的だ。
でも、君が僕に対して、それだけ真剣に向き合ってくれている証拠でもある。
それに、白状すれば、僕だって、君が他の誰か――例えば、あの"王様"の影山とか――と親しげに話しているのを見たら、きっと冷静ではいられないだろう。表面上は平静を装っていても、内心は穏やかじゃない筈だ。認めたくはないけれど。
「名前」
「なに?」
洗面台の水の音に紛れさせて声を掛けると、壁一枚隔てた向こうから、すぐに彼女の声が返ってきた。耳が良いのか、それとも、僕の声にだけ反応するセンサーでも付いているのか。
「僕の心もさ、君が二年くらい放置したその絵の具みたいに、かなり頑固に固まってるんだけど。だから、他の誰かがどんな綺麗な水を持ってきても、びくともしないっていうか、解けないんだけど」
少し遠回しな、僕なりの不器用な愛情表現。
「……ふふ。じゃあ、わたしの特別な水で、丁寧に、溶かしてあげる」
……そういう、こちらの意図を正確に読み取った上で、更に上を行くような、意味深なことをサラッと言うのは反則だろ。心臓に悪い。
絵の具がなんとか使えそうな状態になったのを確認して、僕は部屋に戻った。すると、名前が僕の愛用している白いヘッドフォンを、両手でそっと包み込むように持っていた。まるで祈りを捧げるかのように。そして、僕の顔を見ると、何か言いたげな、それでいて少しだけ不安そうな表情を浮かべた。その目は「こんな無機質で、わたしのような静かな音しか奏でられないものを、貴方は本当に選んでくれるの?」と問い掛けているようだった。
僕は黙って名前に近づき、その繊細な手からヘッドフォンを受け取ると、少しだけ屈んで、ポン、と軽い音を立てて彼女の頭に被せた。サイズが合っていなくて、少し大きいけれど、それがまた妙に可愛らしく見える。
「僕が普段聴いてる、煩いだけの音楽なんかより、君の呼吸とか、心臓の音とか、そういう静かな音を聞いてる方がよっぽど落ち着くんだって、いい加減、気づいてよ」
「……わたしは、蛍くんの、すぐ傍で聴こえる鼓動が、世界で一番好きな音楽」
ああもう、これだから名前は――敵わない。
僕の心のパレットは、とっくに君の色だけで埋め尽くされて、他の色が入り込む隙間なんて、もうどこにも残っていない。それどころか、君という唯一無二の色と混ざり合って、日々新しい、僕らだけの複雑で、深くて、そして決して飽きることのない色合いに変化し続けている。
だから、もう、固まってしまう心配なんて、きっとないのだろう。君が傍に居てくれる限りは。