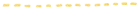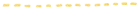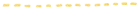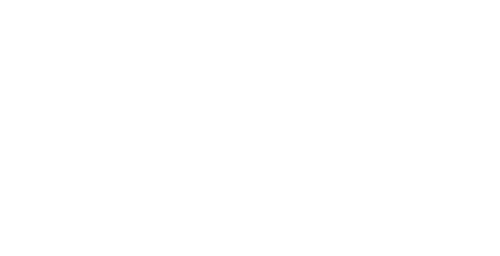冷たくしてしまった理由を言えないまま、
大切な人を傷付けた、最悪な自分に気づく話。
焼け野原、か。何かを形容する比喩としては、余りにも極端で現実味がないと思っていた。ドラマや小説の中だけの、大袈裟な表現だと。
けれど、今、この胸の内を覆い尽くす荒涼とした風景――僕自身の精神状態を言い表すのに、これ以上、しっくりくる言葉が見当たらないのだから皮肉だ。目の前が真っ暗になるとか、頭が真っ白になるとか、そういう有り触れた表現では到底足りない。何もかもが燃え尽きて、灰色の煙だけが虚しく立ち昇っている。そんな感覚。
「……名前に、嫌われた……」
ぽつりと零れ落ちた言葉は酷く惨めで、弱々しい響きを伴って静かな部屋に吸い込まれた。いや、正確には「嫌われた」と言うより、"呆れられた"のかもしれない。或いはもっと深く、静かに"失望された"のか。怒鳴られたわけでも、責め立てられたわけでもない。ただ、あの凪いだ湖面のような瞳の奥に、ほんの一瞬だけ過った温度のない光。それが鋭利なガラスの破片のように、僕の心臓に突き刺さって抜けない。
事の発端は、恐らく昨日。授業の合間の休憩時間だった。
普段、教室では余り近づいてこない名前が、珍しく僕の机までやってきて、他愛のない話を始めた。新しく見つけたカフェの話題だったか、読んでいる本の感想だったか。その時の僕は課題に集中していたわけでも、機嫌が悪かったわけでもない。ただ、クラスメイト達の好奇の視線が、やけに背中に突き刺さる気がした。僕らの関係を知っている者は少ないけれど、それでも、あの独特な雰囲気を持つ名前が、僕の隣に居るだけで、妙な注目を集めるのは分かっていた。それが無性に気恥ずかしくて、苛立たしかった。
だから、言ってしまったのだ。「皆の前でベタベタするの、やめてくれない?」と。
我ながら、最低な言い方だったと思う。突き放すような、冷たい声色。棘のある言葉。
言葉の裏に隠された本音――本当は、彼女がわざわざ僕のところへ来てくれたことが嬉しかった。少しだけ、独占欲が満たされるような感覚があったこと。そういう、自分でも持て余すような感情を読み取るのは得意な筈なのに、いざ自分の事となると、途端に何も見えなくなる。感じている事と思考がちぐはぐになって、口から飛び出すのは、いつも本心とは真逆の皮肉ばかり。まるで生まれ立てのキリンが、自分の長い脚を持て余して不様に転ぶように、僕は恋人への正しい接し方というものが、未だに掴めないでいる。自分で自分の首を絞めているだけだと分かっているのに。
「……馬鹿だな……僕」
自嘲の呟きは誰に聞かれるでもなく、虚空に消えた。
その瞬間、名前の表情がどう変わったのか、僕は見ることができなかった。ただ、ふっと空気が変わったのを感じて、咄嗟に視線を逸らしてしまったから。それきり、彼女は何も言わず、静かに自分の席へ戻っていった。その小さな背中が、やけに遠く感じたのを憶えている。
それからはもう駄目だった。彼女の顔をまともに見ることができない。話し掛けることなんて、到底できそうにない。
本当は昨日の夜、すぐにでも謝りたかった。通話ツールやトークアプリを開いて、彼女の名前をじっと見つめた。けれど、オンラインを示す緑のランプは灯っておらず、僕が最後に送ったメッセージには既読すら付いていなかった。指先が何度もメッセージ入力欄の上を彷徨い、けれど、結局、どんな言葉を送ればいいのか分からなくて、画面を閉じた。
そして、今日。同じ教室で、同じ授業を受けているというのに、僕はずっと、彼女の横顔を盗み見ることしかできなかった。柔らかな髪がさらりと頬に掛かり、窓から差し込む淡い光がその輪郭を縁取っている。あの静かで、どこか深淵を覗き込むような繊細な瞳の中に、今の僕は一体、どんな風に映っているのだろう。そう考えると恐ろしくて、視線を交わすことなんてできなかった。僕の吐いた冷たい言葉が、彼女の中でどんな風に響いているのか。それを確かめるのが、ただただ怖かった。
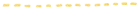 放課後の教室には、まだ数人の生徒達の話し声や、椅子を引く音が疎らに反響していた。窓の外は少しずつ茜色に染まり始め、長く伸びた影が教室の床を横切っていく。
月島は窓際の席で、相変わらず教科書を開いたままだった。しかし、その視線はページの上ではなく、もっと遠く、窓の外の虚空に向けられているように見えた。まるで、そこに答えを探しているかのように。時折、長い指がページを捲る素振りを見せるが、その動きはぎこちなく、すぐに止まってしまう。
山口は、そんな月島の様子に気づかない振りをしながらも、内心ではずっと、彼のことを気に掛けていた。ここ数日の月島は、明らかに様子がおかしかった。いつも以上に口数が少なく、纏う空気もどこか張り詰めている。そして何より、いつもなら昼休みや放課後に、どこかで見掛ける筈の苗字名前の姿が、月島の傍にない。
意を決して、山口は自分の椅子を少し、月島の方へ引き寄せた。
「……ツッキー、最近さ、苗字さんと話してなくない?」
努めて軽い口調で問い掛ける。しかし、返事はなかった。ただ、月島の肩がほんの僅かに強張ったように見えた。窓の外を見ていた瞳が、一瞬だけ揺らぐ。
山口はわざとらしく教科書を閉じ、もう一度、声を掛けた。
「喧嘩……した?」
「……別に」
漸く返ってきた声は低く、抑揚がなかった。
「喧嘩なんて子供みたいなこと、僕がするわけないデショ」
いつもの皮肉めいた響きは鳴りを潜め、ただ硬質な拒絶だけが滲んでいた。だが、山口は怯まなかった。月島がこういう態度を取る時、それは大抵、彼が内心で酷く動揺している証拠だと、長年の付き合いで知っていたからだ。
「でもさ……苗字さん、今朝もずっと俯いてたよ。それに、目が少し赤かった気がする」
その言葉は効果覿面だった。月島の指先が、教科書の端を掴むようにして、ピクリと微かに動いた。表情こそ変わらないものの、その僅かな反応が、彼の動揺を物語っていた。
山口は、ふぅ、と小さく息を吐いて、もう一度椅子を引き、月島の隣に腰を下ろした。
「ツッキーさ……」
少し声を潜める。
「ほんとは、苗字さんのこと、めちゃくちゃ大事に思ってるじゃん。全然顔には出さないけど、俺にはわかるよ。いつも苗字さんのこと、目で追ってるし」
「…………だから、何」
掠れた声。それは肯定も否定もしない、ただ行き場のない感情の表れのように聞こえた。
「だったら、ちゃんと言葉にしてあげなよ。ツッキーのそういう、わざと突き放すような"冷たさ"を、苗字さんはきっと信じてないと思う。ツッキーが本当は優しいって、分かってる筈だよ。ただ……今のままだと、その態度が全部、"本音"みたいに見えちゃってるんじゃないかなって」
山口の言葉は、静かに教室の空気に溶けていった。月島は何か言い返そうと口を開き掛けたが、結局、何も言わずに唇を固く結んだ。そして、数秒の沈黙の後、ゆっくりと椅子を引き、静かに立ち上がった。窓から差し込む夕日が、彼の色素の薄い髪を金色に照らしていた。
「……分かってる」
それは囁くように小さく、けれど、確かな重みを持った本物の声だった。後悔と、決意と、ほんの少しの弱さが滲んでいる。
山口はその背中を見上げ、安心したように微笑んだ。そして、立ち去ろうとする月島の背中を、ぽん、と軽く叩いた。
「頑張って、ツッキー!」
月島は振り返らず、ただ小さく頷くような仕草を見せて、教室を出て行った。
放課後の教室には、まだ数人の生徒達の話し声や、椅子を引く音が疎らに反響していた。窓の外は少しずつ茜色に染まり始め、長く伸びた影が教室の床を横切っていく。
月島は窓際の席で、相変わらず教科書を開いたままだった。しかし、その視線はページの上ではなく、もっと遠く、窓の外の虚空に向けられているように見えた。まるで、そこに答えを探しているかのように。時折、長い指がページを捲る素振りを見せるが、その動きはぎこちなく、すぐに止まってしまう。
山口は、そんな月島の様子に気づかない振りをしながらも、内心ではずっと、彼のことを気に掛けていた。ここ数日の月島は、明らかに様子がおかしかった。いつも以上に口数が少なく、纏う空気もどこか張り詰めている。そして何より、いつもなら昼休みや放課後に、どこかで見掛ける筈の苗字名前の姿が、月島の傍にない。
意を決して、山口は自分の椅子を少し、月島の方へ引き寄せた。
「……ツッキー、最近さ、苗字さんと話してなくない?」
努めて軽い口調で問い掛ける。しかし、返事はなかった。ただ、月島の肩がほんの僅かに強張ったように見えた。窓の外を見ていた瞳が、一瞬だけ揺らぐ。
山口はわざとらしく教科書を閉じ、もう一度、声を掛けた。
「喧嘩……した?」
「……別に」
漸く返ってきた声は低く、抑揚がなかった。
「喧嘩なんて子供みたいなこと、僕がするわけないデショ」
いつもの皮肉めいた響きは鳴りを潜め、ただ硬質な拒絶だけが滲んでいた。だが、山口は怯まなかった。月島がこういう態度を取る時、それは大抵、彼が内心で酷く動揺している証拠だと、長年の付き合いで知っていたからだ。
「でもさ……苗字さん、今朝もずっと俯いてたよ。それに、目が少し赤かった気がする」
その言葉は効果覿面だった。月島の指先が、教科書の端を掴むようにして、ピクリと微かに動いた。表情こそ変わらないものの、その僅かな反応が、彼の動揺を物語っていた。
山口は、ふぅ、と小さく息を吐いて、もう一度椅子を引き、月島の隣に腰を下ろした。
「ツッキーさ……」
少し声を潜める。
「ほんとは、苗字さんのこと、めちゃくちゃ大事に思ってるじゃん。全然顔には出さないけど、俺にはわかるよ。いつも苗字さんのこと、目で追ってるし」
「…………だから、何」
掠れた声。それは肯定も否定もしない、ただ行き場のない感情の表れのように聞こえた。
「だったら、ちゃんと言葉にしてあげなよ。ツッキーのそういう、わざと突き放すような"冷たさ"を、苗字さんはきっと信じてないと思う。ツッキーが本当は優しいって、分かってる筈だよ。ただ……今のままだと、その態度が全部、"本音"みたいに見えちゃってるんじゃないかなって」
山口の言葉は、静かに教室の空気に溶けていった。月島は何か言い返そうと口を開き掛けたが、結局、何も言わずに唇を固く結んだ。そして、数秒の沈黙の後、ゆっくりと椅子を引き、静かに立ち上がった。窓から差し込む夕日が、彼の色素の薄い髪を金色に照らしていた。
「……分かってる」
それは囁くように小さく、けれど、確かな重みを持った本物の声だった。後悔と、決意と、ほんの少しの弱さが滲んでいる。
山口はその背中を見上げ、安心したように微笑んだ。そして、立ち去ろうとする月島の背中を、ぽん、と軽く叩いた。
「頑張って、ツッキー!」
月島は振り返らず、ただ小さく頷くような仕草を見せて、教室を出て行った。
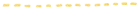 山口の言葉が、妙に胸に残っていた。「分かってる」なんて返事をしたものの、具体的にどうすればいいのか、その答えはまだ見つからないままだった。ただ、このままではいけない、という焦燥感だけが背中を押す。
教室を出て、部室へ向かおうとした、その時だった。
「蛍くん」
背後から、凛とした、けれど、どこか儚げな声が掛かった。心臓が大きく跳ねる。振り返ると、案の定、名前がそこに立っていた。少し離れた場所で、真っ直ぐに僕を見つめている。その瞳には、数日前、僕が感じたような温度のない光はなかった。ただ、静かで深い湖のような色を湛えている。
「部活が終わった後、少し時間、あるかな? 話したいことがあるの」
その声音に、怒気も、苛立ちも、非難の色も含まれていなかったことが、余計に僕の胸を締め付けた。もっと詰られた方が、いっそ楽だったかもしれない。名前のその静けさが、僕の罪悪感をより一層深く抉る。
僕は、ただ頷くことしかできなかった。声を出そうとすると喉が詰まって、上手く言葉にならない気がした。
部活の間も、正直、練習に身が入らなかった。ボールを追う身体の動きとは裏腹に、頭の中は名前のことでいっぱいだった。どんな話をされるのだろう。何を言われるのだろう。そして、僕は、何を言えばいいのだろう。
練習が終わり、汗を拭いて着替えても、思考は纏まらないままだった。校門の付近で待っていた名前は、僕の姿を認めると小さく頷き、何も言わずに歩き出した。
気づけば、僕らはいつもの帰り道を歩いていた。彼女の住むマンションへと続く、あの静かな並木道。外灯がぽつりぽつりと灯り始め、秋の名残を惜しむように色づいた葉を揺らす風が、ひんやりと頬を撫でていく。カサカサと乾いた音を立てて、足元で葉が舞う。
隣を歩く彼女との間に、会話はなかった。けれど、その沈黙が、今は寧ろ有り難かった。僕の頭の中は、謝罪の言葉で埋め尽くされていた。ごめん。本当にごめん。あの時は、そんなつもりじゃなかった。ただ、どうしようもなく、恥ずかしかっただけで――。そんな言葉達がぐるぐると渦巻いているのに、それをどうやって形にして伝えればいいのか、全く分からない。言葉を選ぼうとすればする程、喉が渇いて、指先が冷たくなっていくのを感じた。
彼女の住むマンションのエントランスを抜け、エレベーターで上階へ向かう。誰も住んでいないかのように、静まり返ったフロア。彼女の家のドアが開かれ、慣れた筈の空間に足を踏み入れる。いつもなら、この部屋の静けさや、彼女の纏う独特の空気に安心感を覚えるのに、今日ばかりは息が詰まりそうだった。
リビングに通され、促されるままに、いつものソファに腰を下ろす。ふかふかとしたクッションが、やけに僕の身体を沈み込ませるように感じた。名前がお茶を淹れる為にキッチンへ向かう、その小さな背中を見送りながら、僕は何度も深呼吸を繰り返した。
やがて、彼女が二つのティーカップをローテーブルに置いて、僕の隣に腰を下ろした瞬間、僕は漸く、か細い声を絞り出すことができた。ずっと胸に閊えていた、たった一言。
「……ごめん……」
それは自分でも驚く程、情けない声だった。
彼女は、すぐには何も言わなかった。ただ隣に座り、僕の方をじっと見つめている。その静かな視線に耐え切れず、僕は俯いた。膝の上に置かれた自分の指先が、微かに震えているのが見えた。
どれくらいの時間が経っただろうか。不意に、彼女がすぅ、と深く息を吸う音が聞こえた。そして、僕の耳に届いたのは、予想外にも、ふわりと柔らかな響きを帯びた声だった。
山口の言葉が、妙に胸に残っていた。「分かってる」なんて返事をしたものの、具体的にどうすればいいのか、その答えはまだ見つからないままだった。ただ、このままではいけない、という焦燥感だけが背中を押す。
教室を出て、部室へ向かおうとした、その時だった。
「蛍くん」
背後から、凛とした、けれど、どこか儚げな声が掛かった。心臓が大きく跳ねる。振り返ると、案の定、名前がそこに立っていた。少し離れた場所で、真っ直ぐに僕を見つめている。その瞳には、数日前、僕が感じたような温度のない光はなかった。ただ、静かで深い湖のような色を湛えている。
「部活が終わった後、少し時間、あるかな? 話したいことがあるの」
その声音に、怒気も、苛立ちも、非難の色も含まれていなかったことが、余計に僕の胸を締め付けた。もっと詰られた方が、いっそ楽だったかもしれない。名前のその静けさが、僕の罪悪感をより一層深く抉る。
僕は、ただ頷くことしかできなかった。声を出そうとすると喉が詰まって、上手く言葉にならない気がした。
部活の間も、正直、練習に身が入らなかった。ボールを追う身体の動きとは裏腹に、頭の中は名前のことでいっぱいだった。どんな話をされるのだろう。何を言われるのだろう。そして、僕は、何を言えばいいのだろう。
練習が終わり、汗を拭いて着替えても、思考は纏まらないままだった。校門の付近で待っていた名前は、僕の姿を認めると小さく頷き、何も言わずに歩き出した。
気づけば、僕らはいつもの帰り道を歩いていた。彼女の住むマンションへと続く、あの静かな並木道。外灯がぽつりぽつりと灯り始め、秋の名残を惜しむように色づいた葉を揺らす風が、ひんやりと頬を撫でていく。カサカサと乾いた音を立てて、足元で葉が舞う。
隣を歩く彼女との間に、会話はなかった。けれど、その沈黙が、今は寧ろ有り難かった。僕の頭の中は、謝罪の言葉で埋め尽くされていた。ごめん。本当にごめん。あの時は、そんなつもりじゃなかった。ただ、どうしようもなく、恥ずかしかっただけで――。そんな言葉達がぐるぐると渦巻いているのに、それをどうやって形にして伝えればいいのか、全く分からない。言葉を選ぼうとすればする程、喉が渇いて、指先が冷たくなっていくのを感じた。
彼女の住むマンションのエントランスを抜け、エレベーターで上階へ向かう。誰も住んでいないかのように、静まり返ったフロア。彼女の家のドアが開かれ、慣れた筈の空間に足を踏み入れる。いつもなら、この部屋の静けさや、彼女の纏う独特の空気に安心感を覚えるのに、今日ばかりは息が詰まりそうだった。
リビングに通され、促されるままに、いつものソファに腰を下ろす。ふかふかとしたクッションが、やけに僕の身体を沈み込ませるように感じた。名前がお茶を淹れる為にキッチンへ向かう、その小さな背中を見送りながら、僕は何度も深呼吸を繰り返した。
やがて、彼女が二つのティーカップをローテーブルに置いて、僕の隣に腰を下ろした瞬間、僕は漸く、か細い声を絞り出すことができた。ずっと胸に閊えていた、たった一言。
「……ごめん……」
それは自分でも驚く程、情けない声だった。
彼女は、すぐには何も言わなかった。ただ隣に座り、僕の方をじっと見つめている。その静かな視線に耐え切れず、僕は俯いた。膝の上に置かれた自分の指先が、微かに震えているのが見えた。
どれくらいの時間が経っただろうか。不意に、彼女がすぅ、と深く息を吸う音が聞こえた。そして、僕の耳に届いたのは、予想外にも、ふわりと柔らかな響きを帯びた声だった。
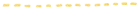 この人は時々、驚くほど不器用になる。
頭の回転は速いし、言葉だって誰よりも巧みに操る。他人に対しては容赦のない皮肉を飛ばして、涼しい顔をしている癖に。どうしてか、わたしや、彼が大切に思っているごく僅かな人達に対してだけ、途端に口下手になってしまう。高度な計算式は解けるのに、簡単な足し算で躓いてしまうみたいに。
そんな蛍くんが、消え入りそうな声で絞り出した「ごめん」という一言は、長い間、日照りが続いた大地に漸く降り始めた慈雨のようだった。
焼け野原みたいに罅割れて、乾き切ってしまっていたわたしの心に、その言葉がゆっくりと、静かに沁み込んでいく。冷たいけれど、決して凍えるような冷たさではない。寧ろ、火照った心を鎮めてくれるような、優しい温度を持った水。ちりちりと胸を焦がしていた棘のような感情や、燻っていた焦げ臭い匂いを、そっと洗い流してくれる。
「怒っていないよ」
わたしがそう言うと、蛍くんは少し驚いたように顔を上げた。そして、ぎこちなく、でも明らかにほっとしたように、きつく結ばれていた唇が僅かに解けた。その表情の変化が、なんだかとても愛おしく思えた。
「……嘘。怒ってた、でしょ」
蛍くんの声には、まだ不安の色が滲んでいる。
「うん。少しだけ、怒っていた。でも、それだけじゃないの。……悲しかった」
正直な気持ちを伝えると、蛍くんの肩がほんの少し、びくりと震えたのが分かった。彼はきっと、わたしが怒っていることばかりを気にしていたのだろう。けれど、わたしの中にあったのは、怒りよりもなお深い、静かな悲しみだった。彼に突き放されたこと。彼の言葉の冷たさ。それが、じわじわと心を蝕んでいくような感覚。
隣に座る彼が躊躇いがちに、そっとこちらに身体を寄せる気配がした。ソファのスプリングが小さく軋む。
「……僕、あの時……本当は、嬉しかったんだ。君がわざわざ、僕のところに来てくれて。だけど、皆の前だと……なんか、変に意識しちゃって……恥ずかしくて。周りにどう見られるかとか、そういうのが気になって……格好悪いんだけど」
蛍くんの声は、壊れ掛けた古いラジオから流れる音楽のように途切れがちで、不安定に揺れていた。けれど、その一つひとつの言葉は、ちゃんとわたしの心に届いた。彼の不器用な本音が、そこにはあった。
「うん。わかってる」
わたしはそっと、蛍くんの手を取った。少し汗ばんだ彼の指先が、まだ微かに震えている。何も言わなくても、彼の動揺と後悔が痛い程に伝わってきた。
わたしが本当に欲しかったのは、彼からの謝罪の言葉そのものではなかったのかもしれない。勿論、謝ってくれたことは嬉しい。けれど、それ以上に、わたしはただ、彼の気持ちが知りたかった。あの冷たい言葉の裏にあった、本当の感情を。
まるで、枯れ掛けた小さな苗に水をやるように。ただ、わたしという"場所"が、彼の心の中で干上がってしまわないように、ほんの少しでいいから、彼の気持ちという名の水を注いでほしかっただけなのだ。
「蛍くん」
名前を呼ぶと、彼は少し不安そうな瞳でわたしを見た。
「なに」
「わたしのこと、好き?」
少し意地悪な質問だったかもしれない。けれど、確かめたかった。この不安を完全に拭い去る為に。
蛍くんは一瞬、息を呑んだように見えた。けれど、すぐに迷いのない真っ直ぐな瞳で、わたしを見つめ返した。
「……うん。ずっと、好き」
その言葉を聞いた瞬間、胸の奥で固く結ばれていた何かが、ふわりと解けていくのを感じた。重く垂れ込めていた灰色の雲が晴れて、柔らかな光が差し込んできたみたいに。わたしの中に広がっていた焼け野原にも、雨に濡れた土の間から、小さな緑の芽が顔を出すような、そんな温かい感覚が広がっていく。
もう大丈夫だ、と思えた。
わたしはそっと、蛍くんの首に両腕を回し、彼の唇に自分の唇を重ねた。
初めて交わすキスではないのに、お互いに少しだけぎこちなくて、探り合うような感触があった。でも、その不器用さが却って、今のわたし達にはぴったりな気がして、堪らなく愛しかった。
蛍くんは少し驚いたように目を見開いた後、すぐに強く、でも壊れ物を扱うように優しく、わたしの背中を抱き締める。彼の腕の力強さと、伝わってくる鼓動の速さが、彼の安堵と愛情を物語っていた。
暫くして、どちらからともなく唇が離れる。吐息が混じり合う距離で、彼が熱っぽい瞳のまま、ぽつりと呟いた。
「……僕、君じゃないと、ダメなんだと思う」
その言葉はいつもの彼らしくない、飾り気のない、剥き出しの告白だった。けれど、だからこそ、すとんと胸の奥深くに落ちてきた。
わたしは微笑んで、蛍くんの広い胸にこつんと額を預けた。とくん、とくん、と規則正しく、でも、少しだけ速い、彼の心音が耳に心地いい。
「わたしも。わたしも、蛍くんじゃないとダメだよ」
静かなリビングに、寄り添う二人の鼓動だけが穏やかに響いていた。
焼け野原に注がれた優しい雨は、乾いた大地を潤し、ちゃんと根まで届いて、きっとまた新しい、綺麗な花を咲かせるだろう。
今はただ、そう信じることができた。彼の腕の中で、温かい安心感に包まれながら。
この人は時々、驚くほど不器用になる。
頭の回転は速いし、言葉だって誰よりも巧みに操る。他人に対しては容赦のない皮肉を飛ばして、涼しい顔をしている癖に。どうしてか、わたしや、彼が大切に思っているごく僅かな人達に対してだけ、途端に口下手になってしまう。高度な計算式は解けるのに、簡単な足し算で躓いてしまうみたいに。
そんな蛍くんが、消え入りそうな声で絞り出した「ごめん」という一言は、長い間、日照りが続いた大地に漸く降り始めた慈雨のようだった。
焼け野原みたいに罅割れて、乾き切ってしまっていたわたしの心に、その言葉がゆっくりと、静かに沁み込んでいく。冷たいけれど、決して凍えるような冷たさではない。寧ろ、火照った心を鎮めてくれるような、優しい温度を持った水。ちりちりと胸を焦がしていた棘のような感情や、燻っていた焦げ臭い匂いを、そっと洗い流してくれる。
「怒っていないよ」
わたしがそう言うと、蛍くんは少し驚いたように顔を上げた。そして、ぎこちなく、でも明らかにほっとしたように、きつく結ばれていた唇が僅かに解けた。その表情の変化が、なんだかとても愛おしく思えた。
「……嘘。怒ってた、でしょ」
蛍くんの声には、まだ不安の色が滲んでいる。
「うん。少しだけ、怒っていた。でも、それだけじゃないの。……悲しかった」
正直な気持ちを伝えると、蛍くんの肩がほんの少し、びくりと震えたのが分かった。彼はきっと、わたしが怒っていることばかりを気にしていたのだろう。けれど、わたしの中にあったのは、怒りよりもなお深い、静かな悲しみだった。彼に突き放されたこと。彼の言葉の冷たさ。それが、じわじわと心を蝕んでいくような感覚。
隣に座る彼が躊躇いがちに、そっとこちらに身体を寄せる気配がした。ソファのスプリングが小さく軋む。
「……僕、あの時……本当は、嬉しかったんだ。君がわざわざ、僕のところに来てくれて。だけど、皆の前だと……なんか、変に意識しちゃって……恥ずかしくて。周りにどう見られるかとか、そういうのが気になって……格好悪いんだけど」
蛍くんの声は、壊れ掛けた古いラジオから流れる音楽のように途切れがちで、不安定に揺れていた。けれど、その一つひとつの言葉は、ちゃんとわたしの心に届いた。彼の不器用な本音が、そこにはあった。
「うん。わかってる」
わたしはそっと、蛍くんの手を取った。少し汗ばんだ彼の指先が、まだ微かに震えている。何も言わなくても、彼の動揺と後悔が痛い程に伝わってきた。
わたしが本当に欲しかったのは、彼からの謝罪の言葉そのものではなかったのかもしれない。勿論、謝ってくれたことは嬉しい。けれど、それ以上に、わたしはただ、彼の気持ちが知りたかった。あの冷たい言葉の裏にあった、本当の感情を。
まるで、枯れ掛けた小さな苗に水をやるように。ただ、わたしという"場所"が、彼の心の中で干上がってしまわないように、ほんの少しでいいから、彼の気持ちという名の水を注いでほしかっただけなのだ。
「蛍くん」
名前を呼ぶと、彼は少し不安そうな瞳でわたしを見た。
「なに」
「わたしのこと、好き?」
少し意地悪な質問だったかもしれない。けれど、確かめたかった。この不安を完全に拭い去る為に。
蛍くんは一瞬、息を呑んだように見えた。けれど、すぐに迷いのない真っ直ぐな瞳で、わたしを見つめ返した。
「……うん。ずっと、好き」
その言葉を聞いた瞬間、胸の奥で固く結ばれていた何かが、ふわりと解けていくのを感じた。重く垂れ込めていた灰色の雲が晴れて、柔らかな光が差し込んできたみたいに。わたしの中に広がっていた焼け野原にも、雨に濡れた土の間から、小さな緑の芽が顔を出すような、そんな温かい感覚が広がっていく。
もう大丈夫だ、と思えた。
わたしはそっと、蛍くんの首に両腕を回し、彼の唇に自分の唇を重ねた。
初めて交わすキスではないのに、お互いに少しだけぎこちなくて、探り合うような感触があった。でも、その不器用さが却って、今のわたし達にはぴったりな気がして、堪らなく愛しかった。
蛍くんは少し驚いたように目を見開いた後、すぐに強く、でも壊れ物を扱うように優しく、わたしの背中を抱き締める。彼の腕の力強さと、伝わってくる鼓動の速さが、彼の安堵と愛情を物語っていた。
暫くして、どちらからともなく唇が離れる。吐息が混じり合う距離で、彼が熱っぽい瞳のまま、ぽつりと呟いた。
「……僕、君じゃないと、ダメなんだと思う」
その言葉はいつもの彼らしくない、飾り気のない、剥き出しの告白だった。けれど、だからこそ、すとんと胸の奥深くに落ちてきた。
わたしは微笑んで、蛍くんの広い胸にこつんと額を預けた。とくん、とくん、と規則正しく、でも、少しだけ速い、彼の心音が耳に心地いい。
「わたしも。わたしも、蛍くんじゃないとダメだよ」
静かなリビングに、寄り添う二人の鼓動だけが穏やかに響いていた。
焼け野原に注がれた優しい雨は、乾いた大地を潤し、ちゃんと根まで届いて、きっとまた新しい、綺麗な花を咲かせるだろう。
今はただ、そう信じることができた。彼の腕の中で、温かい安心感に包まれながら。