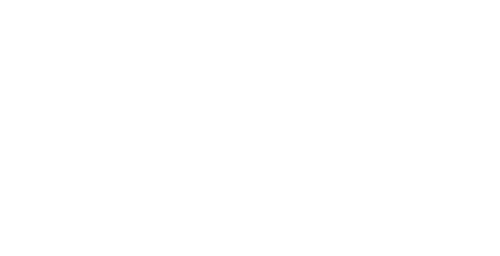乾いた風が砂埃を巻き上げ、ざらついた感触を頬に運んでくる。
部室棟の裏手――そこは校舎の壁と古びた金網フェンスに挟まれた、忘れ去られたような細長い空間だった。陽の光さえも遠慮がちに差し込むその場所は、誰の記憶にも留まらない、打ち捨てられた物達の終着駅。まるで、役目を終えた者達が静かに朽ちていく為の墓場のようだった。
そこに、彼は居た。月島蛍が。
古びてソールの剥がれたバレーシューズ、網目の破れたネット、座面の罅割れたベンチ。あらゆる”過去”が無造作に積み重ねられ、小さな山を築いている。その山の麓に、彼は居た。長い足を持て余すように折り畳み、しゃがみ込んでいる。
「……何をしているの?」
わたしの声は、風に掻き消されそうなほど頼りなかった。彼はゆっくりと顔を上げ、薄い月色の髪が微風にそっと揺れる。逆光の中、眼鏡のレンズが反射して表情は窺い難いけれど、その奥にある琥珀色の瞳が、僅かにこちらを捉えたのがわかった。常の彼からは想像もつかない、静かで、どこか遠くを見ているような眼差しだった。
「……別に。ただの整理」
低く、感情の起伏を抑えた声。彼の視線はすぐに手元に戻される。その指先が弄んでいるのは、見る影もなく草臥れたバレーボールだった。表面は擦り切れ、ところどころ革が捲れ上がり、無数の傷跡が刻まれている。縫い目も限界をとうに超えて大きく口を開き、中の空気は完全に抜け切って、頼りなげに萎んでいた。それでも、彼は慈しむかのように、そのボールを指でなぞり続けている。手放す気配は微塵も感じられなかった。
「それ、捨てるの?」
問い掛けると、彼は虚ろなボールから視線を離さないまま、ほんの少しだけ唇の端を歪めた。自嘲なのか、迷いなのか、判別のつかない曖昧な表情。
「……さあね」
その声は、わたしにではなく、彼自身の中の誰かに向けられた返答のように響いた。宙吊りにした決断を、ただ虚空に預けたように。
堪らなくなって、わたしは彼の隣にそっと腰を下ろした。埃っぽい地面に直接座り込むと、視界の高さが変わった。上から見下ろしていた時には気づかなかった、この場所が内包する時間の重みが、ずしりと迫ってくる。
積み上げられたガラクタの一つひとつが、雄弁に過去を語っていた。使い込まれたシューズの裏には、体育館の床を踏み締めた無数のステップが染み付いている。破れたネットの向こうには、熱狂と汗に塗れたボールの軌跡が、幻のように透けて見える。埃を被ったスコアボードの欠片は、歓声と溜め息が交錯した試合の日々を物語っているかのようだ。ここには確かに、誰かの情熱と、時間の堆積によって生まれた"歴史"と呼ぶべきものが存在していた。
「……懐かしい?」
わたしの呟きに、彼の肩が微かに揺れた。
「……懐かしいって言うか、ただ、まあ……昔のことを思い出しただけ」
いつもの皮肉めいた響きは、その声にはなかった。心の表面を覆っていた硬い殻が、一時的に取り払われたかのように。
不思議な感覚だった。皮肉を口にする時の彼は、どこか挑発的で、生き生きとして見えるのに。今の彼は、魂を抜き取られた抜け殻のようだった。彼が手の中で転がしている、あの萎んだボールのように、空虚で、所在なげで。
「……ここ、ずっと気になっていた?」
わたしの問い掛けに、彼は答えなかった。代わりに萎んだボールをぽん、と軽く指で弾く。乾いた音が、静寂の中に小さく響いた。そして、不意に視線をこちらへ向けた。
「名前は?」
「わたし?」
「捨てられないもの、ある?」
唐突な質問だった。予想もしていなかった問いに、わたしは思わず自分の手元へと視線を落とす。
捨てられないもの。
大切で、手放せなくて、失うことなど考えられないもの。
それは、物質的な何かではない。記憶や、感情や、或いは――
思考が一点に収束していく。迷いはない。答えはずっと前から、わたしの中にあった。
「……蛍くん」
静かに、けれどはっきりと、彼の名前を呼んだ。風が止み、二人の間の空気が張り詰める。彼が息を呑む気配が、すぐ隣で感じられた。
「わたしが捨てられないものは、蛍くん。……蛍くんが居るなら、他のものは全部、どうなってもいい」
迷いなく紡いだ言葉は、自分でも驚くほど真っ直ぐに響いた。彼の手の中で弄ばれていたボールの動きが、ぴたりと止まる。時間が停止したかのような、濃密な沈黙が流れた。
ややあって、彼は漸く口を開いた。その声には、呆れとも、照れともつかない、複雑な色が混じっていた。
「……君って、そういうことを、さらっと言うよね」
「本当のことを言っただけ」
見上げると、彼はわたしをじっと見つめていた。眼鏡の奥の琥珀色の瞳が、ゆらゆらと揺れている。その揺らぎの意味を、わたしはまだ正確には読み取れない。けれど、わたしの言葉が、彼の心の深い所に届いたことだけは確信できた。
「……じゃあさ」
彼はゆっくりと立ち上がり、ズボンに付いた埃を手で払いながら、わたしに向かって手を差し出した。その仕草は、どこかぎこちなく、けれど確かな意志を伴っていた。
「そろそろ、ここから出ない?」
「でも――」
まだ、何か言い掛けたわたしの言葉を遮るように、彼は続けた。
「ゴミの山にずっと居たら、僕らまでくすみそう」
そう言って、彼はわたしの手を取った。予想外の行動に、心臓が小さく跳ねる。彼の掌は少しひんやりとしていたけれど、確かな温もりがそこにはあった。その温もりが、指先からじんわりと伝わってきて、わたしの胸の奥にあった迷いや躊躇いを、ゆっくりと溶かしていく。まるで、春先の雪解け水のように。
「……そうだね」
わたしは差し出された彼の手を、しっかりと握り返した。指が絡み合う瞬間の、微かな感触。
そして、二人で肩を並べ、打ち捨てられた物達の山を後にした。
一歩踏み出す毎に、埃っぽい過去の匂いが遠ざかっていく。まるで、そこに堆積した感傷や未練を振り切るように。
繋いだ手の温もりだけが、ひどく鮮明だった。